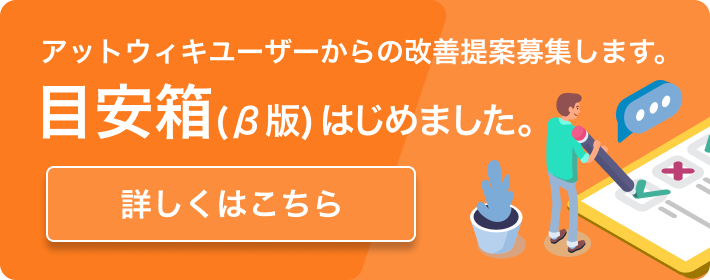相川ユキオプロローグ
最終更新:
dangerousss3
-
view
プロローグ
俺が知る限り、魔導書を手にして幸せになったやつはいないし、幸せになろうとしているやつもいない。
七割は一年と経たずに凄惨な死を遂げるし、二割は行方不明になる。
残り一割は? 他人から幸せである、と形容される人生を歩む者はいない。
魔導書は災いの種だ。
それは少しでも古本屋の世界に足を踏み入れた者なら、誰でもわかっている。
七割は一年と経たずに凄惨な死を遂げるし、二割は行方不明になる。
残り一割は? 他人から幸せである、と形容される人生を歩む者はいない。
魔導書は災いの種だ。
それは少しでも古本屋の世界に足を踏み入れた者なら、誰でもわかっている。
その点、魔導書を死ぬほど貯蔵していた長野県立オーヴァロード図書館は、
わざわざ数世紀をかけて不幸を溜め込んでいたようなものだし、
その中の一冊を失敬してやった俺はちょっとした善行を積んだということになる。
この意見はノートン卿には却下され続けているが、少し分別のつく者ならうなずいてくれるだろう。
わざわざ数世紀をかけて不幸を溜め込んでいたようなものだし、
その中の一冊を失敬してやった俺はちょっとした善行を積んだということになる。
この意見はノートン卿には却下され続けているが、少し分別のつく者ならうなずいてくれるだろう。
俺が盗んだ、もとい、持ち出してやったこのノートン卿は、まさに災いそのものといえた。
おそるべき思いつきで今後の計画をたて、さらには俺にそれを実行させようとする。
おかげで何度死にかけ、長野県からの追っ手に殺されそうになったか?
捕まったら今度こそ焚書にされてもおかしくないのに、懲りるということを知らないのだろうか?
おそるべき思いつきで今後の計画をたて、さらには俺にそれを実行させようとする。
おかげで何度死にかけ、長野県からの追っ手に殺されそうになったか?
捕まったら今度こそ焚書にされてもおかしくないのに、懲りるということを知らないのだろうか?
この日の卿の思いつきも、まさにそんな青天の霹靂のようなものであった。
俺たちは名古屋のガソリンスタンドで装甲輸送車(トヨタ製)を拝借し、
旧世界では決して許されないような速度で、東海道を西へ向かっているところだった。
空は曇天続きだったが、それでも昨日まで夏焼城ヶ山の森林に潜伏していた身としては、
解き放たれた爽快さを楽しむにはじゅうぶんといえた。
俺たちは名古屋のガソリンスタンドで装甲輸送車(トヨタ製)を拝借し、
旧世界では決して許されないような速度で、東海道を西へ向かっているところだった。
空は曇天続きだったが、それでも昨日まで夏焼城ヶ山の森林に潜伏していた身としては、
解き放たれた爽快さを楽しむにはじゅうぶんといえた。
自由!
それこそが、俺とノートン卿が求めたすべてのものだ。
古本屋のバイトとしての退屈な日々からの自由、図書監獄からの自由!
それこそが、俺とノートン卿が求めたすべてのものだ。
古本屋のバイトとしての退屈な日々からの自由、図書監獄からの自由!
追っ手も山中で皆殺しにしたし、ガソリンスタンドを襲撃した結果、金と食糧もかなり手にはいった。
首尾は上々であり、さてどこへ行こうか、春のドライブを満喫するのもいい。
そしてノートン卿は、そういう気分をぶち壊す術に長けていた。
首尾は上々であり、さてどこへ行こうか、春のドライブを満喫するのもいい。
そしてノートン卿は、そういう気分をぶち壊す術に長けていた。
「従者がほしい」
と、ノートン卿は仰せられた。
ノートン卿はただの本だし、空気を震わせるような音は出せないが、
所有者である俺はその声を物理的でない領域で聞くことができた。
ちなみに、遮断はできない。
と、ノートン卿は仰せられた。
ノートン卿はただの本だし、空気を震わせるような音は出せないが、
所有者である俺はその声を物理的でない領域で聞くことができた。
ちなみに、遮断はできない。
「思うに、私の栄光ある物語であるにもかかわらず、従者の数が少な過ぎはしまいか?」
「はあ」
俺は適当に相槌を打ち、助手席を見た。
黒革の、どこか不吉な装丁の一冊の魔導書がそこにある。
表紙には装飾などほとんどないが、ただ一点、中央に小さな赤い石が埋め込まれているのが特徴か。
この一冊の魔導書がノートン卿である。
「はあ」
俺は適当に相槌を打ち、助手席を見た。
黒革の、どこか不吉な装丁の一冊の魔導書がそこにある。
表紙には装飾などほとんどないが、ただ一点、中央に小さな赤い石が埋め込まれているのが特徴か。
この一冊の魔導書がノートン卿である。
基本的に、俺は彼の意向に逆らえない。
よってそのまま話を合わせることにした。
「従者というか、仲間なら俺も欲しいな、整体師とか。
山ン中で寝てたから、背中に激痛が走るんですよ。死んじまう」
よってそのまま話を合わせることにした。
「従者というか、仲間なら俺も欲しいな、整体師とか。
山ン中で寝てたから、背中に激痛が走るんですよ。死んじまう」
「何が整体師だ。そんなものが英雄の物語に従軍するのか?」
「いいじゃないですか。次は整体院襲いますか」
「いいじゃないですか。次は整体院襲いますか」
「ならぬ」
ノートン卿はいつも厳しい。あるいはそれは騎士道精神のつもりなのだろうか?
迷惑以外の何者でもない。
ノートン卿はいつも厳しい。あるいはそれは騎士道精神のつもりなのだろうか?
迷惑以外の何者でもない。
「いいか、私はきみの邪悪な蛮行を、いっさい許すつもりはない。
罪もない市民を襲って物資を略奪など、口にするのもおぞましい」
「ガソリンスタンドのことですか?
お腹すいたんだから仕方ない。金も必要だったし」
俺のこの言い訳は、ノートン卿を激昂させた。
罪もない市民を襲って物資を略奪など、口にするのもおぞましい」
「ガソリンスタンドのことですか?
お腹すいたんだから仕方ない。金も必要だったし」
俺のこの言い訳は、ノートン卿を激昂させた。
「黙れ悪党、誅戮するぞ!」
できるもんならな。
とは思ったが、俺は自制した。
魔導書は、どうせその持ち主――編集者に対して危害を加えることはできない。
できるもんならな。
とは思ったが、俺は自制した。
魔導書は、どうせその持ち主――編集者に対して危害を加えることはできない。
「とにかく整体院はなしだ。従者を探すのだ。
我が宿敵オレイン卿に対抗するには、より強力な手勢が必要となる」
「強力な手勢ですか。いいっすね。それと金も必要ですよ」
金は自由への、一つの手がかりなのは間違いない。
こんな世の中になってしまっても、貨幣経済は世界の大部分で意味を持つ。
我が宿敵オレイン卿に対抗するには、より強力な手勢が必要となる」
「強力な手勢ですか。いいっすね。それと金も必要ですよ」
金は自由への、一つの手がかりなのは間違いない。
こんな世の中になってしまっても、貨幣経済は世界の大部分で意味を持つ。
「よろしい。では引き返せ。
我らの栄光の進軍先は、東京にある」
ノートン卿は耳を疑うようなことを言った。
我らの栄光の進軍先は、東京にある」
ノートン卿は耳を疑うようなことを言った。
「ノートン卿――もしかして」
「何か?」
「俺たちがどういう連中に追われてるか、ご存知じゃないんで?
図書館のやつら、東京で網張ってるに決まってるじゃないですか!」
「そうだな」
「何か?」
「俺たちがどういう連中に追われてるか、ご存知じゃないんで?
図書館のやつら、東京で網張ってるに決まってるじゃないですか!」
「そうだな」
「だから関西圏に逃げこむために逃避行してたんじゃなかったですか?
俺の記憶力が悪くなったんですか?」
「事情が変わった。
先ほどのガソリンスタンドで入手した最新情報を見よ」
俺の記憶力が悪くなったんですか?」
「事情が変わった。
先ほどのガソリンスタンドで入手した最新情報を見よ」
助手席で大人しくしていたノートン卿が唐突に開き、ばらばらとめくれた。
やがて白紙のページが開き、そこに文章が浮かび上がる。
強力な魔導書は、最新のi-padに並ぶディスプレイ機能を誇るらしい。
あとはマインスイーパーさえできれば完璧だ。
俺は横目にその文面を眺めた。
やがて白紙のページが開き、そこに文章が浮かび上がる。
強力な魔導書は、最新のi-padに並ぶディスプレイ機能を誇るらしい。
あとはマインスイーパーさえできれば完璧だ。
俺は横目にその文面を眺めた。
「ザ・キングオブ……なんですって? トーナメント? 魔人?」
そこにはおよそ信じがたい告知が記載されていた。
魔人どもによるトーナメント。勝者には莫大な賞金。
いかにもノートン卿が好きそうな文言だ。
そこにはおよそ信じがたい告知が記載されていた。
魔人どもによるトーナメント。勝者には莫大な賞金。
いかにもノートン卿が好きそうな文言だ。
「武勲の誉れ。勝者には富と名声がもたらされる。
まさに主人公であり、英雄である私にふさわしい戦場ではないだろうか?」
「やめた方がいいですよ。こんな胡散臭いやつ」
俺は正直に忠告した。
ノートン卿はこのトーナメントを、中世のような馬上槍試合と勘違いしているかもしれない。
まさに主人公であり、英雄である私にふさわしい戦場ではないだろうか?」
「やめた方がいいですよ。こんな胡散臭いやつ」
俺は正直に忠告した。
ノートン卿はこのトーナメントを、中世のような馬上槍試合と勘違いしているかもしれない。
魔人との戦いは、その辺のチンピラやフェアリーを相手にするのとは話が違う。
彼らはもしかしたらジェット・リーも真っ青の殺人拳法の使い手かもしれないし、
ラッパを吹き鳴らすだけで頭を爆発させる悪魔のようなやつかもしれない。
生き延びようとするだけでも精一杯なのに、勝ち進むという話なら、さらに難易度は跳ね上がる。
彼らはもしかしたらジェット・リーも真っ青の殺人拳法の使い手かもしれないし、
ラッパを吹き鳴らすだけで頭を爆発させる悪魔のようなやつかもしれない。
生き延びようとするだけでも精一杯なのに、勝ち進むという話なら、さらに難易度は跳ね上がる。
「いやですよ。俺は死にたくない」
だが、俺の意見がノートン卿に聞き入れられたことは、いまだ記憶にない。
だが、俺の意見がノートン卿に聞き入れられたことは、いまだ記憶にない。
「強い従者も見つかるかも知れぬ。その暁には、きみはお払い箱だ」
「だといいんですがね……あの、どうしても行きます?
馬鹿げてるとして思えないんですけどね、俺は」
「きみは私の計画に異議を挟むというのか」
「だといいんですがね……あの、どうしても行きます?
馬鹿げてるとして思えないんですけどね、俺は」
「きみは私の計画に異議を挟むというのか」
ノートン卿の口調が険悪なものとなった。
「ならば、ここからの苦境、ひとりで勝手に切り開くがよい」
まずい兆候だ。俺はすぐに彼の機嫌をとる必要があった。
「ならば、ここからの苦境、ひとりで勝手に切り開くがよい」
まずい兆候だ。俺はすぐに彼の機嫌をとる必要があった。
「わかってます、わかってますって、異議なんてないですよ」
なぜかといえば、道路の進行方向を塞ぐように直進してくる、数台の装甲車両が見えたからだ。
対向車線にはみ出しているぞ、と、注意したところで無駄だろう。
威圧的な迷彩色のボディと、そこから身を乗り出している覆面の男たち。
彼らは手に機関銃やらショットガンやらをかかげ、何か大声で叫んでいる。
なぜかといえば、道路の進行方向を塞ぐように直進してくる、数台の装甲車両が見えたからだ。
対向車線にはみ出しているぞ、と、注意したところで無駄だろう。
威圧的な迷彩色のボディと、そこから身を乗り出している覆面の男たち。
彼らは手に機関銃やらショットガンやらをかかげ、何か大声で叫んでいる。
最近増えた武装強盗団だか、教信者の集団だか、それとも俺にかかっている賞金目当ての連中か?
いずれにしても、死にたくなければここを切り抜ける必要はあった。
――ノートン卿の力が、必要だった。
いずれにしても、死にたくなければここを切り抜ける必要はあった。
――ノートン卿の力が、必要だった。
「俺は閣下の言うとおりにしますよ。いつもそうだったじゃないですか。
主人公はやりたいようにやればいいんです、そうなんです」
「そうだろう」
「もちろんです。だからちょっと」
俺はブレーキを踏み、力いっぱいハンドルをきった。
タイヤとサスペンションが、重たくて鋭い悲鳴を放った。
主人公はやりたいようにやればいいんです、そうなんです」
「そうだろう」
「もちろんです。だからちょっと」
俺はブレーキを踏み、力いっぱいハンドルをきった。
タイヤとサスペンションが、重たくて鋭い悲鳴を放った。
「手伝ってくださいよ」
いい加減なドリフトとともに急減速、正面から向かってくる連中に横を向く格好になる。
車の速度を制御しながら、片手ではノートン卿を掴む。
「よかろう」
黒革の不吉な装丁に触れた瞬間、俺はある種の結びつきを感じた。
いい加減なドリフトとともに急減速、正面から向かってくる連中に横を向く格好になる。
車の速度を制御しながら、片手ではノートン卿を掴む。
「よかろう」
黒革の不吉な装丁に触れた瞬間、俺はある種の結びつきを感じた。
ノートン卿に記された無数のスペルと、その扱い方については、
この数ヶ月を通してある程度は理解を進めていた。
力あるスペルを連結させて、なんというか――編集し、一つの魔法を形作る。
それだけが唯一、魔導書の使い手に許された権利であった。
この数ヶ月を通してある程度は理解を進めていた。
力あるスペルを連結させて、なんというか――編集し、一つの魔法を形作る。
それだけが唯一、魔導書の使い手に許された権利であった。
間に合うだろうか?
装甲車両から身を乗り出していた男の一人が、機関銃を構えるのが見えた。
ただの威嚇か、それとも俺をトマトみたいに潰してからじっくり収穫を吟味するつもりか?
いずれにせよ、ただ見ているほど俺も間抜けではない。
装甲車両から身を乗り出していた男の一人が、機関銃を構えるのが見えた。
ただの威嚇か、それとも俺をトマトみたいに潰してからじっくり収穫を吟味するつもりか?
いずれにせよ、ただ見ているほど俺も間抜けではない。
「私の要塞に、あの程度の兵器と手勢で挑もうとは」
俺はノートン卿の声を聞きながら、その力を編集する。
彼が許す限り、俺は自在にその権利を振るうことができた。
「笑止。我が偉大なる城塞を見せてやれ」
「そうですね」
俺はノートン卿を開いた。
しかるべきスペルの記されたページが何枚もめくれあがり、ひとつの強固な魔法を編集する。
俺はノートン卿の声を聞きながら、その力を編集する。
彼が許す限り、俺は自在にその権利を振るうことができた。
「笑止。我が偉大なる城塞を見せてやれ」
「そうですね」
俺はノートン卿を開いた。
しかるべきスペルの記されたページが何枚もめくれあがり、ひとつの強固な魔法を編集する。
側面を向けた俺の車の影が素早く伸び、立ち上がった。
それはのっぺりとした《壁》を形成すると、そびえたち、
突っ込んできていた装甲車両の群れをまとめて餌食にする。
それはのっぺりとした《壁》を形成すると、そびえたち、
突っ込んできていた装甲車両の群れをまとめて餌食にする。
ノートン卿は腐っても「城塞」の魔導書だ。
壁の堅固さを競わせれば、攻城兵器か、それに値する魔術を行使するしかない。
装甲車両が全速力で突っ込んできたところで、投げつけられた半熟卵のようなものだ。
壁の堅固さを競わせれば、攻城兵器か、それに値する魔術を行使するしかない。
装甲車両が全速力で突っ込んできたところで、投げつけられた半熟卵のようなものだ。
――悲鳴というよりも、怒号と、激しい激突音が《壁》をかすかに震わせた。
《壁》を解除して影に戻すと、そこに残るのは装甲車両の残骸と、
かろうじて這いずろうとする数名の男たちだけだった。
俺はそいつらの銃を奪い、速やかに止めをさしてやり、作業を終えた。
《壁》を解除して影に戻すと、そこに残るのは装甲車両の残骸と、
かろうじて這いずろうとする数名の男たちだけだった。
俺はそいつらの銃を奪い、速やかに止めをさしてやり、作業を終えた。
「……こんなもんでいいかな?」
「愚か者どもにふさわしい末路よ」
彼は自分に歯向かう者には容赦しない。その点は俺も同感だ。
「愚か者どもにふさわしい末路よ」
彼は自分に歯向かう者には容赦しない。その点は俺も同感だ。
結局、俺とノートン卿は一蓮托生の運命にあるのだといえる。
俺が彼を盗んだ――もとい、彼の旅に同行することに決めたのは、
古本屋の退屈な暮らしにうんざりしていたためであり、劇的なブレイクスルーを求めていた。
なんだってよかった。世界を破壊する爆弾だろうが、悪魔との取引だろうが。
俺が彼を盗んだ――もとい、彼の旅に同行することに決めたのは、
古本屋の退屈な暮らしにうんざりしていたためであり、劇的なブレイクスルーを求めていた。
なんだってよかった。世界を破壊する爆弾だろうが、悪魔との取引だろうが。
ノートン卿の事情はもっと単純だ。
彼は英雄になりたいのだ。
宿敵を討伐し、物語の主人公として祝福されたいのである。
まったく、めでたいやつだ。
旧世界ならいざ知らず、いまやそんな物語が成り立つと本気で思っているのか?
まあ、やつは魔導書であり、何世紀も前の人格だから仕方がない。
彼は英雄になりたいのだ。
宿敵を討伐し、物語の主人公として祝福されたいのである。
まったく、めでたいやつだ。
旧世界ならいざ知らず、いまやそんな物語が成り立つと本気で思っているのか?
まあ、やつは魔導書であり、何世紀も前の人格だから仕方がない。
「本当に行くんですかね? その」
「むろんだ」
ノートン卿の頭の中には、すでに勝利の栄光しか存在していないようだった。
「むろんだ」
ノートン卿の頭の中には、すでに勝利の栄光しか存在していないようだった。
俺はつかの間、この大会が罠ではないか考えた。
人間を使った罠は、ノートン卿の宿敵である、オレイン卿の好きそうなことだ。
やつは人間に信仰心を植えつけ、虜にして操る力を持つ。
これはある種の自殺行為ではないだろうか?
だが、次のノートン卿の言葉で、俺のその気分は吹っ飛んだ。
人間を使った罠は、ノートン卿の宿敵である、オレイン卿の好きそうなことだ。
やつは人間に信仰心を植えつけ、虜にして操る力を持つ。
これはある種の自殺行為ではないだろうか?
だが、次のノートン卿の言葉で、俺のその気分は吹っ飛んだ。
「もう逃げ回るのは飽きたのだ。
罠だとしても追っ手をみな駆逐し、堂々とオレイン卿に向かって進軍するべきだ」
簡単なことだが、俺はすっかり忘れていたことを思い出した。
俺たちは自由になるために手を組んだのであって、逃げ回るためではない。
罠だとしても追っ手をみな駆逐し、堂々とオレイン卿に向かって進軍するべきだ」
簡単なことだが、俺はすっかり忘れていたことを思い出した。
俺たちは自由になるために手を組んだのであって、逃げ回るためではない。
「いくぞ、ユキオ!」
と、ノートン卿は俺の名をわめいた。
「いざ東京へ」
「そうですね」
と、ノートン卿は俺の名をわめいた。
「いざ東京へ」
「そうですね」
拒否権のようなものは無さそうだったので、俺は相槌を打つだけの機械になろうと努めた。