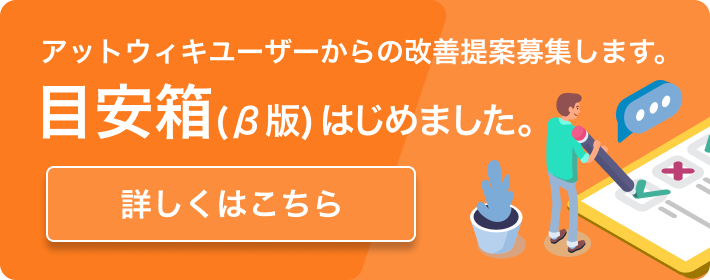第二回戦【ジャンボジェット機】SSその3
最終更新:
dangerousss3
-
view
第二回戦【ジャンボジェット機】SSその3
――六月二日 ジャンボジェット機内
ミツコが鋏を繰り出せば猪狩がそれを躱し、体を立て直す反動でミツコではなく拾翠に攻撃を仕掛ける。後の先を制した拾翠の蹴りを猪狩は両腕で受け止めた。ミツコはその隙に二人の攻撃射程から離れている。
動きやすいとは言えない機内を、三つの影が飛び違うように交差していた。それぞれが優先とする撃破対象を定めずに、咄嗟に状況を判断しながら攻撃を捌き合う乱戦である。
この状態を好んで作り出したのは、ミツコだった。三つの意識を持つ彼は、対戦相手である猪狩や拾翠よりも機転が利く。誰か一人を不利にする二対一よりも、自分一人だけがその機転の分で有利に戦える乱戦のほうが合理的だと考えたらしい。果たして、ここまでの戦いを最も有利に進めているのは彼である。
奇声をあげながら、蜜子が猪狩と拾翠の競り合いに乱入する。鋭い鋏の一撃は今度は拾翠に向けられている。ここまでの戦いから心得るものがあったのか、猪狩はすっと間合いを外す。
蜜子は拾翠の反撃を巧く捌き、小さな傷を負わせることに成功する。障害物が多く狭い戦場、そして息をつく間のない乱戦に、拾翠は巧く仮面から力を引き出すことが出来ず、苦戦を強いられていた。追い打ちをかけるように機体が大きく傾ぎ、体勢を崩しかけていた拾翠が更に大きくよろめいた。機敏に反応した光吾が左手から糸を繰り出す。
「まずは一人!」
「よし!今だ!!」
光吾の糸に全身を搦め捕られた拾翠に光吾が襲い掛かる。続いて猪狩も絶好のタイミングで床を蹴る。
しかし、拾翠を拘束していたはずの糸はいつの間にか全て解かれ、拾翠の右手に束となって握られていた。手の届く範囲であれば、それが自身を縛る拘束具であろうと拾翠の特殊能力は機能する。
「没収だ」
短く言い放ち、光吾に右のパンチを繰り出す。決定打を加える為とはいえ、やや無造作に仕掛けていた光吾はそれを躱しきる事が出来ない。
「ミツゴ君!」
「みっちゃん!」
光吾の口から二人の姉の警告が発せられるも、ひしゃげたアイアンロッドと一緒に光吾の体は後方へと吹っ飛ばされた。光吾の攻撃に合わせて絶好だった猪狩の殺到は、光吾に先んじて攻撃を成功させた拾翠に対しては半歩タイミングが遅い。ステップを踏みながら体を反転させて繰り出された拾翠の左の拳が下から猪狩の顔面を捉え、光吾とは反対方向へと弾き返した。
天井に叩きつけられた猪狩を拾翠の追撃が襲う。辛うじて捌かれた拾翠の蹴りは、ジャンボジェットの側壁から天井付近までをバッサリと切り裂いた。
動きやすいとは言えない機内を、三つの影が飛び違うように交差していた。それぞれが優先とする撃破対象を定めずに、咄嗟に状況を判断しながら攻撃を捌き合う乱戦である。
この状態を好んで作り出したのは、ミツコだった。三つの意識を持つ彼は、対戦相手である猪狩や拾翠よりも機転が利く。誰か一人を不利にする二対一よりも、自分一人だけがその機転の分で有利に戦える乱戦のほうが合理的だと考えたらしい。果たして、ここまでの戦いを最も有利に進めているのは彼である。
奇声をあげながら、蜜子が猪狩と拾翠の競り合いに乱入する。鋭い鋏の一撃は今度は拾翠に向けられている。ここまでの戦いから心得るものがあったのか、猪狩はすっと間合いを外す。
蜜子は拾翠の反撃を巧く捌き、小さな傷を負わせることに成功する。障害物が多く狭い戦場、そして息をつく間のない乱戦に、拾翠は巧く仮面から力を引き出すことが出来ず、苦戦を強いられていた。追い打ちをかけるように機体が大きく傾ぎ、体勢を崩しかけていた拾翠が更に大きくよろめいた。機敏に反応した光吾が左手から糸を繰り出す。
「まずは一人!」
「よし!今だ!!」
光吾の糸に全身を搦め捕られた拾翠に光吾が襲い掛かる。続いて猪狩も絶好のタイミングで床を蹴る。
しかし、拾翠を拘束していたはずの糸はいつの間にか全て解かれ、拾翠の右手に束となって握られていた。手の届く範囲であれば、それが自身を縛る拘束具であろうと拾翠の特殊能力は機能する。
「没収だ」
短く言い放ち、光吾に右のパンチを繰り出す。決定打を加える為とはいえ、やや無造作に仕掛けていた光吾はそれを躱しきる事が出来ない。
「ミツゴ君!」
「みっちゃん!」
光吾の口から二人の姉の警告が発せられるも、ひしゃげたアイアンロッドと一緒に光吾の体は後方へと吹っ飛ばされた。光吾の攻撃に合わせて絶好だった猪狩の殺到は、光吾に先んじて攻撃を成功させた拾翠に対しては半歩タイミングが遅い。ステップを踏みながら体を反転させて繰り出された拾翠の左の拳が下から猪狩の顔面を捉え、光吾とは反対方向へと弾き返した。
天井に叩きつけられた猪狩を拾翠の追撃が襲う。辛うじて捌かれた拾翠の蹴りは、ジャンボジェットの側壁から天井付近までをバッサリと切り裂いた。
機体が大きくその身を揺らし、穿たれた亀裂は、ギシギシと不穏な音を立てながら冷たい外気を猛然と吸い込みだす。
猪狩はすぐさま近くの座席に掴まり、体を安定させた。
拾翠もこれ以上の追撃は自重し、身を低くし冷気に備えている。
遥か風下では、致命傷は免れたらしい満子が肩を押さえていた。
拾翠もこれ以上の追撃は自重し、身を低くし冷気に備えている。
遥か風下では、致命傷は免れたらしい満子が肩を押さえていた。
その圧倒的なスケールから考えてあまりにも脆弱なジャンボジェットの外壁は、その亀裂から設計外の負荷を受け、少しずつ裂け始めていた。戦闘の衝撃によって、一気に限界を超えてしまう危険がある。目まぐるしく戦ってきた三人だが、ここに来て迂闊には動きが取れなくなった。
傷を負わされたものの、満子には主張がある。格闘以外の戦闘力を持たない猪狩と拾翠に対し、満子には機体にダメージを与えない農作業用劇物による攻撃手段がある。二人の、或いはどちらかの風上に立てれば、膠着を有利に打破できる。
拾翠にも成算があった。彼の金属の手足は他の二人に比べて冷気に強い。睨み合いが続けば有利になる。しかし、機体の損傷を考えると仮面の力はより一層使いづらくなった。
猪狩もまた、この状況を自分の優位に結び付けられないかを考えていた。少なくとも、今風上に立っているのは自分だ。分が悪いはずがない。
何より、猪狩は「たとえ飛行機が落ちても自分だけは死なずに助かる」と半ば本気で信じている人種である。拾翠やミツコに比べて、機体の損傷への遠慮があまりない。
ふと、その時。猪狩は自分の身体に強い力が流れ込んでくるのを感じた。すぐさま、園長とマサのことを思い出した。
二人は試合の直前、マサの運転する車でどんぐりの家に向かっている途中の事故により、意識不明の重傷を負っていた。その二人の力を借りて、猪狩はこの試合を戦ってきた。
誰よりも猪狩を応援してくれていた園長。そして、誰よりもどんぐりの家の子供たちのことを案じてくれていたマサ。そのどちらかが、たった今死んだのだ。
「この感覚は……園長!?」
胸の底から溢れてくるものをこらえきれず、猪狩は一筋の涙を流した。
「泣いていらっしゃるの?」
怪訝そうに満子が首をかしげる。
どんぐりの家の子供たちにとってそうであったように、猪狩にとっても園長は父親同然だった。
「あなたが居なくなったら、俺は……子供たちは、この先いったいどうすれば……」
悲しみ、途方に暮れる猪狩だが、全身に漲る熱が、吹き付ける冷気を遥かに上回ってゆく。
猪狩の瞳が強い色に変わる。そう、今は明日を憂いている時ではない。今こそは戦うべき時。
「この、託された力で!!」
より近い拾翠に狙いを決め、猪狩は最大限の力で踏み切った。間近で大きな衝撃を受けた亀裂は悲鳴を上げ、いよいよ機体が反りかえり始める。
一直線。あまりに無謀に映る猪狩の突進は、あっさりと拾翠の左のカウンターで咎められた。続けざまに右の打ち下ろしが猪狩の側頭に突き刺さる。しかし――
「その程度か?」
「――っ!!」
猪狩は拾翠の頭を掴むと、前方の床に目いっぱい叩きつけた。激しく機体を揺らしながら、拾翠の体は満子の更に風下へと床を転がってゆく。
「これもお持ちになって?」
狙っていた好機、すかさず満子は薬品瓶を拾翠に投げつけた。目と鼻を襲う激痛に拾翠は呻き顔を覆う。その隙を見逃さず、風下へ流され弱くなった薬品の残り香の中を猪狩が走り抜ける。満子は敢えて猪狩に先を譲り、背後から二人を狙う形を作る。
拾翠の掌底と猪狩の拳が交差する。猪狩の拳は拾翠の頬をかすめて空を切り、拾翠の掌は猪狩の顔面を的確に捉えているものの、ほとんどダメージを与えることが出来ていない。
「園長!俺に最後の力を!!」
そう叫び、再び拳に活を入れようとした刹那、猪狩を奇妙な脱力感が襲う。
「ち、力が……!園長が俺に与えてくれた力が消えていく!?」
目の前で露わになっている拾翠の素顔に、猪狩の目は戦慄に見開かれた。そういえば、さっきの掌底は感触がおかしかった。
光吾の拘束糸を取り払ったように、拾翠の能力は自分自身を対象にしても発動する。そして、手錠や足枷などの物理的な拘束は勿論、魔人能力によって固定され本来なら外すことが出来ない仮面すらも、その手が届く範囲であれば奪うことが出来た。
猪狩の顔には拾翠の顔から剥がされた仮面が着けられていた。猪狩の特殊能力「All for one」は同じ身体強化系能力である仮面に上書きされて、その効果を失った。
「くっ、そんな手が!?」
不利を察した猪狩は、距離をとろうと飛び退く。1歩、そして2歩――。
拾翠にも成算があった。彼の金属の手足は他の二人に比べて冷気に強い。睨み合いが続けば有利になる。しかし、機体の損傷を考えると仮面の力はより一層使いづらくなった。
猪狩もまた、この状況を自分の優位に結び付けられないかを考えていた。少なくとも、今風上に立っているのは自分だ。分が悪いはずがない。
何より、猪狩は「たとえ飛行機が落ちても自分だけは死なずに助かる」と半ば本気で信じている人種である。拾翠やミツコに比べて、機体の損傷への遠慮があまりない。
ふと、その時。猪狩は自分の身体に強い力が流れ込んでくるのを感じた。すぐさま、園長とマサのことを思い出した。
二人は試合の直前、マサの運転する車でどんぐりの家に向かっている途中の事故により、意識不明の重傷を負っていた。その二人の力を借りて、猪狩はこの試合を戦ってきた。
誰よりも猪狩を応援してくれていた園長。そして、誰よりもどんぐりの家の子供たちのことを案じてくれていたマサ。そのどちらかが、たった今死んだのだ。
「この感覚は……園長!?」
胸の底から溢れてくるものをこらえきれず、猪狩は一筋の涙を流した。
「泣いていらっしゃるの?」
怪訝そうに満子が首をかしげる。
どんぐりの家の子供たちにとってそうであったように、猪狩にとっても園長は父親同然だった。
「あなたが居なくなったら、俺は……子供たちは、この先いったいどうすれば……」
悲しみ、途方に暮れる猪狩だが、全身に漲る熱が、吹き付ける冷気を遥かに上回ってゆく。
猪狩の瞳が強い色に変わる。そう、今は明日を憂いている時ではない。今こそは戦うべき時。
「この、託された力で!!」
より近い拾翠に狙いを決め、猪狩は最大限の力で踏み切った。間近で大きな衝撃を受けた亀裂は悲鳴を上げ、いよいよ機体が反りかえり始める。
一直線。あまりに無謀に映る猪狩の突進は、あっさりと拾翠の左のカウンターで咎められた。続けざまに右の打ち下ろしが猪狩の側頭に突き刺さる。しかし――
「その程度か?」
「――っ!!」
猪狩は拾翠の頭を掴むと、前方の床に目いっぱい叩きつけた。激しく機体を揺らしながら、拾翠の体は満子の更に風下へと床を転がってゆく。
「これもお持ちになって?」
狙っていた好機、すかさず満子は薬品瓶を拾翠に投げつけた。目と鼻を襲う激痛に拾翠は呻き顔を覆う。その隙を見逃さず、風下へ流され弱くなった薬品の残り香の中を猪狩が走り抜ける。満子は敢えて猪狩に先を譲り、背後から二人を狙う形を作る。
拾翠の掌底と猪狩の拳が交差する。猪狩の拳は拾翠の頬をかすめて空を切り、拾翠の掌は猪狩の顔面を的確に捉えているものの、ほとんどダメージを与えることが出来ていない。
「園長!俺に最後の力を!!」
そう叫び、再び拳に活を入れようとした刹那、猪狩を奇妙な脱力感が襲う。
「ち、力が……!園長が俺に与えてくれた力が消えていく!?」
目の前で露わになっている拾翠の素顔に、猪狩の目は戦慄に見開かれた。そういえば、さっきの掌底は感触がおかしかった。
光吾の拘束糸を取り払ったように、拾翠の能力は自分自身を対象にしても発動する。そして、手錠や足枷などの物理的な拘束は勿論、魔人能力によって固定され本来なら外すことが出来ない仮面すらも、その手が届く範囲であれば奪うことが出来た。
猪狩の顔には拾翠の顔から剥がされた仮面が着けられていた。猪狩の特殊能力「All for one」は同じ身体強化系能力である仮面に上書きされて、その効果を失った。
「くっ、そんな手が!?」
不利を察した猪狩は、距離をとろうと飛び退く。1歩、そして2歩――。
猪狩の体は天井を突き破り、飛行機の上空に投げ出されていた。首から上が、不自然な方向に曲がっている。
「え……?」
仮面の力は精妙な加減を要諦とする。体の動きに合わせて激しくON、OFFが切り替わる仮面の力は、その感覚に慣れないうちは、体を意図せぬ方向へ跳ね飛ばしてしまう。仮面の力を完璧にコントロールできるのは仮面自身である冷泉を除けば拾翠ただ一人だけである。
「う、うわぁあああああああ!!!」
遮るもののない風に煽られながら、それでも猪狩は後方に飛ばされまいと外壁の突起にしがみついた。
「嫌だ!俺は、負けたくない!こんなところで、負けるわけにはいかないんだ!!」
必死にもがき、叫ぶ猪狩の顔を、冷気が容赦なく叩く。
「まゆ!めい!ま、まさる!!うわぁあああああああ!!」
「え……?」
仮面の力は精妙な加減を要諦とする。体の動きに合わせて激しくON、OFFが切り替わる仮面の力は、その感覚に慣れないうちは、体を意図せぬ方向へ跳ね飛ばしてしまう。仮面の力を完璧にコントロールできるのは仮面自身である冷泉を除けば拾翠ただ一人だけである。
「う、うわぁあああああああ!!!」
遮るもののない風に煽られながら、それでも猪狩は後方に飛ばされまいと外壁の突起にしがみついた。
「嫌だ!俺は、負けたくない!こんなところで、負けるわけにはいかないんだ!!」
必死にもがき、叫ぶ猪狩の顔を、冷気が容赦なく叩く。
「まゆ!めい!ま、まさる!!うわぁあああああああ!!」
外から聞こえる猪狩の悲痛な叫び声に、拾翠は苦々しく顔をしかめた。
二人の接触に異変を感じ、後方に自重していた満子が拾翠の素顔に感嘆の声をあげた。
「あら、ずいぶんハンサムでいらっしゃるのね?」
仮面の下から覗く半分だけでも十分すぎるほどだった拾翠の美貌は、その全貌が晒されたことで更に際立っている。
「……続けるのか?」
敢えて降参を促した。猪狩を倒す為に仮面は手放したが、武器による戦闘がメインの、ましてや傷を負ったミツコは拾翠にとってあまりに与しやすい相手だ。
「確かに、僕たちにとってあなたは相性が良い相手とは言えないかもしれないけど」
いつの間にか猪狩の声は聞こえなくなっていた。死んだか。拾翠はそう思った。
「だからってさぁー!ひぃー、まいりましたぁ。なんて!言うわけねぇだろォー!?」
蜜子が武器を抜き放ったその瞬間、彼の首筋からは四本の『茎』のようなものが生えていた。
蜜子に向けてまっすぐ向けられた拾翠の左腕の先から4筋の煙が立ちのぼっている。
「迂闊だな。仕掛けのない義手なんてあると思ったか?」
「が……ごぼっ」
血の泡を吹きながら、2歩、3歩と拾翠に近づき、ミツコは床に崩れ落ちた。
まだ息がある。トドメを刺すべきか逡巡する拾翠の背後で、メキメキと何かが剥がれる音がした。いよいよ、機体のダメージが全体に伝播しだしたか?そう思って振り返った拾翠の視線の先で、天井から大きな塊が床に落下した。――猪狩だ。
「馬鹿な……!」
拾翠の狼狽をよそに、半分だけが露わになった猪狩の顔は穏やかな微笑みを浮かべていた。
気が付けば、猪狩の身体は拾翠の脇をすり抜け、ミツコの傍らに立っていた。猪狩はミツコの身体をひょいと持ち上げて外へ投げ捨てた。
二人の接触に異変を感じ、後方に自重していた満子が拾翠の素顔に感嘆の声をあげた。
「あら、ずいぶんハンサムでいらっしゃるのね?」
仮面の下から覗く半分だけでも十分すぎるほどだった拾翠の美貌は、その全貌が晒されたことで更に際立っている。
「……続けるのか?」
敢えて降参を促した。猪狩を倒す為に仮面は手放したが、武器による戦闘がメインの、ましてや傷を負ったミツコは拾翠にとってあまりに与しやすい相手だ。
「確かに、僕たちにとってあなたは相性が良い相手とは言えないかもしれないけど」
いつの間にか猪狩の声は聞こえなくなっていた。死んだか。拾翠はそう思った。
「だからってさぁー!ひぃー、まいりましたぁ。なんて!言うわけねぇだろォー!?」
蜜子が武器を抜き放ったその瞬間、彼の首筋からは四本の『茎』のようなものが生えていた。
蜜子に向けてまっすぐ向けられた拾翠の左腕の先から4筋の煙が立ちのぼっている。
「迂闊だな。仕掛けのない義手なんてあると思ったか?」
「が……ごぼっ」
血の泡を吹きながら、2歩、3歩と拾翠に近づき、ミツコは床に崩れ落ちた。
まだ息がある。トドメを刺すべきか逡巡する拾翠の背後で、メキメキと何かが剥がれる音がした。いよいよ、機体のダメージが全体に伝播しだしたか?そう思って振り返った拾翠の視線の先で、天井から大きな塊が床に落下した。――猪狩だ。
「馬鹿な……!」
拾翠の狼狽をよそに、半分だけが露わになった猪狩の顔は穏やかな微笑みを浮かべていた。
気が付けば、猪狩の身体は拾翠の脇をすり抜け、ミツコの傍らに立っていた。猪狩はミツコの身体をひょいと持ち上げて外へ投げ捨てた。
誤算だった。拾翠が自身を対象に能力を使用できるように、猪狩も自身を能力の「リソース」に使うことが出来たのだ。その力は他者を生贄にした時の比ではない。
相変わらず、猪狩は穏やかな表情を浮かべている。そのあまりにも不気味な静謐に、拾翠は思わず飛びずさった。
その瞬間、鼻先を掠めた手刀に、拾翠は総毛だった。
――もし、あのままそこに立ち続けていたとしたら……?
寸で命を落としかけた拾翠は反射的に、更に後ろへと飛び退いた。
床に転がる自分の頭の上半分を想像し、早くなった鼓動がすべての息を吐き出せと肺を圧迫する。しかし、胸と喉を押しつぶす緊張は、逆に拾翠に開き直りのような冷静さも与えた。
拾翠は両手首をすり合わせるような仕草で構えを取る。金属が擦れるような音を立てて、ミツコに向けて射出された指の残骸が4本の短い薄刃型の鉤爪に換装された。
カラードネイル(血染めの爪)。数ある仕込みの中で接近戦最強の攻撃力を誇る切り札である。
その瞬間、鼻先を掠めた手刀に、拾翠は総毛だった。
――もし、あのままそこに立ち続けていたとしたら……?
寸で命を落としかけた拾翠は反射的に、更に後ろへと飛び退いた。
床に転がる自分の頭の上半分を想像し、早くなった鼓動がすべての息を吐き出せと肺を圧迫する。しかし、胸と喉を押しつぶす緊張は、逆に拾翠に開き直りのような冷静さも与えた。
拾翠は両手首をすり合わせるような仕草で構えを取る。金属が擦れるような音を立てて、ミツコに向けて射出された指の残骸が4本の短い薄刃型の鉤爪に換装された。
カラードネイル(血染めの爪)。数ある仕込みの中で接近戦最強の攻撃力を誇る切り札である。
三度、猪狩の体が床の上を滑る。それは仮面の力が発動して「All for one」が打ち消されるのを回避するための動き、いわば非常手段。錯覚で目には速く映るが、実際の速度はそれほどでもない。
既に三度それを見た拾翠は、仮面の力を使いこなすために鍛え上げた反射神経で先手を奪う。
猪狩はその動きが制限されているにも関わらず、二度、三度と繰り出された鉤爪を躱して見せると、虫でも追い払うように腕を振った。猪狩にとって攻撃ですらないその動作は拾翠を大きく後ろにのけぞらせ、後退を強いる。
素早く体を立て直した拾翠は、鉤爪の射程に入ろうと距離を詰めると見せ、その場から腕を振るった。上腕が蛇腹状に伸び、間合いの外から攻撃を届かせる。仕留めた!確信をもって繰り出された意表の一撃だったが、猪狩は喉元数ミリでその鉤爪を手刀で払いのけた。破壊された掌が破片となって飛び散り、鉤爪が床に突き刺さる。
拾翠は僅か数秒、数度の攻防で、自分の技が何一つ通用しないのだと思い知らされた。
絶望感が、鉛のような重さで全身に圧し掛かってくる。せめて、仮面の力が使えたならば――。
「仮面」。その言葉を頭に思い浮かべた瞬間、拾翠は背中に走る悪寒に震え上がった。
猪狩は既に死んでいる。その意識は既にこの世にはない。
それが何を意味するのか。拾翠は奥歯をかみしめた。
「裏切ったか……冷泉!」
既に三度それを見た拾翠は、仮面の力を使いこなすために鍛え上げた反射神経で先手を奪う。
猪狩はその動きが制限されているにも関わらず、二度、三度と繰り出された鉤爪を躱して見せると、虫でも追い払うように腕を振った。猪狩にとって攻撃ですらないその動作は拾翠を大きく後ろにのけぞらせ、後退を強いる。
素早く体を立て直した拾翠は、鉤爪の射程に入ろうと距離を詰めると見せ、その場から腕を振るった。上腕が蛇腹状に伸び、間合いの外から攻撃を届かせる。仕留めた!確信をもって繰り出された意表の一撃だったが、猪狩は喉元数ミリでその鉤爪を手刀で払いのけた。破壊された掌が破片となって飛び散り、鉤爪が床に突き刺さる。
拾翠は僅か数秒、数度の攻防で、自分の技が何一つ通用しないのだと思い知らされた。
絶望感が、鉛のような重さで全身に圧し掛かってくる。せめて、仮面の力が使えたならば――。
「仮面」。その言葉を頭に思い浮かべた瞬間、拾翠は背中に走る悪寒に震え上がった。
猪狩は既に死んでいる。その意識は既にこの世にはない。
それが何を意味するのか。拾翠は奥歯をかみしめた。
「裏切ったか……冷泉!」
機体がひときわ大きく揺れ、二人は咄嗟に近くの座席を掴んだ。キィキィと悲鳴をあげながら揺れは更に大きくなり、遂に機体の耐久は限界を迎える。
つんのめるような衝撃が走り、機体がぐしゃりと二つに割れた。
つんのめるような衝撃が走り、機体がぐしゃりと二つに割れた。
ヒダのついた急斜面を滑り落ちるように細かく身を震わせながら、飛行機は地面へと速度を上げてゆく。
拾翠は大きく傾いた機体の下方で、同じように座席に掴まり体を安定させている猪狩を、冷泉を見た。
二人の実力は、攻撃を当てることはおろか、体勢を崩す事すらできない程に隔たっている。それでももし、冷泉に攻撃を当てられるとしたら、今この瞬間こそが最大にして最後のチャンスだった。
だが、拾翠の身体は動かなくなっていた。
拾翠は大きく傾いた機体の下方で、同じように座席に掴まり体を安定させている猪狩を、冷泉を見た。
二人の実力は、攻撃を当てることはおろか、体勢を崩す事すらできない程に隔たっている。それでももし、冷泉に攻撃を当てられるとしたら、今この瞬間こそが最大にして最後のチャンスだった。
だが、拾翠の身体は動かなくなっていた。
――怖い。
全身を締め付ける加速度が心拍数を押し上げてゆく。
奥歯が音をたてて震えることを、止めることが出来ずにいた。
乱暴なスピードで、自分の身体が死に向かって運ばれている。それが恐ろしかった。
走馬灯ではないが、拾翠は仮面を手にした日のことを思い出す。
全身を締め付ける加速度が心拍数を押し上げてゆく。
奥歯が音をたてて震えることを、止めることが出来ずにいた。
乱暴なスピードで、自分の身体が死に向かって運ばれている。それが恐ろしかった。
走馬灯ではないが、拾翠は仮面を手にした日のことを思い出す。
(冷泉。お前に嘘をついていた)
(俺は、自分の意思でお前を手に取り)
(自分の意思でお前を被ったのさ)
(何も考えられなかった。なぜなら……)
(なぜなら、お前は美しかった)
(俺は、自分の意思でお前を手に取り)
(自分の意思でお前を被ったのさ)
(何も考えられなかった。なぜなら……)
(なぜなら、お前は美しかった)
(そう、この震えは、初めてお前に手を伸ばしたあの時と同じ)
体を縛っていた迷いが解けてゆく。恐怖が去ったわけではない。それでも、腕は、脚はもう一度動いてくれるようだった。
拾翠は飛び降りるように、斜めになった床を蹴った。厚い空気の壁が彼を押し返そうとする。
だからもう一度、蹴る。もっと強く、届くように強く。
互いに差し伸べあった手を取り違うかのように、二人の腕が交差する。
冷泉の腕は拾翠の身体の中心から肩口までを深く切り裂いた。
紅い血の滴がぱらぱらと散る。
仮面を奪い取ろうと突き立てられた拾翠の指は、それを果たすことが出来なかった。
拾翠の能力はその射程の短さから強い強制力をもつ。しかし、対象の生命維持を脅かすものは奪うことが出来ない。
今の猪狩を生かすのは、脳でも心臓でも、血液ですらなく、仮面だった。
拾翠は飛び降りるように、斜めになった床を蹴った。厚い空気の壁が彼を押し返そうとする。
だからもう一度、蹴る。もっと強く、届くように強く。
互いに差し伸べあった手を取り違うかのように、二人の腕が交差する。
冷泉の腕は拾翠の身体の中心から肩口までを深く切り裂いた。
紅い血の滴がぱらぱらと散る。
仮面を奪い取ろうと突き立てられた拾翠の指は、それを果たすことが出来なかった。
拾翠の能力はその射程の短さから強い強制力をもつ。しかし、対象の生命維持を脅かすものは奪うことが出来ない。
今の猪狩を生かすのは、脳でも心臓でも、血液ですらなく、仮面だった。
(夕霧、あなたは知らない)
(私はあの時、あなたの心を完全に隠すことが出来たのに)
(自らを二つに裂いてまで、あなたを半分隠すにとどめた)
(強く、まっすぐに立っているようで)
(戸惑い、迷うあなたの弱さに寄り添いたいと思ったから)
(でも、私は仮面。隠すことこそが世に在る喜び)
(あなたを隠せない私ならせめて、あなたを殺して、あなたを隠す)
(私はあの時、あなたの心を完全に隠すことが出来たのに)
(自らを二つに裂いてまで、あなたを半分隠すにとどめた)
(強く、まっすぐに立っているようで)
(戸惑い、迷うあなたの弱さに寄り添いたいと思ったから)
(でも、私は仮面。隠すことこそが世に在る喜び)
(あなたを隠せない私ならせめて、あなたを殺して、あなたを隠す)
――六月四日 拾翠亭
色とりどりの花が咲く池に木造の橋がかかっている。
拾翠がどこからか仕入れて来た資金と伝手で復旧した庭園である。
庭園の西側には二階建ての木造住宅が、やはり彼の手に依って復元されている。拾翠亭と呼ばれるその建物のたたずまいを、彼はとても気にいり、偽名に使っている。
拾翠がどこからか仕入れて来た資金と伝手で復旧した庭園である。
庭園の西側には二階建ての木造住宅が、やはり彼の手に依って復元されている。拾翠亭と呼ばれるその建物のたたずまいを、彼はとても気にいり、偽名に使っている。
縁側に座り、庭園を眺めながら拾翠は心を落ち着かせた。
禅と呼べるような大層なものではない。ただ、うとうとと意識を緩めているだけである。そうやって仮面の意識に語りかけようとしていた。
禅と呼べるような大層なものではない。ただ、うとうとと意識を緩めているだけである。そうやって仮面の意識に語りかけようとしていた。
「……冷泉。応えろ、冷泉」
意識の中を夕霧の声が波紋のように伝わってゆく。
不意にその円の端が別の波に触れた。
「あなたはもう、私と話をするつもりは無いのだと思っていましたよ、夕霧」
冷泉の少しつっかかるような態度を夕霧は無視した。
「お前に確認したい事がある」
「ええ、どうぞ」
「このあいだの試合、俺は確かに殺された」
「はい?」
「しかし、記録では俺は殺されるどころか、試合の勝者となっている」
「私の記憶でもそうなっていますが」
「だが、俺は自分の断末魔を、覚えている」
「不思議だこと。で、私の考えを聞きたいと?」
「冷泉、俺はいったいどうなってしまったのだろう」
あなたは、意外と甘えん坊ですね――。冷泉はそう言いかけてやめた。
短い沈黙ののち、冷泉から返された言葉は意外なものだった。
「夕霧、あなたは神さまを信じますか?」
「神さま……?あまりピンと来ないな」
夕霧は海賊を辞めて暫くの間、高野山で密教に匿われて隠遁生活を送っている。しかし、それはそれとして、神仏問わず宗教に対する関心は非常に低い。
「じゃあ、この世界には一定のルールが存在しますよね。たとえば気まぐれに今日が昨日より長くなったりはしないでしょう?」
「認める」
「夕霧、あなたはルールの境目をまたいでしまったのだと思います」
予想していなかった冷泉の言葉に夕霧の思考は追いつけずにいた。それをわかってか、冷泉は間を取りながら、ゆっくりと話す。
「たとえば、あなたが漂流者だった世界のルールと、この世界のルールは違うものなのかもしれません」
「或いは、あなたが海賊だった世界もまた、この世界のそれとは別の誰かが作ったルールが存在していたのでしょう」
「あなたはいつの間にか、それぞれ異なるルールが支配する世界と世界の境界を越えてしまったのでしょう」
「異なる世界のルールから生まれ、この世界のルールから外れた存在。極端に強くあり、或いは弱く居る事も出来る」
「そのような異端の存在を、あなたも知っているでしょう、夕霧。『転校生』と呼ぶんですよ」
「俺が、転校生だと?」
「実際には転校生の成り損ないといったところなのでしょうね」
「心しておきなさいね、夕霧。あなたの存在は複数の世界のルールの干渉を受け、ぶれて重なり不安定になっています」
「俺が、俺ではいられなくなる。そう言いたいのか?」
「或いは、突然にふっと消えて無くなってしまうかも。そして、それは私も同じです。夕霧」
意識の中を夕霧の声が波紋のように伝わってゆく。
不意にその円の端が別の波に触れた。
「あなたはもう、私と話をするつもりは無いのだと思っていましたよ、夕霧」
冷泉の少しつっかかるような態度を夕霧は無視した。
「お前に確認したい事がある」
「ええ、どうぞ」
「このあいだの試合、俺は確かに殺された」
「はい?」
「しかし、記録では俺は殺されるどころか、試合の勝者となっている」
「私の記憶でもそうなっていますが」
「だが、俺は自分の断末魔を、覚えている」
「不思議だこと。で、私の考えを聞きたいと?」
「冷泉、俺はいったいどうなってしまったのだろう」
あなたは、意外と甘えん坊ですね――。冷泉はそう言いかけてやめた。
短い沈黙ののち、冷泉から返された言葉は意外なものだった。
「夕霧、あなたは神さまを信じますか?」
「神さま……?あまりピンと来ないな」
夕霧は海賊を辞めて暫くの間、高野山で密教に匿われて隠遁生活を送っている。しかし、それはそれとして、神仏問わず宗教に対する関心は非常に低い。
「じゃあ、この世界には一定のルールが存在しますよね。たとえば気まぐれに今日が昨日より長くなったりはしないでしょう?」
「認める」
「夕霧、あなたはルールの境目をまたいでしまったのだと思います」
予想していなかった冷泉の言葉に夕霧の思考は追いつけずにいた。それをわかってか、冷泉は間を取りながら、ゆっくりと話す。
「たとえば、あなたが漂流者だった世界のルールと、この世界のルールは違うものなのかもしれません」
「或いは、あなたが海賊だった世界もまた、この世界のそれとは別の誰かが作ったルールが存在していたのでしょう」
「あなたはいつの間にか、それぞれ異なるルールが支配する世界と世界の境界を越えてしまったのでしょう」
「異なる世界のルールから生まれ、この世界のルールから外れた存在。極端に強くあり、或いは弱く居る事も出来る」
「そのような異端の存在を、あなたも知っているでしょう、夕霧。『転校生』と呼ぶんですよ」
「俺が、転校生だと?」
「実際には転校生の成り損ないといったところなのでしょうね」
「心しておきなさいね、夕霧。あなたの存在は複数の世界のルールの干渉を受け、ぶれて重なり不安定になっています」
「俺が、俺ではいられなくなる。そう言いたいのか?」
「或いは、突然にふっと消えて無くなってしまうかも。そして、それは私も同じです。夕霧」
冷泉はそれっきり何もしゃべらなかった。
夕霧の意識は覚醒へと向かい、ゆっくりと閉じていた瞳が開かれた。
サラサラと草木が風に揺れ、チラチラと水面は赤く夕陽に輝いている。
夕霧は冷泉がその体を支配している時と同じように、ぼんやりとそれを眺め続けていた。
夕霧の意識は覚醒へと向かい、ゆっくりと閉じていた瞳が開かれた。
サラサラと草木が風に揺れ、チラチラと水面は赤く夕陽に輝いている。
夕霧は冷泉がその体を支配している時と同じように、ぼんやりとそれを眺め続けていた。
――六月二日 墜ちる飛行機の中で
仮面にかけられた拾翠の手に、猪狩の、冷泉の手が重ねられた。
氷よりも冷たい金属の手が、その指を紅く焼く。
拾翠の意識が少しずつ遠ざかっていくのが分かる。
いつもなら、聞こえてくるはずの夕霧が冷泉を呼ぶ声が、今は聞こえない。
氷よりも冷たい金属の手が、その指を紅く焼く。
拾翠の意識が少しずつ遠ざかっていくのが分かる。
いつもなら、聞こえてくるはずの夕霧が冷泉を呼ぶ声が、今は聞こえない。
(冷泉、お前を手に取った時、俺は何も考えられなくなっていた)
(お前は美しかった)
(だから俺はいつの日か、お前を元の姿に戻したかったんだ)
(例えばお前が)
(俺を裏切ったとしても)
(お前は美しかった)
(だから俺はいつの日か、お前を元の姿に戻したかったんだ)
(例えばお前が)
(俺を裏切ったとしても)
仮面に触れた拾翠の指に、ほんの少しだけ強く力が籠められたように感じた。
(未練ですか、夕霧?)
冷泉の指が、初めて戸惑うように小さく震えた。
(ええ、そう……。私もです)
どちらの指に籠められた力だったのか。霜をふむような音をたて、仮面が顔の表面ごと猪狩の顔から引きはがされた。
(未練ですか、夕霧?)
冷泉の指が、初めて戸惑うように小さく震えた。
(ええ、そう……。私もです)
どちらの指に籠められた力だったのか。霜をふむような音をたて、仮面が顔の表面ごと猪狩の顔から引きはがされた。
死体に戻った猪狩の身体は、飛行機の振動に翻弄されながら、ずるずると床の上を這っている。
粗末に成り果てた座席の上で、冷泉は自らが付けた傷の痛みに浸っていた。
粗末に成り果てた座席の上で、冷泉は自らが付けた傷の痛みに浸っていた。
※補足:冷泉院=転校生もどき
冷泉院は特殊能力ガイドラインやBLダンゲロスのノリをSSキャンペーンに持ち込んでいるので、トリニティの能力をガイドラインで分析したり、夕霧として冷泉を落とそうとしたりします(冷泉は無性だけど)。拾翠が転校生並みに強いという意味ではありません。
冷泉院は特殊能力ガイドラインやBLダンゲロスのノリをSSキャンペーンに持ち込んでいるので、トリニティの能力をガイドラインで分析したり、夕霧として冷泉を落とそうとしたりします(冷泉は無性だけど)。拾翠が転校生並みに強いという意味ではありません。