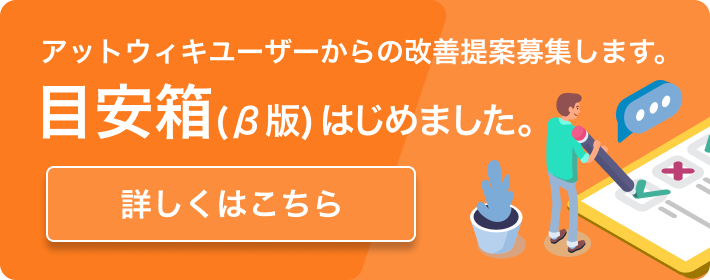白王みずきSS(決勝)
最終更新:
dangerousss
-
view
決勝 白王みずき
| 名前 | 性 | 魔人能力 |
| 白王みずき | 女 | みずのはごろも |
| 伝説の勇者ミド | 女 | おもいだす |
採用する幕間SS
『どうしてみずきちゃんは転校生化の条件なんか知ってるの?』
(「図書館の男」に関する野試合が非公開になったそうです。)
『白王みずき 幕間SS みかどエンペラー』
(一∞に眼鏡を貰いました。みずきは氷穴に向け準備万端です。みずきは新たなる誓いを胸に秘めました。みずきはホーネットと戦いました。みかどは変態を狩っています。えーと他なにがあるかな……。)
『どうしてみずきちゃんは転校生化の条件なんか知ってるの?』
(「図書館の男」に関する野試合が非公開になったそうです。)
『白王みずき 幕間SS みかどエンペラー』
(一∞に眼鏡を貰いました。みずきは氷穴に向け準備万端です。みずきは新たなる誓いを胸に秘めました。みずきはホーネットと戦いました。みかどは変態を狩っています。えーと他なにがあるかな……。)
試合内容
「――わっ! 寒いっ!」
決勝戦の舞台たる【氷穴】MAPへと降り立ち、反射的に声が漏れてしまう。
希望崎学園の“秩序の守護者”たる風紀委員・白王みずきである。
吐く息の白さが、周囲の気温を実際以上に厳しいものとして感覚野に意識させた。
希望崎学園の“秩序の守護者”たる風紀委員・白王みずきである。
吐く息の白さが、周囲の気温を実際以上に厳しいものとして感覚野に意識させた。
「でも、しっかり対策して来ましたからね……! これくらい、へっちゃらです!」
そうひとりごちて、暖かそうなミトンに包まれた両手をギュッと握る。
みずきの能力『みずのはごろも』によって生成されたコートやマフラー、耳当て、ミトン等の防寒具は、この冷徹な環境を生き抜く暖かさを彼女にもたらしていた。
それらよりなにより、今の少女の胸には熱き闘志が漲っている――!
みずきの能力『みずのはごろも』によって生成されたコートやマフラー、耳当て、ミトン等の防寒具は、この冷徹な環境を生き抜く暖かさを彼女にもたらしていた。
それらよりなにより、今の少女の胸には熱き闘志が漲っている――!
「いざ、尋常に勝負です! 渡葉――……さん? せんぱい? あれっ?
学年……ええと……。ど、どうお呼びすればいいんでしょう……。
――ええいっ、伝説の勇者ミドさん! 首を洗って待っていてくださいっ!!」
学年……ええと……。ど、どうお呼びすればいいんでしょう……。
――ええいっ、伝説の勇者ミドさん! 首を洗って待っていてくださいっ!!」
「――っくしゅんっ!」
大きなくしゃみの音が氷穴の内部にこだまする。
希望崎学園の“秩序の破壊者”たるビッチ・渡葉美土こと伝説の勇者ミドである。
少女はぶるりと身体を震わせ、気だるげに言葉を発する。
希望崎学園の“秩序の破壊者”たるビッチ・渡葉美土こと伝説の勇者ミドである。
少女はぶるりと身体を震わせ、気だるげに言葉を発する。
「あっつい【製鉄所】の次が、さっむい【氷穴】って……。運営なに考えてんのよ。
しかもこんなに寒くちゃ、えろい気分にもなりゃしないって……あーっくしゅんっ!」
しかもこんなに寒くちゃ、えろい気分にもなりゃしないって……あーっくしゅんっ!」
ハァ……、と溜め息をつくミド。周囲の気温の如く、なんだかテンション低めである。
その姿は、いつも通りの着崩した制服姿。天下御免のビッチたる彼女にとって、例え【氷穴】に向かうことになったとて厚着など以ての外であった。
ところが、対戦相手は白王みずき。折角薄着で迎えても、一回戦の練道や準決勝の真野のような、熱く、激しいプレイは期待できそうにない。テンションも低くなろう。
その姿は、いつも通りの着崩した制服姿。天下御免のビッチたる彼女にとって、例え【氷穴】に向かうことになったとて厚着など以ての外であった。
ところが、対戦相手は白王みずき。折角薄着で迎えても、一回戦の練道や準決勝の真野のような、熱く、激しいプレイは期待できそうにない。テンションも低くなろう。
「まあ、それでも。ここを制せば優勝賞金げっと……! やるっきゃないわね!
そんじゃ、いつもどおり――『おもいだす』っ!!」
そんじゃ、いつもどおり――『おもいだす』っ!!」
『SNOW-SNOWトーナメントオブ女神オブトーナメント ~「第一回結昨日の使いやあらへんで!チキチキ秋の大トーナメント」~』決勝戦。
白王みずき VS 伝説の勇者ミド。
――試合、開始である。
白王みずき VS 伝説の勇者ミド。
――試合、開始である。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
都内、某所。時刻は朝のラッシュアワー。
通勤に通学にと慌ただしく流れる人の波が、不自然な程ぱっくりと開かれてゆく。
まるでモーセの『十戒』の如くに割れた人波は、“その者”の進行を妨げない。
道を開けし人々の視線の注がれる先には――悠々と闊歩する、大山を思わせる人影。
通勤に通学にと慌ただしく流れる人の波が、不自然な程ぱっくりと開かれてゆく。
まるでモーセの『十戒』の如くに割れた人波は、“その者”の進行を妨げない。
道を開けし人々の視線の注がれる先には――悠々と闊歩する、大山を思わせる人影。
「ふむ……。今日は道が空いているな……」
関脇・股ノ海である。求道者は、駅へと続く道を征く。
土俵の外でもまわし一丁で過ごす彼は、普段稽古場へ赴くにも当然上裸である。
さらには、「闊歩」とは言え、足並みはすり足である。コンクリートの道の上で。
――日々是鍛錬。そこには、日常の所作に潜む弛まぬ研鑽が窺えた。
土俵の外でもまわし一丁で過ごす彼は、普段稽古場へ赴くにも当然上裸である。
さらには、「闊歩」とは言え、足並みはすり足である。コンクリートの道の上で。
――日々是鍛錬。そこには、日常の所作に潜む弛まぬ研鑽が窺えた。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
試合開始から半刻程が経過した。
足元がつるつると滑る入り組んだ道を、みずきはそろりそろりと進んでいる。
足元がつるつると滑る入り組んだ道を、みずきはそろりそろりと進んでいる。
「足元が怖いですね……。こんなことなら、ブーツも“着替え”ておくべきでした」
白王みずきの能力『みずのはごろも』で生成できる物体の範囲は、実は意外に広い。
『身に纏う物』という制限があるにしろ、その範囲については存外緩めに『認識』されており、例えば一回戦で生成した野球のスパイクなど、『履物』も生成可能である。
出来たはずのことをやりはぐった。会敵前にして、ひとつのミスが浮き彫りとなった。
『身に纏う物』という制限があるにしろ、その範囲については存外緩めに『認識』されており、例えば一回戦で生成した野球のスパイクなど、『履物』も生成可能である。
出来たはずのことをやりはぐった。会敵前にして、ひとつのミスが浮き彫りとなった。
「――今更気にしても仕方ありません。気を取り直して行きましょう!」
みずきは己に言い聞かせるように、努めて明るい声を出す。
準備段階でのミスは、本番中の細心の注意で取り戻せばよい。伸びる氷柱や氷筍を掴みながら、転ばぬよう、一歩一歩を確実に踏みしめてゆく。
誤って手折ってしまわぬよう、繊細な力加減が必要とされる作業であったが、みずきの手は指の自由の利かぬミトンに包まれている。見るからに精密さに欠けていた。
準備段階でのミスは、本番中の細心の注意で取り戻せばよい。伸びる氷柱や氷筍を掴みながら、転ばぬよう、一歩一歩を確実に踏みしめてゆく。
誤って手折ってしまわぬよう、繊細な力加減が必要とされる作業であったが、みずきの手は指の自由の利かぬミトンに包まれている。見るからに精密さに欠けていた。
またもや、地味にミスしていた。が、そのことで立ち止まったりはしない。
赫々と燃える魂は、ただひたすらに前へと歩を進めさせる。
光苔が煌々と照らす道を、少女は慎重な足取りで攻略していった。
赫々と燃える魂は、ただひたすらに前へと歩を進めさせる。
光苔が煌々と照らす道を、少女は慎重な足取りで攻略していった。
やがて、長く、細く括れた通路を抜けると、一転して大きく開けた場所に出た。
薄く氷の張った地底湖と、その畔であるように思われる。
淡い光に照らされ、幻想的な雰囲気を醸し出していた。
薄く氷の張った地底湖と、その畔であるように思われる。
淡い光に照らされ、幻想的な雰囲気を醸し出していた。
「綺麗……!」
見惚れていたのは、しかして一瞬。和みかけた思考を、すぐさま切り替える。
小柄な体躯を活かし、【竹林】、【ジャングル】、そして【製鉄所】と、入り組んだMAPでの戦いを勝ち進んできたミドの身軽さは、最早言及するまでもない。
対する自分の武器は、ミドにない遠距離攻撃である。であれば、辺りをよく見渡せる広い場所で待ち構える方が勝算は高かろうと判断し、みずきはここを決戦場と定めた。
小柄な体躯を活かし、【竹林】、【ジャングル】、そして【製鉄所】と、入り組んだMAPでの戦いを勝ち進んできたミドの身軽さは、最早言及するまでもない。
対する自分の武器は、ミドにない遠距離攻撃である。であれば、辺りをよく見渡せる広い場所で待ち構える方が勝算は高かろうと判断し、みずきはここを決戦場と定めた。
そうと決まれば、行動は迅速に、である。みずきは辺りを見回すと、畔に聳える、大きく太い氷筍の影に身を隠した。
ここで息を潜め、降りてきたミドのイニシアチブをとる構えである。
奇襲戦法。勝利を求める新たな“誓い”が、みずきの思考を怜悧に研ぎ澄ましていた。
ここで息を潜め、降りてきたミドのイニシアチブをとる構えである。
奇襲戦法。勝利を求める新たな“誓い”が、みずきの思考を怜悧に研ぎ澄ましていた。
「…………」
真剣な眼差しで、みずきは氷柱の裏より辺りを窺う。
どんな小さな動きも見逃すまいとシルバーフレームの眼鏡の奥の瞳は鋭く光り、またどんな小さい物音も聞き逃すまいとみずきは耳当てを首元まで下げ、精神を集中する。
全てが静止したような空間に、氷柱から水滴の落ちるような、ぽたり、ぽたりという音だけが響く。それに混じり、じゅぷり、じゅぷりという粘り気を含んだ水音もする。
どんな小さな動きも見逃すまいとシルバーフレームの眼鏡の奥の瞳は鋭く光り、またどんな小さい物音も聞き逃すまいとみずきは耳当てを首元まで下げ、精神を集中する。
全てが静止したような空間に、氷柱から水滴の落ちるような、ぽたり、ぽたりという音だけが響く。それに混じり、じゅぷり、じゅぷりという粘り気を含んだ水音もする。
「――!?」
大自然の賜物たる、透き通るような清水。不自然な粘度などあろうはずもない。
では、この水音は一体何か。耳を澄ませば、「あんっ」「いいよおっ」などという熱を孕んだ艶やかな声も聞こえてくるではないか。
幻聴ではないのか。いやむしろ幻聴であってほしいような不思議な気持ちで、みずきは音のする方へと目を向け――そこに、氷筍に跨り快楽に喘ぐ、半裸の少女を見た。
では、この水音は一体何か。耳を澄ませば、「あんっ」「いいよおっ」などという熱を孕んだ艶やかな声も聞こえてくるではないか。
幻聴ではないのか。いやむしろ幻聴であってほしいような不思議な気持ちで、みずきは音のする方へと目を向け――そこに、氷筍に跨り快楽に喘ぐ、半裸の少女を見た。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
日本は、世界でも有数のラッシュアワー大国である。
とりわけ顕著なのが、鉄道である。日中の収容数を遥かに超える鮨詰め状態はしばしば「殺人的混雑」とも揶揄され、鉄道会社もその対策に頭を悩ませてきた。
乗客を想い、少しでも快適な通勤・通学時間を提供しようと為してきた彼らの努力により、現在の混雑状況は以前のそれと比較しても相当の改善を見せている。
その努力の跡は、この桃球電鉄にも同様に見られるものであった。
とりわけ顕著なのが、鉄道である。日中の収容数を遥かに超える鮨詰め状態はしばしば「殺人的混雑」とも揶揄され、鉄道会社もその対策に頭を悩ませてきた。
乗客を想い、少しでも快適な通勤・通学時間を提供しようと為してきた彼らの努力により、現在の混雑状況は以前のそれと比較しても相当の改善を見せている。
その努力の跡は、この桃球電鉄にも同様に見られるものであった。
積み重ねた努力の結実を己の身で実感し、股ノ海は感動にその巨躯を震わせた。
自分は力士である。その体格は、力士でない一般人より一回りも二回りも巨きい。
そんな自分が、こうしてつり革を握っていられる。揺れに翻弄され、周りの人間にぶつかってしまう危険を意識せずに済む程、確かな空間が広がっている。
自分は力士である。その体格は、力士でない一般人より一回りも二回りも巨きい。
そんな自分が、こうしてつり革を握っていられる。揺れに翻弄され、周りの人間にぶつかってしまう危険を意識せずに済む程、確かな空間が広がっている。
「これぞ、人情……。人が人を想い、結集させた心・技・体の粋……」
ひとりごち、左方に連なるカチグミ・サラリマンたちに会釈をする。スズナリめいて密集した七三分けの男たちが、苦しげな表情の中にも一抹の余裕を湛えた笑みを返す。
それから正面に目を向けると、座席に座る年端もいかぬ少女と視線が交差する。
少女の無垢な瞳はしばし股ノ海を見つめた後、座席を降り、次の言葉を放った。
それから正面に目を向けると、座席に座る年端もいかぬ少女と視線が交差する。
少女の無垢な瞳はしばし股ノ海を見つめた後、座席を降り、次の言葉を放った。
「おすもうさんっ! どうぞっ!」
股ノ海は逡巡する。
他人の厚意を無碍にするなど力士の風上にも置けぬ行為だが、それにしても、だ。
困り果てた股ノ海が口を開くが早いか、少女の母親が少女の小さな手をとり、
他人の厚意を無碍にするなど力士の風上にも置けぬ行為だが、それにしても、だ。
困り果てた股ノ海が口を開くが早いか、少女の母親が少女の小さな手をとり、
「お気になさらず! 私たちは次で降りますので!」
と早口で捲し立て、少女の手を引き、人ごみを強引に掻き分けて立ち去った。
残された股ノ海は、しばし立ち尽くしていた。その双眸は感涙に輝いていた。
残された股ノ海は、しばし立ち尽くしていた。その双眸は感涙に輝いていた。
「(自分のような未熟者に席を譲る少女と、気を遣わせぬよう進んで身を引く母親……。
ああ、これぞ、和の心!
このような素晴らしい国に生まれることができ、自分は本当に幸せ者だ……)」
ああ、これぞ、和の心!
このような素晴らしい国に生まれることができ、自分は本当に幸せ者だ……)」
股ノ海は有難く譲られた席に座し、決意を新たに思いを馳せる。
誇り高き我が国と、その国技・相撲の世界に身を置けることの幸福に感謝する。
誇り高き我が国と、その国技・相撲の世界に身を置けることの幸福に感謝する。
そして、精神を集中させる。
せめて自分の活躍が、それら全てへの恩返しとなることを祈りながら――。
せめて自分の活躍が、それら全てへの恩返しとなることを祈りながら――。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「――ああっ、奥まできてるっ! 固いの、きちゃってるうっ!
アツいのも最高だけど、ひんやりしてるのも、これはこれでオツなものねっ……!」
アツいのも最高だけど、ひんやりしてるのも、これはこれでオツなものねっ……!」
氷筍を相手に上下に揺らめきながら、ファイナリストの一人・ミドが喘ぐ。
官能に濁った瞳は虚空を見つめ、だらしなく開いた口からは涎が垂れている。
右手は己と氷筍の結合部のすぐ傍に宛がわれ、左手は薄い胸を揉みしだいている。
官能に濁った瞳は虚空を見つめ、だらしなく開いた口からは涎が垂れている。
右手は己と氷筍の結合部のすぐ傍に宛がわれ、左手は薄い胸を揉みしだいている。
「なっ……なんなんですか、あのひと……!?」
両の頬に朱を差しながら、みずきは驚きの声を上げる。
それもそのはず。対戦相手の少女が、脇目も振らず氷とのプレイに興じているのだ。
初心なみずきの鼓動は早鐘を打ち、しばし氷と踊る少女の幻想的な光景に目を奪われていた。理性が「見てはいけない」と諌める程に、その視線は不思議に離れなかった。
それもそのはず。対戦相手の少女が、脇目も振らず氷とのプレイに興じているのだ。
初心なみずきの鼓動は早鐘を打ち、しばし氷と踊る少女の幻想的な光景に目を奪われていた。理性が「見てはいけない」と諌める程に、その視線は不思議に離れなかった。
「くるよお! ゾクゾクするよおっ! き、きちゃう――――あっ」
ぽきり、と小気味の良い音がして、ミドのお相手たる氷荀は折れた。
いわゆるひとつの中折れである。
ミドはショックに打ちのめされた表情で茫然としていたが、次の瞬間その場にぱったりと倒れ伏した。息は荒く、顔も真っ赤である。そして、うわ言のように呟いた。
いわゆるひとつの中折れである。
ミドはショックに打ちのめされた表情で茫然としていたが、次の瞬間その場にぱったりと倒れ伏した。息は荒く、顔も真っ赤である。そして、うわ言のように呟いた。
「汗が凍って……さ、寒い……。死んじゃう……!」
歯をがちがちを鳴らしながら、ミドは絞り出すような声を漏らす。
みずきはこの発言に「ええーっ!」とずっこけかけたが、なんとか踏みとどまった。
完全なる自業自得による凍傷。本来ならそのような対戦相手を見逃す道理などありはしなかったが、しかしてみずきは隠れていた氷荀から躍り出て、ミドの元へと急いだ。
みずきはこの発言に「ええーっ!」とずっこけかけたが、なんとか踏みとどまった。
完全なる自業自得による凍傷。本来ならそのような対戦相手を見逃す道理などありはしなかったが、しかしてみずきは隠れていた氷荀から躍り出て、ミドの元へと急いだ。
「今行きますっ!」
極力、対戦相手を傷つけることを避けてきたみずきの甘ちゃんは、この決勝戦においても遺憾なく発揮されていた。
例え自業自得でも。例えワン・ターレンが治してくれると分かっていても。
それでもみずきは駆けつけずには、助けずにはいられない。
目の前で凍傷に苦しむ相手を、見捨てられやしないのだ。
例え自業自得でも。例えワン・ターレンが治してくれると分かっていても。
それでもみずきは駆けつけずには、助けずにはいられない。
目の前で凍傷に苦しむ相手を、見捨てられやしないのだ。
「――大丈夫ですか!?」
「ああ、川が見える……。向こうで、真野さんが私を呼んでる……」
「真野さんは生きてますし、それは渡っちゃダメな川ですっ!
気をしっかり持って下さい! ああっ、眠っちゃダメですーっ!」
気をしっかり持って下さい! ああっ、眠っちゃダメですーっ!」
みずきは唇を紫色に染めた死に体のミドを励ましながら、肩を貸して移動した。
足首に引っかかった状態の縞模様のぱんつが外れて落ちた。
ミドがプレイに興じていたのは氷荀の林立する場所であった。
介抱するならひらけた場所で、と考え、みずきはミドを引っ張り氷荀の森を抜けた。
足首に引っかかった状態の縞模様のぱんつが外れて落ちた。
ミドがプレイに興じていたのは氷荀の林立する場所であった。
介抱するならひらけた場所で、と考え、みずきはミドを引っ張り氷荀の森を抜けた。
「ここなら大丈夫ですね……。少し我慢してて下さい! すぐ暖まりますので!」
みずきはミドを降ろすと、コートを脱いでミドに着せた。マフラーも巻いてやる。
剥き出し上半身に短いスカートのみという姿の上からコートを羽織ったミドは、さながら深夜の街を徘徊する痴女の如き様相を呈していた。そこまで間違ってない。
それからみずきは片手のミトンを外し、能力を解除する。糸が解れるように雫が落ち、ミドの口に注がれてゆく。湯気をたてるそれを嚥下し、ミドの目は驚愕に見開かれる。
剥き出し上半身に短いスカートのみという姿の上からコートを羽織ったミドは、さながら深夜の街を徘徊する痴女の如き様相を呈していた。そこまで間違ってない。
それからみずきは片手のミトンを外し、能力を解除する。糸が解れるように雫が落ち、ミドの口に注がれてゆく。湯気をたてるそれを嚥下し、ミドの目は驚愕に見開かれる。
「嘘……。これ、あったかい……」
みずきはミドににっこりと笑いかける。
白王みずきの能力『みずのはごろも』には、いくつかの隠されたルールがあった。
『みずのはごろも』は、能力対象とした水の温度を保存するという副次効果を持つ。
白王みずきの能力『みずのはごろも』には、いくつかの隠されたルールがあった。
『みずのはごろも』は、能力対象とした水の温度を保存するという副次効果を持つ。
水、と一口に言っても、それは冷たい、いわゆる“水”に限定しない。
温度の高低は『認識』の揺れの内に在り、しかるに“湯”もまた“水”なのである。
出陣の際、みずきが汗ばんでいた理由もここにある。暖かい室内で厚着をしていたこともあったが、何より、湯を纏っていたために身体が火照っていたのだった。
温度の高低は『認識』の揺れの内に在り、しかるに“湯”もまた“水”なのである。
出陣の際、みずきが汗ばんでいた理由もここにある。暖かい室内で厚着をしていたこともあったが、何より、湯を纏っていたために身体が火照っていたのだった。
「……どうですか? 楽になりましたか?」
両のミトンをミドに振る舞い、もう充分に暖まったのではないかとみずきは推測する。
実際にミドの唇には赤みが戻りつつあり、震えも若干の落ち着きを見せていた。
だがミドは鳥肌の立つ手でみずきのカーディガンを握り、か細い声を出す。
実際にミドの唇には赤みが戻りつつあり、震えも若干の落ち着きを見せていた。
だがミドは鳥肌の立つ手でみずきのカーディガンを握り、か細い声を出す。
「まだ寒い……。私、死んじゃう……」
そう言われましても……。みずきは困惑する。
今やみずき自身も普段の制服姿にはずした耳当てを首にかけているだけで、用意した防寒具の恩恵にはまったく与れていない。
それに、こんなものは所詮は応急処置未満。付け焼刃のその場凌ぎに過ぎぬ。
早いところで棄権を打診し、暖かな控室への避難を促そうと思っていたが――。
今やみずき自身も普段の制服姿にはずした耳当てを首にかけているだけで、用意した防寒具の恩恵にはまったく与れていない。
それに、こんなものは所詮は応急処置未満。付け焼刃のその場凌ぎに過ぎぬ。
早いところで棄権を打診し、暖かな控室への避難を促そうと思っていたが――。
「そうだわ……」
何かを思いついたようで、ミドが口を開く。傾注するみずき。
「よく漫画とかで、雪山で遭難したひとが、肌を重ねて暖を取ってるじゃない……。
あれなら、きっと元気が出るに違いないわ……!」
あれなら、きっと元気が出るに違いないわ……!」
「えっ……それって……!」
みずきも年頃の女子であり、少女漫画などを嗜む趣味もあった。
どきどきと胸を高鳴らせながら読んだ件のシーンが頭を過ぎり、頬が熱を帯びる。
それは流石に、と辞しかけたみずきに、ミドの追撃が入る。
どきどきと胸を高鳴らせながら読んだ件のシーンが頭を過ぎり、頬が熱を帯びる。
それは流石に、と辞しかけたみずきに、ミドの追撃が入る。
「ああ、もうダメ……、今にも死んじゃう……!
真野さん……、兼石さん……、石田くん……。待ってて、今そっちに……!」
真野さん……、兼石さん……、石田くん……。待ってて、今そっちに……!」
「わあーっ! だからダメですって! 分かりましたっ! 分かりましたからあ!」
崩れかけたミドを慌てて宥め、みずきは観念した。
猶もカタカタと震え続けるミドを前に、手を差し伸べずにはいられなかったのだ。
恥ずかしそうに俯きながら、おずおずと服を脱いでゆく。上から下へと制服を畳んでゆき、やがて、上下の下着とミサンガとリストバンドのみを纏った姿になった。
猶もカタカタと震え続けるミドを前に、手を差し伸べずにはいられなかったのだ。
恥ずかしそうに俯きながら、おずおずと服を脱いでゆく。上から下へと制服を畳んでゆき、やがて、上下の下着とミサンガとリストバンドのみを纏った姿になった。
「は、早くきて……! もう限界……!」
ミドは切実そうな声をあげる。
ここまできてしまったなら、躊躇する方がむしろ厳しい。
みずきは歓迎するように広げられたコートの中へと身を投じる。
ここまできてしまったなら、躊躇する方がむしろ厳しい。
みずきは歓迎するように広げられたコートの中へと身を投じる。
「お、お邪魔します……」
己よりも小柄なミドの胸に、みずきは小さくなって身体を寄せる。
みずきの到来を受け、ミドはコートを広げていた両手で来客を抱き締める。
コートの密室の中で、二人の少女が素肌を寄せ合う。
みずきの到来を受け、ミドはコートを広げていた両手で来客を抱き締める。
コートの密室の中で、二人の少女が素肌を寄せ合う。
「ああ、あったかい……!」
「これで満足でしょうか……?」
肌と肌とが吸いつくような感覚に、みずきは顔を真っ赤に染める。
最初は半信半疑だったこの抱きあいも、やってみると意外に体温が身体が火照り出していることが分かる。
まあ、みずきの場合は恥じらいが主な原因かもしれないが。
最初は半信半疑だったこの抱きあいも、やってみると意外に体温が身体が火照り出していることが分かる。
まあ、みずきの場合は恥じらいが主な原因かもしれないが。
ともあれ、ミドの顔色もよくなってきている。
そろそろ降参を促そうかとみずきが開きかけた唇は、瞬いた刹那、塞がれていた。
――ミドの唇によって。
そろそろ降参を促そうかとみずきが開きかけた唇は、瞬いた刹那、塞がれていた。
――ミドの唇によって。
「――!?」
唇に触れる柔らかな感触は、みずきにとって未知なるものだった。
理解が追い付かず、それでも状況を把握せんと動き出す脳をすら振り切るように、ミドの舌が唇を割ってみずきへ侵入する。
蠢く舌はそれ自体が別の生き物のようにみずきの舌に吸いつき、舐めとり、絡みつく。
理解が追い付かず、それでも状況を把握せんと動き出す脳をすら振り切るように、ミドの舌が唇を割ってみずきへ侵入する。
蠢く舌はそれ自体が別の生き物のようにみずきの舌に吸いつき、舐めとり、絡みつく。
「ふぅんっ……。はっ、んんっ……!」
漏れ出るくぐもった息が二人の眼鏡を曇らせ、同時にその思考をも曇らせてゆく。
とろんと蕩けた思考回路がようやく復旧する頃にはみずきの口腔はミドに味わい尽くされ、どちらのものとも分からぬ唾液が糸を引きながら離れる二人の唇を繋いでいた。
口元に零れる唾液をぺろりと舐めとりながら、妖しく濡れた瞳を光らせミドが言う。
とろんと蕩けた思考回路がようやく復旧する頃にはみずきの口腔はミドに味わい尽くされ、どちらのものとも分からぬ唾液が糸を引きながら離れる二人の唇を繋いでいた。
口元に零れる唾液をぺろりと舐めとりながら、妖しく濡れた瞳を光らせミドが言う。
「満足? まだまだね……。これから、たっぷり“満足”させて貰うわ――!」
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
目的地の駅に電車が着き、股ノ海は下車する。
この時も、人々は股ノ海の移動の邪魔にならぬ様に動いた。
またもや日本人の心優しさに触れ、股ノ海は去りゆく車両に向け深々とお辞儀した。
この時も、人々は股ノ海の移動の邪魔にならぬ様に動いた。
またもや日本人の心優しさに触れ、股ノ海は去りゆく車両に向け深々とお辞儀した。
股ノ海は踵を返し、改札口を目指す。
彼らへ感謝の気持ちを伝えるには、自分の相撲を取り続けることしかできない。
不器用な彼なりの恩返しの決意を胸に秘め、歩みを進める。
彼らへ感謝の気持ちを伝えるには、自分の相撲を取り続けることしかできない。
不器用な彼なりの恩返しの決意を胸に秘め、歩みを進める。
「……む」
線路をまたぐ跨線橋の麓に、キャリーバッグを抱えた老婆が立ち竦んでいた。
キャリーバッグを担いで段差を登ることができないのだろう、老婆は途方に暮れた様子であり、一方、周りの人々は、その横を淡々と通り過ぎてゆくのみ。
都合の悪いことに、エレベーターも工事中であった。
股ノ海は老婆の元へと急ぎ、柔和な笑みを湛えて言葉を掛けた。
キャリーバッグを担いで段差を登ることができないのだろう、老婆は途方に暮れた様子であり、一方、周りの人々は、その横を淡々と通り過ぎてゆくのみ。
都合の悪いことに、エレベーターも工事中であった。
股ノ海は老婆の元へと急ぎ、柔和な笑みを湛えて言葉を掛けた。
「御婦人。自分が運びましょう」
「あら……。どうもすみませんねえ」
人には人の事情がある。
今このホームにいる人間は、それぞれ火急の用を抱えているに違いない。
股ノ海はひとを疑うことを知らぬ。その愚直さこそが強さでもあった。
今このホームにいる人間は、それぞれ火急の用を抱えているに違いない。
股ノ海はひとを疑うことを知らぬ。その愚直さこそが強さでもあった。
「あなた、お相撲をやられてるんですか?」
「ええ、まあ」
「あら……! 私も主人も、お相撲が大好きなんですよ」
取り留めのない会話をしながら、階段をゆっくり登ってゆく。
そういえば、と股ノ海は思い出す。
自分の母も、ちょうど背後の女性と同じくらいの年齢ではないだろうか。
そういえば、と股ノ海は思い出す。
自分の母も、ちょうど背後の女性と同じくらいの年齢ではないだろうか。
母は、遠い実家にいる。
自分をここまで育て上げてくれた恩を忘れたことはなかったが、関脇となってからは忙しく、手紙のやり取りばかりで顔を合わせることが出来ていなかった。
近いうちに、一度帰ろうか。そして、このように母をおぶって、散歩でもしようか。
小さい頃に母におぶられて歩いた、あの道を――。
自分をここまで育て上げてくれた恩を忘れたことはなかったが、関脇となってからは忙しく、手紙のやり取りばかりで顔を合わせることが出来ていなかった。
近いうちに、一度帰ろうか。そして、このように母をおぶって、散歩でもしようか。
小さい頃に母におぶられて歩いた、あの道を――。
「どうも、ありがとうねえ」
「当然のことをしたまでです」
階段を登り切り、女性を降ろした。下りの同行も申し出たが、丁重に断られた。
あなたにも、御用事がおありでしょう? そう、微笑みながら言われた。
その慎ましさに大和撫子の姿を見、股ノ海は御言葉に甘えさせてもらうことにした。
あなたにも、御用事がおありでしょう? そう、微笑みながら言われた。
その慎ましさに大和撫子の姿を見、股ノ海は御言葉に甘えさせてもらうことにした。
去り際、女性は一言残していった。
「それじゃあ、さようなら。いつも応援していますよ、亜山田関」
「!!」
関脇・亜山田関。大関昇進を相争う、股ノ海の次の取り組み相手であった。
人違いの衝撃に固まること数秒。股ノ海は己の両頬を思い切り叩いた。
対戦相手を応援していることがなんだ。相撲を愛する、その心をこそ尊ぶべきだ。
人違いの衝撃に固まること数秒。股ノ海は己の両頬を思い切り叩いた。
対戦相手を応援していることがなんだ。相撲を愛する、その心をこそ尊ぶべきだ。
股ノ海は四股を踏む。未熟な己を諌めるように。
股ノ海は四股を踏む。乱れた心が正されてゆく。
股ノ海は四股を踏む。正しいダイヤが乱れてゆく。
股ノ海は四股を踏む。乱れた心が正されてゆく。
股ノ海は四股を踏む。正しいダイヤが乱れてゆく。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
白王みずきは、兄である白王みかどを慕っている。家族としてではなく、男女として。
友達のコイバナを聞くたび、自分のこの唇は一体誰に捧げられるのだろうか、と考えることがある。そんなとき、恥ずかしい話だが、兄に捧げられたら嬉しいな、と思う。
そのファーストキスは、無惨にも奪われた。目の前の少女――渡葉美土によって。
友達のコイバナを聞くたび、自分のこの唇は一体誰に捧げられるのだろうか、と考えることがある。そんなとき、恥ずかしい話だが、兄に捧げられたら嬉しいな、と思う。
そのファーストキスは、無惨にも奪われた。目の前の少女――渡葉美土によって。
「ごちそうさま♪ でも、これはまだ前菜ね。フルコースは始まったばかり……♪」
妖艶な笑みと共にするりと動いたミドの手が、みずきの両の下着を器用に下ろす。
我に返ったみずきはミドを押し退けようと手をあげるが、その挙動も読まれていた。
先んじて動いていた唇がみずきの首筋に触れる。思わず声が漏れてしまう。
我に返ったみずきはミドを押し退けようと手をあげるが、その挙動も読まれていた。
先んじて動いていた唇がみずきの首筋に触れる。思わず声が漏れてしまう。
「ふふっ、可愛い。もしかして、誘ってたりするワケ?」
「違っ――あああっ!」
否定しかけたみずきの乳房に吸い付き、薄桃色の蕾を口に含むミド。
舌先で転がしながら、軽く隆起しだしたそれを唇で甘噛む。
先程までの衰弱が嘘のように活き活きとしたミドに翻弄されながら、みずきは痛感していた。騙された。嵌められた。ペテンにかけられていた、と――。
舌先で転がしながら、軽く隆起しだしたそれを唇で甘噛む。
先程までの衰弱が嘘のように活き活きとしたミドに翻弄されながら、みずきは痛感していた。騙された。嵌められた。ペテンにかけられていた、と――。
寒さで衰弱しつつあったことは事実であろう。肉体は特別頑強でないのだから。
問題は、それをみずきが助けることも含め全て計算ずくであったことだ。
これまでの試合を研究したのだろうか、ミドは、みずきが例え対戦相手だろうが苦しむ者を放っておけない性格だと看破し、敢えてその身を危険に晒したのだ。
問題は、それをみずきが助けることも含め全て計算ずくであったことだ。
これまでの試合を研究したのだろうか、ミドは、みずきが例え対戦相手だろうが苦しむ者を放っておけない性格だと看破し、敢えてその身を危険に晒したのだ。
みずきは見誤っていた。否、見くびっていたとでも言おうか。
伝説の剣『まるごし』ではなく、その中に潜むナイフでもなく、ましてや身軽さでもSLG能力でもない、ミドの真の『武器』。
阿野次のもじや真野風火水土といった、大会屈指の頭脳派魔人を出し抜き下してきた、参加者中最強の『頭脳』。その狡猾さが、まさかこれほどまでとは――。
伝説の剣『まるごし』ではなく、その中に潜むナイフでもなく、ましてや身軽さでもSLG能力でもない、ミドの真の『武器』。
阿野次のもじや真野風火水土といった、大会屈指の頭脳派魔人を出し抜き下してきた、参加者中最強の『頭脳』。その狡猾さが、まさかこれほどまでとは――。
「……どう? 気持ちよくなってきたでしょ?」
「そんなことっ……! はあっ、ありませんっ……!」
「へーえ? もっと激しいのがお好みってワケね」
全身に降り注ぐ愛撫の雨が敏感なみずきを攻め立てる。
それも、闇雲に撃っているわけではない。官能の壺を的確に突いている。
いつの間にやらマウントをとられていたみずきに、ビッチに抗う術はない。
それも、闇雲に撃っているわけではない。官能の壺を的確に突いている。
いつの間にやらマウントをとられていたみずきに、ビッチに抗う術はない。
「(それにしても、チョロいもんだわ。まさか、本当に助けに来るなんて)」
懐疑的な独白をするミド。
だが、彼女は自分の危機に、みずきが100%助けを出すと確信していた。
ゆえに、この発言はみずきに対する呆れの意味合いが強かった。
だが、彼女は自分の危機に、みずきが100%助けを出すと確信していた。
ゆえに、この発言はみずきに対する呆れの意味合いが強かった。
ミドは、ビッチとしての自分に自信がない。
事実はさておき、男を魅了する才能に欠けていると思い込んでいた。
故に彼女は、努力するビッチ。アイテムを駆使し、口先を弄し、常に思考を止めず、ありとあらゆる策を用いて男の一物を狙う。彼女のビッチは、言わば闘争であった。
事実はさておき、男を魅了する才能に欠けていると思い込んでいた。
故に彼女は、努力するビッチ。アイテムを駆使し、口先を弄し、常に思考を止めず、ありとあらゆる策を用いて男の一物を狙う。彼女のビッチは、言わば闘争であった。
だが――。目の前の少女は、自分とは異なる人種だ。
胸は同程度でも、やや高めの背丈にそれはスレンダーとして映え、背伸びをしたような赤フレームの眼鏡とは違う、色気のないメタルフレームの眼鏡をつけていて猶、委員長然とした色香を醸し出している。
意志乃鞘や羽山莉子に見初められたその魅力は、悔しいが確かなものだと言える。
まさに、自分とは対照的な存在。“天然モノ”のみずきに、ミドは嫉妬していた。
胸は同程度でも、やや高めの背丈にそれはスレンダーとして映え、背伸びをしたような赤フレームの眼鏡とは違う、色気のないメタルフレームの眼鏡をつけていて猶、委員長然とした色香を醸し出している。
意志乃鞘や羽山莉子に見初められたその魅力は、悔しいが確かなものだと言える。
まさに、自分とは対照的な存在。“天然モノ”のみずきに、ミドは嫉妬していた。
「持って生まれた魅力だけで渡っていけるほど、世間は甘くないわよ? 処女ちゃん」
「なっ――!」
混濁する意識で抗議しかけたみずきだったが、背筋をつぅとなぞる指先に封殺される。
実のところ、このミドのビッチもまたみずきに対し、非常に効果的であった。
実のところ、このミドのビッチもまたみずきに対し、非常に効果的であった。
ミドの言うとおり、みずきは甘ちゃんで処女で、それに敏感で天然である。
自分が感じているものの正体も分からない。みずきには自慰の経験もなかった。
無垢なるがゆえ、みずきは次々ともたらされる快楽の波に抗うことができない。呼び覚まされる己の肉欲をどのように封じればよいのかも分からないのだ。
自分が感じているものの正体も分からない。みずきには自慰の経験もなかった。
無垢なるがゆえ、みずきは次々ともたらされる快楽の波に抗うことができない。呼び覚まされる己の肉欲をどのように封じればよいのかも分からないのだ。
それでもさっきのように、言葉に反応してふやけきった心が起き上がることもある。
だから、ミドはそれすらも折りにいった。
己の独壇場で徹底的に相手の優位に立つ。戦いの基本だ。
ミドはみずきの太腿を撫ぜていた手を左の手首まで持っていく。
そして次の瞬間、二人の“約束”の証たる、ミサンガを解いた――。
だから、ミドはそれすらも折りにいった。
己の独壇場で徹底的に相手の優位に立つ。戦いの基本だ。
ミドはみずきの太腿を撫ぜていた手を左の手首まで持っていく。
そして次の瞬間、二人の“約束”の証たる、ミサンガを解いた――。
「あああああ――っ!」
みずきの口から洩れた声は、絶望の色を濃く表していた。
巻かれてから数年、片時も離さず生きてきた、愛しの兄の分身。
そのミサンガは今やみずきの肉体を離れ、氷上に堕ちた。
巻かれてから数年、片時も離さず生きてきた、愛しの兄の分身。
そのミサンガは今やみずきの肉体を離れ、氷上に堕ちた。
「どう? 愛しのお兄さんからのプレゼントを喪った気分は?」
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「貴様だな」
背後から凛とした声に呼び止められ、股ノ海は振り返る。
そこには、マントを靡かせ豪奢な鎧を身に纏った人物が立っていた。
全身から闘気を放ち、股ノ海を睨み付けている。
そこには、マントを靡かせ豪奢な鎧を身に纏った人物が立っていた。
全身から闘気を放ち、股ノ海を睨み付けている。
「僕の名前は白王みかど。『風紀皇帝』たる僕の元に、一般女性から通報が入った。
卑猥な格好で電車に乗り、少女から座席を奪う不届きな男がいると」
卑猥な格好で電車に乗り、少女から座席を奪う不届きな男がいると」
そんな者が、この場に!?
だとすればそれは一大事だ。自分も確保に協力せねば。
辺りを見回す股ノ海だったが、今や人々は二人を避けて通行している。
円形状に空いた区画には、自分と白王みかどの二人しかいない。
そして白王みかどの視線の先にはいるのは、まさしく自分だ。
まさか――自分?
だとすればそれは一大事だ。自分も確保に協力せねば。
辺りを見回す股ノ海だったが、今や人々は二人を避けて通行している。
円形状に空いた区画には、自分と白王みかどの二人しかいない。
そして白王みかどの視線の先にはいるのは、まさしく自分だ。
まさか――自分?
「誤解だ」
なんとかそれだけ絞り出す。心当たりはなかった。
まわしは自分にとって、戦いに臨む神聖な衣装だ。常在戦陣の心構えである。
少女から座席を奪った覚えもない。これは何かの間違いだと伝えようとした。
だが、目の前の『風紀皇帝』は聞く耳を持たない。
まわしは自分にとって、戦いに臨む神聖な衣装だ。常在戦陣の心構えである。
少女から座席を奪った覚えもない。これは何かの間違いだと伝えようとした。
だが、目の前の『風紀皇帝』は聞く耳を持たない。
「ふんっ! 不埒者どもは、決まってそう言う。
その格好が、何よりの動かぬ証拠だ! 詳しい話は『向こう』で聞こうッ!」
その格好が、何よりの動かぬ証拠だ! 詳しい話は『向こう』で聞こうッ!」
言い終わるが早いか、みかどは股ノ海に向かって駆け出した。
腰の鞘から剣を抜き放ち、上段で構えて突進する。
腰の鞘から剣を抜き放ち、上段で構えて突進する。
「我が『帝ソード』の錆になれっ!」
「ぬうっ!」
振り下ろされた剣にあわせ、股ノ海は額の上で両の掌を叩き合わせる。
猫騙しだ! だが、その目的は相手の目を眩ませることに非ず。
果たして両の掌は、みかどの剣撃をガッチリと挟み、受け止める。
猫騙しだ! だが、その目的は相手の目を眩ませることに非ず。
果たして両の掌は、みかどの剣撃をガッチリと挟み、受け止める。
そう、白刃取りであった。
武器を持った相手への対処法を身につけねば、関脇として生きて行くことは出来ぬ。
みかどは舌打ちし、しかして不敵な笑みを浮かべ、叫ぶ。
武器を持った相手への対処法を身につけねば、関脇として生きて行くことは出来ぬ。
みかどは舌打ちし、しかして不敵な笑みを浮かべ、叫ぶ。
「――『まばゆいひかり』っ!」
刹那、焼き切るような閃光が瞬いた。
股ノ海は咄嗟に目を閉じたが、数瞬遅く、目頭に痛みが走り思わず手を離してしまう。
みかどはその隙を見逃さなかった。
一歩後ろへ跳び退ると、勢いをつけて股ノ海の胴を薙いだ。
股ノ海は咄嗟に目を閉じたが、数瞬遅く、目頭に痛みが走り思わず手を離してしまう。
みかどはその隙を見逃さなかった。
一歩後ろへ跳び退ると、勢いをつけて股ノ海の胴を薙いだ。
「ぐッ――!」
ダメージ自体は然程問題ではない。
日々のぶつかり稽古に比べれば、大したことのない一撃であった。
だが、不意の閃光の正体が分からない。これでは、攻撃を喰らい続けるのみ。
日々のぶつかり稽古に比べれば、大したことのない一撃であった。
だが、不意の閃光の正体が分からない。これでは、攻撃を喰らい続けるのみ。
「むっ……。能力の性質上仕方ないが、護るべき民草にも影響するのは問題だな」
みかどがひとりごつ。見ると、周りの人垣の中にも目を押さえ蹲る者が散見された。
白王みかどの能力『ひかりのよろい』は、光を纏って自在に放つ能力である。
先程の技『まばゆいひかり』ように目潰しとして使用した場合、指向性のない閃光は周囲一帯に効果を及ぼしてしまう。一瞬のこととはいえ、被害者は少なくない。
白王みかどの能力『ひかりのよろい』は、光を纏って自在に放つ能力である。
先程の技『まばゆいひかり』ように目潰しとして使用した場合、指向性のない閃光は周囲一帯に効果を及ぼしてしまう。一瞬のこととはいえ、被害者は少なくない。
「散れっ! ここは僕に任せ、皆は去るんだ!」
檄を飛ばすみかど。その声に従い、人々は方々へ散ってゆく。
能力のとばっちりを受けた者も、幸い複数人連れの者ばかりだった。
仲間に連れられいなくなる野次馬たちの中で、ただひとり、先刻の老婆が残った。
能力のとばっちりを受けた者も、幸い複数人連れの者ばかりだった。
仲間に連れられいなくなる野次馬たちの中で、ただひとり、先刻の老婆が残った。
「ッ!!」
股ノ海は驚愕した。まさか、あの女性がここにいるとは――。
そしてあろうことか、閃光の被害を受けてしまったとは――!
股ノ海は女性の元へ駆けつける。そして、その小柄な身体を持ち上げた。
そしてあろうことか、閃光の被害を受けてしまったとは――!
股ノ海は女性の元へ駆けつける。そして、その小柄な身体を持ち上げた。
「御婦人、先程の力士です。貴女を安全なところへ運びます」
「ああ、ごめんなさいねえ。急に目が開けられなくなっちゃって……歳かねえ」
女性を近くのベンチに座らせると、股ノ海はみかどの前へと戻った。
礼をして一歩進み、その場で二度、大きく四股を踏む。地鳴りが起きた錯覚がした。
そして拳をつき、立会いの姿勢を取る。張りつめた緊張が一帯を包む。
礼をして一歩進み、その場で二度、大きく四股を踏む。地鳴りが起きた錯覚がした。
そして拳をつき、立会いの姿勢を取る。張りつめた緊張が一帯を包む。
「(申し訳ない、親方。一般人相手に相撲の技を使う、自分の未熟さは分かっている。
――だが。自分は、自分の相撲を取るんだ)」
――だが。自分は、自分の相撲を取るんだ)」
異様な気合を見せる股ノ海に、みかども僅かに丈の縮まったマントを翻す。
帝ソードを構え、感覚を研ぎ澄ます。
一拍の後――両者は、同時に敵にぶつかっていった。
帝ソードを構え、感覚を研ぎ澄ます。
一拍の後――両者は、同時に敵にぶつかっていった。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
決勝の前日。ミドは仲間のモヒカンザコと触手を連れ、いつもの如く過ごしていた。
薬草を調達してきた盗賊・逆立当真は与えられたぱんつに御執心であり、また賢者・姦崎絡はそんなミドを説教しながらレイプしていた。
いつもと変わらぬ勇者パーティの日常。だがそこに、一人の闖入者が現れたのだった。
薬草を調達してきた盗賊・逆立当真は与えられたぱんつに御執心であり、また賢者・姦崎絡はそんなミドを説教しながらレイプしていた。
いつもと変わらぬ勇者パーティの日常。だがそこに、一人の闖入者が現れたのだった。
「不埒者どもめ、覚悟しろーっ! 我が名は白王みかど!
『風紀皇帝』白王みかどだっ! そこの婦女子から離れろぉー!!」
『風紀皇帝』白王みかどだっ! そこの婦女子から離れろぉー!!」
閃光と共に現れたその人物は、ミドの決勝の相手と同じ名字であった。
そう言えば、身辺を洗った際に、対戦相手・白王みずきの兄の存在を知ったはずだ。
これは、使える。そう判断したミドは、哀れな性犯罪の被害者を装いみかどに救出された。早い話が、仲間を売ったのである。何、優勝すれば保釈金も出せる。問題ない。
そう言えば、身辺を洗った際に、対戦相手・白王みずきの兄の存在を知ったはずだ。
これは、使える。そう判断したミドは、哀れな性犯罪の被害者を装いみかどに救出された。早い話が、仲間を売ったのである。何、優勝すれば保釈金も出せる。問題ない。
「怖かったですぅ……くすん、くすん」
「よしよし、もう安心していい。悪は僕が成敗した。
心と身体に負った傷は、癒えるのに時間が必要かもしれない……。
だが、君なら大丈夫だ! 僕が保証するっ!」
心と身体に負った傷は、癒えるのに時間が必要かもしれない……。
だが、君なら大丈夫だ! 僕が保証するっ!」
ビッチを相手に斯様な慰めをするみかどの滑稽さは、ミドに計画の成功を確信させた。
それから可哀想な少女の振りをし、ミドはみかどから幾つかの情報を引き出した。
その内の一つを『ふかくこころにきざみこ』み、冒頭にて『おもいだ』した。
それから可哀想な少女の振りをし、ミドはみかどから幾つかの情報を引き出した。
その内の一つを『ふかくこころにきざみこ』み、冒頭にて『おもいだ』した。
『みずきのやつ、別れ際に僕が贈ったミサンガをまだ着けているのか……。
ふふっ、愛い奴だ。心優しかったあの頃から、何も変わってないんだな……。』
ふふっ、愛い奴だ。心優しかったあの頃から、何も変わってないんだな……。』
メモリーの二つ目には、にこやかな笑みで妹のことを語った台詞が収録されている。
この発言の後段より、ミドはみずきに「氷荀オナニーで凍傷になって介抱される」という作戦――名付けて『こごえるビッチ』を用いることを決定した。
元々、これまでの試合の経過からみずきにこの作戦が有効であることは自信があった。その裏付けが、他ならぬ実の家族から得られたとなれば、使わない理由はない。
この発言の後段より、ミドはみずきに「氷荀オナニーで凍傷になって介抱される」という作戦――名付けて『こごえるビッチ』を用いることを決定した。
元々、これまでの試合の経過からみずきにこの作戦が有効であることは自信があった。その裏付けが、他ならぬ実の家族から得られたとなれば、使わない理由はない。
この捨て身の選択からも分かる通り、ミドはみずきに戦力的に大きく劣っていた。
遠距離攻撃主体のみずきとは元より相性が悪く、二本のナイフの投擲も、不動の時速200キロの攻撃を弾き飛ばしたその動体視力を前にしては余りにも心許なかった。
もっと言ってしまえば、兼石次郎と双璧をなす大会優勝候補・池松叢雲を破った不動が勝ち上がると思っていたミドにとって決勝は既に泣きたい状況であり、その不動を破ったみずきにも、真正面から挑んで勝てる気は全くしていなかったのである。
遠距離攻撃主体のみずきとは元より相性が悪く、二本のナイフの投擲も、不動の時速200キロの攻撃を弾き飛ばしたその動体視力を前にしては余りにも心許なかった。
もっと言ってしまえば、兼石次郎と双璧をなす大会優勝候補・池松叢雲を破った不動が勝ち上がると思っていたミドにとって決勝は既に泣きたい状況であり、その不動を破ったみずきにも、真正面から挑んで勝てる気は全くしていなかったのである。
だが、不動がみずきに敗れたことはミドにとってこの上ない僥倖であった。
みずきは甘ちゃんである。弱者の振りをして精神を揺さぶれば、きっと手玉に取れる。
事実、ミドはこの乾坤一擲の作戦を成功させ、みずきを追い詰めていた。
みずきは甘ちゃんである。弱者の振りをして精神を揺さぶれば、きっと手玉に取れる。
事実、ミドはこの乾坤一擲の作戦を成功させ、みずきを追い詰めていた。
結果的に、ミドに騙されたみかどが、みずきが騙される後押しをしてしまった形だ。
さらには上記台詞の前段も、ミドは活用していた。
一つ目のメモリーが、以下である。
さらには上記台詞の前段も、ミドは活用していた。
一つ目のメモリーが、以下である。
『それにしても、みずき君の想い人とは一体誰なんだろうなあ。
ミサンガに関係ある人物だとは思うのだが……。』
ミサンガに関係ある人物だとは思うのだが……。』
これは、みずきの一回戦の対戦相手が一人・意志乃鞘の言葉である。
カフェテリアで談笑するヒーロー部員たちの会話に耳を澄ましていたミドは、当部の部長である鞘のこの発言を咄嗟に『ふかくこころにきざみこ』んだ。
一回戦のクライマックスで、鞘の情熱を袖にしたみずきは、確かにその時ミサンガを気にしていたように思えた。当事者の鞘が言うのだから、恐らく間違いないだろう。
カフェテリアで談笑するヒーロー部員たちの会話に耳を澄ましていたミドは、当部の部長である鞘のこの発言を咄嗟に『ふかくこころにきざみこ』んだ。
一回戦のクライマックスで、鞘の情熱を袖にしたみずきは、確かにその時ミサンガを気にしていたように思えた。当事者の鞘が言うのだから、恐らく間違いないだろう。
そこにきて、白王みかどの発言である。
男性関係に潔癖なみずきが、唯一心を許しているであろう存在。それが、兄。
二つの発現を符合させ、ミドはみずきのブラコンを見破り――ミサンガを解くという、非人道的行為にてみずきの心をへし折る策略を立てた。
男性関係に潔癖なみずきが、唯一心を許しているであろう存在。それが、兄。
二つの発現を符合させ、ミドはみずきのブラコンを見破り――ミサンガを解くという、非人道的行為にてみずきの心をへし折る策略を立てた。
『はあ、はあ……! みずきちゃん、敏感なんだね……! 眼鏡に撥ねた水滴にも感じてしまいそうなほど……! んんっ、最高だよおおおおっ!』
みかどと別れた後、授業をサボってブラブラしていた際に偶然通りがかった校内の一箇所で、ミドは扉にへばり付き自慰に耽る一∞を見かけた。
∞はみずきの名を呼んでおり、ミドは反射的に『ふかくこころにきざみこむ』。
三つ目のメモリーとして残されたこの台詞は、∞の能力の一つ『眼鏡サーチ』によって裏打ちされたみずきの敏感さを表しており、これがミドのビッチ戦術を生んだ。
∞はみずきの名を呼んでおり、ミドは反射的に『ふかくこころにきざみこむ』。
三つ目のメモリーとして残されたこの台詞は、∞の能力の一つ『眼鏡サーチ』によって裏打ちされたみずきの敏感さを表しており、これがミドのビッチ戦術を生んだ。
『こごえるビッチ』で誘い込み、『ビッチ』で無力化し、『ミサンガぎり』でトドメを刺す。
これが、ミドの『おもいだす』によって弾きだされた、白王みずきの攻略法。
【氷穴】MAPでのラスボス戦は、ミドにとって結果の分かり切った勝負だった。
これが、ミドの『おもいだす』によって弾きだされた、白王みずきの攻略法。
【氷穴】MAPでのラスボス戦は、ミドにとって結果の分かり切った勝負だった。
そして現在――。ミドの小さな尻の下には、仰向けに転がるみずきの姿があった。
今やみずきは、ミサンガだけでなく、築き上げた『絆』の証左たるメダルもリストバンドも、挙句は眼鏡すらも外され、数年ぶりの一糸纏わぬ姿を晒していた。
下着はとうに剥ぎ取られ、切り札のヘアゴムも抜け目なく取られた。
兄も仲間たちも離れ、心も折れ、身体は骨抜き、戦闘力も皆無。――絶体絶命だ。
今やみずきは、ミサンガだけでなく、築き上げた『絆』の証左たるメダルもリストバンドも、挙句は眼鏡すらも外され、数年ぶりの一糸纏わぬ姿を晒していた。
下着はとうに剥ぎ取られ、切り札のヘアゴムも抜け目なく取られた。
兄も仲間たちも離れ、心も折れ、身体は骨抜き、戦闘力も皆無。――絶体絶命だ。
「恋愛感情はまやかしで、仲間はビジネスパートナーよ。
『約束』だの『絆』だの、そんなもんを大事にしてる処女じゃ、私には勝てないよ」
『約束』だの『絆』だの、そんなもんを大事にしてる処女じゃ、私には勝てないよ」
言い放ちながら、ミドはみずきの恥丘に触れる。
淫靡な水音と共に体液が糸を引く。みずきの口からも、申し訳程度の喘ぎが響く。
心が折れ為されるがままになっていたみずきは、ミドの『ビッチ』によって完全に手籠めにされていた。
淫靡な水音と共に体液が糸を引く。みずきの口からも、申し訳程度の喘ぎが響く。
心が折れ為されるがままになっていたみずきは、ミドの『ビッチ』によって完全に手籠めにされていた。
「――そうだっ! 私がみずきちゃんの処女、もらってあげるっ!」
ことさら明るい声を出し、ミドは上体を曲げて何かを漁る。
それは、みずきが氷荀の森からミドを連れ出した際に一緒に運んできた、脱いだブラウスやブラに、ミドの武器たる伝説の剣『まるごし』等の装備一式であった。
ミドはブラウスに包まれたナイフを取り出し、近くに一本だけ生えていた氷荀を柄で叩いて折ると、ナイフは一旦戻し、透き通る氷荀をぺろりと舐めて言う。
それは、みずきが氷荀の森からミドを連れ出した際に一緒に運んできた、脱いだブラウスやブラに、ミドの武器たる伝説の剣『まるごし』等の装備一式であった。
ミドはブラウスに包まれたナイフを取り出し、近くに一本だけ生えていた氷荀を柄で叩いて折ると、ナイフは一旦戻し、透き通る氷荀をぺろりと舐めて言う。
「これで、私と同じ『氷荀プレイ』……しましょ♪」
氷荀が光苔に淡く照らされ妖しさを際立たせる中、みずきは思考の海を漂っていた。
奪われたミサンガ。自分をここまで支えてくれた、兄そのものを失った。
光の届かない暗闇に閉じ籠ったみずきに、声が聞こえた。
奪われたミサンガ。自分をここまで支えてくれた、兄そのものを失った。
光の届かない暗闇に閉じ籠ったみずきに、声が聞こえた。
――決勝戦こそ、正々堂々相手とぶつかり合い、そして勝つんだ。
――君が確かな勝利を手にした、その時こそ、僕は君を迎えに行こう。祝福しよう。
――我が妹の、華々しい活躍を切に期待しているよ。
――君が確かな勝利を手にした、その時こそ、僕は君を迎えに行こう。祝福しよう。
――我が妹の、華々しい活躍を切に期待しているよ。
それは、最愛の兄の言葉。いや、それは全てが正しいわけじゃない。
言葉こそ兄のものだが、これは手紙の文面。実際に兄の声で再生はされない。
この声は……自分のものだ。兄の言葉を読み上げ、自分自身を鼓舞している。
言葉こそ兄のものだが、これは手紙の文面。実際に兄の声で再生はされない。
この声は……自分のものだ。兄の言葉を読み上げ、自分自身を鼓舞している。
そう、みずきの中にも、まだ立ち上がる意志は残されてた。
でもその意志を持つみずきは少ない。多くのみずきが、このままを望んでいた。
最後の灯火は、まさしく風前であった。だが、火とは得てして消え際に燃え上がる!
でもその意志を持つみずきは少ない。多くのみずきが、このままを望んでいた。
最後の灯火は、まさしく風前であった。だが、火とは得てして消え際に燃え上がる!
――確かにミサンガは兄さんのくれたものです。ではミサンガは兄さんですか?
――違うでしょう! 兄さんは、私たちの心で赫々と燃えるこの『想い』です!
――ミサンガがなくなったら兄さんは失われますか!? 違いますよね!?
――違うでしょう! 兄さんは、私たちの心で赫々と燃えるこの『想い』です!
――ミサンガがなくなったら兄さんは失われますか!? 違いますよね!?
――勝負を諦めた時、はじめて兄さんが失われるのですっ!!
俯いていたみずきたちが、その頭をあげた。
愛しの兄は、『正々堂々』『ぶつかり合い』『勝つ』ことを望んだ。
そして『その時』、『迎えに』来ると言ったのだ。
愛しの兄は、『正々堂々』『ぶつかり合い』『勝つ』ことを望んだ。
そして『その時』、『迎えに』来ると言ったのだ。
暗き世界が、暖かな光によって照らされ――――。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「くああっ!」
凄まじい衝撃がみかどを襲う。
股ノ海の張り手を後ろに跳びながら握った帝ソードで受けるも、その威力は殺しきれず
ガリガリと地面を削りながら後退る。
なんとか剣を取り零さずには済んだが、戦況は芳しくなかった。
股ノ海の張り手を後ろに跳びながら握った帝ソードで受けるも、その威力は殺しきれず
ガリガリと地面を削りながら後退る。
なんとか剣を取り零さずには済んだが、戦況は芳しくなかった。
「これが関脇の本気か……! ふ、ふ、ふ。面白いじゃないか……!」
口では強がるみかどだったが、一方では冷静に勝機の薄いことを自覚していた。
股ノ海は一撃一撃が重く、さらには相撲の技だけでなく柔道技や蹴り技、果ては関節技までを体得している。
鍛え抜かれた肉体は矛であり、また盾でもあった。閃光と共に繰り出すみかどの攻撃は確かに股ノ海に命中するが、効果はいまひとつ。みかどが一方的に消耗するのみ。
股ノ海は一撃一撃が重く、さらには相撲の技だけでなく柔道技や蹴り技、果ては関節技までを体得している。
鍛え抜かれた肉体は矛であり、また盾でもあった。閃光と共に繰り出すみかどの攻撃は確かに股ノ海に命中するが、効果はいまひとつ。みかどが一方的に消耗するのみ。
「Coooooo――!」
おまけに謎の呼吸法まで身につけている。
実力の差は明白。みかどの脳裏に『敗北』の二文字が浮かびかけた。
だが、みかどはそれを叩き潰した。笑みすらも湛え、剣を構え直す。
実力の差は明白。みかどの脳裏に『敗北』の二文字が浮かびかけた。
だが、みかどはそれを叩き潰した。笑みすらも湛え、剣を構え直す。
「今頃、みずきも戦っている……! どんな窮地でも、きっと諦めないはずさ……!
だったら、兄たる僕が諦めるわけにはいかないな! 絶対に、勝って見せる!!」
だったら、兄たる僕が諦めるわけにはいかないな! 絶対に、勝って見せる!!」
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「ふふっ、安心して。これだけ濡れてれば痛くないし、スグに良くなるから♪」
未だ動かないみずきの下腹部に氷荀を宛がい、にこやかに笑うミド。
無垢な少女の純潔が散る瞬間を待ち切れぬ様に、その手に力が込められる。
そして輸送を開始せんとした、その時――。
無垢な少女の純潔が散る瞬間を待ち切れぬ様に、その手に力が込められる。
そして輸送を開始せんとした、その時――。
――しぱっ。
鋭い音がしたかと思うと、標準はミドの握る部分のみとなっていた。先端が、ない。
鋭い音がしたかと思うと、標準はミドの握る部分のみとなっていた。先端が、ない。
「えっ――」
脳が自力で答えに辿り着くのを待てぬように、離れた位置で涼やかな落下音がした。
そこに転がるは、惚れ惚れするような切断面をこちらに向けた氷荀。
真相に辿り着くと同時に、ミドはみずきに押し倒されていた。
そこに転がるは、惚れ惚れするような切断面をこちらに向けた氷荀。
真相に辿り着くと同時に、ミドはみずきに押し倒されていた。
「きゃあっ! あ、あんた――!」
「ミサンガがなくても! 皆さんのくれたものが奪われても!
『想い』は私と共に在ります! 諦めてなんて、やるもんですかっ――!!」
『想い』は私と共に在ります! 諦めてなんて、やるもんですかっ――!!」
激情を叫びながら、みずきは今度は、自分からミドに口付けた。舌も入れた。
たどたどしい舌遣いは素人のそれだったが、初めての反攻にミドは対処が遅れる。
とはいえ、ミドも百戦錬磨の猛者である。処女のテクニックに翻弄されるようではビッチの名が廃ると言うもの。すぐさま反撃に転じ、みずきを脱力させる。
そしてみずきの身体を押し退けて立ち上がる。口中の唾液を飲み下し口を開く。
たどたどしい舌遣いは素人のそれだったが、初めての反攻にミドは対処が遅れる。
とはいえ、ミドも百戦錬磨の猛者である。処女のテクニックに翻弄されるようではビッチの名が廃ると言うもの。すぐさま反撃に転じ、みずきを脱力させる。
そしてみずきの身体を押し退けて立ち上がる。口中の唾液を飲み下し口を開く。
「ふ、んっ! 驚いたけど、そんなテクで私を攻めようなんて百年早―― っ!?」
異変は、身体の内側から起こっていた。
それは言うなれば、内臓を愛撫されるに等しかった。未だかつてない快楽が襲う。
巨根や触手が子宮深くまでを抉るのとは決定的に違う、別次元からの征服であった。
それは言うなれば、内臓を愛撫されるに等しかった。未だかつてない快楽が襲う。
巨根や触手が子宮深くまでを抉るのとは決定的に違う、別次元からの征服であった。
「な、に、これえ……! はっ、はじめてっ……だよおっ……!!」
かたかたと震え股間は洪水を引き起こしながら、ミドはやっとのことで問いかける。
みずきは黙したまま、荒い息をついてへたり込んでいる。
みずきは黙したまま、荒い息をついてへたり込んでいる。
白王みずきの『みずのはごろも』は水を纏い、操る能力である。
しかしその効力は字面ほど強いと言えなかった。
例えば『操る』方では、量や方向、勢い等の調節はまだしも、命令自体はかなり大雑把にしか設定することができない。利用法が水弾一辺倒なのもこのためだ。
また、『水』の解釈も緩めとはいえ、この能力は最大に利用しうる『水』を能力対象に選択することができなかった。『己の体液』である。
しかしその効力は字面ほど強いと言えなかった。
例えば『操る』方では、量や方向、勢い等の調節はまだしも、命令自体はかなり大雑把にしか設定することができない。利用法が水弾一辺倒なのもこのためだ。
また、『水』の解釈も緩めとはいえ、この能力は最大に利用しうる『水』を能力対象に選択することができなかった。『己の体液』である。
これが可能であれば、衣服を消費しつくした後も汗や涙で戦うことが出来たろう。
だが、「血とかが衣服になったら、私の血管はどうなってしまうのでしょう……」というスプラッタな想像がブレーキをかけたのか、みずきは己の体液は纏えなかった。
それでも、『他人の体液』なら纏える。みずき自身意識したことはなかったが、出来ると言う確信めいた『認識』を信じ、ミドを相手にぶっつけ本番で試した。
だが、「血とかが衣服になったら、私の血管はどうなってしまうのでしょう……」というスプラッタな想像がブレーキをかけたのか、みずきは己の体液は纏えなかった。
それでも、『他人の体液』なら纏える。みずき自身意識したことはなかったが、出来ると言う確信めいた『認識』を信じ、ミドを相手にぶっつけ本番で試した。
すなわち、みずきは反攻の際に舐めとったミドの唾液を口中で纏い、ミドの反撃にあわせて纏うのを解除した。飲み込まれたミドの唾液はみずきの支配下にある。
与えた命令は至ってシンプル――『這って下さい』。
埴井ホーネットの蜂姦調教をヒントに土壇場で編み出した、一発逆転の奥義である。
与えた命令は至ってシンプル――『這って下さい』。
埴井ホーネットの蜂姦調教をヒントに土壇場で編み出した、一発逆転の奥義である。
ちなみにみずきがミドの唾液で生成したのは、驚くなかれ、マルチブラケット――歯列の矯正器具である。
『みずのはごろも』の解釈に広さは前述した通りであるが、その材質のレパートリーもまた広い。一回戦で生成したスパイクなどでは、金属をも再現していたのだから。
ただ、金属の質感や重量は『認識』できていても、詳しい硬度や化学的反応などは教科書レベルの曖昧な『認識』でしかないため、これで戦うといった真似は不可能だが。
『みずのはごろも』の解釈に広さは前述した通りであるが、その材質のレパートリーもまた広い。一回戦で生成したスパイクなどでは、金属をも再現していたのだから。
ただ、金属の質感や重量は『認識』できていても、詳しい硬度や化学的反応などは教科書レベルの曖昧な『認識』でしかないため、これで戦うといった真似は不可能だが。
「ふ、ふふふふ。すごいよっ、こんなっ! こんなのが、あったなんてえ!」
喘ぎ続けるミドであったが、みずきはこれで勝ったとは思っていなかった。
『みずのはごろも』が水を制御化に置く時間は永続でないどころか、さほど長くない。
ミドを倒すには、次の一手が必要だ。そう考えたみずきは、静かに動きだす。
『みずのはごろも』が水を制御化に置く時間は永続でないどころか、さほど長くない。
ミドを倒すには、次の一手が必要だ。そう考えたみずきは、静かに動きだす。
「ふああっ、あっ、あっ、……。あえっ……もう、終わり……?」
つい名残惜しそうな本心が出てしまったが、冷静になってみれば危なかった。
この素人娘の浅知恵で、ミドはイカされかけたのである。
みずきのエロポテンシャルの高さに僅かばかりの畏れを抱いたミドは、一旦体勢を立て直さんとその場を離れようとしたが――。
この素人娘の浅知恵で、ミドはイカされかけたのである。
みずきのエロポテンシャルの高さに僅かばかりの畏れを抱いたミドは、一旦体勢を立て直さんとその場を離れようとしたが――。
「行かせません! あなたは、ここで降参させますっ!」
みずきの声を背中で聞く。
転ばぬよう慎重に移動しながら、ちらと振り返った先には、水着にパレオを巻いた姿のみずきがいた。心が折れたときに制御を失い湯に戻った制服やらが、【氷穴】内の氷を溶かしてできた水を纏ったのだ。その水で生成できる限界が水着とパレオなのだろう。
当初の攻略法は完全に崩れた。ミドには新たな策を練るため時間が必要だった。
転ばぬよう慎重に移動しながら、ちらと振り返った先には、水着にパレオを巻いた姿のみずきがいた。心が折れたときに制御を失い湯に戻った制服やらが、【氷穴】内の氷を溶かしてできた水を纏ったのだ。その水で生成できる限界が水着とパレオなのだろう。
当初の攻略法は完全に崩れた。ミドには新たな策を練るため時間が必要だった。
「能力復活とか、冗談じゃないわよ……! これでも、くらえっ!」
服が置いてある場所へと急ぐ過程で、ミドは氷漬けになったぱんつを拾っていた。
みずきに肩を借りて移動する最中に脱げて凍ったぱんつを放り投げると、畳まれたブラウスの上に置いたナイフでそれを突き砕き、礫の如く飛ばした。
無論、飛距離も威力もなきに等しい。これはみずきの練り上げられた注意力をひっぺがす――『いてつくぱんつ』だ! 本命は、それに隠れて飛来するナイフ!
みずきに肩を借りて移動する最中に脱げて凍ったぱんつを放り投げると、畳まれたブラウスの上に置いたナイフでそれを突き砕き、礫の如く飛ばした。
無論、飛距離も威力もなきに等しい。これはみずきの練り上げられた注意力をひっぺがす――『いてつくぱんつ』だ! 本命は、それに隠れて飛来するナイフ!
「見せてあげます。私の中に息づく、みなさんとの『絆』を――!」
みずきの声が聞こえた気がした。ナイフが迫り、一刻の猶予もないはずなのに。
胸の中央めがけて滑空するナイフは、涼やかな音色を奏でて胸に刺さった。
いや、おかしい。目と耳を疑うミドだったが、どちらも嘘はついていなかった。
胸の中央めがけて滑空するナイフは、涼やかな音色を奏でて胸に刺さった。
いや、おかしい。目と耳を疑うミドだったが、どちらも嘘はついていなかった。
「――『この胸にキミを抱きしめたい』!!」
みずきの胸からは、透き通る手が生えていた。
水着の胸の部分を人の手めいた形で小さく放射し、僅かな時間で凍結させたのだ。
何せ、元がこの【氷穴】の氷である。纏う過程の超低温にさえ耐えきってしまえば、保存された超低温が、解除と同時に固体を取り戻すのは必然である。
水着の胸の部分を人の手めいた形で小さく放射し、僅かな時間で凍結させたのだ。
何せ、元がこの【氷穴】の氷である。纏う過程の超低温にさえ耐えきってしまえば、保存された超低温が、解除と同時に固体を取り戻すのは必然である。
「それって……確か……!」
みずきの一回戦の相手のひとり・糺礼の魔人能力の再現であった。
トーナメントで只一人みずきがマトモに交戦した相手である彼女は、意志の疎通こそ為せなかったがみずきの魂にその技術や能力を強く印象付けた。
礼と戦えてよかった。みずきは今ではそう思っていた。
トーナメントで只一人みずきがマトモに交戦した相手である彼女は、意志の疎通こそ為せなかったがみずきの魂にその技術や能力を強く印象付けた。
礼と戦えてよかった。みずきは今ではそう思っていた。
「こっちの番です!」
みずきが人差し指を前方に掲げる。嫌な予感がミドの背筋を撫ぜた。
直後、指先より細長く放たれる水流。それもすぐさま凍り、質量を得たビームの如くにミドに迫ってゆく。
ミドは辛うじて足元の『まるごし』を広い、間一髪で避けた。
直後、指先より細長く放たれる水流。それもすぐさま凍り、質量を得たビームの如くにミドに迫ってゆく。
ミドは辛うじて足元の『まるごし』を広い、間一髪で避けた。
「今度は、鞘せんぱいの力です! 『クーゲルシュライバー』!!」
意志乃鞘の能力『HERO DESTINY』は論理能力であり、流石に『みずのはごろも』による再現は不可能であった。
故にみずきは鞘の主武装であった改造ペンに望みを託した。
メダルはなかったが、鞘のヒーローたらんとする心意気はその胸で燃え続けていた。
故にみずきは鞘の主武装であった改造ペンに望みを託した。
メダルはなかったが、鞘のヒーローたらんとする心意気はその胸で燃え続けていた。
「ちょっ……! これ、キツイって!」
ビームに追い立てられながらミドは遁走する。
オリジナルのクーゲルシュライバーには一発撃ったらバッテリーが空になるという弱点が存在したが、みずきの場合は纏っている分だけ照射できる。
右から左から放たれるビームがミドの進行ルートを掌握していた。
オリジナルのクーゲルシュライバーには一発撃ったらバッテリーが空になるという弱点が存在したが、みずきの場合は纏っている分だけ照射できる。
右から左から放たれるビームがミドの進行ルートを掌握していた。
逃げ惑って辿り着いたのは、薄氷の張った地底湖の上。
小柄で華奢なミドだからこそギリギリで支えられていたが、長居は実際危険である。
もしも落ちれば、下には極寒の水が待ち受けている。命の保証はない。
小柄で華奢なミドだからこそギリギリで支えられていたが、長居は実際危険である。
もしも落ちれば、下には極寒の水が待ち受けている。命の保証はない。
脱出を画策するミドだったが、みずきのビームが移動を制限するだろう。
逃げ場なし。厳しい状況の中、さらなる声が響く。
逃げ場なし。厳しい状況の中、さらなる声が響く。
「次は莉子せんぱい、力を貸して下さい! 『メルティーボム』っ!!」
みずきは握りこんでいた四本の指を広げ、球状に水を斜方投射した。
放たれた水球は中空で凍り、質量を得て降下する。
思わずその行方を目で追っていたミドだったが――はたと気付く。
迫る氷塊。薄氷の湖。その上に立つ自分――。
放たれた水球は中空で凍り、質量を得て降下する。
思わずその行方を目で追っていたミドだったが――はたと気付く。
迫る氷塊。薄氷の湖。その上に立つ自分――。
「えっ、ちょっ、嘘お――!?」
チョコを起爆させる莉子の『メルティーボム』も、みずきには再現不能な能力だ。
よってみずきは、今度はその活用法をコピーした。
一回戦で【摩天楼】のビルを倒壊せしめたその光景を、【氷穴】の地底湖に再現する。
よってみずきは、今度はその活用法をコピーした。
一回戦で【摩天楼】のビルを倒壊せしめたその光景を、【氷穴】の地底湖に再現する。
果たして氷塊は湖に落ちる。
薄氷に穴があき、波紋を描くかのように周囲に罅が広がってゆく。
遂には打開策を求め必死に頭を回すミドの足元へも――。
薄氷に穴があき、波紋を描くかのように周囲に罅が広がってゆく。
遂には打開策を求め必死に頭を回すミドの足元へも――。
「――――!!」
ミドを支える氷は割れた。
重力の手が少女を掴み、魔物の口の中へと引きずり込む――。
重力の手が少女を掴み、魔物の口の中へと引きずり込む――。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「ハイ!(high:「高い」という意味の英語)
ニイ!(knee:「ひざ」という意味の英語)
ヤッ!(yah:「Yes」という意味の英語)」
ニイ!(knee:「ひざ」という意味の英語)
ヤッ!(yah:「Yes」という意味の英語)」
火打石の力士から生じた火球がみかどを襲う。
帝ソードを振るい全てを叩き落とすが、股ノ海は擦り足で距離を詰めてくる。
みかどは閃光を放ち姿をくらます――が、股ノ海はそれすらも捉えてきた。
帝ソードを振るい全てを叩き落とすが、股ノ海は擦り足で距離を詰めてくる。
みかどは閃光を放ち姿をくらます――が、股ノ海はそれすらも捉えてきた。
「どすこい!(doss-coil:掛け声。特に意味はない)」
「ぐうあっ!」
跳ね飛ばされるみかど。さながら土俵際まで追い詰められた形だ。
英検に、心眼。牙を剥く関脇の実力をみかどは痛感していた。
しかしてみかどに絶望はない。逆転の策が胸にあったのだ。
英検に、心眼。牙を剥く関脇の実力をみかどは痛感していた。
しかしてみかどに絶望はない。逆転の策が胸にあったのだ。
「僕をここまで追い詰めたのは、貴様が初めてだ……。だが、これでどうだあっ!!」
突進するみかど。その勢いのままに、剣を地面に接触させる。
発生する閃光。だが、これまでの比ではない。心眼をも眩まし、股ノ海は顔を背ける。
みかどの纏う『ひかりのよろい』を喰い尽くさんばかりに遣い、やがて生まれるは稲妻めいた大閃光――!
発生する閃光。だが、これまでの比ではない。心眼をも眩まし、股ノ海は顔を背ける。
みかどの纏う『ひかりのよろい』を喰い尽くさんばかりに遣い、やがて生まれるは稲妻めいた大閃光――!
「――『ギガスラッシュ』!!」
白王みかど最強の一撃が、股ノ海を襲った。
激突の刹那、みかどは確かに手ごたえを感じた。あの大山の如き股ノ海を動かした。
みかどの服装は鎧もマントも消えうせ、今や簡素な『ぬののふく』状態だ。
激突の刹那、みかどは確かに手ごたえを感じた。あの大山の如き股ノ海を動かした。
みかどの服装は鎧もマントも消えうせ、今や簡素な『ぬののふく』状態だ。
「ぜえ、ぜえ……。くっ、はーっはっは! これぞ『風紀皇帝』たる僕の必殺技――」
「――ゴッツァンデス(gots-and-death:「獲得と死」という意味の英語)」
股ノ海が姿を現した。
唇からは血が垂れ、身体もところどころ焦げていたが、まだ戦えそうである。
みかどは戦慄する。よもやこれほどのタフネスとは――。
唇からは血が垂れ、身体もところどころ焦げていたが、まだ戦えそうである。
みかどは戦慄する。よもやこれほどのタフネスとは――。
「――失礼した。民間人に本気を出してはまずいと、力をセーブしていたが……。
あなたほどの武人なら、自分も本気の相撲をお見せするのが筋というもの」
あなたほどの武人なら、自分も本気の相撲をお見せするのが筋というもの」
――本気! これからが、だ。
みかどは今度こそ絶望しかけた。視界が遠くなるのを感じる。
そんなみかどの前で、股ノ海はまわしに手を掛け、それを解いた。
みかどは今度こそ絶望しかけた。視界が遠くなるのを感じる。
そんなみかどの前で、股ノ海はまわしに手を掛け、それを解いた。
「!!」
「もっとスピードが必要だ……」
解けた帯は、そのまま地面に落ちる。特別重いわけでもなかった。
ともかく、ここからが股ノ海の本領発揮らしい。雄々しき一物も気合十分だ。
一方みかどは、拘束解除の股ノ海の姿を見て、顔を真っ赤にして、口をパクパクといわせている。そして、次の瞬間――。
ともかく、ここからが股ノ海の本領発揮らしい。雄々しき一物も気合十分だ。
一方みかどは、拘束解除の股ノ海の姿を見て、顔を真っ赤にして、口をパクパクといわせている。そして、次の瞬間――。
「いっ、いやああああああああああああああっ!!」
甲高い悲鳴を上げながら、股ノ海の股間を帝ソードでフルスイングした!
「――っ!!」
言葉にならない股ノ海。確実に『ギガスラッシュ』よりも痛そうだ。
思わず膝をついた股ノ海には目もくれず、そのままみかどは走り去った。
額に脂汗を浮かべ荒い呼吸を整えながら、股ノ海は呟く。
思わず膝をついた股ノ海には目もくれず、そのままみかどは走り去った。
額に脂汗を浮かべ荒い呼吸を整えながら、股ノ海は呟く。
「じ……自分の負け、か」
股ノ海は、膝をついていた。相撲のルールでは、土俵に膝をつくと負けである。
高速で走り去ったみかども土俵を割っていたが、股ノ海の屈服の方が先であった。
高速で走り去ったみかども土俵を割っていたが、股ノ海の屈服の方が先であった。
「……自分の相撲がとれた。悔いはない」
爽やかに笑う股ノ海。その表情は勝者を讃えていた。
そんな彼の肩に、ぽんと手が乗せられる。
振り返った先には、警察官が立っていた。
そんな彼の肩に、ぽんと手が乗せられる。
振り返った先には、警察官が立っていた。
「えーと、ちょっと署までご同行願えますかな?」
全裸の股ノ海は、パトカーに収容され何処かへ消えた。
【決まり手:もろだし】――!
なお、白王みかどは女の子である。
息子を欲しがった父親により男子として育てられ、自身もそのように振る舞っているはが、男性の裸で真っ赤になるほどには乙女な心を秘めている。
みずきがこの事実を知るのは、もう少し先の話である――。
息子を欲しがった父親により男子として育てられ、自身もそのように振る舞っているはが、男性の裸で真っ赤になるほどには乙女な心を秘めている。
みずきがこの事実を知るのは、もう少し先の話である――。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「――まだ言わないんですね。あなたも、諦めの悪いひとなんですね」
気がつけば、ミドは生きていた。
思ったほど冷たくない。というか、水中にいなかった。陸上にも、だ。
宙を浮いていたのだ。右腕を掴む手の感触が暖かい。
思ったほど冷たくない。というか、水中にいなかった。陸上にも、だ。
宙を浮いていたのだ。右腕を掴む手の感触が暖かい。
「あ、あんた……。どうして、浮いて……」
「あは、やっぱりそう見えますか? ふふっ、『インフィールドフライ』ですっ!!」
みずきは水球を放った後、パレオの残りの布地全てを消費し、小さな波を生んだ。
それはすぐさま凍り、ミドを飛び越え地底湖に架かるアーチを描いた。
そして水着のぱんつ部分を足元から噴射し、アーチを滑り落下するミドの手を掴んだ。
それはすぐさま凍り、ミドを飛び越え地底湖に架かるアーチを描いた。
そして水着のぱんつ部分を足元から噴射し、アーチを滑り落下するミドの手を掴んだ。
透き通るアーチは、光苔に照らされ神秘的な雰囲気を醸し出している。
目を凝らさねば見えぬそれは湖に眼鏡を取り落としたミドにとっては無きに等しく、まるでみずきが不動昭良の『インフィールドフライ』で浮遊しているようであった。
呆けたようなミドに、みずきは言葉を紡ぐ。
目を凝らさねば見えぬそれは湖に眼鏡を取り落としたミドにとっては無きに等しく、まるでみずきが不動昭良の『インフィールドフライ』で浮遊しているようであった。
呆けたようなミドに、みずきは言葉を紡ぐ。
「私はですね。甘ちゃんでも、しょ……ぇと、はい、なんでもいいんですっ。
だって、大切なんですもん。『想い』も『絆』も、もちろん、ミドさんのことも」
だって、大切なんですもん。『想い』も『絆』も、もちろん、ミドさんのことも」
右腕を握る力が増す。加わる力がミドに不思議な感情を芽生えさせていた。
と、薄氷のアーチが軋みだす。流石に二人分の体重を支えるのは無茶であった。
と、薄氷のアーチが軋みだす。流石に二人分の体重を支えるのは無茶であった。
「ど、ど、どうしましょう……!」
慌てふためくみずき。そんなみずきに笑いかけ、ミドは呟く。
「こうすればいいんだよ。私、降参でーす」
ミドの言葉と共に、アーチが崩れた。落下するみずきとミド。
転送リングに包まれながら、二人はどちらともなく互いを抱き締めた。 <終>
転送リングに包まれながら、二人はどちらともなく互いを抱き締めた。 <終>