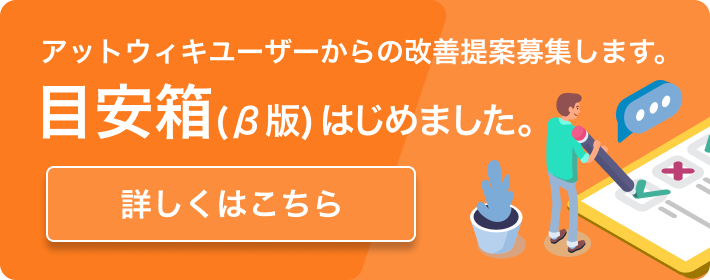『白王みずき 幕間SS みかどエンペラー』(by あやまだ)
「ああ、もう! どいつもこいつも分かっちゃいないっ!」
がちゃんっ! と、硝子と硝子のぶつかり合う音が響き、白王みどりは何度目とも分からぬ溜め息をついた。
白王みどりは主婦である。現在は娘と二人で暮らしている。
今は平日の昼過ぎ。品行方正な女子高生たる娘・みずきは学校にいるため、白王家にはみどりしかいないはずである――が。
白王みどりは主婦である。現在は娘と二人で暮らしている。
今は平日の昼過ぎ。品行方正な女子高生たる娘・みずきは学校にいるため、白王家にはみどりしかいないはずである――が。
「何が『もっと自重しろ』だ! 高貴なる僕の強大なる能力を妬んだに違いない! まったく、これだから庶民は!」
「あんたも庶民でしょうが……」
「うるさーいっ! 僕は皇帝だ! 早く次を持って来いっ!」
ソファに腰掛け、コーラの瓶を片手にくだを巻く人物――白王家のもう一人の子どもである、自称『風紀皇帝』白王みかど、その人であった。
数年前に父親と共に家を出て、全国を流浪しながら風紀の乱れを正してきたみかどは、ひょんなことから懐かしき地・希望崎へと舞い戻ってきた。
その際に希望崎において行われた秘密主義者たちによるハルマゲドンに参戦し、先陣切って粛清すべき変態どもを叩き潰そうと息巻いていたのだが――。
数年前に父親と共に家を出て、全国を流浪しながら風紀の乱れを正してきたみかどは、ひょんなことから懐かしき地・希望崎へと舞い戻ってきた。
その際に希望崎において行われた秘密主義者たちによるハルマゲドンに参戦し、先陣切って粛清すべき変態どもを叩き潰そうと息巻いていたのだが――。
「チームの方針に合わないって、戦列から外されたんだっけ?」
「そう! よく分かったな、さすがは母上だ!」
「(何度も聞かされたからねぇ……)」
次のコーラを差し出しながら、みどりはまたも、大きな溜息をつく。
意気揚々と秘密番長グループに加わったみかどは、そこで予期せぬ不当な扱いを受け、最終的に自分から戦列を辞した――とは本人の談だが、どこまで本当かは定かではない。少なくとも、戦わせてもらえなかったことは、この振る舞いからして確からしいが。
そんなこんなで実家へとやってきたみかどは、開口一番に「ヤケ酒だ!」と叫び、コーラをラッパ飲みしながら今のような酔っ払いになり果てた。
後片付けをさせられている母・みどりは、久方ぶりの再会を喜ぶ暇もなく「こいつ早くどっか行かねーかな」とすら思っていた。
意気揚々と秘密番長グループに加わったみかどは、そこで予期せぬ不当な扱いを受け、最終的に自分から戦列を辞した――とは本人の談だが、どこまで本当かは定かではない。少なくとも、戦わせてもらえなかったことは、この振る舞いからして確からしいが。
そんなこんなで実家へとやってきたみかどは、開口一番に「ヤケ酒だ!」と叫び、コーラをラッパ飲みしながら今のような酔っ払いになり果てた。
後片付けをさせられている母・みどりは、久方ぶりの再会を喜ぶ暇もなく「こいつ早くどっか行かねーかな」とすら思っていた。
「ああ、そういえば、みずきには会っていかないの?」
どっかに行って欲しい一念で振った話題だったが、これが意外にも好手であった。
「おお、みずきか! あいつにもしばらく会ってなかったからなあ……。ふふっ、僕との約束を守り、立派な女性になっているだろうか……!」
「ああー……、うん。今学校にいるだろうから、見に行けばいいんじゃないかな……」
トーナメントでのみずきの戦いぶりを思い出し、“立派な女性”というセリフを素直に肯定しかねたみどりは言葉を濁しながら、みかどに暗に「出ていけ」と促す。
いい感じに酔った(コーラで!)みかどはそんな言葉の裏に気付いた様子もなく、すっくと立ち上がり、玄関へと歩を進める。
その表情は晴れやかである。扉を開けながら、青空に向かってつぶやく。
いい感じに酔った(コーラで!)みかどはそんな言葉の裏に気付いた様子もなく、すっくと立ち上がり、玄関へと歩を進める。
その表情は晴れやかである。扉を開けながら、青空に向かってつぶやく。
「あのミサンガは、まだ着けているかな……。ああ、待ち遠しいぞ、みずきっ!」
一方、当のみずきは、暗雲に覆われたような表情で学校の廊下を歩いていた。
傍らを並行する吾妻操子が、心配そうに尋ねる。
傍らを並行する吾妻操子が、心配そうに尋ねる。
「ま、まあ……あんまり気落ちしないことだよ、うん。あんたは悪くないって」
「ありがとうございます……。でも、私がキッカケであることは間違いないですし……」
操子は既に、みずきの口からその憂鬱の理由を聞いていた。
トーナメント準決勝において、みずきに悪気はなかったとはいえ、彼女は対戦相手の少年・不動昭良を『転校生』と変じさせてしまっていた。
他人の人生を狂わせてしまうに等しい己の所業を、みずきは心底悔いていた。
トーナメント準決勝において、みずきに悪気はなかったとはいえ、彼女は対戦相手の少年・不動昭良を『転校生』と変じさせてしまっていた。
他人の人生を狂わせてしまうに等しい己の所業を、みずきは心底悔いていた。
みずきは、今朝よりずっとこの調子であった。
操子をはじめとした風紀委員の仲間たちも彼女を励まそうとしたが、効果はなかった。
暗くなっているみずきと、どうしたものかなあ、と悩む操子。並んで歩く二人の元へ、前方から、一般風紀委員の少女が息を切らしながら走り寄ってきた。
操子をはじめとした風紀委員の仲間たちも彼女を励まそうとしたが、効果はなかった。
暗くなっているみずきと、どうしたものかなあ、と悩む操子。並んで歩く二人の元へ、前方から、一般風紀委員の少女が息を切らしながら走り寄ってきた。
「た、大変ですっ!」
そう叫びながら、少女は窓の外を指さす。釣られるがままにその方を向く二人。
すると、眼下のグラウンド――その片隅。部活動の昼練に勤しむ生徒たちからは少しばかり離れた位置で、一人の少女が大量の触手に襲われているではないか!
緊急事態である。現場への最短ルートを思案し始める操子の横をすり抜けみずきは窓に飛び付きそれを開けると、サッシに手を掛け、そこから飛び降りた――!
すると、眼下のグラウンド――その片隅。部活動の昼練に勤しむ生徒たちからは少しばかり離れた位置で、一人の少女が大量の触手に襲われているではないか!
緊急事態である。現場への最短ルートを思案し始める操子の横をすり抜けみずきは窓に飛び付きそれを開けると、サッシに手を掛け、そこから飛び降りた――!
「ちょっ、ばか、みずきっ!」
「お先に失礼しますっ!」
スカートを押さえながら落下するみずき。いくら魔人の肉体を持つとはいえ、ここは三階である。操子もみずきの行方を追おうと慌てて窓から首を出す。
みずきは自由落下に身を任せていたが、絶妙なタイミングで足の裏より水を噴射。落下スピードを相殺し、見事衝撃をやわらげ、無事に地上に降り立った。
対戦後、メールのやり取りをするようになった卓越した空間把握能力を持つ羽山莉子がある時教えてくれた、『高い所から落ちても大丈夫な方法 ~学校編~』が役に立った。
みずきは自由落下に身を任せていたが、絶妙なタイミングで足の裏より水を噴射。落下スピードを相殺し、見事衝撃をやわらげ、無事に地上に降り立った。
対戦後、メールのやり取りをするようになった卓越した空間把握能力を持つ羽山莉子がある時教えてくれた、『高い所から落ちても大丈夫な方法 ~学校編~』が役に立った。
「……みずきっ! 私が着くまで、無茶するんじゃないわよっ!」
疾走し、どんどん小さくなるみずきの背中めがけて叫ぶ操子。
操子の目に、みずきはどうも死に急いでいるように映ったのである。
独断専行や窓からの飛び降りなど、『らしくない』その行動に、不安は拭えなかった。
操子の目に、みずきはどうも死に急いでいるように映ったのである。
独断専行や窓からの飛び降りなど、『らしくない』その行動に、不安は拭えなかった。
間もなく、みずきは問題の現場へと到着した。
そこで彼女を待ち受けていたのは、触手に襲われ泣き叫ぶ哀れな少女――ではなく、全身で快楽を享受する少女の姿。
みずきの頭上にいくつもの疑問符が浮かぶ。ここで、少女が口を開いた。
そこで彼女を待ち受けていたのは、触手に襲われ泣き叫ぶ哀れな少女――ではなく、全身で快楽を享受する少女の姿。
みずきの頭上にいくつもの疑問符が浮かぶ。ここで、少女が口を開いた。
「あああっ! そこ、いいですっ! すごくいいですっ! もっと激しくう!」
傍らには、ビデオカメラをまわしながら檄を飛ばす女性。
「ほら、みんな! ホーネットちゃんもこう言ってるわよ! もっと頑張りなさい!
さあっ! えぐりこむように、犯すべしっ! 犯すべしっ! 犯すべしっ!!」
さあっ! えぐりこむように、犯すべしっ! 犯すべしっ! 犯すべしっ!!」
犯されたるは、蜂と触手をこよなく愛する少女・埴井ホーネット。
少女の傍らで撮影するは、天才プロデュース魔人・悪鬼悖屋Sucie。ホーネットを犯しているのは、彼女がプロデュースした触手アイドルグループ・SKS48である。
どちらも風紀委員のブラックリストにその名を連ねる問題児である。
少女の傍らで撮影するは、天才プロデュース魔人・悪鬼悖屋Sucie。ホーネットを犯しているのは、彼女がプロデュースした触手アイドルグループ・SKS48である。
どちらも風紀委員のブラックリストにその名を連ねる問題児である。
「い、一体、これは……!?」
困惑するみずき。
説明すると、これはSKS48のセールスポイントの一つ、『凌辱券』――CDを買った枚数に応じて貰える、SKSに犯してもらえる権利のことである――を、ホーネットが親類がSucieの元でアイドルをしているという縁を伝ってプライベートで使用し、『白昼の学校で出張凌辱会』を開催しているのであった。こっちの方が興奮するらしい。
このように、ホーネットは突拍子もなく頭の悪いことを思いついては実行する。撮影も自分からSucieに申し出た。乗るSucieもSucieだが、なんたる変態性欲だろうか。
説明すると、これはSKS48のセールスポイントの一つ、『凌辱券』――CDを買った枚数に応じて貰える、SKSに犯してもらえる権利のことである――を、ホーネットが親類がSucieの元でアイドルをしているという縁を伝ってプライベートで使用し、『白昼の学校で出張凌辱会』を開催しているのであった。こっちの方が興奮するらしい。
このように、ホーネットは突拍子もなく頭の悪いことを思いついては実行する。撮影も自分からSucieに申し出た。乗るSucieもSucieだが、なんたる変態性欲だろうか。
「ブブーン!(風紀委員がきたよ!)」「にゃんれふって!?」
行為の邪魔とならぬよう近くを飛んでいたホーネットの相棒たるミツバチ達が、みずきの存在に――その腕に着けられた、風紀委員の腕章に気付いた。
蜂からのメッセージを受け取ったホーネットは、口腔にて貪っていた触手を名残惜しそうに離すと、己を持ち上げていた触手に下ろしてもらいながら、言葉を発する。
蜂からのメッセージを受け取ったホーネットは、口腔にて貪っていた触手を名残惜しそうに離すと、己を持ち上げていた触手に下ろしてもらいながら、言葉を発する。
「私の至福の時間を邪魔する無粋な風紀委員さんめ! 許しません!
みなさん、おねがいしますっ!」
みなさん、おねがいしますっ!」
ホーネットの突撃指令を受け、蜂たちがその眼を獰猛に光らせる。
素晴らしき以心伝心により命令の前から既にみずきを囲んでいた蜂たちは、四方八方から次々にみずき目掛けて襲い掛かる!
衝撃的光景に茫然としていたみずきも、頭を切り替え立ち向かうが――。
素晴らしき以心伝心により命令の前から既にみずきを囲んでいた蜂たちは、四方八方から次々にみずき目掛けて襲い掛かる!
衝撃的光景に茫然としていたみずきも、頭を切り替え立ち向かうが――。
「くっ――!」
みずきも水弾で蜂達に応戦するが、いかんせん数と範囲が違いすぎる。
そのうえ、今は心のコンディションも普段通りとは言い難い。陥落は、時間の問題。
やがてみずきの迎撃をすり抜けた数匹の蜂が、みずきの制服の内部へと侵入する。
そのうえ、今は心のコンディションも普段通りとは言い難い。陥落は、時間の問題。
やがてみずきの迎撃をすり抜けた数匹の蜂が、みずきの制服の内部へと侵入する。
「ひゃあっ! ちょっ、そんなトコ――!」
敏感なる柔肌を、蜂たちが這いまわる。
手足がこそばゆい感覚を与え、大顎や尾針の甘噛み・甘刺しが絶妙な刺激を生む。
蜂姦の天才・ホーネットに仕込まれた蜂たちのテクニックは、初心なみずきを快楽の奔流へと誘う。動きの鈍ったみずきの元へ、一匹、もう一匹と、さらに蜂が群がる。
手足がこそばゆい感覚を与え、大顎や尾針の甘噛み・甘刺しが絶妙な刺激を生む。
蜂姦の天才・ホーネットに仕込まれた蜂たちのテクニックは、初心なみずきを快楽の奔流へと誘う。動きの鈍ったみずきの元へ、一匹、もう一匹と、さらに蜂が群がる。
「みなさん、その調子ですっ! ……なんだか羨ましくなってきてしまいました……!」
「はあ、はあ……蜂姦も悪くないわね……! 今度一回お願いしようかしら……!」
快楽と嫌悪の波間に揺れるみずきを見ながら、それぞれ股間を濡らす二者。
特にSucieは、危険が及ばぬようSKSを避難させた後、ホーネットの凌辱を撮影していたビデオの続きにみずきの痴態を録画している。当然の如くこの女も頭がおかしかった。
二人の変態に見守られながら、みずきの思考は暗黒へと堕ちてゆく。
特にSucieは、危険が及ばぬようSKSを避難させた後、ホーネットの凌辱を撮影していたビデオの続きにみずきの痴態を録画している。当然の如くこの女も頭がおかしかった。
二人の変態に見守られながら、みずきの思考は暗黒へと堕ちてゆく。
「(これは、きっと罰……。昭良君の人生を壊してしまった、私への……)」
肉体と共に心を犯されるにつれ、みずきの能力もその制御を失ってゆく。
制服を形成できていたはずの水も少しずつ溶けだし、グラウンドにシミを作る。
それに伴いみずきの精神もより崩れてゆく。相乗的に破壊される心。やがて――。
制服を形成できていたはずの水も少しずつ溶けだし、グラウンドにシミを作る。
それに伴いみずきの精神もより崩れてゆく。相乗的に破壊される心。やがて――。
「(なら、いっそこのまま、私も壊されてしまった方が……彼への、償いに……)」
一旦心が折れてしまえば、それは意外にも心地よいものであった。
蜂姦調教に己が身を委ね、みずきは暗き深淵へと意識を手放した。
少女の目に最後に映ったのは、全てを照らす、眩き閃光であった――。
蜂姦調教に己が身を委ね、みずきは暗き深淵へと意識を手放した。
少女の目に最後に映ったのは、全てを照らす、眩き閃光であった――。
目が覚めた時、視界には真っ白な天井が広がっていた。
首を傾けてみると、文庫本へと目を落とす一人の少女の姿があった。
少女は本を閉じると、笑みを浮かべながら言葉を紡いだ。
首を傾けてみると、文庫本へと目を落とす一人の少女の姿があった。
少女は本を閉じると、笑みを浮かべながら言葉を紡いだ。
「やあ、お目覚めかな」
「……えっと、ここは……。それに、あなたは……」
「ここは保健室で、ぼくは一∞さ。そして君は、白王みずき。他に質問は?」
みずきの目の前にいる少女――否、眼鏡っ子の名は一∞(にのまえ むげん)。みずきと同じくトーナメントに出場していた彼女が、何故ここに。
そのような疑問を予知したのか、眼鏡をくいっと直しながら∞が口を開く。
そのような疑問を予知したのか、眼鏡をくいっと直しながら∞が口を開く。
「順を追って説明しよう。まず、蜂使いの魔人に襲われていた君は、通りすがりの『風紀皇帝』を名乗る人物によって助け出された。一撃で、二人の変態魔人は蜘蛛の子を散らす様に逃げ去ったという。
それからこの保健室へと運びこまれた。眼鏡を掛けた風紀委員の子が、君を心配していたよ。まったく、羨ましい限りさ。で、ぼくが看病を仰せつかった、というわけさ」
それからこの保健室へと運びこまれた。眼鏡を掛けた風紀委員の子が、君を心配していたよ。まったく、羨ましい限りさ。で、ぼくが看病を仰せつかった、というわけさ」
操子せんぱいだ……。みずきは感謝と、そして申し訳なさを感じる。
時計をちらと見、昼休みはもう終わり、午後の授業が始まっていることを知る。
風紀委員の仲間たちは、みなそれぞれの授業に出席しているのだろう。今この場には、みずきと∞の二人きり。その不思議な安心感が、みずきの本心を吐露させた。
時計をちらと見、昼休みはもう終わり、午後の授業が始まっていることを知る。
風紀委員の仲間たちは、みなそれぞれの授業に出席しているのだろう。今この場には、みずきと∞の二人きり。その不思議な安心感が、みずきの本心を吐露させた。
「……私は、助かってしまってよかったのでしょうか」
「ふむ?」
首を傾げる∞に、みずきは言葉を続ける。
「私は準決勝で、昭良君の人生を壊してしまいました。許されざることです。
だから……さっきの人たちに、そのままやられてしまった方が――」
だから……さっきの人たちに、そのままやられてしまった方が――」
「それは、冒涜だよ」
みずきの言葉を遮り、∞が断言する。驚くみずきに、∞は言い放つ。
「先へ進むことを諦めるのは、確かに楽だろうね。君にとっては。
だがそれは、君の帰りを待つ家族や、君を心配している仲間たち、なにより――、
不動昭良を含め、君に全てを託した対戦相手たちの想いに対する冒涜に他なるまい」
だがそれは、君の帰りを待つ家族や、君を心配している仲間たち、なにより――、
不動昭良を含め、君に全てを託した対戦相手たちの想いに対する冒涜に他なるまい」
「…………」
「不動君も、君の破滅など望んでいないさ。君の勝利を願い、自ら身を引いたのだから。
……彼の所属を考えれば、遅かれ早かれ彼は『転校生』となっていただろう。
それを思えば、引き金を引いたのが君で、むしろ彼にとっては幸せだったろう」
……彼の所属を考えれば、遅かれ早かれ彼は『転校生』となっていただろう。
それを思えば、引き金を引いたのが君で、むしろ彼にとっては幸せだったろう」
そう言って∞は聖母のような笑みを見せ、みずきの頭を軽く撫でた。
風紀委員の仲間たちとは違う――自分や不動と同じ、トーナメント参加者という事実のためだろうか。∞の言葉は、みずきの心に深く沁み込んでいった。
いつの間にか目尻に浮かんでいた涙の粒を拭うと、みずきも微笑みを返した。
風紀委員の仲間たちとは違う――自分や不動と同じ、トーナメント参加者という事実のためだろうか。∞の言葉は、みずきの心に深く沁み込んでいった。
いつの間にか目尻に浮かんでいた涙の粒を拭うと、みずきも微笑みを返した。
「……ありがとうございます。なんだか、少し元気がでてきちゃいました」
「それは良かった。……と、そうだ、本題を忘れるところだった」
言いつつ、∞はセーラー服の胸元に目を突っ込み、そこから眼鏡を取り出す。
ほのかな温もりを帯びたシルバーフレームのそれをみずきに手渡すと、再びにっこりと笑みを浮かべる。
どうしたものかと迷うみずきは、ふと、手の中の眼鏡に既視感を覚えた。
ほのかな温もりを帯びたシルバーフレームのそれをみずきに手渡すと、再びにっこりと笑みを浮かべる。
どうしたものかと迷うみずきは、ふと、手の中の眼鏡に既視感を覚えた。
「これ……。兄さんが昔着けていたものとそっくり……」
「気付いたようだね……。そうとも、それは君の兄・白王みかど君の眼鏡――によく似たデザインの眼鏡さ」
∞が言うには、彼女の能力の一つ『眼鏡サーチ』により、みかどの潜在眼鏡を観測し、そのタイプによく似た眼鏡を妹たるみずきにプレゼントしたいとのことだった。
みずきには彼女が何を言っているのか半分も理解できなかったし、そもそもいつ兄と∞が会っていたのかも分からなかったが、魔人など元より曖昧な存在だ。
そういうことなのだろう、と強引に納得し、別の問題を口にした。
みずきには彼女が何を言っているのか半分も理解できなかったし、そもそもいつ兄と∞が会っていたのかも分からなかったが、魔人など元より曖昧な存在だ。
そういうことなのだろう、と強引に納得し、別の問題を口にした。
「……でも、私、別に目はそんなに悪くないですよ……?」
「問題ないさ、その眼鏡は伊達。眼鏡に貴賤なし! ぼくは伊達眼鏡をも愛そう!」
力説する∞に思わずたじろぐみずき。
そう、この眼鏡っ子は、みずきに眼鏡を掛けさせるためだけに彼女を訪ねていた。
みずきの決勝の対戦相手こと渡葉美土――通称・伝説の勇者ミド。彼女もまた眼鏡っ子であり、映えある決勝戦こそ、眼鏡っ子VS眼鏡っ子であるべき、と∞は考えたのだ。
そう、この眼鏡っ子は、みずきに眼鏡を掛けさせるためだけに彼女を訪ねていた。
みずきの決勝の対戦相手こと渡葉美土――通称・伝説の勇者ミド。彼女もまた眼鏡っ子であり、映えある決勝戦こそ、眼鏡っ子VS眼鏡っ子であるべき、と∞は考えたのだ。
無論、そのようなキチガイじみた考えが頭を過ぎったとて、凡百の眼鏡フェチならば実行には移すまい。
“この世で最も眼鏡に愛された、世界で一番眼鏡っ子”を自称する彼女なればこそ、このような行為も平然と行うのだ。なんたる眼鏡愛か。もはや病気だ。
自分を立ち直らせてくれた相手の厚意を無碍になどできないみずきは、その眼鏡をありがたく頂戴することにし、∞の要望に従いこの場でそれを掛けた。
“この世で最も眼鏡に愛された、世界で一番眼鏡っ子”を自称する彼女なればこそ、このような行為も平然と行うのだ。なんたる眼鏡愛か。もはや病気だ。
自分を立ち直らせてくれた相手の厚意を無碍になどできないみずきは、その眼鏡をありがたく頂戴することにし、∞の要望に従いこの場でそれを掛けた。
「――うむ! やはりぼくの見立てに狂いはなかった……。素晴らしい眼鏡力だ……。
ありがとう。これで勝負は見えなくなった……。決勝も楽しめそうだ。
さて、ぼくはそろそろ退散するとしよう。その『イデアの眼鏡』……大切に、な」
ありがとう。これで勝負は見えなくなった……。決勝も楽しめそうだ。
さて、ぼくはそろそろ退散するとしよう。その『イデアの眼鏡』……大切に、な」
「あ、はいっ! ありがとうございましたっ! いろいろとっ!」
最後まで訳の分からぬことを捲し立て、眼鏡っ子は去った。
残された眼鏡っ子は、自分の心がずいぶんと軽くなっていることに気付く。
もう自棄も迷いもなかった。全てを受け止め、携え――決勝に臨む!
残された眼鏡っ子は、自分の心がずいぶんと軽くなっていることに気付く。
もう自棄も迷いもなかった。全てを受け止め、携え――決勝に臨む!
「――あっ」
途中からでも授業に出席しようと保健室のベッドから出かけたみずきは、自分の制服の丈が短くなったり穴があいていたりと、具合の悪くなっていることに気付く。
戦いの際、制御を失った能力が解除されたことの影響であった。
このままでは授業になど出られぬと、みずきは一旦シャワー室を目指す。
戦いの際、制御を失った能力が解除されたことの影響であった。
このままでは授業になど出られぬと、みずきは一旦シャワー室を目指す。
「……はあ、はあ。みずきちゃんのシャワー……! 眼鏡っ子の濡れ場……!」
シャワーを浴び“着替え”るみずきを、扉に張り付いて∞が見ていた。
∞の能力の一つ『眼鏡サーチ』を以てすれば、薄い扉越しに眼鏡っ子を視姦することなど児戯に等しい。上昇する体温を感知し、∞の息遣いも荒くなる。
そして指先もついついイケないところへと滑ってゆき――。
∞の能力の一つ『眼鏡サーチ』を以てすれば、薄い扉越しに眼鏡っ子を視姦することなど児戯に等しい。上昇する体温を感知し、∞の息遣いも荒くなる。
そして指先もついついイケないところへと滑ってゆき――。
その日、『シャワー室の前で一心不乱に自慰に耽る眼鏡っ子』の噂が学校中を席巻したが、よくよく考えれば希望崎学園ではそこまで珍しい話でもなかった。
その後、残りの授業に出席し、放課後の風紀委員業務もこなし、ようやくみずきが帰路に就いた頃には、辺りは夕闇に黒く染まっていた。
家に入ると、夕食のシチューの香りが鼻腔をくすぐり、みずきのお腹が可愛く鳴いた。
頬を染めながら部屋に戻ろうとしたみずきに、母・みどりは一通の手紙を渡した。
家に入ると、夕食のシチューの香りが鼻腔をくすぐり、みずきのお腹が可愛く鳴いた。
頬を染めながら部屋に戻ろうとしたみずきに、母・みどりは一通の手紙を渡した。
「えっと……私宛、なんですか?」
差出人の名もなければ、閉じられてもいない封筒。訝しむみずきを「いいから読んでみなって」と促す母に従い、みずきは中の便箋を取り出した。
達筆のボールペンの字が躍る文面を眼鏡の奥の瞳が辿ってゆく。
達筆のボールペンの字が躍る文面を眼鏡の奥の瞳が辿ってゆく。
『親愛なる我が妹へ。
久しぶりだな、みずき。僕のことを覚えているかな? 君の兄、白王みかどだ。』
久しぶりだな、みずき。僕のことを覚えているかな? 君の兄、白王みかどだ。』
「み、みかど兄さんっ!? うそ、なんで!?」
仰天するみずきを見ながら、みどりは「ブフーッ」と思わず噴き出した。
知っていて、反応を見るためにわざと黙っていたのだろう。
だが、今のみずきに母親に構っている暇などない。次の行へと目が急ぐ。
知っていて、反応を見るためにわざと黙っていたのだろう。
だが、今のみずきに母親に構っている暇などない。次の行へと目が急ぐ。
『諸事情により僕はこの地に戻ってきた。今はこちらの「連合」支部の宿舎にいる。
希望崎学園にも寄らせてもらった。そこで何人かの変態魔人に会い粛清したが、
まったくあそこも落ちぶれたものだ。考えられないほどの、酷い有様だ。
そんな世界で、学園の秩序を守ろうと戦う妹を、僕は嬉しく思う。』
希望崎学園にも寄らせてもらった。そこで何人かの変態魔人に会い粛清したが、
まったくあそこも落ちぶれたものだ。考えられないほどの、酷い有様だ。
そんな世界で、学園の秩序を守ろうと戦う妹を、僕は嬉しく思う。』
――嬉しい、って! 兄さんが、私のことをっ!
ぱああ、という擬音と共に花びらでも舞いそうな、そんな幻想を抱くほどにみずきの表情は輝いている。兄の言葉は偉大なり。
ぱああ、という擬音と共に花びらでも舞いそうな、そんな幻想を抱くほどにみずきの表情は輝いている。兄の言葉は偉大なり。
『ところで、みずき。君が今、とあるバトル・トーナメントに出場していると聞いた。
あの温厚だったみずきが、なあ。なんだか、時の流れを実感するよ。
映像も見させてもらった。そして思うが……みずき、君は何故戦っているんだ?』
あの温厚だったみずきが、なあ。なんだか、時の流れを実感するよ。
映像も見させてもらった。そして思うが……みずき、君は何故戦っているんだ?』
なんだか、雲行きが怪しくなってきた。
それでも嫌な予感を飲み下し、兄の言葉を求め、瞳が次の行へと滑ってゆく。
それでも嫌な予感を飲み下し、兄の言葉を求め、瞳が次の行へと滑ってゆく。
『戦いぶり自体は悪くない。能力と折り合いをつけ、うまくやっていると思う。
だが! あんな醜態を放送され、映像にまで残し、恥ずかしいとは思わないのか!?
みだりに裸体を晒し! 汚物に塗れ! 挙句は対戦相手に勝ちを譲ってもらうなど!!
賞金も出るそうだが……君が参戦する理由について細かく詮索しようとは思わない。
が……正直、失望したよ。』
だが! あんな醜態を放送され、映像にまで残し、恥ずかしいとは思わないのか!?
みだりに裸体を晒し! 汚物に塗れ! 挙句は対戦相手に勝ちを譲ってもらうなど!!
賞金も出るそうだが……君が参戦する理由について細かく詮索しようとは思わない。
が……正直、失望したよ。』
冷や汗が頬を伝い、指先から熱が消えうせたような、そんな気がした。
脳を揺さぶられる感覚を覚え、思わず眩暈がする。兄の言葉は、諸刃の剣であった。
それでもなんとか最後まで読もうと、足腰に力を入れ、瞼を開く。
脳を揺さぶられる感覚を覚え、思わず眩暈がする。兄の言葉は、諸刃の剣であった。
それでもなんとか最後まで読もうと、足腰に力を入れ、瞼を開く。
『みずき、あの“約束”はまだ覚えているか? ミサンガは、まだ着けているか?
決勝戦こそ、正々堂々相手とぶつかり合い、そして勝つんだ。
君が確かな勝利を手にした、その時こそ、僕は君を迎えに行こう。祝福しよう。
我が妹の、華々しい活躍を切に期待しているよ。 君の兄、白王みかどより』
決勝戦こそ、正々堂々相手とぶつかり合い、そして勝つんだ。
君が確かな勝利を手にした、その時こそ、僕は君を迎えに行こう。祝福しよう。
我が妹の、華々しい活躍を切に期待しているよ。 君の兄、白王みかどより』
最後まで読み――みずきは、しばし立ち尽くしていた。
やがて冷え切った彼女の心を鼓舞するように、熱く、熱く滾る想いが溢れてきた。
迸る激情は、自然と口から漏れ出していた。
やがて冷え切った彼女の心を鼓舞するように、熱く、熱く滾る想いが溢れてきた。
迸る激情は、自然と口から漏れ出していた。
「兄さん、見てて下さい! きっと優勝して御覧に入れます! えい、えい、おーっ!」
突然叫び出した娘に怪訝な視線を送りながら、しかしてみどりは安堵していた。
準決勝の後、ずっと意気消沈していたみずきもどうにか立ち直ったみたいだ。
新たな決意を胸に秘めた少女は、その日、久しぶりにぐっすりと眠った。
準決勝の後、ずっと意気消沈していたみずきもどうにか立ち直ったみたいだ。
新たな決意を胸に秘めた少女は、その日、久しぶりにぐっすりと眠った。
翌日。決戦の朝。
軽い朝食を済ませたみずきは“着替え”を終え、浴室から出てきた。
決戦の地・氷穴――。みずきは行った事がなかったが、そこが想像を絶する寒さであろうことは想像に難くない。
軽い朝食を済ませたみずきは“着替え”を終え、浴室から出てきた。
決戦の地・氷穴――。みずきは行った事がなかったが、そこが想像を絶する寒さであろうことは想像に難くない。
「ですが、準備は万端! 寒さ対策もバッチリですっ!」
故に、みずきは普段の制服姿の上から厚手のコートを纏い、首にはマフラーを巻いている。ふわふわ耳当てを着け、ピンクのミトン状の手袋もしている。
もちろんミサンガ・メダル・リストバンドのいつもの『絆』セットに加え、今回は∞から貰ったシルバーフレームの眼鏡をしている。
室内でこれほどの厚着をしているためか、それとも燃える瞳のためか、みずきの全身はじっとりと汗ばみ、ほのかな官能を紡ぎ出していた。
もちろんミサンガ・メダル・リストバンドのいつもの『絆』セットに加え、今回は∞から貰ったシルバーフレームの眼鏡をしている。
室内でこれほどの厚着をしているためか、それとも燃える瞳のためか、みずきの全身はじっとりと汗ばみ、ほのかな官能を紡ぎ出していた。
「それでは、行って参りますっ!」
だが、何より――兄との再会を望む、熱い心がある。今のみずきに、死角なし。
転送ゲートを潜り抜け、みずきは決戦の舞台へと赴いた。
勝利の、そして、みずきとみかど、二人の“約束”の行方や如何に――。 <終>
転送ゲートを潜り抜け、みずきは決戦の舞台へと赴いた。
勝利の、そして、みずきとみかど、二人の“約束”の行方や如何に――。 <終>
『眼鏡っ娘∞(インフィニティ)』(by サンライズ)
「眼鏡っ娘だ…眼鏡っ娘がいるぞ!」
決勝戦前夜の話である。一∞は興奮気味に「ユキ使」本部ビルの廊下を駆けていた。彼女の「眼鏡サーチ」はビル内に2人、眼鏡っ娘の存在を感知していた。
一方は決勝戦進出者・伝説の勇者ミドである。そしてもう一方は…眼鏡が指し示す先に向かって走り、たどり着いた先は選手控え室であった。名前は「白王 みずき」、もう一方のファイナリスト。
一方は決勝戦進出者・伝説の勇者ミドである。そしてもう一方は…眼鏡が指し示す先に向かって走り、たどり着いた先は選手控え室であった。名前は「白王 みずき」、もう一方のファイナリスト。
ゴンッゴンッ
「はい。」
運営の人だろうか、決勝戦開始まではまだだいぶ時間があるはずなのに、もしかして莉子先輩?などと思いながら白王みずきはドアを開ける。そこにいたのは一∞。
「に、一さん!?どうしてここに?」
同じ希望崎学園の魔人で、割りと有名な人物の彼女だったが、今までの学園生活で特に接点は無かった。その彼女が何故ここに、同じ学校だから応援に来たにしても、対戦相手のミドも希望崎である。
「秋元康が金の匂いのするところに現れるように、女子高生ハンターが女子高生のいるところに現れるように、眼鏡っ娘がいるところに現れるのが僕さ。」
そう言って不敵に微笑む∞の眼鏡には、みずきのかけたメタルフレームの眼鏡が映しだされていた。ツーテールの髪型と生真面目そうな雰囲気にマッチして、彼女の持つ「委員長っぽさ」をより演出している。
机の上にはテキストとノート、筆記用具が広げられ、どうやら学校の課題をやっていたらしいと言うことがわかる。こんなところでも勉強している辺りに彼女の生真面目さが伺える。
「わあっ…いい香り」
控え室にはティ-パックもあったが、かなり高級な茶葉もあった。最初はみずきがやろうとしたのだが、
一方的におしかけたのだからと∞が淹れた。紅茶を美味しく淹れるにはけっこうな知識と技術が必要なのだが、∞のそれはとても美味しかった。
やはり眼鏡以外の面でも彼女は優秀なようだ。
一方的におしかけたのだからと∞が淹れた。紅茶を美味しく淹れるにはけっこうな知識と技術が必要なのだが、∞のそれはとても美味しかった。
やはり眼鏡以外の面でも彼女は優秀なようだ。
「そういえばまずこれを言うべきだったね。決勝進出おめでとう。」
「ありがとうございます。でも…実際のところ明良君に勝ちを譲ってもらっただけですし、それに私が下手なことを言ったせいで明良君、『転校生』に-」
何も知らないみずきは自分を責めているが、恐らく彼女が引き金を引かされただけであろうことを∞は察していた。自分のように裏社会にも通じた者だけが知る「転校生化」を、
普通の少女であるみずきが都合よく知っていて、恐らく不動にそれを指摘した瞬間-都合よく音声が途切れていた。この大会の闇に気づいている者は他にもいるのだろうが、
興味本位で身を乗り出し深淵を覗き込めば、逆に引きずり込まれることになるかも知れない。それに、仮にみずきが指摘しなかったとしても、
これからの人生でそういった裏社会と深く関わることになっただろう彼が、「転校生化」の方法を知らぬまま魔人警官の人生を終えるという保証は無い。
普通の少女であるみずきが都合よく知っていて、恐らく不動にそれを指摘した瞬間-都合よく音声が途切れていた。この大会の闇に気づいている者は他にもいるのだろうが、
興味本位で身を乗り出し深淵を覗き込めば、逆に引きずり込まれることになるかも知れない。それに、仮にみずきが指摘しなかったとしても、
これからの人生でそういった裏社会と深く関わることになっただろう彼が、「転校生化」の方法を知らぬまま魔人警官の人生を終えるという保証は無い。
「でも…、君の言葉に彼は随分救われていたんじゃないかな?本気で臨んでいた試合で勝ちを譲ってもいいと思うくらいに。」
そう言って頭を撫でてやるとみずきは少し涙ぐんで微笑み、礼を言った。
「ところで-本題だけど-」
「はい?」
「君は家では眼鏡をかけているのかい?それとも勉強するとき?」
「勉強するときですね。試合中はコンタクトをつけてます。…ひゃっ!?」
レンズの奥の∞の双眸がくわっと見開かれる。試合中でも不敵な笑みを崩さない彼女の、初めて見る明らかな怒りの表情だ。今にも眼鏡レーザーを発射してみずきを撃ち殺しそうに思えるほどの怒気を湛えている。
「…コンタクトは…敵だ…」
「すっすみませんっ…!」
眼鏡を何より愛する∞は逆にコンタクトレンズを何より嫌っていた。「目が悪い」ということは眼鏡をかける理由があるということなのに(もちろん伊達眼鏡も素晴らしいが)、コンタクトレンズなどという、つけても見た目には裸眼と全く変わらないモノを好む人間がいる。こんなモノが発明されなければ目が悪い人間はみんな眼鏡を掛けていたのに。
「でも…この眼鏡…いなくなった兄のモノなんです…。だから、もし戦いで割れちゃったらと思うと…。それに…私の能力は『身に纏うモノ』じゃなきゃ作れませんから…。眼鏡は無理です。」
「そう…だったのか…。」
確かにみずきのめがねは男性がかけても違和感の無いデザインに思えた。兄・みかどが中学生のころ、勉強するときに掛けていたメガネ。度が合わなくなったために机の奥にしまわれていたのを、ミサンガと同様、もうひとつの兄の分身として、彼女は使うようになった。しかし、ミサンガなどと違い、破損する可能性も大きい眼鏡を試合で掛けているのはみずきにとって抵抗があった。コンタクトレンズならば、眼球に張り付いているモノであるから、涙から瞬時に精製出来る。
「すまない。事情も知らずに怒ったりして。」
「いえ、いいんです。」
たとえ眼鏡が好きじゃないからコンタクトだとしても怒られる筋合いは無いのだけれど、彼女は眼鏡原理主義者であるから、そのことについて詫びるという発想は全く無かった。
「君はお兄さんが好きなんだね」
「えっ…いや…その、あの…」
∞が普段中々見せない優しげな笑みを浮かべてそう言うと、みずきは顔を赤らめてしどろもどろになった。昔、友人にブラコンぶりをからかわれて以来、そのことはバレないようにしてきたのに。
「気にすることないさ。僕も自分の兄さんや妹が大好きだから。」
本人達の前ではこんなことは決して言わないのだけれど。澄ましているかツンツンしているか、違いはあっても性根は妹と変わらない。
「大好きです、兄さんのこと。」
花の綻ぶような笑顔とはこういう顔なのだろうと思えるみずきの表情だった。
「お兄さんの眼鏡をかけて戦えないってのはわかったけど、でも…。」
「でも?」
「それでも僕は君に眼鏡をかけてほしい!」
「ほら…こういうのどうかな?」
みずきの2つ結びを解き、鏡の前で編んでやる。お下げなのは変わらないが今度は三つ編みお下げだ。
編み終わると、どこからともなく黒縁眼鏡を取り出した。
編み終わると、どこからともなく黒縁眼鏡を取り出した。
「今の眼鏡もいいけど、三つ編みには黒縁が似合うと思うんだ。眼鏡をかけると知性は少なくとも120%上昇、
一撃悩殺の技量も63%上昇するんだよ。」
一撃悩殺の技量も63%上昇するんだよ。」
鏡の前には三つ編みに黒縁眼鏡という、如何にもな文学少女ルックのみずきがいた。ビッチっぽく見えるのは一体何故だろうか。
「他にも、眼鏡は∞にあるからね。好きなのを選んでいいよ。」
「あ…ありがとうございます。」
そう言うとセーラー服の中から次々に眼鏡を取り出す。鼈甲、赤縁、セルフレーム、サングラス、鼻眼鏡…etc、
本当に∞に出てくるのではと疑う程、どこにしまっていたのかわからないが素材も色も形状も様々な眼鏡が出てくる。
本当に∞に出てくるのではと疑う程、どこにしまっていたのかわからないが素材も色も形状も様々な眼鏡が出てくる。
「(この人…本当に私に眼鏡をかけさせるために来たんだなあ。)」
やや呆れながらも、自分のためにこんなにも熱心になってくれる∞は素晴らしい人だと感じた。
実際のところ、彼女は眼鏡っ娘を見たいだけなのだが。
実際のところ、彼女は眼鏡っ娘を見たいだけなのだが。
「私…これにします。」
みずきが選んだのは結局、兄の眼鏡に一番近いデザインのモノだった。
∞がここに来たときと同じ、お下げでメガネの委員長っぽい女の子。
∞がここに来たときと同じ、お下げでメガネの委員長っぽい女の子。
「君が選んだなら、それが君の『イデアの眼鏡』だ。」
真野の「イデアの金貨」を真似た言い方だが、彼女の用法は正反対だった。唯一無二の真の眼鏡では無い。
物質世界に眼鏡が生まれて3000年弱、今までに生まれた、そしてこれから生まれるあらゆる眼鏡が愛おしく、素晴らしい「イデア」。
それが誰よりも眼鏡を愛し、誰よりも眼鏡に愛された少女、一∞。
物質世界に眼鏡が生まれて3000年弱、今までに生まれた、そしてこれから生まれるあらゆる眼鏡が愛おしく、素晴らしい「イデア」。
それが誰よりも眼鏡を愛し、誰よりも眼鏡に愛された少女、一∞。
みずきに眼鏡をプレゼント出来て、上機嫌に部屋を出る一∞。
「(決勝戦は眼鏡っ娘対決か…果たしてどちらが勝つのかな…?)」
先ほどまでなら確実にミドだったろう。眼鏡っ娘にコンタクトで勝てるはずがない。しかし、今は∞の眼鏡にも勝敗は見通せない。
「ふうっ…若い娘の体力にはついていけないな…」
準決勝終了後、ミドと不眠不休のSEXをしていた真野風火水土だったが、ミドが満足して解放される頃には彼は精根尽き果てていた。
ツヤツヤとしたミドに対して真野は目に見えてやつれている。同じようにミドとSEXをしても、体力精力共に人知を超えている練道に対して
真野は体力的に特筆すべきモノは無い。酷使した腰をコキコキと鳴らし、マムシドリンクを飲みながら廊下を行くと、
自分が二回戦で破った一∞が白王みずきの控え室の前で膝立ちになり、-自慰をしていた。
ツヤツヤとしたミドに対して真野は目に見えてやつれている。同じようにミドとSEXをしても、体力精力共に人知を超えている練道に対して
真野は体力的に特筆すべきモノは無い。酷使した腰をコキコキと鳴らし、マムシドリンクを飲みながら廊下を行くと、
自分が二回戦で破った一∞が白王みずきの控え室の前で膝立ちになり、-自慰をしていた。
「(何をしているんだこの娘は…。)」
普通に人も通る、監視カメラもある廊下で、乳房を露出し、スカートを捲り上げて。
「みずきちゃん…最高だよ君は…。」
「眼鏡サーチ」が捉えるのは、バスルームで眼鏡を掛けて「お着替え」をするみずき。
水がいけない部分にまとわりつく感触に思わず声を漏らし、体温が上昇しているのがわかる。
水がいけない部分にまとわりつく感触に思わず声を漏らし、体温が上昇しているのがわかる。
「あの坊主が『転校生』か…。」
本部ビルの屋上、練道は夜空に浮かぶ満月を肴にカップ酒を煽っていた。自分や池松も及びもつかない最強の魔人。
ワンターレンと同等の存在、「転校生」。自分も「そちら側」へ行ってみたいような、しかし肉弾戦を主とする自分が
その土俵で無敵になって戦いを楽しめるのか、そんな気持ちが半々だった。第一、彼は「認識の衝突」を経験していない。
なりたくてもなれないのが現状である。そして、転校生の全てを知っているわけでは無いが、
恐らく戦いばかりとなるだろう「転校生」人生に、自分と違って戦いを好まないだろうあの少年は堪えられるのだろうか。
ワンターレンと同等の存在、「転校生」。自分も「そちら側」へ行ってみたいような、しかし肉弾戦を主とする自分が
その土俵で無敵になって戦いを楽しめるのか、そんな気持ちが半々だった。第一、彼は「認識の衝突」を経験していない。
なりたくてもなれないのが現状である。そして、転校生の全てを知っているわけでは無いが、
恐らく戦いばかりとなるだろう「転校生」人生に、自分と違って戦いを好まないだろうあの少年は堪えられるのだろうか。
「大丈夫かね…あの坊主…」
「不動…remember English」
夜空を見上げながら、池松叢雲も独りごちていた。
「『転校生』と言えば…」
練道は更に思い出していた。
「メガネ=カタの娘…恐らくアイツは…」
メガネ=カタ、それは都市国家グラッスィアに於いて眼鏡原理主義をかかげた独裁政党
「テトラグラストン」の捜査官が用いた戦闘術である。その支配体制が崩壊したのもまた、
「転校生」の暗躍があるのだと言う。テトラグラストンの崩壊で途絶えたと思われていたメガネ=カタを
何故か会得している日本人の一∞、彼女のルーツは…。
「テトラグラストン」の捜査官が用いた戦闘術である。その支配体制が崩壊したのもまた、
「転校生」の暗躍があるのだと言う。テトラグラストンの崩壊で途絶えたと思われていたメガネ=カタを
何故か会得している日本人の一∞、彼女のルーツは…。
「(何を思う…一∞?眼鏡を独裁の道具にしていた体制を崩壊させた『転校生』を、
恨んでいるのか…感謝しているのか…。)」
恨んでいるのか…感謝しているのか…。)」
自慰に耽る∞を見下ろしながら、真野は内心でそう呟いた。
「真野さんだ…みずきちゃんに夢中で気付かなかった。」
自慰の手を止めてこちらを見上げ、そう言う∞に「心にも無いことを」と思ったが、
医死仮面とは別な意味で、この少女の透明な闇は見通せない。いや、見通そうと思っているモノには
わからないだけかも知れない。
医死仮面とは別な意味で、この少女の透明な闇は見通せない。いや、見通そうと思っているモノには
わからないだけかも知れない。
「真野さんも掛ける…?眼鏡」
そう言ってモノクルを差し出す∞。今この場で、彼はイデア界から眼鏡のイデアを顕現させることも出来たが、
それをするのはえらく無粋に思えた。
それをするのはえらく無粋に思えた。
「ありがたく掛けさせてもらうよ。」
苦笑してそれを受け取り、掛けると、かっこ良さと胡散臭さが同居したような19世紀風の紳士が出来上がる。
「ところで、君は何を見てそんなはしたない真似をしているのかね?」
「今、みずきちゃんが扉の向こうで全裸で恥ずかしい行為に耽っているのさ…。」
「何…だと…?」
ミドと同じく貧乳の少女が、この部屋で全裸に。入浴中か、いやこの娘は恥ずかしい行為に、と。
しかし彼女のことだからからかっているだけでは無いか。ぐぬぬぬ…ダメだ…透視出来ない…。
この娘の眼鏡自体に能力があるのやも知れない。貸してくれないかな?いやしかしいくらなんでも紳士として-。
しかし彼女のことだからからかっているだけでは無いか。ぐぬぬぬ…ダメだ…透視出来ない…。
この娘の眼鏡自体に能力があるのやも知れない。貸してくれないかな?いやしかしいくらなんでも紳士として-。
悩んだ挙句、真野は、イデアの金貨に、紳士からは到底かけ離れた望みを託すことにしたのである。
金貨を弾いた瞬間にはみずきはとっくにパジャマに「着替え」終わっていたのだが。
そして、そんな彼の姿を見て笑い転げる運営本部の姿があった。
金貨を弾いた瞬間にはみずきはとっくにパジャマに「着替え」終わっていたのだが。
そして、そんな彼の姿を見て笑い転げる運営本部の姿があった。