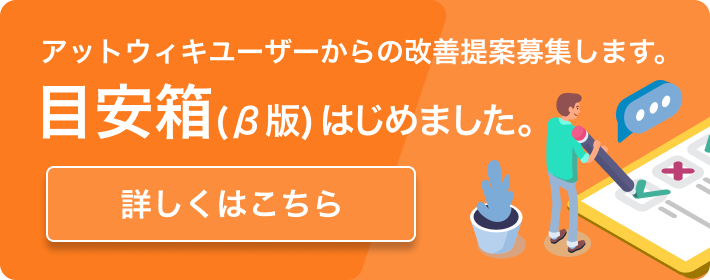麻雀とは、成長の遅い植物である。それが上がりという名の花を咲かすまでは、幾度かのムダヅモ・振り込み回避の回り道を受けて、耐え抜かねばならぬ。そしてそれ故に相手の花壇をクッソ荒らし、咲いてもいない花を摘み取り、相手の花壇で焼き畑農業始めるレベルの場外乱闘まであるので、やっぱり麻雀ってクソだわ。
麻雀とは、頭脳の要素と運の要素で構成されたテーブルゲームである。
娯楽として長きに渡り愛されてきたこのゲームは、世界各国で定着している。
国によってはどうしても金銭のやり取りを連想させる汚い遊びのイメージがあるが、それでもなお、競技人口は増大の一途を辿っていた。
娯楽として長きに渡り愛されてきたこのゲームは、世界各国で定着している。
国によってはどうしても金銭のやり取りを連想させる汚い遊びのイメージがあるが、それでもなお、競技人口は増大の一途を辿っていた。
「ツモォォォォォォッ! リーヅモのみィィィィィィィィッ!」
運の要素を考慮し、確率に基づいて最も期待値の高い道を選ぶ。
デジタル打ちと呼ばれるそれを、デジタルなどという知的な単語とは不釣り合いな男が使いこなしていた。
男の名はルドル・フォン・シュトロハイム。
今しがた無駄な大声で上がった男であるッ!
デジタル打ちと呼ばれるそれを、デジタルなどという知的な単語とは不釣り合いな男が使いこなしていた。
男の名はルドル・フォン・シュトロハイム。
今しがた無駄な大声で上がった男であるッ!
「貴様の親は流れたぞッ! アカクロポンコツソ連野郎ッ!」
シュトロハイムにとって、まず第一の目標はウォーズマンの点棒を上回ることである。
たったの半荘1回だけの勝負では、倒したい相手の親を如何に蹴散らすかが大事になるッ! 多分ッ!
たったの半荘1回だけの勝負では、倒したい相手の親を如何に蹴散らすかが大事になるッ! 多分ッ!
「我がナチスの数学力は世界一ィィィィィィィィッ!!!
最効率を求めることくらい造作もないわーーーーッ!」
最効率を求めることくらい造作もないわーーーーッ!」
シュトロハイムは、東三局を終えた所でウォーズマンを大きく離しプラス収支となっている。
まさに今ッ! 彼は乗りに乗っていたッ!
まさに今ッ! 彼は乗りに乗っていたッ!
「なるほど俺の親番じゃねーの」
サイボーグ手術のついでにスピーカーでも喉に取り付けたのかと勘違いするほどのシュトロハイムの騒音を華麗に無視し、跡部がサイコロを回す。
何故かこの首相官邸には高級な自動卓が大量に設置されていたので、麻雀は自動卓で行っている。
何故かこの首相官邸には高級な自動卓が大量に設置されていたので、麻雀は自動卓で行っている。
……余談だが、跡部やシュトロハイムは首相官邸に自動卓が大量設置されていることに疑問を呈していた。
金将軍による「国を代表する連中なんだから麻雀の練習しないわけねーだろ」との言葉に納得したわけではないが、殺し合いの事実と比較をすれば些事に過ぎないし、
もはや誰も気にかけてはいないので、本当にまったくもっての余談なのだけど。
金将軍による「国を代表する連中なんだから麻雀の練習しないわけねーだろ」との言葉に納得したわけではないが、殺し合いの事実と比較をすれば些事に過ぎないし、
もはや誰も気にかけてはいないので、本当にまったくもっての余談なのだけど。
「コーホー……まだ諦めん……正義超人はテンカウントのその瞬間まで決して諦めることはないッ!」
一方のウォーズマンはというと、ダントツの最下位だった。
リーチをかけたら「え、自殺したいの?」と言われるであろう程である。
彼にも確かに最新技術が詰め込まれているのだが、如何せんプロレス以外のことがまともにプログラムされていない。
それに加えての生来のアホの子っぷりである。
麻雀で敵うわけがない。
リーチをかけたら「え、自殺したいの?」と言われるであろう程である。
彼にも確かに最新技術が詰め込まれているのだが、如何せんプロレス以外のことがまともにプログラムされていない。
それに加えての生来のアホの子っぷりである。
麻雀で敵うわけがない。
(さっさとあのソ連野郎を飛ばして終わるか)
シュトロハイムからの直撃狙いというのが分かりやすく、また捨て牌からウォーズマンの狙う大物手が容易く分かるため、現在ウォーズマンは見事な焼き鳥である。
それどころか、現在までで振り込みをした唯一の者であり、立派なATMといえる。
そんなウォーズマンを飛ばせばいいと考えるのは、シュトロハイムを抑えて首位の金将軍その人である。
それどころか、現在までで振り込みをした唯一の者であり、立派なATMといえる。
そんなウォーズマンを飛ばせばいいと考えるのは、シュトロハイムを抑えて首位の金将軍その人である。
(大体素人に負けるわけがねぇっつーの!)
金将軍が首位であることに特別な理由などない。
首相クラスの中では下位の実力とはいえ、素人に近い連中相手に敗れるほど雑魚でもないというだけの話。
親番で連荘を重ね、じわりじわりとウォーズマンから搾り取って、金将軍は常にトップを走り続けていた。
首相クラスの中では下位の実力とはいえ、素人に近い連中相手に敗れるほど雑魚でもないというだけの話。
親番で連荘を重ね、じわりじわりとウォーズマンから搾り取って、金将軍は常にトップを走り続けていた。
(ククク……俺ほどの男にもなると配牌イーシャンテンなど当たり前よっ!)
日本国の首相である小泉ジュンイチローのような猛者ならば、開幕テンパイするのが基本なのだが、そこは、まあ、知らぬが仏というやつだ。
早々にケリをつけるべく、手元にある役牌二枚を早々に鳴いて仕掛けるつもりだった。
そして不要牌を切り――
早々にケリをつけるべく、手元にある役牌二枚を早々に鳴いて仕掛けるつもりだった。
そして不要牌を切り――
「ポンだ」
最も負けたくない相手を、金将軍は鳴かせてしまった。
日本国の、そして跡部王国の代表、跡部景吾その人である。
日本国の、そして跡部王国の代表、跡部景吾その人である。
現時点では、跡部は三着と振るわない。
だがしかし、それは決して跡部が弱いことを意味しない。
現時点で振り込んだのはウォーズマンのみ――即ち、跡部は決して振り込んでいないのだ。
だがしかし、それは決して跡部が弱いことを意味しない。
現時点で振り込んだのはウォーズマンのみ――即ち、跡部は決して振り込んでいないのだ。
圧倒的観察眼で危険を察知し手堅く降りる。
それを続けてきた男が、ついに動いた。
それを続けてきた男が、ついに動いた。
「ポンッ!」
次ツモを待たずしてのポン。
役配のみの可能性が非常に高い。
連荘狙いといったところか。
役配のみの可能性が非常に高い。
連荘狙いといったところか。
「っしゃあ! リィィィーーーチ!」
ハネマンまで見える手に、意気揚々と金将軍が牌を切る。
だが、しかし。
だが、しかし。
「ああ、リー棒はいらないぜ……ロンだ」
「何ィ!?」
「何ィ!?」
金将軍がわなわなと震える。
振り込んだという事実にもぶちギレ寸前であるが、それ以上に、跡部の上がり牌が不可解だった。
何故打点が上がるわけでもないのに、上がり牌が極めて少ない待ちを選んだのか。
振り込んだという事実にもぶちギレ寸前であるが、それ以上に、跡部の上がり牌が不可解だった。
何故打点が上がるわけでもないのに、上がり牌が極めて少ない待ちを選んだのか。
「悪いな将軍。将軍はキングには触れ伏すもんだ」
跡部は、東場ではひたすら“見”に回っていた。
その観察眼を研ぎ澄ませてベタオリをする――というだけではない。
それはあくまでもオマケ。
その観察眼を研ぎ澄ませてベタオリをする――というだけではない。
それはあくまでもオマケ。
真の狙いは、牌の透過。
……「なにいってんだこいつ」と思われるかも知れないが、事実であるものはしょうがない。
跡部はその優れた眼力により、物質をスケスケにできるのだッ!
ちなみに眼力と書いてインサイトと読む。ガンリキでもメヂカラでもない。
もっと、こう、キング感溢れる高貴な感じの技なのだ。
だからこの技は『眼力』なんて無粋な名前などではなく――
跡部はその優れた眼力により、物質をスケスケにできるのだッ!
ちなみに眼力と書いてインサイトと読む。ガンリキでもメヂカラでもない。
もっと、こう、キング感溢れる高貴な感じの技なのだ。
だからこの技は『眼力』なんて無粋な名前などではなく――
「跡部王国……」
跡部によって、その名が静かに呟かれる。
テニスコートという大陸に建国された人口一人の軍事大国は、とうとう他の大国を通り越し雀卓という四角い宇宙に侵攻した。
その様、まさに宇宙戦争ッ!
テニスコートという大陸に建国された人口一人の軍事大国は、とうとう他の大国を通り越し雀卓という四角い宇宙に侵攻した。
その様、まさに宇宙戦争ッ!
麻雀とは即ち! 四角い宇宙で繰り広げられる殺し合いと停戦協定ッ!
最終的に勝利のための知謀策謀飛び交う世界ッ!
最終的に勝利のための知謀策謀飛び交う世界ッ!
しかし跡部は! 新興国に君臨した圧倒的カリスマキングはッ! 独力による勝利を望んだッ!
他ならぬ自分自身が、自身の力を持ってして他国を圧倒するのを望んだッ!
そして彼は知っているッ! 己の強みは読みよりも運よりも、卓越した眼力であることをッ!
他ならぬ自分自身が、自身の力を持ってして他国を圧倒するのを望んだッ!
そして彼は知っているッ! 己の強みは読みよりも運よりも、卓越した眼力であることをッ!
「スケスケだぜ!」
そんな彼が麻雀牌を透視することに注力し、それにより勝利しようとするのは至極当然ッ!
そう、当然ッ! マスターボールをうっかりコラッタに投げ付けたら電源ボタンをそっと切るくらい当然のことなのだッ!
そう、当然ッ! マスターボールをうっかりコラッタに投げ付けたら電源ボタンをそっと切るくらい当然のことなのだッ!
「ツモォ!」
勿論運を全く使わぬわけではない。
だがしかし跡部に麻雀運などなく、良配牌など望めない。
だからこそ、のみ手のような安手しか上がれていない。
だがしかし跡部に麻雀運などなく、良配牌など望めない。
だからこそ、のみ手のような安手しか上がれていない。
「ツモッ!」
勿論読みを全く使わぬわけではない。
牌山全てが見えたとしても、その3/4は他の者にいく。
彼らがその牌をどう使うか読み切らねば、山が全て見えたとしても上がりなど望めない。
しかし跡部は、東場で下位に甘んじる屈辱と引き換えに、徹底的に対戦相手を観察した。
それにより、彼らが次の手をツモった際どうするのかが、切った牌で鳴くかどうか、全ての予知が可能となっているッ!
牌山全てが見えたとしても、その3/4は他の者にいく。
彼らがその牌をどう使うか読み切らねば、山が全て見えたとしても上がりなど望めない。
しかし跡部は、東場で下位に甘んじる屈辱と引き換えに、徹底的に対戦相手を観察した。
それにより、彼らが次の手をツモった際どうするのかが、切った牌で鳴くかどうか、全ての予知が可能となっているッ!
(何だァ!? 今ッ! 何かが光り輝いたような……!?)
シュトロハイムの視界にちらちら映る光り。
それこそは、『才気煥発の極み』という“無我の扉”の片鱗ッ!
卓越した観察眼が! 普段と違う戦場がッ! 跡部を更なるステージへと導くッ!
まだ覚醒はしていないが、確かに片鱗は現れたッ!
まさに今ッ! 無我の扉の半ドア状態ッ!
それこそは、『才気煥発の極み』という“無我の扉”の片鱗ッ!
卓越した観察眼が! 普段と違う戦場がッ! 跡部を更なるステージへと導くッ!
まだ覚醒はしていないが、確かに片鱗は現れたッ!
まさに今ッ! 無我の扉の半ドア状態ッ!
「ツモスケだぜ!」
跡部の進化は止まらないッ!
当初は牌が丸ごと透けてしまったために観察と推理による防御しか取れなかったが、今の跡部は全ての牌を“向こう側の薄皮一枚”残して透過することが出来る!
余裕でその文字を読める!
牌山の下段だろうと読み取れるッ!
当初は牌が丸ごと透けてしまったために観察と推理による防御しか取れなかったが、今の跡部は全ての牌を“向こう側の薄皮一枚”残して透過することが出来る!
余裕でその文字を読める!
牌山の下段だろうと読み取れるッ!
「フフフ……」
負ける要素などない。
鳴いてツモをずらされた際も振る可能性やツモられる可能性がないことを確認し、勢いよく牌を切る。
鳴いてツモをずらされた際も振る可能性やツモられる可能性がないことを確認し、勢いよく牌を切る。
「ハーーッハッハッ!」
ようやくの大物手。
テンションが上がらぬわけがない。
牌が90度曲がって置かれると同時に、突如謎の声援が響き渡る。
テンションが上がらぬわけがない。
牌が90度曲がって置かれると同時に、突如謎の声援が響き渡る。
『氷帝っ……氷帝っ……!』
『跡部っ……! 勝者は跡部っ……!』
『圧倒的王者……! 負けるのは金将軍っ……!』
『跡部っ……! 勝者は跡部っ……!』
『圧倒的王者……! 負けるのは金将軍っ……!』
少なからず他の三人に動揺が走る。
慌てて辺りを見渡すが、そこには誰一人いない。
慌てて辺りを見渡すが、そこには誰一人いない。
「どうした? オレ様に圧倒されるが余り、幻聴でも聴こえたか?」
一頻り天を仰いで笑ったあと、格好つけて掌を顔面に添えながら、視線を金将軍へと向ける。
そして、主に金将軍に向け、挑発が叩き込まれた。
そして、主に金将軍に向け、挑発が叩き込まれた。
「諦めな。勝つのは―――俺だ」
もはやこのメンバーが麻雀で跡部を止めることなど不可能。
金将軍ほど運に恵まれておらずとも、異常なテンパイ速度は無くとも、腐っても一国の王。
ノーテンになるほど運気が腐ることはない。
金将軍ほど運に恵まれておらずとも、異常なテンパイ速度は無くとも、腐っても一国の王。
ノーテンになるほど運気が腐ることはない。
「はん……幻聴だろうが関係ねぇ! 粛清だ!」
そう言って、金将軍は手牌を倒した。
まだテンパイもしていなかったはずの牌を。
まだテンパイもしていなかったはずの牌を。
「ロォォォ~~~~ン! ミサイル侵攻劇(テポドン・アタック)ッ!!!」
にたりと下卑た笑いを浮かべ、金将軍が鉄壁の跡部王国に不意打ちミサイルをぶち込む。
「バカな! なんだこの手は……ぐあぁぁっ!」
――まともに“麻雀”をしても止められないなら、まともじゃない麻雀をすればいい。
金将軍にも、跡部が手牌を見る能力を持っていることは分かっていた。
金将軍にも、跡部が手牌を見る能力を持っていることは分かっていた。
だからこその、イカサマ。
支給されたメスを使って、将軍は白を生み出した生み出したッ!
ウォーズマンとシュトロハイムが謎の声の発生源を探すべく注意を周りに向けていて、跡部が勝利を確信し天井を見ながら笑っていたその時!
金将軍は大胆にもメスで牌の正面を削っていたのだッ!
支給されたメスを使って、将軍は白を生み出した生み出したッ!
ウォーズマンとシュトロハイムが謎の声の発生源を探すべく注意を周りに向けていて、跡部が勝利を確信し天井を見ながら笑っていたその時!
金将軍は大胆にもメスで牌の正面を削っていたのだッ!
「大丈夫かっ!」
跡部は、王であり、本物のお坊ちゃまである。
とはいえ、温室でぬくぬくとしてきただけというわけではない。
常に厳しいトレーニングに挑み、異常なまでの体力をつけ、自らコートで死闘を繰り広げてきた。
とはいえ、温室でぬくぬくとしてきただけというわけではない。
常に厳しいトレーニングに挑み、異常なまでの体力をつけ、自らコートで死闘を繰り広げてきた。
ただ一点、彼に対し「ぬるい」だの「本当のつらい試合を経験してない」だの言える要素があるとすれば、彼が一度も破壊を目的としたテニスプレイヤーと対戦したことがないことが挙げられる。
結果的にKO敗けをしたことはあれど、KO狙いで攻撃された経験はない。
勿論、ダメージを受ける特訓もしたことはなかった(それを温室育ちと呼ぶのかは読者諸君の判断に任せるが)
結果的にKO敗けをしたことはあれど、KO狙いで攻撃された経験はない。
勿論、ダメージを受ける特訓もしたことはなかった(それを温室育ちと呼ぶのかは読者諸君の判断に任せるが)
即ち、跡部はダメージというものに慣れていない。
“それ”が堪えていいダメージなのか、今後を見据えギブアップすべき重症なのか、見極めることが出来ない。
“それ”が堪えていいダメージなのか、今後を見据えギブアップすべき重症なのか、見極めることが出来ない。
「これが……麻雀ッ……!」
肩で息をし、初めて振り込んだ跡部が忌々しげに呟く。
失点の度に微量のダメージがあることは、最初の局で判明していた。
金将軍曰く、麻雀とはそういうものなのだとか。
殺意がなければ命を奪う程のダメージはないと聞いていたので続行したが――
失点の度に微量のダメージがあることは、最初の局で判明していた。
金将軍曰く、麻雀とはそういうものなのだとか。
殺意がなければ命を奪う程のダメージはないと聞いていたので続行したが――
「やってくれるじゃねーの」
跡部は言葉ではなく心で理解した。
金将軍には、殺意があると。
単なる嫌悪だけではない。
あわよくば飛ばして亡き者にしようというドス黒い悪意が、確かに彼の上がり攻撃からは感じ取ることが出来た。
金将軍には、殺意があると。
単なる嫌悪だけではない。
あわよくば飛ばして亡き者にしようというドス黒い悪意が、確かに彼の上がり攻撃からは感じ取ることが出来た。
「白の枚数がおかしなことになってるぜ……!」
跡部王国(技名であり、国名ではない)によって、本来の金将軍の手に白が無いことは分かっている。
それでも敢えて言葉にしたのは、“手元にあってすぐに確認できる牌”だけで、
白の数が通常の上限である4を上回ることが見えていたからだッ!
それでも敢えて言葉にしたのは、“手元にあってすぐに確認できる牌”だけで、
白の数が通常の上限である4を上回ることが見えていたからだッ!
「何!? 確かにここに一枚だけつい切り損ねて持ち続けた白があるが……」
ウォーズマンが、手元から白を一枚切ってみせる。
それに呼応するように、フンと鼻で息をしてからシュトロハイムが手牌を倒した。
そこには、2枚の白が含まれている。
それに呼応するように、フンと鼻で息をしてからシュトロハイムが手牌を倒した。
そこには、2枚の白が含まれている。
「知らねえなぁ~~~~。不良品の雀卓だったんじゃねーの?」
「き、貴様~~~~! いけしゃあしゃあと!」
「何だァ? ポンコツ機械野郎! イカサマでもした証拠があるっつーのかよ!」
「き、貴様~~~~! いけしゃあしゃあと!」
「何だァ? ポンコツ機械野郎! イカサマでもした証拠があるっつーのかよ!」
怒りのあまり立ち上がるウォーズマンに対し、不遜な態度を取り続ける金将軍。
一触即発の空気を沈めるのは、麻雀開始前の時と同じくこの人。
一触即発の空気を沈めるのは、麻雀開始前の時と同じくこの人。
「……ま、気付かなかった俺が間抜けだったってことだ。
再開だ。ただし、卓はあっちに移らせてもらうがな」
再開だ。ただし、卓はあっちに移らせてもらうがな」
跡部とて、水掛け論をする気はない。
気付かなかった自分を棚の上にあげ、相手を責めて勝ちを拾おうとは思わない。
ただ、もうさせないという意思表明として、イカサマに気付いたぞという宣戦布告として、
白がこの場にあると伝えただけにすぎない。
気付かなかった自分を棚の上にあげ、相手を責めて勝ちを拾おうとは思わない。
ただ、もうさせないという意思表明として、イカサマに気付いたぞという宣戦布告として、
白がこの場にあると伝えただけにすぎない。
「次はこんなことがないよう、いい台を選んでくれ」
ウォーズマンとシュトロハイムにそう言いながら、跡部は金将軍を睨む。
これ以上好き勝手はやらせない。
そう思いながら、もう使わない牌を自動卓に流し込む。
これ以上好き勝手はやらせない。
そう思いながら、もう使わない牌を自動卓に流し込む。
「けっ……」
雀卓の片付けを跡部に押し付け、さっさと席を立つ金将軍。
ウォーズマンには何が“ちゃんとした卓”なのか分からぬため、適当に離れた場所の自動卓が選ばれていた。
そこに先程と同じ席順で座る。
ウォーズマンには何が“ちゃんとした卓”なのか分からぬため、適当に離れた場所の自動卓が選ばれていた。
そこに先程と同じ席順で座る。
「早くしろや、チョッパリがよぉ!」
「貴様ぁ……!」
「落ち着けウォーズマン。奴は立派な国王として、己の足でやってきとるッ!
下手な情けはむしろ無礼ッ! 遅いと言いつつ笑顔で出迎えてやろうじゃあないかッ!」
「貴様ぁ……!」
「落ち着けウォーズマン。奴は立派な国王として、己の足でやってきとるッ!
下手な情けはむしろ無礼ッ! 遅いと言いつつ笑顔で出迎えてやろうじゃあないかッ!」
慣れない傷のせいか、跡部の動きはぎこちない。
それでもしっかり卓につき、勝負は再開となった。
それでもしっかり卓につき、勝負は再開となった。
(詰んでんだよ、おめーはよぉ……)
跡部には、まだラス親が残っている。
逆転可能性はまだまだ残されていると言えよう。
しかし。
逆転可能性はまだまだ残されていると言えよう。
しかし。
(親で連チャンなんていうあま~い夢が最後まで残されてるからよォ~~~~!
痛い思いをするリスクを犯してまで勝負になんて出られねーだろぉ?)
痛い思いをするリスクを犯してまで勝負になんて出られねーだろぉ?)
跡部は、金将軍の目から見ても、ダメージ慣れしていなかった。
だから、金将軍には分かる。
跡部がこの先、使い物にならないということを。
甘ったれた生活が大好きで、痛いのは嫌いな自分だからこそ、そのことが分かるのだ。
だから、金将軍には分かる。
跡部がこの先、使い物にならないということを。
甘ったれた生活が大好きで、痛いのは嫌いな自分だからこそ、そのことが分かるのだ。
「リィィィィチッ!」
そしてその勢いのまま、リーチ棒を投げ捨てる金将軍。
跡部はというと、悩まずに現物を切っていた。
跡部王国を使った、完全なる降り麻雀だ。
跡部はというと、悩まずに現物を切っていた。
跡部王国を使った、完全なる降り麻雀だ。
――跡部王国は手牌も山札も透かす。
ただ、まだ暴けてない金将軍のイカサマまでは防げない。
最悪の事態を回避しオーラスを迎えるために、消極的になってしまっているのだ。
勿論、痛みへの恐怖からくる日和見も、全くないとは言えなかった。
ただ、まだ暴けてない金将軍のイカサマまでは防げない。
最悪の事態を回避しオーラスを迎えるために、消極的になってしまっているのだ。
勿論、痛みへの恐怖からくる日和見も、全くないとは言えなかった。
「何ィ!?」
「けっ、かの国の先行者の足元にも及ばねー無名会社のポンコツロボット二人め!
お前らはさっさと飛ばされりゃいーんだよ!」
「けっ、かの国の先行者の足元にも及ばねー無名会社のポンコツロボット二人め!
お前らはさっさと飛ばされりゃいーんだよ!」
このまま普通に打ち続ければ、もはや金将軍の勝利は揺るがない。
純粋な雀力ならばこのメンツでナンバーワンだッ! 依然変わりなくッ!
差など詰まりようがないのだッ!
純粋な雀力ならばこのメンツでナンバーワンだッ! 依然変わりなくッ!
差など詰まりようがないのだッ!
「さっさと切れよ箒頭ァ……ま、そんだけ無様な鳴き晒して、ちゃんとオリれるならだけどよぉ!」
「“オリれる”だとォ……? ふん! 貴様のようなヤツを前に、何故オリる必要がある?
動物園の檻の中の灰色熊……否! ロンドンの街を駆ける少女の腕に抱かれたテディーベアにも劣る貴様を! 恐れる理由がどこにある!」
「な、何を~~~~~!? いいからさっさとツモりやがれ!」
「“オリれる”だとォ……? ふん! 貴様のようなヤツを前に、何故オリる必要がある?
動物園の檻の中の灰色熊……否! ロンドンの街を駆ける少女の腕に抱かれたテディーベアにも劣る貴様を! 恐れる理由がどこにある!」
「な、何を~~~~~!? いいからさっさとツモりやがれ!」
シュトロハイムが、自身の手牌に指を押し付けている。
そして、にたりと笑い、手牌をそのまま倒して、言った。
そして、にたりと笑い、手牌をそのまま倒して、言った。
「そんなものを怖がる子供がおるか? いなァァァ~~いッ! ましてや! 勝つことが決まっていたらなァ!
ロン! 緑のベンチ!!(この土地が枯れるくらいにユダヤ人を消せばよかった)ッ!!」
「ぐわああああああああ!!」
ロン! 緑のベンチ!!(この土地が枯れるくらいにユダヤ人を消せばよかった)ッ!!」
「ぐわああああああああ!!」
金将軍に倣い、国家由来の技名を叫び、シュトロハイムが派手に上がる。
派手にといっても白のみの手なのだが、金将軍と、そして手牌を透かしてみていた跡部に取って、それは派手な上がりだった。
派手にといっても白のみの手なのだが、金将軍と、そして手牌を透かしてみていた跡部に取って、それは派手な上がりだった。
「テメーーーーっ! どーいうこった! 白は俺が二枚持ってんだぞッ!」
跡部は見ていた!
シュトロハイムがものすごい握力を持って、上がれる手にすべく牌を白に作り替えたことをッ!
サンタナのパワーを基準に作られたサイボーグの握力ならばッ!
轟盲牌をすることくらい造作もないッ!!
シュトロハイムがものすごい握力を持って、上がれる手にすべく牌を白に作り替えたことをッ!
サンタナのパワーを基準に作られたサイボーグの握力ならばッ!
轟盲牌をすることくらい造作もないッ!!
「さぁなァ~~~!! 自動卓の故障じゃあないかッ!?」
そう、シュトロハイムにとって、イカサマで白を生み出すことは造作も無い。
出来て当然ッ! どこからでも開けられますと書かれた醤油がどこからでも開かないくらい当然のことであるッ!
だがしかし、敢えてそれを封じてきた。
それは、誇りを賭け、真っ向から麻雀をしようと思ったからであるッ!
出来て当然ッ! どこからでも開けられますと書かれた醤油がどこからでも開かないくらい当然のことであるッ!
だがしかし、敢えてそれを封じてきた。
それは、誇りを賭け、真っ向から麻雀をしようと思ったからであるッ!
「て、てめーーー! この場で粛清してやろうか!」
「やめな。そーいう事故もありうる――あんたもそう言ったんだろ」
「やめな。そーいう事故もありうる――あんたもそう言ったんだろ」
だがしかし、イカサマをする奴が出たのなら話は別だ。
跡部がオリに回ったのを見て、シュトロハイムは直感した!
もはやこれは、自分と金将軍の一騎打ちだと!
つまりそれは、イカサマ野郎との一騎打ちを意味しているッ!
イカサマを自重する理由がどこにあると言うのか! いや、ない! 反語ッ!
跡部がオリに回ったのを見て、シュトロハイムは直感した!
もはやこれは、自分と金将軍の一騎打ちだと!
つまりそれは、イカサマ野郎との一騎打ちを意味しているッ!
イカサマを自重する理由がどこにあると言うのか! いや、ない! 反語ッ!
「卓を移動だ。次こそまともな卓にしてくれよ」
「さあ、どうなるかな」
「さあ、どうなるかな」
跡部の牽制を受け流し、シュトロハイムは金将軍を睨みつける。
シュトロハイムが睨みを効かせている限り、金将軍はメスで白を生み出せない。
しかし一方のシュトロハイムは、素手で白を生み出す故、注視されても問題などないッ!
しっかりと創りあげてからロンをすれば、決定的瞬間など生まれやしないのだッ!
シュトロハイムが睨みを効かせている限り、金将軍はメスで白を生み出せない。
しかし一方のシュトロハイムは、素手で白を生み出す故、注視されても問題などないッ!
しっかりと創りあげてからロンをすれば、決定的瞬間など生まれやしないのだッ!
「ぶわぁかめ! ナチスの迷彩は世界一ィィィィィィ!」
「ぐぎい~~~~~~!?」
「ロォォォ~~~~~~ン! 索子混一色!!(グリーンラベルでビールが美味い)ッ!!」
「ぐぎい~~~~~~!?」
「ロォォォ~~~~~~ン! 索子混一色!!(グリーンラベルでビールが美味い)ッ!!」
シュトロハイムにネーミングセンスなどない。
しかしながら腐っても軍で出世した男。
ネーミングセンスは無けれど、策謀のセンスはある。
相手をハメることは決して不得手ではないのだッ!
しかしながら腐っても軍で出世した男。
ネーミングセンスは無けれど、策謀のセンスはある。
相手をハメることは決して不得手ではないのだッ!
ましてや席順の関係で、シュトロハイムは金将軍をハメやすい位置にいる。
結局その後数局に渡り、シュトロハイムによる金将軍狙い撃ちが行われた。
そのいずれも白を使ったイカサマ混じりの安いが速い速攻手によるものだ。
結局その後数局に渡り、シュトロハイムによる金将軍狙い撃ちが行われた。
そのいずれも白を使ったイカサマ混じりの安いが速い速攻手によるものだ。
「これで終わりだ! 我がナチスがアジアのモンキーにトドメを刺すッ!
喰らえッ! 紫外線照射リーチィィィィィィ!!!」
喰らえッ! 紫外線照射リーチィィィィィィ!!!」
しかしながら、チリも積もれば山となる。
もはや、金将軍を飛ばすことも不可能ではない。
今回はイカサマを使うまでもなく、大物手が入ってきた。
流れのある証拠である。
もはや、金将軍を飛ばすことも不可能ではない。
今回はイカサマを使うまでもなく、大物手が入ってきた。
流れのある証拠である。
これならば、終わらせられる――
そんな想いで、シュトロハイムがリーチをかけた。
そんな想いで、シュトロハイムがリーチをかけた。
金将軍以外はアウトオブ眼中。
それでも振り込む恐れがないかはしっかり確認していたが――――
それでも振り込む恐れがないかはしっかり確認していたが――――
「カン!!」
「ハァ? カンだァ!? タイマン中カンするな。見苦しいぞアカクロッ!」
「黙れ脳筋が! 最後の最後まで諦めない――それが正義超人だ!」
「フン! リーチする点数すらない弱小野郎がなにをほざく!
貴様がオレを逆転出来るわけないだろぶゎぁ~~~~かめ!」
「ハァ? カンだァ!? タイマン中カンするな。見苦しいぞアカクロッ!」
「黙れ脳筋が! 最後の最後まで諦めない――それが正義超人だ!」
「フン! リーチする点数すらない弱小野郎がなにをほざく!
貴様がオレを逆転出来るわけないだろぶゎぁ~~~~かめ!」
ウォーズマンが、シュトロハイムの捨て牌を拾い、自身の牌とくっつける。
明槓。
それはダンラスのウォーズマンの、最期の悪あがきにしか見えない。
明槓。
それはダンラスのウォーズマンの、最期の悪あがきにしか見えない。
「宣言してやる! 貴様は逆転敗北を味わい、金欠のあまりアルコールランプを飲み出すアル中みたいな惨めな姿を晒すことになるッ!」
「何ィ~~~~!?」
「暗刻を敢えて槓することで、対々和に一歩近づき2翻パワー!」
「何ィ~~~~!?」
「暗刻を敢えて槓することで、対々和に一歩近づき2翻パワー!」
ガシャンと派手にウォーズマンが自身の手を申告する。
まさかの対々和宣言。
それはまさに、リーチをかけて逃げることが封じられたシュトロハイムだけを狙って討ち取るという宣言だった。
まさかの対々和宣言。
それはまさに、リーチをかけて逃げることが封じられたシュトロハイムだけを狙って討ち取るという宣言だった。
「さらに手牌をもいっこカンで特に変わらず2翻パワー!」
もう一組、ウォーズマンの牌が晒される。
そこに刻まれし数字は、先ほどの牌と同じもの。
そこに刻まれし数字は、先ほどの牌と同じもの。
「さらにいつもの3倍の槓数で三色同刻が付き2翻+2翻で4翻パワー!!」
「ぐうう~~~~……!」
「更に三槓子がついて4翻+2翻で6翻パワーッ!!」
「ぐうう~~~~……!」
「更に三槓子がついて4翻+2翻で6翻パワーッ!!」
慄くシュトロハイム
さすがにマズイ。ここまでされるとさすがにマズイッ!
さすがにマズイ。ここまでされるとさすがにマズイッ!
「……嶺上開花……ならずだ!」
そして格好つけて嶺上牌をツモ切るウォーズマン。
このままカンカンカン嶺上開花32000ですニッコリなんてオカルトありえませんよ、ファンタジーやメルヘンじゃあないんですから。
このままカンカンカン嶺上開花32000ですニッコリなんてオカルトありえませんよ、ファンタジーやメルヘンじゃあないんですから。
「こ、こちらは親リー! ドイツ人はうろたえないッ!! そのカンドラ、美味しく頂いてやるわァ!」
上がり勝てば問題ではない。
そう言い聞かせ、シュトロハイムは自身のツモる予定の牌に念を送る。
どうかツモらせてくれと。
そう言い聞かせ、シュトロハイムは自身のツモる予定の牌に念を送る。
どうかツモらせてくれと。
「やってられっか、クソが!」
「ポンだ!」
「ポンだ!」
吐き捨てながら金将軍が切った牌を、跡部が鳴く。
跡部の手はこれで役なし。無様な手牌。
跡部の手はこれで役なし。無様な手牌。
だがしかし――これでいいのだ。
大事なのは、“この順番”にツモ順をずらすこと。
金将軍が鳴ける牌で降りてくれるか賭けだったが――跡部は賭けに勝ったのだッ!
大事なのは、“この順番”にツモ順をずらすこと。
金将軍が鳴ける牌で降りてくれるか賭けだったが――跡部は賭けに勝ったのだッ!
「ば、馬鹿なァァァ~~~~~~~!!」
「悪いなシュトロハイム。独走を許すわけにはいかねーんだ」
「悪いなシュトロハイム。独走を許すわけにはいかねーんだ」
跡部の手により、シュトロハイムの手には危険な牌が舞い降りる。
生牌の白。それこそ金将軍がイカサマすら出来てしまう危険牌。
普段ならば、轟盲牌で白を生み出し上がってしまう所だが、今回ばかりはそうはいかない。
どこから白を生み出しても、打点を犠牲にしても、上がれるようには出来ないのだッ!
生牌の白。それこそ金将軍がイカサマすら出来てしまう危険牌。
普段ならば、轟盲牌で白を生み出し上がってしまう所だが、今回ばかりはそうはいかない。
どこから白を生み出しても、打点を犠牲にしても、上がれるようには出来ないのだッ!
切りたくない。しかし、切らざるを得ない。
ぐぬうとしばし呻いた後、シュトロハイムは言った。
ぐぬうとしばし呻いた後、シュトロハイムは言った。
「人間の偉大さは恐怖に耐える誇り高き姿にある――ギリシアの史家、プルタルコスの言葉だ」
再びシュトロハイムの瞳に熱き戦士の炎が宿る。
今度は金将軍でなく、いけ好かないロシア野郎を燃え尽くすべくッ!
真っ向から打ち勝つため、威勢よく白を切るッ!
今度は金将軍でなく、いけ好かないロシア野郎を燃え尽くすべくッ!
真っ向から打ち勝つため、威勢よく白を切るッ!
「勝負だァァァーーーー! 我がナチスに敗北などぬわァァァァァァ~~~~~~いッ!!」
「ロンッ!」
「ロンッ!」
ズダンといい子気味のいい打牌音が響くと同時、ウォーズマンの叫びが聞こえる。
それは、ラスを引いても、点棒が底をついても、決して諦めることのなかった男の叫び。
耐えぬいて、やっと訪れた奇跡を掴みとった戦士の雄叫び。
それは、ラスを引いても、点棒が底をついても、決して諦めることのなかった男の叫び。
耐えぬいて、やっと訪れた奇跡を掴みとった戦士の雄叫び。
「ロンッ……! ロンッ……! ロンッ……!」
びゅうと一陣の風が吹く。
肌を突き刺す、冷たい冷気。
肌を突き刺す、冷たい冷気。
「ロォ~~~~~~~~~~ンッ……!」
否! もはやそれは単なる風などではないッ! 冷気ですらないッ!
まさに吹雪ッ! 圧倒的吹雪っ……!
ウォーズマン渾身の上がりにより、辺りにブリザードが吹き荒れるッ!
まさに吹雪ッ! 圧倒的吹雪っ……!
ウォーズマン渾身の上がりにより、辺りにブリザードが吹き荒れるッ!
「コーホー……先程までの6翻に加え、三暗刻が付き6翻+2翻の8翻パワー! 」
しかしながら、その場に異変が生じる。
発生源は、他ならぬブリザードを起こしたはずのウォーズマン。
その漆黒のボディから、ぶすぶすと煙が立ち込めていた。
発生源は、他ならぬブリザードを起こしたはずのウォーズマン。
その漆黒のボディから、ぶすぶすと煙が立ち込めていた。
「さ……更に喰い断状態で8翻+1翻で9翻パワー!」
限界――――何故そのようなものが来たのか理解できない跡部やシュトロハイムにも、ウォーズマンに限界が来ていることは理解できた。
しかしながら、それでも点数申告を続けようとするウォーズマンの気迫に何も言えないでいる。
吹き荒れる雪で雪だるま並に雪にまみれ、ウォーズマンの言葉に耳を傾ける。
しかしながら、それでも点数申告を続けようとするウォーズマンの気迫に何も言えないでいる。
吹き荒れる雪で雪だるま並に雪にまみれ、ウォーズマンの言葉に耳を傾ける。
「そして……手牌の暗刻がカンドラなので、9翻+3翻で12翻パワー!」
ウォーズマンの体から煙が上がっている理由は、ズバリ“戦闘時間制限”のせいである。
ロボ超人故に、長時間の戦闘には耐えられず、ショートしてしまうのだ。
ロボ超人故に、長時間の戦闘には耐えられず、ショートしてしまうのだ。
勿論今行われているのは麻雀であり、超人レスリングではない。
だがしかし、脳の回路は超人プロレスの時以上に酷使されるし、
ましてや振り込み続けたウォーズマンは小さなダメージを何度もその身に受けている。
普段より遅れてとはいえ、時間切れを起こすのは必然の事だったと言えよう。
だがしかし、脳の回路は超人プロレスの時以上に酷使されるし、
ましてや振り込み続けたウォーズマンは小さなダメージを何度もその身に受けている。
普段より遅れてとはいえ、時間切れを起こすのは必然の事だったと言えよう。
「そして! 手牌の暗刻の一つが赤ドラなことを考慮し、更に1翻を加えれば12翻+1翻の……!」
ウォーズマンの体が、高速回転していく。
勿論麻雀の上がりによるイメージ映像的なものだが、それでも気迫に押され、その動作に恐怖を感じずにはおれない。
勿論麻雀の上がりによるイメージ映像的なものだが、それでも気迫に押され、その動作に恐怖を感じずにはおれない。
「シュトロハイム! お前を上回る数え役満だーーーーーッ!!!」
高速回転したウォーズマンが、シュトロハイムの腹をぶち破る。
勿論イメージ映像であり、現実のシュトロハイムにダメージは無いが、それでもシュトロハイムの心はバッキバキであるッ!
勿論イメージ映像であり、現実のシュトロハイムにダメージは無いが、それでもシュトロハイムの心はバッキバキであるッ!
「あ、あああありえないィィィィィィッ! 下手こいてしまったァァーーーーーーーッ!
ここで圧倒し、指揮権を得るはずがァァァァァァァ~~~~~~ッ!」
「我々ソ連は……極寒の地で耐え続けながら、仲間の屍を越え永久凍土の上に国家を築いてきたのだ。
スターリングラードで音を上げたナチスと比べられるなど……笑止千万ッ!!!」
ここで圧倒し、指揮権を得るはずがァァァァァァァ~~~~~~ッ!」
「我々ソ連は……極寒の地で耐え続けながら、仲間の屍を越え永久凍土の上に国家を築いてきたのだ。
スターリングラードで音を上げたナチスと比べられるなど……笑止千万ッ!!!」
冷静なファイティングコンピューター。
そんな正義超人が、回路のショートの影響か、熱き想いを叩きつける。
同時にイメージ映像で、シュトロハイムが爆散した。
サイボーグは爆発して散る。これは世界の法則である。
そんな正義超人が、回路のショートの影響か、熱き想いを叩きつける。
同時にイメージ映像で、シュトロハイムが爆散した。
サイボーグは爆発して散る。これは世界の法則である。
「コー……ホー……」
勝った。勝ったのだ。
その勝利に酔いしれるようにウォーズマンは空を仰ぐ。
己の体から出る煙が視界に映り、やがてはそれも見えなくなった。
その勝利に酔いしれるようにウォーズマンは空を仰ぐ。
己の体から出る煙が視界に映り、やがてはそれも見えなくなった。
「ウォーズマンよ……気絶してなお君臨するというのか」
ウォーズマンは、立ったまま気絶していた。
牌を倒した勢いのまま両腕を挙げたポーズで、堂々とした姿で。
ウォーズマンは、意識を手放していた。
かつて自分も執念により立ったまま気絶したことのある跡部が、彼に称賛を贈る。
牌を倒した勢いのまま両腕を挙げたポーズで、堂々とした姿で。
ウォーズマンは、意識を手放していた。
かつて自分も執念により立ったまま気絶したことのある跡部が、彼に称賛を贈る。
「だが――悪いな。お前に勝たせてやることは出来ない」
しかし、ウォーズマンが気絶してなお、吹雪が止んだ今でもなお、シュトロハイムの体は冷気に包まれているッ!
何故かッ! 簡単なことであるッ!
ウォーズマンだけではないッ! 今! この場にッ!
冷気を操る男は二人いたッ!
というかそもそもウォーズマンは冷気を操ったりしない。
何故かッ! 簡単なことであるッ!
ウォーズマンだけではないッ! 今! この場にッ!
冷気を操る男は二人いたッ!
というかそもそもウォーズマンは冷気を操ったりしない。
「悪いが――ダブロンだ」
皆がウォーズマンに集中している時。
まさにその時、跡部は動いていたのだッ!
まさにその時、跡部は動いていたのだッ!
「な……!? 馬鹿なッ! 鳴いた牌がいつの間にか白になっているだとッ!?」
牌のすり替え。非常に原始的なトリック。
跡部もまた、真っ当にイカサマなしでの逆転が厳しいことを理解していた。
そしてこれが熾烈なイカサマ合戦になると考えていた。
結果としては、イカサマなしのウォーズマンがシュトロハイムを引きずり下ろしたけれども。
跡部もまた、真っ当にイカサマなしでの逆転が厳しいことを理解していた。
そしてこれが熾烈なイカサマ合戦になると考えていた。
結果としては、イカサマなしのウォーズマンがシュトロハイムを引きずり下ろしたけれども。
それでも跡部は、前述のとおり、己の力で一位を取ることを望んだ。
だからこそ、ウォーズマンの上がり支援。
そちらに皆の視線が行くよう、己の勝利のために、布石として行ったのだッ!
だからこそ、ウォーズマンの上がり支援。
そちらに皆の視線が行くよう、己の勝利のために、布石として行ったのだッ!
「ああ、悪いな、白くなったのは、それだけじゃねーぜ」
パタパタと流れるように跡部の手牌が倒される。
その手牌、圧倒的大雪原ッ……!
否! 雪というよりも、絶対零度の氷ッ!
白、白、白――――その手牌は、氷の世界が如く、真っ白で埋められていた。
その手牌、圧倒的大雪原ッ……!
否! 雪というよりも、絶対零度の氷ッ!
白、白、白――――その手牌は、氷の世界が如く、真っ白で埋められていた。
「跡部様の宇宙開拓史(ビギニングオブザアトベユニバース)」
ここに氷の惑星を作ろう。
跡部は、王国の王如きで終わる器ではない。
テニス部部長から王様まで駆け上がった偉大なるテニスプレイヤーは、ついに自分の宇宙を想像するに至ったッ!
かつて彼のライバルが劇場版で敵にやってみせたように、跡部もまた、己の作り上げた惑星ビジョンで敵を討つッ!
跡部は、王国の王如きで終わる器ではない。
テニス部部長から王様まで駆け上がった偉大なるテニスプレイヤーは、ついに自分の宇宙を想像するに至ったッ!
かつて彼のライバルが劇場版で敵にやってみせたように、跡部もまた、己の作り上げた惑星ビジョンで敵を討つッ!
「ぜ、全部の牌が白……だと……!?」
ウォーズマンの絶対零度により絶滅したシュトロハイムと全生命。
それを全て包み込むように、新たな星が誕生した。
いや――星ではない。そんな規模を上回る、宇宙が誕生したのだ!
それを全て包み込むように、新たな星が誕生した。
いや――星ではない。そんな規模を上回る、宇宙が誕生したのだ!
「馬鹿な……あ、新しい宇宙が生まれた……だとォ……」
「どうやら……今回も壊れた自動卓を掴まされたみてーだな。困ったもんだぜ」
「どうやら……今回も壊れた自動卓を掴まされたみてーだな。困ったもんだぜ」
しれっと言ってのける跡部。
跡部はベタオリに徹しながら、コツコツと集めていたのだ。
ダメージが残っているから立ち上がるのが遅いふりをして、
プライド故にウォーズマンやシュトロハイムに肩は借りないと宣言して、
卓上に必ず残る白を集めていたのだッ!
跡部はベタオリに徹しながら、コツコツと集めていたのだ。
ダメージが残っているから立ち上がるのが遅いふりをして、
プライド故にウォーズマンやシュトロハイムに肩は借りないと宣言して、
卓上に必ず残る白を集めていたのだッ!
「文句はねーだろ?」
文句など、言えるはずがない。
跡部の手牌の白は、どれもこれも歪なもので、シュトロハイムや金将軍が捏造したものであると分かった。
自分が使って上がりを認めさせた牌で上がることを、認めないわけにはいかない。
シュトロハイムは観念し、惑星に押しつぶされたイメージで吐血しながら、言った。
跡部の手牌の白は、どれもこれも歪なもので、シュトロハイムや金将軍が捏造したものであると分かった。
自分が使って上がりを認めさせた牌で上がることを、認めないわけにはいかない。
シュトロハイムは観念し、惑星に押しつぶされたイメージで吐血しながら、言った。
「認めよう。少なくとも字一色。俺は飛び――――お前の一位で決着だ」
跡部の勝利が確定し、再び場に謎の氷帝コールが響く。
しかしシュトロハイムはもはやそのことを気にかけない。
ただただ目の前の勝利者に敬意を払い、その姿を見つめていた。
しかしシュトロハイムはもはやそのことを気にかけない。
ただただ目の前の勝利者に敬意を払い、その姿を見つめていた。
(悪いな、ウォーズマン。勝つのは――――俺だ)
跡部は、ウォーズマンに敬意を払う。
彼だけはイカサマを使わぬまま、数え役満で首位を掴み取れるところまできていた。
立ったまま気絶している立派な雀士に、特別な敬意を持たずにはいられない。
彼だけはイカサマを使わぬまま、数え役満で首位を掴み取れるところまできていた。
立ったまま気絶している立派な雀士に、特別な敬意を持たずにはいられない。
「あーん……?」
ウォーズマンを見ていたから。
敬意を払っていたから。
跡部もシュトロハイムも、何が起きたのか気付かなかった。
気付いたのは、二度目の銃声と共に跡部の腕に大穴が空き、その衝撃で半回転してからだった。
敬意を払っていたから。
跡部もシュトロハイムも、何が起きたのか気付かなかった。
気付いたのは、二度目の銃声と共に跡部の腕に大穴が空き、その衝撃で半回転してからだった。
「な、なァァァァァァ~~~~~~ッ!?」
シュトロハイムが驚愕の声を上げる。
二発の銃弾を撃ち込まれてなおも倒れずに踏ん張る跡部に向けて、三発目の銃弾が撃ち込まれた。
頭部も心臓部も狙えないへっぽこなスナイパーの正体、それは。
二発の銃弾を撃ち込まれてなおも倒れずに踏ん張る跡部に向けて、三発目の銃弾が撃ち込まれた。
頭部も心臓部も狙えないへっぽこなスナイパーの正体、それは。
「文句はねーだぁ? 大ありだっつーーーーーーーの!」
金将軍が、いつの間にかデザートイーグルを手にしていた。
ウォーズマンの上がりにシュトロハイムと金将軍が気を取られている隙に跡部が牌を入れ替えたように。
金将軍は、跡部の上がりにシュトロハイムと跡部が気を取られている隙にバッグからデザートイーグルを取り出していたのだッ!
ウォーズマンの上がりにシュトロハイムと金将軍が気を取られている隙に跡部が牌を入れ替えたように。
金将軍は、跡部の上がりにシュトロハイムと跡部が気を取られている隙にバッグからデザートイーグルを取り出していたのだッ!
「俺が負けるなんてありえねーーーーーーし!」
跡部の眼力により弾道を予測できても、ラケットなき今の跡部に銃弾を防ぐ術はない。
体と頭への被弾を防ぐべく身を捩るが、テニスのために必要な指を吹き飛ばされたり、完全回避に至れない。
次は頭部被弾を避けれない――――そう思った跡部の体を、シュトロハイムが突き飛ばす。
体と頭への被弾を防ぐべく身を捩るが、テニスのために必要な指を吹き飛ばされたり、完全回避に至れない。
次は頭部被弾を避けれない――――そう思った跡部の体を、シュトロハイムが突き飛ばす。
「やらせはせんぞォォォォォォッ! 提供されて3時間常温放置されたビールにも劣るクソ以下の野郎なぞにィィィィィィッ!
麻雀勝負の決着を、武力で決する無粋極まりないゲスなどにィィィィィィーーーーーーーーーーッッ!!!」
「ああ!? 殺し合えとか言われてんのに真面目に麻雀する方がどーかしてんだよバーーーーカ!!」
麻雀勝負の決着を、武力で決する無粋極まりないゲスなどにィィィィィィーーーーーーーーーーッッ!!!」
「ああ!? 殺し合えとか言われてんのに真面目に麻雀する方がどーかしてんだよバーーーーカ!!」
一理ある。
「そぅら凍れ……シュトロハイム! あそこの陰だッ!」
氷の世界は死角を見つける。
それは、デザートイーグルで撃てない遮蔽物を探すことすら可能ッ!
跡部の指示を受けて、跡部の首根っこを掴んでシュトロハイムが跡部にしか見えない氷柱へと駆け込む。
それは、デザートイーグルで撃てない遮蔽物を探すことすら可能ッ!
跡部の指示を受けて、跡部の首根っこを掴んでシュトロハイムが跡部にしか見えない氷柱へと駆け込む。
「くっ……跡部! 跡部! しっかりしろッ!」
「ちっ……これじゃあ……テニスをやるのに……苦労しそうだな……」
「ちっ……これじゃあ……テニスをやるのに……苦労しそうだな……」
跡部の傷は、並々ならぬものであった。
デザートイーグルの反動と、その反動を制御できない金将軍の下手くそな腕。
それが見事に噛み合って、跡部の腕ばかりを破壊していたのだ。
デザートイーグルの反動と、その反動を制御できない金将軍の下手くそな腕。
それが見事に噛み合って、跡部の腕ばかりを破壊していたのだ。
「跡部……跡部ッ!」
痛み慣れをしていない王様に、限界が訪れる。
命の炎は消えてはいないが、その意識は闇へと落ちた。
目覚められるか、怪しいものだ。
命の炎は消えてはいないが、その意識は闇へと落ちた。
目覚められるか、怪しいものだ。
「おお……神よッ!! 日本にいるというメチャクチャに多いという神よッ!!!
もし本当に……おまえに人命を司る力があるのなら、こいつをッ……!!
この優しくも聡明な素晴らしい男だけは生かしてくれッ!!!」
もし本当に……おまえに人命を司る力があるのなら、こいつをッ……!!
この優しくも聡明な素晴らしい男だけは生かしてくれッ!!!」
死角に飛び込む際、一緒に引っ掴んできたデイパック。
一縷の望みに賭けて、その中身をひっくり返す。
一縷の望みに賭けて、その中身をひっくり返す。
「すぐれた人間のみ生き残ればよい!
敗れた俺とあの豚の命を奪うことは構わんッ! だがコイツはッ! この男だけはッ!」
敗れた俺とあの豚の命を奪うことは構わんッ! だがコイツはッ! この男だけはッ!」
その時だった。
ガシャンと派手な音を立て、シュトロハイムの視界に何かが飛び込んできた。
その大きくて黒い物体は、
ガシャンと派手な音を立て、シュトロハイムの視界に何かが飛び込んできた。
その大きくて黒い物体は、
「ポンコツ!」
「な……何が起き……」
(ドジこいたーーッ! 緊急事態だったせいでコイツの回収を忘れとったわーーーー!)
「な……何が起き……」
(ドジこいたーーッ! 緊急事態だったせいでコイツの回収を忘れとったわーーーー!)
ウォーズマンの体も被弾している。
おそらくその衝撃でふっ飛ばされてきたのだろう。
おそらくその衝撃でふっ飛ばされてきたのだろう。
「……跡部!?」
回路がショートしまともな判断の効かないウォーズマン。
それでも彼の壊れかけの頭脳は、友の体を見て覚醒した。
今、ここで立たねば、正義超人を名乗れない。
それでも彼の壊れかけの頭脳は、友の体を見て覚醒した。
今、ここで立たねば、正義超人を名乗れない。
「……な、ナチ公……」
「あァん?」
「き、貴様などに……こ、このような……ことを……」
「……フン! 我がドイツの先読み能力は世界一ィィィィィィ!
喋れもせんポンコツが無理せんでも、言いたいことくらい分かっておるわッ!」
「あァん?」
「き、貴様などに……こ、このような……ことを……」
「……フン! 我がドイツの先読み能力は世界一ィィィィィィ!
喋れもせんポンコツが無理せんでも、言いたいことくらい分かっておるわッ!」
このようなことを頼むのは、不本意なことだろう。
シュトロハイムとウォーズマンは、結局犬猿の仲だった。
だから、守りたい人間を、そんな相手に託すのは不本意なはずだ。
シュトロハイムとウォーズマンは、結局犬猿の仲だった。
だから、守りたい人間を、そんな相手に託すのは不本意なはずだ。
だが――それでも託すのだ。
不本意だろうと、屈辱だろうと。
友を、人を、誇り高き少年を守れぬことは、屈辱よりも辛いことだから。
不本意だろうと、屈辱だろうと。
友を、人を、誇り高き少年を守れぬことは、屈辱よりも辛いことだから。
「あ、あれを……」
ウォーズマンが自身のデイパックを指さす。
一々デイパックを持って移動していたシュトロハイムと違い、
ウォーズマンは面倒臭がりデイパックを部屋の隅に置いていた。
そう、今シュトロハイム達のいる、この場所に。
一々デイパックを持って移動していたシュトロハイムと違い、
ウォーズマンは面倒臭がりデイパックを部屋の隅に置いていた。
そう、今シュトロハイム達のいる、この場所に。
「……こ、これはッ!」
意外ッ! それは医療セットッ!
感染症を起こさぬよう無菌状態を保てる簡易なオペ室までついているッ!
やはり跡部は、生き残るべく天に選ばれた王なのだッ!
感染症を起こさぬよう無菌状態を保てる簡易なオペ室までついているッ!
やはり跡部は、生き残るべく天に選ばれた王なのだッ!
「う……腕を……やってくれ……こ、この……俺の……ベアクローを……」
ウォーズマンが、自分自身の腕をもぐ。
それを、シュトロハイムに差し出した。
それを、シュトロハイムに差し出した。
超人として、何より大事なベアクロー。
守るべき男のために、それを差し出そうというのだ。
守るべき男のために、それを差し出そうというのだ。
「代わりに……こ、こいつを……貰うぞ……」
先程床に散らばった、カセットガスボンベセット。
シュトロハイムに支給されたコンロのオマケのようなものを、ウォーズマンは4本取った。
その意図を汲み取って、シュトロハイムが頷いた。
シュトロハイムに支給されたコンロのオマケのようなものを、ウォーズマンは4本取った。
その意図を汲み取って、シュトロハイムが頷いた。
「……アカクロ野郎。俺は最後まで貴様のことが気に入らんし、ぶっ殺してやりたい」
「こっちもだ」
「だが――貴様の想いは確かに受け取ったッ! この勇敢なる少年はッ! ナチスの誇りに賭けて絶対に生かすッ!」
「こっちもだ」
「だが――貴様の想いは確かに受け取ったッ! この勇敢なる少年はッ! ナチスの誇りに賭けて絶対に生かすッ!」
跡部と共に、シュトロハイムが無菌室へと駆け込む。
リロード中なのだろうか、今は銃撃が止んでいる。
飛び出すなら、今である。
リロード中なのだろうか、今は銃撃が止んでいる。
飛び出すなら、今である。
「好意はやらんが、敬意は払うぞ、ウォーズマンッ!」
「か……感謝だけはしてやるぞ、シュトロハイムッ!」
「か……感謝だけはしてやるぞ、シュトロハイムッ!」
ウォーズマンが飛び出す。
命に替えても、あの悪鬼を討ち滅ぼすべく。
氷のような精神で、守るべきはずの人間を――金将軍を討ち滅ぼすべく。
命に替えても、あの悪鬼を討ち滅ぼすべく。
氷のような精神で、守るべきはずの人間を――金将軍を討ち滅ぼすべく。
「ひゃっはー! 騙されたなバァーーーーカ!」
飛び出したウォーズマンが見たのは、デザートイーグルを構える金将軍ではなかった。
そこには、回転式機関砲を構える金将軍の姿。
そこには、回転式機関砲を構える金将軍の姿。
金将軍は、リロードをしていたというわけではない。
設置に時間がかかり、不意打ちには向かないため隠していた回転式機関砲を用意していたのだ。
馬鹿が飛び出してくるのを待ちながら。
設置に時間がかかり、不意打ちには向かないため隠していた回転式機関砲を用意していたのだ。
馬鹿が飛び出してくるのを待ちながら。
「鉄くずにしてやるぜェェェーーーーーーーーーーッ!」
弾丸の雨がウォーズマンへと降り注ぐ。
もとよりショート気味のウォーズマンに、機敏な動きなど出来ない。
ウォーズマンは弾丸の雨に吹き飛ばされた。
もとよりショート気味のウォーズマンに、機敏な動きなど出来ない。
ウォーズマンは弾丸の雨に吹き飛ばされた。
「はっはァーーー! たぁまんねぇなァ!!」
ビクンビクンと小刻みに震える金将軍。
口端からヨダレを垂らし、愉悦に身を委ねていた。
口端からヨダレを垂らし、愉悦に身を委ねていた。
「べ……ベアクローを失えど……友に貰った熱き心は失わんッ!」
その愉悦は、ポンコツ超人を侮ったことに起因する。
もう、立ち上がらないと思っていた。
立ち上がれても、近づかれる前に殺せる。
そう思っていたから。
もう、立ち上がらないと思っていた。
立ち上がれても、近づかれる前に殺せる。
そう思っていたから。
余裕?
これは油断と――いうものだッ!
これは油断と――いうものだッ!
「おわっ!?」
立ち上がったウォーズマンを撃とうとした。
狙える腕なんてないので、とりあえず撃ちっぱなしにしたまま銃口を向ければいいと思っていた。
だから、途中でウォーズマンのしかけたカセットガスボンベをうっかり撃ち抜いてしまい、爆発に気を取られてしまったのだ。
狙える腕なんてないので、とりあえず撃ちっぱなしにしたまま銃口を向ければいいと思っていた。
だから、途中でウォーズマンのしかけたカセットガスボンベをうっかり撃ち抜いてしまい、爆発に気を取られてしまったのだ。
「お前を……見習って……なってやるさ……奇跡の逆転ファイターにッ!」
ウォーズマンは知っている。
どんな逆境になっても、諦めずに勝利を掴んだ超人を。
彼に倣い、ウォーズマンも諦めない。
命終えるその時まで、決して。
どんな逆境になっても、諦めずに勝利を掴んだ超人を。
彼に倣い、ウォーズマンも諦めない。
命終えるその時まで、決して。
「す……スクリュードライバーッ!」
ベアクローはない。威力などない。
それでも唯一無二の突進力に賭け、スクリュードライバーを繰り出す。
慌てて回転式機関砲を撃ったとしてももう遅い。
動揺から放った銃弾はウォーズマンに当たらない。
何しろ、体を寝かせて突進をすることで、被弾面積を最小限に減らしたのだから。
それでも唯一無二の突進力に賭け、スクリュードライバーを繰り出す。
慌てて回転式機関砲を撃ったとしてももう遅い。
動揺から放った銃弾はウォーズマンに当たらない。
何しろ、体を寝かせて突進をすることで、被弾面積を最小限に減らしたのだから。
「し、死にぞこないがァァァーーーー!」
「ぱ……パロスペシャルッ!」
「ぱ……パロスペシャルッ!」
至近距離に迫られて、慌ててデザートイーグルに獲物を変える金将軍。
しかしその手は引き金にかかるより早く、ウォーズマンのパロスペシャルにかかっていた。
しかしその手は引き金にかかるより早く、ウォーズマンのパロスペシャルにかかっていた。
「人間を……こ、殺すのは……心苦しいが……」
「ふざっけんじゃねーぞ! 俺は北の将軍様ッ!
あの糞ガキみてーに、人間じゃねえんだ! 人間を超越した偉大なる存在なんだよ!」
「そうか……人間じゃない、か……ならば遠慮はしないッ!」
「ふざっけんじゃねーぞ! 俺は北の将軍様ッ!
あの糞ガキみてーに、人間じゃねえんだ! 人間を超越した偉大なる存在なんだよ!」
「そうか……人間じゃない、か……ならば遠慮はしないッ!」
パロスペシャルに、渾身の力を込める。
それでも限界時間を越え、被弾までした体では、人間の体一つ壊せない。
だがしかし――決して離しなどしない。
何より信頼出来るフェイバリットホールドは、回路の落ちるその瞬間まで解除はしないッ!
それでも限界時間を越え、被弾までした体では、人間の体一つ壊せない。
だがしかし――決して離しなどしない。
何より信頼出来るフェイバリットホールドは、回路の落ちるその瞬間まで解除はしないッ!
「こんなへなちょこ技で死んでたまるかァァァァァァ~~~~~~!!」
「た……確かに今の俺の力じゃ……腕一本もぎとれない……だが……離しもしないぞッ……」
「た……確かに今の俺の力じゃ……腕一本もぎとれない……だが……離しもしないぞッ……」
喚く金将軍。
その無様な言葉をかき消すように、全ての力を持ってウォーズマンが叫んだ。
その無様な言葉をかき消すように、全ての力を持ってウォーズマンが叫んだ。
「やれェェェーーーーーーーーーーッ! シュトロハイムーーーーッ!」
パロスペシャルに決められた金将軍には見えないが、オペ室から何かが飛来してきた。
それは、所謂パイナップルと呼ばれるもの。
金将軍は最後までそれに気付かぬまま、自分の尊さを叫び、そして閃光に消えた。
それは、所謂パイナップルと呼ばれるもの。
金将軍は最後までそれに気付かぬまま、自分の尊さを叫び、そして閃光に消えた。
☆ ★ ☆ ★ ☆
「跡部ェェェーーーーーーーーーーッ! 寝ている場合かァァァーーーーッ!」
「……シュトロ……ハイム……?」
「……シュトロ……ハイム……?」
やかましいシュトロハイムが目覚ましとなり、跡部が重たい瞼を開ける。
視界に映るシュトロハイムの表情は、特に普段と変わりはない。
変わりがあるとするならば、その背景が炎に包まれた首相官邸だということくらいだ。
視界に映るシュトロハイムの表情は、特に普段と変わりはない。
変わりがあるとするならば、その背景が炎に包まれた首相官邸だということくらいだ。
「な……これは……」
跡部が体を起こす。
腕が痛い。当然だ。何せ撃たれて千切れかけ――――
腕が痛い。当然だ。何せ撃たれて千切れかけ――――
「何……だと……」
跡部の目が驚愕に見開かれる。
もう動かないことさえ覚悟していた腕が動いた。
痛みはあるが動いていた。
しかし痛みなど些細な問題。
腕がどう見ても別人のものになっていることを除けば。
もう動かないことさえ覚悟していた腕が動いた。
痛みはあるが動いていた。
しかし痛みなど些細な問題。
腕がどう見ても別人のものになっていることを除けば。
「あの馬鹿ロボめ……ボンベを撒く量が多すぎるッ!
我がナチスの科学力がなければ、守るべき者も死んでいたぞッ!」
我がナチスの科学力がなければ、守るべき者も死んでいたぞッ!」
そして、目の前の腕を失ったシュトロハイムが、全身から血を流していることを除けば。
「シュトロハイム!?」
「無断で俺とウォーズマンの腕をお前に移植したッ! だが謝らんぞッ! 恨ませんぞッ!
俺達は、俺達がもう駄目だと判断して、一番信用出来る者に大切なモノを託したのだッ!
貴様はその腕を誇れッ! そして俺とウォーズマンに代わって、この殺し合いを討ち滅ぼせッ!」
「無断で俺とウォーズマンの腕をお前に移植したッ! だが謝らんぞッ! 恨ませんぞッ!
俺達は、俺達がもう駄目だと判断して、一番信用出来る者に大切なモノを託したのだッ!
貴様はその腕を誇れッ! そして俺とウォーズマンに代わって、この殺し合いを討ち滅ぼせッ!」
シュトロハイムは、ウォーズマンの右腕を跡部の腕に移植した。
ナチスの科学力と医学薬学用いればどうということはない。
ナチスの科学力と医学薬学用いればどうということはない。
ましてやシュトロハイムは自身でサイボーグ手術を経験済み。
自身に施された超医療の内容を気になって聞かない者がおるか?
いなァァァ~~いッ!
そう、シュトロハイムには知識があったのだッ!
自身に施された超医療の内容を気になって聞かない者がおるか?
いなァァァ~~いッ!
そう、シュトロハイムには知識があったのだッ!
「そして……我がナチスを……祖国を頼む……
気に入らんが……まあ……あのソ連のクソ野郎どももな……」
気に入らんが……まあ……あのソ連のクソ野郎どももな……」
シュトロハイムは、右腕だけで、自身の左腕を跡部の左腕に移植した。
左腕に関してだけは、動作保証が出来ない完成度だが、やむを得まい。
左腕に関してだけは、動作保証が出来ない完成度だが、やむを得まい。
「シュトロハイム……」
「クク……そんな顔をするな……祖国と……祖国を守ってくれるであろう友のためなら……
腕の二本や三本……簡単に……くれてやるわ……」
「クク……そんな顔をするな……祖国と……祖国を守ってくれるであろう友のためなら……
腕の二本や三本……簡単に……くれてやるわ……」
やかましいシュトロハイムの言葉が徐々に弱々しくなる。
それは終わりの到来を意味していた。
それは終わりの到来を意味していた。
「ハーイル……」
シュトロハイムの瞳が跡部を映さなくなる。
その目に最期に映したのは、敬愛する総統閣下。
彼に敬意を示すべく、残された右腕を持ち上げ、そして――
その目に最期に映したのは、敬愛する総統閣下。
彼に敬意を示すべく、残された右腕を持ち上げ、そして――
右腕を誇らしく突き上げたまま、ルドル・フォン・シュトロハイムは、首相官邸で誇り高き名誉の戦死を遂げる。
大爆発の最中跡部を抱きしめて、爆炎から守ったことが致命傷だった。
けれども後悔はない。
跡部は、同盟国の聡明な少年は、己の命を賭すに相応しい男だと思ったから。
けれども後悔はない。
跡部は、同盟国の聡明な少年は、己の命を賭すに相応しい男だと思ったから。
「……シュトロハイム……ウォーズマン……」
跡部は、生かされた。
己で生を掴みとったわけではない。
跡部は、生かされたのだ。二人の戦士に。
己で生を掴みとったわけではない。
跡部は、生かされたのだ。二人の戦士に。
「この借りは……必ず返すぜ……跡部王国の大都市に、その名前をつけてやる」
冗談めかしながら、シュトロハイムの亡骸の目を閉じさせる。
それから、ふらふらと立ち上がり、デイパックを拾い上げた。
それから、ふらふらと立ち上がり、デイパックを拾い上げた。
「今の俺じゃ……王なんて名乗れねえな……だが……諦めねえ……」
諦めたら、誇り高き友の行いが無駄に終わる。
それだけは、認められない。
それだけは、認められない。
「日吉じゃねーが……下克上だ……また、王に返り咲く」
決意の言葉を口にしながら、燃え落ちていく首相官邸を眺める。
それは、国の終わりを象徴していた。
それは、国の終わりを象徴していた。
「いや……以前と同じ地位に戻るだけじゃねえ。それこそ……大陸を統べる勢いだ。
ナチスも……ソ連も……全部まとめて……俺が導いてやるッ」
ナチスも……ソ連も……全部まとめて……俺が導いてやるッ」
跡部王国は終わった。
だがしかし、王は――王だった者はまだ生きている。
再び建国し、他国もまとめて導くために。
言うならば、跡部大陸を作るために。
だがしかし、王は――王だった者はまだ生きている。
再び建国し、他国もまとめて導くために。
言うならば、跡部大陸を作るために。
燃え落ちていく国家の象徴に背を向け、多くを失った王は、ただの一人の少年として、歩きはじめた。
【A-7/首相官邸(絶賛炎上中)/一日目-昼】
【跡部景吾@新・テニスの王子様】
[参戦時期]:不明、すくなくとも跡部王国建国後より参戦ッ
[状態]:右手にウォーズマンを、左手にシュトロハイムを
[装備]:なし
[道具]:基本支給品×2、カセットコンロ、カセットガスボンベ×2、手榴弾×1、不明支給品(1~3)
[スタンス]:跡部大陸を作る
[思考]
基本:主催を打ち倒し、参加者を導き勝利する
1:人を探そう。ナチスとソ連の人物は優先的に守りたい
[参戦時期]:不明、すくなくとも跡部王国建国後より参戦ッ
[状態]:右手にウォーズマンを、左手にシュトロハイムを
[装備]:なし
[道具]:基本支給品×2、カセットコンロ、カセットガスボンベ×2、手榴弾×1、不明支給品(1~3)
[スタンス]:跡部大陸を作る
[思考]
基本:主催を打ち倒し、参加者を導き勝利する
1:人を探そう。ナチスとソ連の人物は優先的に守りたい
※金将軍とウォーズマンの基本支給品は燃え盛る炎の中に残されています。
※回転式機関砲・デザートイーグル・メンゲレのメス・医療セットは大爆発でダメになりました。
※回転式機関砲・デザートイーグル・メンゲレのメス・医療セットは大爆発でダメになりました。
【金将軍@ムダヅモ無き改革 死亡】
【ウォーズマン@キン肉マン 死亡】
【ルドル・フォン・シュトロハイム 死亡】
【ウォーズマン@キン肉マン 死亡】
【ルドル・フォン・シュトロハイム 死亡】
【メンゲレのメス@ムダヅモ無き改革】
金将軍に支給。
死の天使ことヨーゼフ・メンゲレが使っていたメス。
切れ味バツグンで、牌の表面を削ることで白を生み出す『ゾーリンゲン轟盲牌』を可能にする。
金将軍に支給。
死の天使ことヨーゼフ・メンゲレが使っていたメス。
切れ味バツグンで、牌の表面を削ることで白を生み出す『ゾーリンゲン轟盲牌』を可能にする。
【デザートイーグル@現実】
金将軍に支給。
威力と反動に定評のあるマグナム銃。
フィクション作品にやたらと出るので、名前だけの知名度は抜群。
金将軍に支給。
威力と反動に定評のあるマグナム銃。
フィクション作品にやたらと出るので、名前だけの知名度は抜群。
【回転式機関砲@現実】
金将軍に支給。
いわゆるガトリングガンであり、持ち運びには不適だが非常に強力な武器。
持ってるだけでヒャッハーしたくなる魅力がある。
ある意味男のロマンである。たまんねぇなァ!
金将軍に支給。
いわゆるガトリングガンであり、持ち運びには不適だが非常に強力な武器。
持ってるだけでヒャッハーしたくなる魅力がある。
ある意味男のロマンである。たまんねぇなァ!
【医療セット@現実】
ウォーズマンに支給。
オペ室にあるようなものがごっそり揃った簡易無菌室。
その全てが最先端であり、地味に相当な金がかかった支給品。
多分、サハラ砂漠だろうとオペをすることが可能。
ナチスの医学薬学を駆使すれば多分爆死していても復活できたものと思われる。
そのチートっぷりの反動か、跡部にはこれだけしか支給されなかった。
ウォーズマンに支給。
オペ室にあるようなものがごっそり揃った簡易無菌室。
その全てが最先端であり、地味に相当な金がかかった支給品。
多分、サハラ砂漠だろうとオペをすることが可能。
ナチスの医学薬学を駆使すれば多分爆死していても復活できたものと思われる。
そのチートっぷりの反動か、跡部にはこれだけしか支給されなかった。
【カセットコンロ@現実】
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
調理にも使える便利なコンロ。
当たり前だが、カセットガスボンベがなければただのお荷物である。
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
調理にも使える便利なコンロ。
当たり前だが、カセットガスボンベがなければただのお荷物である。
【カセットガスボンベ6本セット@現実】
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
カセットコンロとセットで支給されていたボンベ。
この殺し合い中に野外でグルメを楽しむならば必須アイテムである。
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
カセットコンロとセットで支給されていたボンベ。
この殺し合い中に野外でグルメを楽しむならば必須アイテムである。
【手榴弾@現実】
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
通称パイナップル。
爆弾としてあまりにも有名で、原作バトル・ロワイアルでも支給された逸品。
原作のように劣化威力というわけではない。二個セット。
ルドル・フォン・シュトロハイムに支給。
通称パイナップル。
爆弾としてあまりにも有名で、原作バトル・ロワイアルでも支給された逸品。
原作のように劣化威力というわけではない。二個セット。
| 豚少女 | 投下順 | これは親友ですか?いいえ、その孫です。 |
| ここに雀荘を建てようッ! | 跡部景吾 | |
| ここに雀荘を建てようッ! | 金将軍 | GAME OVER |
| ここに雀荘を建てようッ! | ウォーズマン | GAME OVER |
| ここに雀荘を建てようッ! | ルドル・フォン・シュトロハイム | GAME OVER |