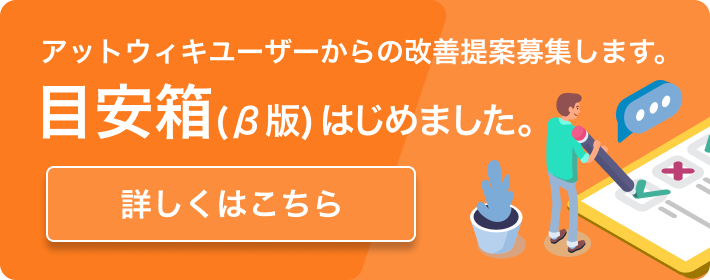遠藤終赤プロローグ
最終更新:
dangerousss3
-
view
プロローグ
上野駅周辺。
大勢の野次馬が見守る中、睨み合う者がいた。
核とウィルスによって世紀末と化した街で、争い事はいつもの事。だが、いつものように見物人がその争いに野次を挟むことは無かった。
なぜなら、その二人は『探偵』で、推理を業物としていたからである。
核とウィルスによって世紀末と化した街で、争い事はいつもの事。だが、いつものように見物人がその争いに野次を挟むことは無かった。
なぜなら、その二人は『探偵』で、推理を業物としていたからである。
「……おい見ろよ、探偵だ」
「ヒャッハー!探偵とは年代物だな、しかもそれが、二人も!」
「ああ、たいした推理だ、見るだけで伝わってくるぜ」
「……こりゃあ凄い戦いが見られるな。もちろん、この戦い、どちらかが死ぬだろう」
「ヒャッハー!探偵とは年代物だな、しかもそれが、二人も!」
「ああ、たいした推理だ、見るだけで伝わってくるぜ」
「……こりゃあ凄い戦いが見られるな。もちろん、この戦い、どちらかが死ぬだろう」
◆
(――隙が、ありませんね)
この話の主役となる探偵『遠藤終赤』は、胸の内で呟いた。
探偵同士の仕合。一瞬の不覚で勝負は決まる。互いに推理の視線をぶつけあい、指は下ろしたまま。微動だにしない。
対峙する探偵は黒いコートに片目を眼帯で覆った、長身の男。14歳の少女とは30cm以上の差がある。
探偵同士の仕合。一瞬の不覚で勝負は決まる。互いに推理の視線をぶつけあい、指は下ろしたまま。微動だにしない。
対峙する探偵は黒いコートに片目を眼帯で覆った、長身の男。14歳の少女とは30cm以上の差がある。
独自のアレンジが加えられているが、男は遠藤と同じ流派だろう。即ち、『本格派』。嘘偽りないアリバイの間合いと、慧眼の姿勢でまっすぐに構えられた伏線。
(実に、スマートな伏線です)
完全な静止。
吸血で血ぶくれした蚊が、遠藤の、羽織の袖からボタリ、と落ちた。
(実に、スマートな伏線です)
完全な静止。
吸血で血ぶくれした蚊が、遠藤の、羽織の袖からボタリ、と落ちた。
(犯人)
二者が同時に動く。
(は)
指先が互いのアリバイを崩す。
(お前――……)(貴方――……)
敵の方が速い。その指が、遠藤の額を捕らえた。
二者が同時に動く。
(は)
指先が互いのアリバイを崩す。
(お前――……)(貴方――……)
敵の方が速い。その指が、遠藤の額を捕らえた。
◆
「「ダッ!!」」
決着がつき、眼帯の男が仰向けに倒れこんでからも、観衆はしばらくの間動けなかった。
その気迫と、鼓膜がやぶれんばかりの空気の振動に圧倒されたのだ。
男は遠藤の推理光線で眉間を撃ちぬかれていた。
遠藤の袖の、内側に張り付けられた蛍光ピンクの付箋が、桜のようにあたりを舞う。彼女はそっと腕をおろし、気を付けの姿勢を取った。
その気迫と、鼓膜がやぶれんばかりの空気の振動に圧倒されたのだ。
男は遠藤の推理光線で眉間を撃ちぬかれていた。
遠藤の袖の、内側に張り付けられた蛍光ピンクの付箋が、桜のようにあたりを舞う。彼女はそっと腕をおろし、気を付けの姿勢を取った。
観衆が騒ぎ出すより前に、人々の間をぬって二人の人間が歩み出る。
二人の顔は、今まさに戦っていた探偵達と瓜二つ。
「ふむ……」眼帯男は死んだ自分自身の顔を覗き込む。「見事な腕前でござる」
二人の顔は、今まさに戦っていた探偵達と瓜二つ。
「ふむ……」眼帯男は死んだ自分自身の顔を覗き込む。「見事な腕前でござる」
「貴方も、素晴らしい推理でした」「お手合わせ、ありがとうございます」二人の遠藤が同時にお辞儀した。よく見ると、その場にいる四人はどれも『厚み』がおかしい。包丁で二等分された食パンのように、横から見た厚さが無い。
どよめく観衆は驚きながらも納得する。彼らは探偵。何が起こっても不思議は無いのだ、と。
どよめく観衆は驚きながらも納得する。彼らは探偵。何が起こっても不思議は無いのだ、と。
「よっこらせぃ」眼帯男は死んだ自分の両腕を抱えると、自分の体に貼り付ける。二つの体はピタリと同化した。
「今回は拙どもの能力で『二等分した体』を使いましたが、使わなければ、やはり結果は違ってくるでしょう」遠藤が言う。「体力も力も、二等分されていますから、勝手が違ったはずです」
「いやいや、変わらんでござろう。己の未熟を痛感いたした。 『大会』への参加は見送るとしよう」眼帯男は古風な探偵言葉を話す。「遠藤殿が、代わりに出場していただきたい」チケットのようなものを取り出し、遠藤へ渡す。「無理な果し合いを受けてくださり、礼を言う。大会で、是非とも、探偵の一分を立てて欲しい」
「は」遠藤はうやうやしく礼をして、それを受け取った。 「ありがたく頂戴致します」彼女は誰に対してもこの態度を崩さない。
「あッははは! 勝ったおぬしが、そんなにかしこまる事は……」眼帯はそう笑うと言葉を止め、頭を押さえた。「む……」額から血が流れている。「これは……」
「今回は拙どもの能力で『二等分した体』を使いましたが、使わなければ、やはり結果は違ってくるでしょう」遠藤が言う。「体力も力も、二等分されていますから、勝手が違ったはずです」
「いやいや、変わらんでござろう。己の未熟を痛感いたした。 『大会』への参加は見送るとしよう」眼帯男は古風な探偵言葉を話す。「遠藤殿が、代わりに出場していただきたい」チケットのようなものを取り出し、遠藤へ渡す。「無理な果し合いを受けてくださり、礼を言う。大会で、是非とも、探偵の一分を立てて欲しい」
「は」遠藤はうやうやしく礼をして、それを受け取った。 「ありがたく頂戴致します」彼女は誰に対してもこの態度を崩さない。
「あッははは! 勝ったおぬしが、そんなにかしこまる事は……」眼帯はそう笑うと言葉を止め、頭を押さえた。「む……」額から血が流れている。「これは……」
「しばらくは頭痛がやまないでしょう」と『もう一人』の遠藤が言った。「半身の眉間が打ち抜かれたのですから。力や耐久力も、半分のままです」
「なるほど」眼帯男は顎に手をやる。「もう少し会話したいところだが……、この調子では迷惑か。 療養して、しばらくは山篭りかな」ふ、と鼻をならす。
「ええ、来るべき攘夷の時に、……備えましょう」片方の遠藤は笑い、もう片方の遠藤は真剣に頷く。
眼帯男はバサリとコートを翻し、礼をする。「左様ならば遠藤殿。またの機会にして。 拙者は、これにて失礼つかまつる」
「なるほど」眼帯男は顎に手をやる。「もう少し会話したいところだが……、この調子では迷惑か。 療養して、しばらくは山篭りかな」ふ、と鼻をならす。
「ええ、来るべき攘夷の時に、……備えましょう」片方の遠藤は笑い、もう片方の遠藤は真剣に頷く。
眼帯男はバサリとコートを翻し、礼をする。「左様ならば遠藤殿。またの機会にして。 拙者は、これにて失礼つかまつる」
「「ええ、さようなら」」二人の遠藤は、去る男の背が見えなくなるまで、気を付けの姿勢で礼をしていた。
◆
遠藤が郊外に出ると、人の姿は一人も見当たらなくなった。
関東滅亡から復興途中だった日本は、パンデミック事件で最も被害を受けた国の一つだ。国力は大幅に減少し、国の吸収合併を望む声も多い。しかしこのほとんどが、外国の軍事探偵による工作である。
故に、急務なのだ。かつて廃偵令によって失われた、大日本軍事探偵制の復活が。
関東滅亡から復興途中だった日本は、パンデミック事件で最も被害を受けた国の一つだ。国力は大幅に減少し、国の吸収合併を望む声も多い。しかしこのほとんどが、外国の軍事探偵による工作である。
故に、急務なのだ。かつて廃偵令によって失われた、大日本軍事探偵制の復活が。
「貴女に、謝らないといけません」遠藤はもう一人の自分に顔を向け、言った。
「どうかしたの?」軽い口調で答える。
遠藤がこのように敬語とため語の入り混じった言葉を話すのは、自分自身が相手の時だけだ。
「はい」遠藤は地に膝をつく。「……う」手をこぶしにして膝に置いた。「情けない……。情け、ない……!」ぼろぼろと涙をこぼす。
「おや、肩に」一方の遠藤がそれを見ると、肩から血が滲んでいる。「先の仕合で撃たれたんだね」泣き崩れたもう一人の自分の着物をはだけさせ、肩を見る。探偵彫りの桜吹雪が赤く染まっていた。
「驕っておりました。叔父の本格派を学んだ拙が、別で学んだそれに遅れをとるはずが無いと」
「それで怪我を」
「力不足です」
「驕りというのは」
「手を抜きました」
「よく、わからないよ?」
「うん。……いや、……いえ」言葉を敬語に正し、前に立つ自分に顔を向ける。「あの男性は、思いつめた様子でした」
「ああ……」
「拙との戦いに、何か重いものを感じていたようです。探偵としての誇りをかけて。仕合に負けた場合、もしや、命を断つつもりなのでは無いか、と」
「では、負けても良いと思って?」
「そう……ですね。手を抜きました」遠藤はうつむいて語る。「叔父上に、申し訳が立ちません。それにあの男性にも、失礼なことをしました。遠下村塾の看板を背負う立場の者として、拙は……」
「でも。それは」
「介錯をお願いします」顔をあげた。「拙を、貴女の『中』に入れるべきではありません。ここで、切り捨てるべきです」彼女はここで、探偵の習俗『切腹』をしようというのだ。
「どうかしたの?」軽い口調で答える。
遠藤がこのように敬語とため語の入り混じった言葉を話すのは、自分自身が相手の時だけだ。
「はい」遠藤は地に膝をつく。「……う」手をこぶしにして膝に置いた。「情けない……。情け、ない……!」ぼろぼろと涙をこぼす。
「おや、肩に」一方の遠藤がそれを見ると、肩から血が滲んでいる。「先の仕合で撃たれたんだね」泣き崩れたもう一人の自分の着物をはだけさせ、肩を見る。探偵彫りの桜吹雪が赤く染まっていた。
「驕っておりました。叔父の本格派を学んだ拙が、別で学んだそれに遅れをとるはずが無いと」
「それで怪我を」
「力不足です」
「驕りというのは」
「手を抜きました」
「よく、わからないよ?」
「うん。……いや、……いえ」言葉を敬語に正し、前に立つ自分に顔を向ける。「あの男性は、思いつめた様子でした」
「ああ……」
「拙との戦いに、何か重いものを感じていたようです。探偵としての誇りをかけて。仕合に負けた場合、もしや、命を断つつもりなのでは無いか、と」
「では、負けても良いと思って?」
「そう……ですね。手を抜きました」遠藤はうつむいて語る。「叔父上に、申し訳が立ちません。それにあの男性にも、失礼なことをしました。遠下村塾の看板を背負う立場の者として、拙は……」
「でも。それは」
「介錯をお願いします」顔をあげた。「拙を、貴女の『中』に入れるべきではありません。ここで、切り捨てるべきです」彼女はここで、探偵の習俗『切腹』をしようというのだ。
『スマート・ポスト・イット』のコピー能力は、一時間でコピーが消滅し、土台となったオリジナルだけが残る。
その前に、二つが一体化すれば消滅は起こらずに済む。
切腹しようという遠藤はオリジナルであり、消滅することはない。だが、記憶を消すためにあえて死ぬ気だ。死んだ側の記憶は一体化しても継承されない。
その前に、二つが一体化すれば消滅は起こらずに済む。
切腹しようという遠藤はオリジナルであり、消滅することはない。だが、記憶を消すためにあえて死ぬ気だ。死んだ側の記憶は一体化しても継承されない。
介錯を頼まれた遠藤は目を伏せ、言った。「そう……ですか」……しかし、逆だ。死ぬほど後悔する失敗なら、その記憶を継承しなければ次に生かすことができない。わかっていながらも、二人の遠藤は自分の強情さをよく理解していた。
◆
探偵の作法にのっとり姿勢を正す。目礼ののち、衣服を脱いだ。上半身は胸の部分にだけさらしを巻いている。手には叔父の形見の虫眼鏡。ご存知のように、探偵の虫眼鏡はその柄が刃物のようにとがっており、犯人を刺し殺す凶器となる。
その刃を左腹部へ突き立てる。「……っ」
ヒュンッ、と。その時点で、介錯人の遠藤が切腹人の後頭部を推理光線で撃ちぬいた。
その刃を左腹部へ突き立てる。「……っ」
ヒュンッ、と。その時点で、介錯人の遠藤が切腹人の後頭部を推理光線で撃ちぬいた。
そう。刃物を使うよりも、探偵は素手のほうが強い。
事が終ってからも、生き残ったほうの遠藤はしばらく呆としていた。
そろそろ一時間経つ。(自分が消える前に、オリジナルと一体化しなければ)
遠藤は死体となった遠藤に自分の背中を貼りつけ、一体化した。
そろそろ一時間経つ。(自分が消える前に、オリジナルと一体化しなければ)
遠藤は死体となった遠藤に自分の背中を貼りつけ、一体化した。
体を起こし、見渡せば、ここはかつて上野公園と呼ばれた場所だ。
(叔父上への面目……ですか)
遠藤は付箋を取り出し、書いたメモを見返す。
眼帯探偵との仕合の間、『バックアップ』役として離れて見物していたもう一人の遠藤と眼帯は、少しの会話をしていた。
(叔父上への面目……ですか)
遠藤は付箋を取り出し、書いたメモを見返す。
眼帯探偵との仕合の間、『バックアップ』役として離れて見物していたもう一人の遠藤と眼帯は、少しの会話をしていた。
話によると、眼帯の男性は記憶喪失でさまよう野探偵との事だった。
はっきりした証拠が無いために口にしなかったが、遠藤の推理によると彼は叔父の遠下村塾、その塾生。つまり『遠藤の兄弟子』の可能性が高い。
彼の攘夷の思想やその立ちふるまい。探偵としては珍しく洋服を着ていること。これは、遠下村塾で主として教えられた『洋学』『兵学』『地理学』の影響を想起させる。
遠藤と仕合をした男性が思いつめた様子だったのは、彼が遠藤と対峙した事で記憶を取り戻したからでは無いのか。彼が死んだ今ではそれを確かめることはできない。それなら、生き残った方の彼は記憶を取り戻していないため、死を選ぶことは無いだろう。
はっきりした証拠が無いために口にしなかったが、遠藤の推理によると彼は叔父の遠下村塾、その塾生。つまり『遠藤の兄弟子』の可能性が高い。
彼の攘夷の思想やその立ちふるまい。探偵としては珍しく洋服を着ていること。これは、遠下村塾で主として教えられた『洋学』『兵学』『地理学』の影響を想起させる。
遠藤と仕合をした男性が思いつめた様子だったのは、彼が遠藤と対峙した事で記憶を取り戻したからでは無いのか。彼が死んだ今ではそれを確かめることはできない。それなら、生き残った方の彼は記憶を取り戻していないため、死を選ぶことは無いだろう。
(相手が『兄弟子』なら、貴女がそれほど気負う必要は無かったかもしれません。しかし、拙は強情な人間ですからね……)それでも、死にたがったかもしれない。
齢14にして死に急ぐ遠藤を、叔父がもし生きていれば、叱っただろう。
だがそもそも、この死にたがりの気質は叔父譲りといえる。
遠藤は辺りを見る。上野公園にかつてあった木々は枯れ。維新の探偵『西郷隆盛』の像は半壊していた。
「東京に桜が戻るのは、いつになるでしょうか」
桜の代わりに、遠藤の袖から散ったピンク色の付箋が、ひゅう、と風に舞った。桜と呼ぶにはまだ赤すぎる。
だがそもそも、この死にたがりの気質は叔父譲りといえる。
遠藤は辺りを見る。上野公園にかつてあった木々は枯れ。維新の探偵『西郷隆盛』の像は半壊していた。
「東京に桜が戻るのは、いつになるでしょうか」
桜の代わりに、遠藤の袖から散ったピンク色の付箋が、ひゅう、と風に舞った。桜と呼ぶにはまだ赤すぎる。