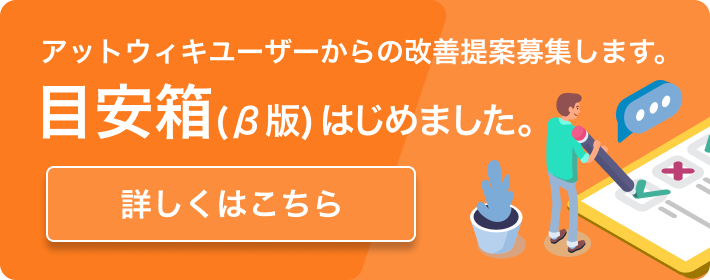エキシビジョンSSその2
最終更新:
dangerousss3
-
view
エキシビジョンSSその2
おれだ。
……『誰だ?』って? おいおいおい、ヒヒヒ!
今更しらばっくれてもらっちゃ困るよなァー?
そりゃ、フツーに考えたらよオー、わかるだろ。エキシビジョンなんだから。
今更しらばっくれてもらっちゃ困るよなァー?
そりゃ、フツーに考えたらよオー、わかるだろ。エキシビジョンなんだから。
フツー、あんたが書くとしたらどうするんだ。出すだろ?
『参加選手がオールスター!』ってのはよォーーー、
そりゃ『第一回』の頃から客寄せの定番だからなアー、ヒヒヒヒ!
『参加選手がオールスター!』ってのはよォーーー、
そりゃ『第一回』の頃から客寄せの定番だからなアー、ヒヒヒヒ!
アーーーーーー心配すンなって。わかるわかる。
おれが出たらまたワケ分かんない展開になるだろ、とか思ってんだろ。
大丈夫大丈夫、心配すんなよ、おれが保証してやるからよ、ヒヒヒヒヒ!
メタはうまく書けねえと票が落ちるって……分かってるからこうなんだろ?なあ。
大丈夫大丈夫、心配すんなよ、おれが保証してやるからよ、ヒヒヒヒヒ!
メタはうまく書けねえと票が落ちるって……分かってるからこうなんだろ?なあ。
このSSで……おれが登場してンのは、ここ。本編開始前だけだ。
メタなナレーションが許されるのは本編開始前だから。そういう事だろォ?
これで、まあ名目上も『全員登場』ってわけだ。
メタなナレーションが許されるのは本編開始前だから。そういう事だろォ?
これで、まあ名目上も『全員登場』ってわけだ。
でもさァー、おれが本編前でこーやって喋ってると、この後の展開!
何が起こっても嘘くせー感じになっちまうんじゃねえかなアーー?
メタが苦手って、冒頭からメタメタじゃねーか。ヒヒヒヒ!
何が起こっても嘘くせー感じになっちまうんじゃねえかなアーー?
メタが苦手って、冒頭からメタメタじゃねーか。ヒヒヒヒ!
ヒヒヒ! おれのせいで……票が、落ちちまうじゃねーーか。
つまりおれをこうやって喋らせるだけで?
投票で負けた時? そーいう責任を?
おれのせいにできちまう……って事じゃねえか? なあ?
つまりおれをこうやって喋らせるだけで?
投票で負けた時? そーいう責任を?
おれのせいにできちまう……って事じゃねえか? なあ?
ヒヒヒヒヒッ……
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ!!
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ!!
ギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギ
ャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャ
ャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャ
+ + + + +
静寂が支配していた。
世界最強の存在を決めるための戦い――『ザ・キングオブトワイライト』。
その決勝戦は、他のどの試合よりも密かに一瞬で……
決着を終えていた。
世界最強の存在を決めるための戦い――『ザ・キングオブトワイライト』。
その決勝戦は、他のどの試合よりも密かに一瞬で……
決着を終えていた。
「勝利です。赤羽ハル選手」
運営委員――実況の佐倉光素は、感情を表に出さぬよう努めた。
そこに黄樺地セニオはいない。戻ることもない。
この決勝の結末を見届けたスタッフは、彼女と埴井きららの2人だけだ。
「あなたが……この大会の優勝者です」
運営委員――実況の佐倉光素は、感情を表に出さぬよう努めた。
そこに黄樺地セニオはいない。戻ることもない。
この決勝の結末を見届けたスタッフは、彼女と埴井きららの2人だけだ。
「あなたが……この大会の優勝者です」
赤羽ハルは2人に背を向けたまま答えた。
「そっか」
「そっか」
「すげえ嬉しいよ」
山から見下ろす眼下、街の所々から煙が立ち昇りつつある。
人間による魔人狩りの行き着く果てがどうなるのか――
この世界において、過去にあらゆる形でその予想は語り尽くされていた。
人間による魔人狩りの行き着く果てがどうなるのか――
この世界において、過去にあらゆる形でその予想は語り尽くされていた。
魔人狩り。
文字通り「女」を「人」に置き換えただけの魔女狩りが始まるのだろう。
その外見で魔人と人間とを判別することは、殆どの場合不可能であるからだ。
文字通り「女」を「人」に置き換えただけの魔女狩りが始まるのだろう。
その外見で魔人と人間とを判別することは、殆どの場合不可能であるからだ。
消失した黄樺地セニオが最後に何を思ったかなど、誰にも知り得ない。
世界最後のチャラ男。無差別に軽薄に世界平和を望む彼は――
その理不尽な幸福の力で、全てを救い得るだろうか?
世界最後のチャラ男。無差別に軽薄に世界平和を望む彼は――
その理不尽な幸福の力で、全てを救い得るだろうか?
どちらにせよ、赤羽ハルは行動する必要があった。
そもそも神仏に頼る質ではなく、その点で赤羽ハルは凡庸な暗殺者であった。
ならばきっと、不確定な奇跡に頼る事もないのだろう。
そもそも神仏に頼る質ではなく、その点で赤羽ハルは凡庸な暗殺者であった。
ならばきっと、不確定な奇跡に頼る事もないのだろう。
「……なあ、副賞だ。副賞をくれ」
「不可能です。私達にその権限はありません。もう運営本部が機能するとも――」
「……! でも光素ちゃん、60億の契約を帳消しにできないと!
能力の制約が……赤羽さん死んじゃうんじゃないの!?」
「不可能です。私達にその権限はありません。もう運営本部が機能するとも――」
「……! でも光素ちゃん、60億の契約を帳消しにできないと!
能力の制約が……赤羽さん死んじゃうんじゃないの!?」
「すぐじゃあない。余裕はまだ十分にある」
赤羽ハルは苦笑した。
「だから副賞をくれ。今しかない」
赤羽ハルは苦笑した。
「だから副賞をくれ。今しかない」
「――戦争は止められない。でも何かができるかもしれないよな。
世界の敵やら世界の味方やらが、これだけ集まって……
あれだけの戦いを、実際にやらかしたんだ」
世界の敵やら世界の味方やらが、これだけ集まって……
あれだけの戦いを、実際にやらかしたんだ」
ザ・キングオブトワイライトは世界を変えるための戦いだった。
大会を仕組んだものすら、こうして世界を変えようとしていた。
誰も彼もが、自らの世界を変えるために――戦っていたはずだった。
大会を仕組んだものすら、こうして世界を変えようとしていた。
誰も彼もが、自らの世界を変えるために――戦っていたはずだった。
「副賞の願いを、今ここで使う。俺に協力しろ。
そして奴らを協力させてくれ。
何か……こういうどうしようもない事に抗う何か……」
そして奴らを協力させてくれ。
何か……こういうどうしようもない事に抗う何か……」
何かを、しなきゃあいけない――そう続けた。
「例えば俺に……何ができるのかを、教えてくれ」
「例えば俺に……何ができるのかを、教えてくれ」
「……聞き届けました。その願いをお受けしましょう。
私達の力が及ぶ限り」
佐倉光素と対照的に、埴井は不安げに視線を巡らせた。
「赤羽さんは……そのまま戦うつもりなんですか?
副賞もないのに、なんの理由があって……」
私達の力が及ぶ限り」
佐倉光素と対照的に、埴井は不安げに視線を巡らせた。
「赤羽さんは……そのまま戦うつもりなんですか?
副賞もないのに、なんの理由があって……」
「………………。
俺も格好をつけたくなった。ミツコや黄樺地……セニオみたいに。
コピー能力者に逆に影響されたわけだ。笑い話にならねえよな。
ハハハハハハハ」
俺も格好をつけたくなった。ミツコや黄樺地……セニオみたいに。
コピー能力者に逆に影響されたわけだ。笑い話にならねえよな。
ハハハハハハハ」
軽薄だが空虚な笑いだった。
準決勝までの赤羽ハルは、目的を達成するために抜け目なく手を打ってきた。
だが彼に、もはやそうするだけの理由はない。
準決勝までの赤羽ハルは、目的を達成するために抜け目なく手を打ってきた。
だが彼に、もはやそうするだけの理由はない。
ミツコが行使した能力、最後の『世界の敵の敵』。
赤羽ハルに纏わる関わりを断つささやかな世界改変は……
大切な存在の記憶さえをも消去している。
赤羽ハルに纏わる関わりを断つささやかな世界改変は……
大切な存在の記憶さえをも消去している。
「……“ケルベロス”ミツコ選手の『世界の敵の敵』。
それは“淘汰の選択”を行う能力と、私は理解しています」
誰よりも深い知識と経験――あらゆる魔人能力を知っている。
彼女は中立だ。魔人能力を、魔人の営みを見届ける事のみを目的とする。
(赤羽ハルの肩を持つわけではない。
……けれど、ここで、この世界から魔人が淘汰されてしまったら)
、 、
(私が、『観察』できなくなってしまうから)
それは“淘汰の選択”を行う能力と、私は理解しています」
誰よりも深い知識と経験――あらゆる魔人能力を知っている。
彼女は中立だ。魔人能力を、魔人の営みを見届ける事のみを目的とする。
(赤羽ハルの肩を持つわけではない。
……けれど、ここで、この世界から魔人が淘汰されてしまったら)
、 、
(私が、『観察』できなくなってしまうから)
「いくら魂の力を使って世界の改変を成したところで――
『勝ち進んでいない』可能性は実現できません。
恐らく、それがその魔人能力の本質。
ミツコ選手が猪狩誠を打ち負かし、それに繋がる悲劇を改変したように。
だから負けさせる必要があります……。例えば核を。病を。戦争を」
「……その原因が『勝ち進んだ』から、この世はこうなってる、ってわけか」
『勝ち進んでいない』可能性は実現できません。
恐らく、それがその魔人能力の本質。
ミツコ選手が猪狩誠を打ち負かし、それに繋がる悲劇を改変したように。
だから負けさせる必要があります……。例えば核を。病を。戦争を」
「……その原因が『勝ち進んだ』から、この世はこうなってる、ってわけか」
額の血を拭って、赤羽ハルは自嘲的に笑った。
時代遅れの暗殺者。現代の戦争でもはや不要と断ぜられた『強大な個人』。
思えば彼自身が、まさに敗北した時代の象徴だった。
時代遅れの暗殺者。現代の戦争でもはや不要と断ぜられた『強大な個人』。
思えば彼自身が、まさに敗北した時代の象徴だった。
「黄樺地セニオ選手の力は……理不尽で、誰よりも都合がよく。
けれど軽薄な力であるかもしれません。
歴史を改変するレベルには至らず、人類が少しチャラくなり。
“脅威”に対する敵意が、少しだけ弱くなって。
少しだけこれからの世界が良くなっていく……それだけの力、かも」
「……」
それとて紛れもなく世界平和、なのでしょうが。と佐倉光素は言った。
「――それでは、満足できないのでしょう?」
けれど軽薄な力であるかもしれません。
歴史を改変するレベルには至らず、人類が少しチャラくなり。
“脅威”に対する敵意が、少しだけ弱くなって。
少しだけこれからの世界が良くなっていく……それだけの力、かも」
「……」
それとて紛れもなく世界平和、なのでしょうが。と佐倉光素は言った。
「――それでは、満足できないのでしょう?」
「当たり前だ。
どうして俺がそう思うのか……分からない。けれど」
歯を食いしばった。彼は思い出すことができない。
「このままじゃあ、俺は全然納得できねえ」
どうして俺がそう思うのか……分からない。けれど」
歯を食いしばった。彼は思い出すことができない。
「このままじゃあ、俺は全然納得できねえ」
「俺は殺し屋だ。この戦争を仕掛けている連中を殺す。
必ず殺す」
必ず殺す」
「……そう選択すると、信じていた」
人気の失せた病院の中に、硬質な革靴の音が響いた。
非常時に打ち捨てられた病院には非常灯の光すらもなく、
カーテンの隙間から差し込む陽の光だけが、緑色の学ランを映す。
非常時に打ち捨てられた病院には非常灯の光すらもなく、
カーテンの隙間から差し込む陽の光だけが、緑色の学ランを映す。
「『振り返るな』。『前を歩け』。
――それが僕の信じた全て」
――それが僕の信じた全て」
少年は、病室の片隅に座り込む死体に話しかけている。
エプロンドレスは真紅の血に染まり、答える声はない。
エプロンドレスは真紅の血に染まり、答える声はない。
「可能性を奪って救済をもたらす力は、その能力の本質ではない。
この世界に生きる魔人の、誰もが知っているように……
もっとも価値ある『制約』とは、自らの魂そのもの。
だからこそ、それができる相手に受け渡すために、君達は死んだ」
この世界に生きる魔人の、誰もが知っているように……
もっとも価値ある『制約』とは、自らの魂そのもの。
だからこそ、それができる相手に受け渡すために、君達は死んだ」
「他人を殺して世界を救えると知っていても……
弱者のためになら、迫害される少数者のためになら、
自分達をも『殺す』事を『選択することができる』殺人鬼。
……だから君達に分け与えたのだ」
弱者のためになら、迫害される少数者のためになら、
自分達をも『殺す』事を『選択することができる』殺人鬼。
……だから君達に分け与えたのだ」
――――
学園坂正門
魔人能力名:『サクリファイス・ヒーロー』
――自身の生命と引き換えに、運命をささやかにやり直す。
http://www53.atwiki.jp/dangebalance/pages/65.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/50.html
魔人能力名:『サクリファイス・ヒーロー』
――自身の生命と引き換えに、運命をささやかにやり直す。
http://www53.atwiki.jp/dangebalance/pages/65.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/50.html
――――
「……」
病室の白いカーテンを開け放って、彼は街を眺めた。
黄樺地セニオの力は、世界の理不尽を変えるかもしれない。
たとえば治癒法のない病。核戦争。滅びた街。
黄樺地セニオの力は、世界の理不尽を変えるかもしれない。
たとえば治癒法のない病。核戦争。滅びた街。
そんな世界では、自由に物語を紡ぐことはできない。
深刻(シリアス)である、という巨大な重荷が人に覆いかぶさる限り、
無限の物語はその可能性を狭め、画一化されていく一方だからだ。
深刻(シリアス)である、という巨大な重荷が人に覆いかぶさる限り、
無限の物語はその可能性を狭め、画一化されていく一方だからだ。
深刻過ぎる世界も、平和過ぎる世界も、同様に世界を歪める『理不尽』。
少しだけ不思議で混沌とした、しかし気楽な世界――
過去の出来事を振り返らず、前に進んでいける世界を彼は望んでいる。
少しだけ不思議で混沌とした、しかし気楽な世界――
過去の出来事を振り返らず、前に進んでいける世界を彼は望んでいる。
「……黄樺地セニオは、果たしてどうだっただろうね?」
ザ・キングオブトワイライト――
その決勝まで勝ち進んだ彼の魂の力を以ってしても、
戦争という巨大な理不尽は変えられないのかもしれない。
巨大な歪みほど、その修正には多大なエネルギーを必要とする。
今のこの現実が少しでも、残された彼らの望む方向へ変わらなければ。
その決勝まで勝ち進んだ彼の魂の力を以ってしても、
戦争という巨大な理不尽は変えられないのかもしれない。
巨大な歪みほど、その修正には多大なエネルギーを必要とする。
今のこの現実が少しでも、残された彼らの望む方向へ変わらなければ。
……そしてそれは、
“転校生”学園坂正門の仕事ではない。
“転校生”学園坂正門の仕事ではない。
「ああ」
古アパートの小さな部屋で、彼はため息を突いた。
モニタが映し出すニュースを眺めるのは、小心そうな痩せぎすの中年。
田村草介は、どこにでもいる平凡な男性であった。
モニタが映し出すニュースを眺めるのは、小心そうな痩せぎすの中年。
田村草介は、どこにでもいる平凡な男性であった。
「……始まるのか……戦争が」
彼はどこか、他人事のように呟いていた。
魔人達の存在を常々恐怖していた田村だったが――
まさかここまでの事をしでかすとは、想像もしていなかった。
魔人達の存在を常々恐怖していた田村だったが――
まさかここまでの事をしでかすとは、想像もしていなかった。
番組は、魔人達の攻撃による理不尽な犠牲者達の映像に切り替わった。
今回の戦争は魔人達による蜂起であり、民衆の生活が脅かされている、と。
――これらの放送はその実殆どが目高機関の仕組むプロパガンダだ。
全ての放送局はこの戦争の開始前から、既に彼らの支配下にある。
今回の戦争は魔人達による蜂起であり、民衆の生活が脅かされている、と。
――これらの放送はその実殆どが目高機関の仕組むプロパガンダだ。
全ての放送局はこの戦争の開始前から、既に彼らの支配下にある。
無論、魔人達の反抗が今も多数の死者を生んでいるのは確かだ。
彼らの大部分が邪悪な存在である――という報道も、紛れもなく事実である。
だが、その戦争を仕掛けた黒幕について……それらは何も語らない。
彼らの大部分が邪悪な存在である――という報道も、紛れもなく事実である。
だが、その戦争を仕掛けた黒幕について……それらは何も語らない。
「恐ろしい……恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい」
田村は体を震わせながら立ち上がると、準備を始めた。
今にも、恐ろしい魔人達がやってくるのだ。
今にも、恐ろしい魔人達がやってくるのだ。
モニタの中では、魔人を標的とした核攻撃の是非についての議論が始まる。
「…………………。これで、全滅。
ふん。所詮はこの程度……何十年と戦争をしたこともない国だもの」
ふん。所詮はこの程度……何十年と戦争をしたこともない国だもの」
巨像の如き威容だった。
町中を悠然と打ち崩しながら進む主力戦車。
町中を悠然と打ち崩しながら進む主力戦車。
少女はそこにいた。
遠隔操作用の端末を手に笑う笑みは、11歳の少女のそれとはかけ離れている。
都内を射程内に捉える日本国保有のミサイルサイロを示すアイコン上には、
『Deleted』の赤文字が6つ並んだ。0.1秒の誤差もない。
遠隔操作用の端末を手に笑う笑みは、11歳の少女のそれとはかけ離れている。
都内を射程内に捉える日本国保有のミサイルサイロを示すアイコン上には、
『Deleted』の赤文字が6つ並んだ。0.1秒の誤差もない。
――自衛隊保有のICBMよりも『少しだけ精度の高い』ミサイル。
高島平四葉は、現在発射したものを除いても16基の『生産』を完了している。
敵の武器よりも少しだけ強い武器を作り出す。
……魔人能力『モア』による、世界最強の攻撃兵器。
高島平四葉は、現在発射したものを除いても16基の『生産』を完了している。
敵の武器よりも少しだけ強い武器を作り出す。
……魔人能力『モア』による、世界最強の攻撃兵器。
「これで核は撃てない。あなた達がやるっていうなら、私も相手をしてあげる」
世界を征服するために、既存の体制を破壊する必要がある。
それが自壊するというのならば話は早い。
存分に力を見せつけ、いずれ来る高島平四葉の治世への畏怖を刻みこむ。
それが自壊するというのならば話は早い。
存分に力を見せつけ、いずれ来る高島平四葉の治世への畏怖を刻みこむ。
(さあ、どうするか)
鉄のシェルターの中、少女は思いを巡らせる。
新黒死病よりも『二段階強い』ウィルスを材料とした脅迫で味方を引き込むか。
それとも、たった今奴らが用いようとした『核』をそのまま
――否、もう少し“強く”お返ししてやるべきか。
新黒死病よりも『二段階強い』ウィルスを材料とした脅迫で味方を引き込むか。
それとも、たった今奴らが用いようとした『核』をそのまま
――否、もう少し“強く”お返ししてやるべきか。
コンソールが異常を示したのは、その時だった。
「……狙撃ね」
外装への攻撃。当然のごとく、MBT――主力戦車の装甲を貫くことは不可能だ。
通常のMBTよりも『ちょっとだけ強い』この戦車の防御性能は、対戦車地雷にすら無傷で耐える。現行兵器による外からの破壊は不可能に等しい。
外装への攻撃。当然のごとく、MBT――主力戦車の装甲を貫くことは不可能だ。
通常のMBTよりも『ちょっとだけ強い』この戦車の防御性能は、対戦車地雷にすら無傷で耐える。現行兵器による外からの破壊は不可能に等しい。
《回線はこれで構わないメカ?》
だが突如、車内の軍事無線に割り込む声があった。
その声を知っていた。たとえ直接は戦ったことがなくとも……
その外見も声も、忘れようもないインパクトの選手。
その声を知っていた。たとえ直接は戦ったことがなくとも……
その外見も声も、忘れようもないインパクトの選手。
「あなたは」
《やはり日本国側の無線で通じるメカね――
成る程。自衛隊の兵器をそのままコピーできるのならば、
無線の機構も周波数も同じ……傍受も当然可能という理屈。
核の在処も、複数の通信網から推測を立てて先手を打った、メカか》
《やはり日本国側の無線で通じるメカね――
成る程。自衛隊の兵器をそのままコピーできるのならば、
無線の機構も周波数も同じ……傍受も当然可能という理屈。
核の在処も、複数の通信網から推測を立てて先手を打った、メカか》
「オーウェン・ハワード」
《ガキの割には、頭が回る……メカ》
《ガキの割には、頭が回る……メカ》
アキカンにして、元アメリカ陸軍レンジャー部隊長。
オーウェン・ハワードであった。
オーウェン・ハワードであった。
「……あなた。米軍のくせに、日本の猿を助けるつもり?」
《この国を最後に奪るのは我々メカ。同胞もまだこの国にはいる。
――我らの所有物を焦土にしてもらっては困る。
故にお前には止まってもらう。メカ》
《この国を最後に奪るのは我々メカ。同胞もまだこの国にはいる。
――我らの所有物を焦土にしてもらっては困る。
故にお前には止まってもらう。メカ》
……目的は、もう一つ。
オーウェン・ハワードが、その真意を気取らせる事はない。
(本命は俺ではない。オペレーション・ファントムルージュ。
政府が混乱している、この機に乗ずる。
兵器として管理されているそれの完全データを回収するまで……
『まだ』核攻撃をされてもらっては困る、メカ)
オーウェン・ハワードが、その真意を気取らせる事はない。
(本命は俺ではない。オペレーション・ファントムルージュ。
政府が混乱している、この機に乗ずる。
兵器として管理されているそれの完全データを回収するまで……
『まだ』核攻撃をされてもらっては困る、メカ)
「どいてちょうだい。……あなたは標的にはない。
だけど邪魔をするつもりなら、すぐにでも消す」
《メカカカカ……今のは少し面白い冗談だったメカよ》
だけど邪魔をするつもりなら、すぐにでも消す」
《メカカカカ……今のは少し面白い冗談だったメカよ》
《小娘ごときが……俺に『どけ』と言ったな?》
「そう? 冗談に聞こえたのなら――」
端末の画面には、地図があった。
正確には、四葉の潜む車両……その周囲500m圏内の俯瞰図。
端末の画面には、地図があった。
正確には、四葉の潜む車両……その周囲500m圏内の俯瞰図。
生体ではないアキカンに対し、自動兵器のロック機構は働かないだろうか?
――否。高島平四葉を除いた『アキカンの大きさ以上』の目標物。
その全てを自動で殲滅し尽くす、という指示を、四葉は下す事ができる。
――否。高島平四葉を除いた『アキカンの大きさ以上』の目標物。
その全てを自動で殲滅し尽くす、という指示を、四葉は下す事ができる。
「それがあなたの最後」
黒雲。指令を下した瞬間、数千機のUAVが動く。
『モア』に無駄弾など存在しない。
弾薬程度は、いくらでも――兵器ごと、“少しだけ強く”増産が効く。
『モア』に無駄弾など存在しない。
弾薬程度は、いくらでも――兵器ごと、“少しだけ強く”増産が効く。
――日本政府所有、極秘の保管施設。
ここに収められた魔人関連の押収品はその全てが特A級以上の危険物であるが、
そこに6年前から部屋ごと閉ざされた、『赤い倉庫』なる保管室が存在する。
ここに収められた魔人関連の押収品はその全てが特A級以上の危険物であるが、
そこに6年前から部屋ごと閉ざされた、『赤い倉庫』なる保管室が存在する。
「……クリア! 進め!」
フルフェイスヘルメットで顔を覆った、完全武装の特殊部隊が階段を駆け下りる。
施設は戦争の混乱で真っ先に奇襲を受け、職員は全て肉塊に変わっている。
襲撃者は近代兵器で武装を固めており――魔人ですらない。
施設は戦争の混乱で真っ先に奇襲を受け、職員は全て肉塊に変わっている。
襲撃者は近代兵器で武装を固めており――魔人ですらない。
「目標“スカーレット”。この部屋で間違いありません」
「了解……いいか! 確保の際には十分に注意しろ!
爆発物の取り扱いよりも危険な仕事と考えろ! 突入!」
「了解……いいか! 確保の際には十分に注意しろ!
爆発物の取り扱いよりも危険な仕事と考えろ! 突入!」
顔立ちこそ日本人であるが、彼らは日本人ではなかった。少なくともその精神は。
日本国内に浸透した米軍特殊工作部隊。
彼らは潜入に特化した人材であり、戦闘の練度自体は軍人にやや劣る。
だがこのような好機にあって、真っ先に動くことを期待される部隊であった。
日本国内に浸透した米軍特殊工作部隊。
彼らは潜入に特化した人材であり、戦闘の練度自体は軍人にやや劣る。
だがこのような好機にあって、真っ先に動くことを期待される部隊であった。
――オペレーション・ファントムルージュ。
それは日本政府の暗部たる『あの映画』の入手である。
今後の日本との外交において、核よりも有効足り得る交渉カード。
だが……
それは日本政府の暗部たる『あの映画』の入手である。
今後の日本との外交において、核よりも有効足り得る交渉カード。
だが……
「……真の滅びを、知っているか?」
突入者の足が止まった。
『赤い倉庫』の中には、既に一人の男が存在したのだ。
突入者の足が止まった。
『赤い倉庫』の中には、既に一人の男が存在したのだ。
「ファントムルージュ原典の捜索。
俺が取り憑かれてから……それは最初にやった事だ。お前らより先に」
落ち窪んだ眼光。不健康な肌。だが、鋭さを秘めた肉体。
薄汚れたコートが扉からの風に揺れる。
俺が取り憑かれてから……それは最初にやった事だ。お前らより先に」
落ち窪んだ眼光。不健康な肌。だが、鋭さを秘めた肉体。
薄汚れたコートが扉からの風に揺れる。
「原典の保管箇所は、全て把握している。
俺が真っ先に動いた。お前らより先に」
俺が真っ先に動いた。お前らより先に」
狂った男の言葉に応える声はなかった。
彼らは訓練された動きで一斉にライフルの引き金を引き、
寸前、その全てが拳ごと切り飛ばされた。
彼らは訓練された動きで一斉にライフルの引き金を引き、
寸前、その全てが拳ごと切り飛ばされた。
「ぐっ、うがっ……!?」
「……」
苦悶する隊長を虚ろに見下ろして、男は淡々と言葉を続ける。
「痛そうだな」
「……」
苦悶する隊長を虚ろに見下ろして、男は淡々と言葉を続ける。
「痛そうだな」
「どうしてこんな俺が、簡単に軍事施設に侵入できたのか……
……今、不思議に思ったか?
仮にそうなら、教えてやらないでもないが」
……今、不思議に思ったか?
仮にそうなら、教えてやらないでもないが」
男――元魔人公安、偽原光義は、タバコに火を点けた。
室内とは思えぬほど湿気った空気の中、煙がゆらゆらと揺れた。
隊長の背後では隊員が一人、胸を貫かれて死んでいた。
室内とは思えぬほど湿気った空気の中、煙がゆらゆらと揺れた。
隊長の背後では隊員が一人、胸を貫かれて死んでいた。
「今は救済期間中でな。
正直言って、もう同じような展開はうんざりだ。つまり」
正直言って、もう同じような展開はうんざりだ。つまり」
背後に気配を感じた隊長が、その主を目撃することはなかった。
幻影は不可視のまま、武傘の質量で防具ごと頭蓋を砕き、
飛散する紅で『赤い倉庫』の室内を文字通り赤く染めた。
幻影は不可視のまま、武傘の質量で防具ごと頭蓋を砕き、
飛散する紅で『赤い倉庫』の室内を文字通り赤く染めた。
「災厄を『繰り返し』はさせない……
善意の協力者がいたって事さ」
善意の協力者がいたって事さ」
霧の中から姿を現した『共犯者』が偽原の言葉を続ける。
雨竜院雨弓は、凶悪な矛先を残りの隊員へと向けた。
雨竜院雨弓は、凶悪な矛先を残りの隊員へと向けた。
「……わたしのたすけを?」
暗い坑道の下。声に答えながらも、聖槍院九鈴は、
ただただロボットのごとく、東京駅地下に巣食う甲殻類の『掃除』を続けていた。
暗い坑道の下。声に答えながらも、聖槍院九鈴は、
ただただロボットのごとく、東京駅地下に巣食う甲殻類の『掃除』を続けていた。
声の主の姿はない。
それは、その場に姿を現さずとも運営アナウンスを執り行う事のできる能力――
数多持つ佐倉光素の力のひとつであるが、
それはただ『伝える』だけで、返答を聞くことまではできない性質のものだ。
それは、その場に姿を現さずとも運営アナウンスを執り行う事のできる能力――
数多持つ佐倉光素の力のひとつであるが、
それはただ『伝える』だけで、返答を聞くことまではできない性質のものだ。
《赤羽ハル選手の『副賞』の内容は、今お伝えしたとおりです。
俄には信じられない話かもしれません。
けれど……世界は、変わるかもしれないのです》
「……」
俄には信じられない話かもしれません。
けれど……世界は、変わるかもしれないのです》
「……」
《関西崩壊。核攻撃。ファントムルージュ。……そして新黒死病。
この世界が変わってしまったのは、私達魔人達のせいなのでしょう。
ならば、それを取り戻すこともできる道理ではありませんか。
……助けをください。失ったものを取り戻す、その助けを》
姿無き声はそれで終わった。
この世界が変わってしまったのは、私達魔人達のせいなのでしょう。
ならば、それを取り戻すこともできる道理ではありませんか。
……助けをください。失ったものを取り戻す、その助けを》
姿無き声はそれで終わった。
「わたしのせいだ」
トングで甲殻類を取りのけながら、彼女は掠れた声で言った。
「わたしが、やった……。だから掃除をしないと。
何もかわらない……ゴミをそうじする。
全部ぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶ――」
トングで甲殻類を取りのけながら、彼女は掠れた声で言った。
「わたしが、やった……。だから掃除をしないと。
何もかわらない……ゴミをそうじする。
全部ぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶ――」
佐倉光素が助力を乞うまでもなかった。
彼女はずっと、その戦いを孤独に続けてきたのだから。
敗者の時代の残骸が赤羽ハルだとするのならば、
聖槍院九鈴は勝者の時代の犠牲者であった。
彼女はずっと、その戦いを孤独に続けてきたのだから。
敗者の時代の残骸が赤羽ハルだとするのならば、
聖槍院九鈴は勝者の時代の犠牲者であった。
『ザ・キングオブトワイライト』。
聖槍院九鈴が求めたのは、栄光ではなく贖罪である。
聖槍院九鈴が求めたのは、栄光ではなく贖罪である。
東京駅の地下が揺れた。
贖罪の使者が今動き出す。
贖罪の使者が今動き出す。
「あのさぁ~、依頼を受けるのはいいけど、これじゃあ3件目なんだよねぇ~」
「条件に関しては不問と先方からは承ってってッうおおおおあ!?
危ねえ! 一発抜けてきたぞ今!」
「条件に関しては不問と先方からは承ってってッうおおおおあ!?
危ねえ! 一発抜けてきたぞ今!」
咄嗟の『堅い言葉』で作り出した『ロジカルエッジ』の盾(これも立派な武器だ)
を投げ捨てた後、内亜柄影法は回廊の角に飛び込むように身を隠した。
やや反応がゆっくりなこまねの襟首を掴んで引っ張りこむのも忘れない。
を投げ捨てた後、内亜柄影法は回廊の角に飛び込むように身を隠した。
やや反応がゆっくりなこまねの襟首を掴んで引っ張りこむのも忘れない。
「……ッ、とにかく! 佐倉光素だったか? あいつから頼まれたんだよ!
なんでも優勝者のヤロウの副賞がそうだって……ヤべッ!
くそ、隠れるところ変えたほうが良くないか……」
「でも~、戦争を仕掛けた連中を探れって言っても、
それって強制力があるわけじゃあないんじゃないかい~?
あたしが相手方と通じて裏切るかも……?」
なんでも優勝者のヤロウの副賞がそうだって……ヤべッ!
くそ、隠れるところ変えたほうが良くないか……」
「でも~、戦争を仕掛けた連中を探れって言っても、
それって強制力があるわけじゃあないんじゃないかい~?
あたしが相手方と通じて裏切るかも……?」
魔人と言えども、銃で撃たれれば死ぬ。……にも関わらず、
人間達に襲撃されるこまねのテンションは平常そのものだ。
元からの性質か、恐るべき災禍を経験したが故の豪胆かは計り知れないが。
人間達に襲撃されるこまねのテンションは平常そのものだ。
元からの性質か、恐るべき災禍を経験したが故の豪胆かは計り知れないが。
「そりゃそうだ! こんな状況で契約とかルールを守るバカがいるわけがない。
それを信じてるバカが居るとしたら、相当のバカだ。
でもできるのはお前しかいないと思ったし、あと偶然近くにいたんだ!」
「…………」
偽名探偵は少しだけ空を見上げて思案する、振りをした。
それを信じてるバカが居るとしたら、相当のバカだ。
でもできるのはお前しかいないと思ったし、あと偶然近くにいたんだ!」
「…………」
偽名探偵は少しだけ空を見上げて思案する、振りをした。
「ま、いいよ~。
それにこの件なら、協力してくれんのはあたしだけじゃないと思うしね~~」
「うわ、軽々しく受けやがって……知らねえぞ」
それにこの件なら、協力してくれんのはあたしだけじゃないと思うしね~~」
「うわ、軽々しく受けやがって……知らねえぞ」
内亜柄影法は廊下の突き当りの窓を見る。4階。
こまねを抱えて飛び降りて、無事でいられるか。
こまねを抱えて飛び降りて、無事でいられるか。
「忘れてるかもしれないけど、俺は検事だからな。
口約束だろうが、そういう約束は――」
口約束だろうが、そういう約束は――」
銃を手にした魔人狩りの追手も追いついてくる。
だが彼らの視点からは、内亜柄の後ろ手に回した指先は見えない。
だが彼らの視点からは、内亜柄の後ろ手に回した指先は見えない。
「破らせねえぞ……ッと!!」
具現化したそれは指先のスナップと共に凄まじい勢いで射出されて、
襲撃者達の足に文字通り『釘を刺し』た。
襲撃者達の足に文字通り『釘を刺し』た。
「ハァーッ、ハァーッ!」
会議室に辿り着いた田村草介は、恐怖に息を荒げながら座り込んだ。
……昔から、自分はそうだった。
魔人が怖い。
……関東に、核を落とした魔人が。
死の疫病を蔓延させた魔人が。
一人息子と妻……家族を奪った魔人が。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
だが、自分がまさかこんな事をしでかしてしまうとは!
……昔から、自分はそうだった。
魔人が怖い。
……関東に、核を落とした魔人が。
死の疫病を蔓延させた魔人が。
一人息子と妻……家族を奪った魔人が。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
だが、自分がまさかこんな事をしでかしてしまうとは!
「どうして……どうしてこんな事に……!」
魔人相手の戦争。未だに他人事のようだ。
しかし、目高機関――日本統括部部長、田村草介にとって。
実のところ、それは全く他人事ではないのだった。
魔人相手の戦争。未だに他人事のようだ。
しかし、目高機関――日本統括部部長、田村草介にとって。
実のところ、それは全く他人事ではないのだった。
(魔人能力の独占。新たなビジネス。一般魔人排斥の動きは元から存在した。
会議を誘導して、議論をそちらに傾けるまでもなかった……
軍需による利益! 魔人の排斥……長期的治安の向上!
だが……だが、本当にこれは? 私がやったのか?)
会議を誘導して、議論をそちらに傾けるまでもなかった……
軍需による利益! 魔人の排斥……長期的治安の向上!
だが……だが、本当にこれは? 私がやったのか?)
田村草介はどこにでもいる平凡な男性であった。
地位や名誉を求めたことはない。
単に少しばかり、自分の生活を守るために必死なだけだ。
地位や名誉を求めたことはない。
単に少しばかり、自分の生活を守るために必死なだけだ。
そして田村には時にそれを『やりすぎる』癖があった。
保身の勢いのあまり、身の丈に合わぬプロジェクトを推進してしまう。
それが幸運にも成果を挙げてしまう。その繰り返しだ。
繰り返しの果てに……このポジションにいる。
保身の勢いのあまり、身の丈に合わぬプロジェクトを推進してしまう。
それが幸運にも成果を挙げてしまう。その繰り返しだ。
繰り返しの果てに……このポジションにいる。
時計を何度も確認しながら、自身のノートPCを開いて報告を確認する。
(目高機関。上層部からは何も言ってこない。
戦争開始の動きにも、干渉は一切なかった。
この極東の辺境がどう潰れたところで、影響のない……安全な連中ばかりだ)
戦争開始の動きにも、干渉は一切なかった。
この極東の辺境がどう潰れたところで、影響のない……安全な連中ばかりだ)
……つまり、この件は完全に田村の責任でしかなかった。
彼の感情が、その事実を拒絶していたとしても。
彼の感情が、その事実を拒絶していたとしても。
(……『安全』。そうだ! ここもまだ安全ではない!
利用されたトーナメントの魔人が動く。盤石の手を打つ必要がある。
こちらも……手持ちの駒を1つ……いや2つ……!)
利用されたトーナメントの魔人が動く。盤石の手を打つ必要がある。
こちらも……手持ちの駒を1つ……いや2つ……!)
会議室に現れ、席に腰を下ろしてから20秒。
複雑な勢力の絡みあう情勢の中、
彼は『自分に危害の及び得る』事案を一瞬で取捨選択する。
複雑な勢力の絡みあう情勢の中、
彼は『自分に危害の及び得る』事案を一瞬で取捨選択する。
魔人の存在そのものすらをも過大な『リスク』として見做す。
どのような小さな可能性でも、その“おそれ”を見抜く能力。
どのような小さな可能性でも、その“おそれ”を見抜く能力。
その恐怖心こそが、彼をここまでのし上げてきた能力であった。
「……高島平四葉。仮に俺が本来の体だったとしたら……。
それがこのオーウェン・ハワードだとしても。
MBT相手に100m圏内まで生身で近づくなんて、自殺行為以外の何物でもないメカ。
すぐさま検知されて、消し炭になっていたはずメカ」
それがこのオーウェン・ハワードだとしても。
MBT相手に100m圏内まで生身で近づくなんて、自殺行為以外の何物でもないメカ。
すぐさま検知されて、消し炭になっていたはずメカ」
「しかしアキカンのような小型オブジェクトに対してすらも、
お前は徹底殲滅という有効な攻撃手段を所有していたメカ。
通常は考え得ない戦術、故にお前はそれを仕掛けてくる……と読んでいたメカ」
お前は徹底殲滅という有効な攻撃手段を所有していたメカ。
通常は考え得ない戦術、故にお前はそれを仕掛けてくる……と読んでいたメカ」
ひとつの建物の瓦礫の下から、ヒョコ、という擬音と共にアキカンが顔を出した。
無敵の城塞に立てこもった、世界最悪の魔人……を、彼は打倒していた。
無敵の城塞に立てこもった、世界最悪の魔人……を、彼は打倒していた。
「……アキカンの体も、悪いことばかりではないメカね」
《い……いつから、わたし……微妙に汚れキャラ、に……》
「排泄の度にその痛みを思い出すメカ」
「排泄の度にその痛みを思い出すメカ」
無線から漏れ聞こえる苦悶の呻きは、高島平四葉だ。
オーウェン・ハワードの『アキカン招来』。
半径100m以内、『空間』が存在する座標にアキカンを召喚する魔人能力である。
四葉の呻きはアキカンを体のとある箇所にねじ込まれたが故の戦闘不能であるが、
箇所の明記は良識上避ける。
オーウェン・ハワードの『アキカン招来』。
半径100m以内、『空間』が存在する座標にアキカンを召喚する魔人能力である。
四葉の呻きはアキカンを体のとある箇所にねじ込まれたが故の戦闘不能であるが、
箇所の明記は良識上避ける。
「作戦完了。もう帰投して構わないメカ」
《……随分あっさりしたもんっすね。
あの高島平四葉ですよ。1秒遅れていたら、2人共々消し炭だ》
《……随分あっさりしたもんっすね。
あの高島平四葉ですよ。1秒遅れていたら、2人共々消し炭だ》
「ふん。俺が君の能力を運用する以上、当然の結果、メカ。
もっとも……君の狙撃で注意を引き。
そして殲滅攻撃を誘導することで、
一時的にも奴の『座標を止める』必要はあったメカが」
もっとも……君の狙撃で注意を引き。
そして殲滅攻撃を誘導することで、
一時的にも奴の『座標を止める』必要はあったメカが」
無線の相手は、オーウェン・ハワードの位置から彼方300m――
ビル最上階で狙撃姿勢を取っていた。
巨大なアンチマテリアルライフル。
足元に転がる薬莢の巨大さが、威力の凄まじさを物語る。
ビル最上階で狙撃姿勢を取っていた。
巨大なアンチマテリアルライフル。
足元に転がる薬莢の巨大さが、威力の凄まじさを物語る。
狙撃者の名を、山田、という。
《こんなゴツい銃を使っても傷ひとつつかない……が、
スコープ越しでも、俺の『目ッケ!(アイスパイ!アイ)』は有効だ。
相手のケツの穴まで、座標は正確に伝えられる》
「……うむ」
――比喩ではないのだ。
スコープ越しでも、俺の『目ッケ!(アイスパイ!アイ)』は有効だ。
相手のケツの穴まで、座標は正確に伝えられる》
「……うむ」
――比喩ではないのだ。
(ともかく、これで俺も“スカーレット”の奪取に全力を傾けられる……
後は、本国からの指示メカ……
…………………?)
後は、本国からの指示メカ……
…………………?)
《どうしました? 何かマズイことでも?》
「フッ、山田君。君は目敏いメカね。
……少々、マズイことになったメカ。……君達、日本人にとって」
《はい?》
「動き出したメカよ」
「フッ、山田君。君は目敏いメカね。
……少々、マズイことになったメカ。……君達、日本人にとって」
《はい?》
「動き出したメカよ」
目高機関。正解最強のアメリカ軍が、いまだ軍備を増強し続けねばならぬ理由。
あのソ連をも凌ぐ、戦後最悪の『仮想敵』。
あのソ連をも凌ぐ、戦後最悪の『仮想敵』。
「……本当の『世界の敵』が」
「ルールの境目というものを知っているか、赤羽」
「……ルールだと?」
「……ルールだと?」
高速道路、高架上。同じトラックの荷台に降り立った数秒、両者は会話した。
吹き付ける風にも、赤羽は指に挟んだ紙幣を手放すことはない。
吹き付ける風にも、赤羽は指に挟んだ紙幣を手放すことはない。
「守るか破るか。俺のルールはそれだけだ」
「そうではない」
「そうではない」
2人は同時に跳躍した。ジープからの機銃が、荷台を破壊しながら舐めた。
だがトラックが炎上するその瞬間、3枚の10円玉が防弾ガラスにヒビを入れる。
ヒビを突き割って車内へと飛び込んだ鋼鉄の義足が、運転手の肋骨を砕いた。
だがトラックが炎上するその瞬間、3枚の10円玉が防弾ガラスにヒビを入れる。
ヒビを突き割って車内へと飛び込んだ鋼鉄の義足が、運転手の肋骨を砕いた。
冷泉院拾翠の体が宙にある間――人外の膂力を発揮する、
それが『仮面の力』。
それが『仮面の力』。
「世界にはルールがある。この世界であれば……
『疫病が蔓延する終末』『魔人のトーナメント』。それがルールだ。
平行世界の存在を信じるか?」
至近距離から放たれた射手の弾丸は、それよりも先に冷泉院の手の中にあった。
そのまま額を打ち据え、昏倒させる。
『疫病が蔓延する終末』『魔人のトーナメント』。それがルールだ。
平行世界の存在を信じるか?」
至近距離から放たれた射手の弾丸は、それよりも先に冷泉院の手の中にあった。
そのまま額を打ち据え、昏倒させる。
「訳がわからねぇな! 暗殺者に哲学を説くか?」
車両一つ分離れていては、叫ぶようにして会話する他ない。
が、静かに話す冷泉院の声は不思議と赤羽の距離まで届いた。
「冷泉は平行世界が『ある』と考えている。
――『悲しいねえ』『そんなに俺の相手が嫌かい?』」
車両一つ分離れていては、叫ぶようにして会話する他ない。
が、静かに話す冷泉院の声は不思議と赤羽の距離まで届いた。
「冷泉は平行世界が『ある』と考えている。
――『悲しいねえ』『そんなに俺の相手が嫌かい?』」
「……?」
「覚えがないか? 俺はそれを、覚えている。
黄樺地セニオが勝利したその時、紛れもなくその言葉を口にしたはずだ。
そして現にその世界が『選択されている』以上は、
2つの事実を説明しうる『平行世界』は、この世界のルールに存在するのだ」
黄樺地セニオが勝利したその時、紛れもなくその言葉を口にしたはずだ。
そして現にその世界が『選択されている』以上は、
2つの事実を説明しうる『平行世界』は、この世界のルールに存在するのだ」
「……どういうことだ!!」
運転手が意識を失い、ジープは減速しつつあった。
赤羽の取りついた車との距離は、少しずつ離れていく。
運転手が意識を失い、ジープは減速しつつあった。
赤羽の取りついた車との距離は、少しずつ離れていく。
「………………。
、 、
……幸福な結末! 理不尽なき『平行世界』はある、という事だ!
行け赤羽ハル! その結末を信ずるからこそ俺達は、副賞を!
佐倉光素の頼みを受けたのだ!」
、 、
……幸福な結末! 理不尽なき『平行世界』はある、という事だ!
行け赤羽ハル! その結末を信ずるからこそ俺達は、副賞を!
佐倉光素の頼みを受けたのだ!」
赤羽は何かを言い返そうとした。
だが冷泉院は既に彼方にいて、言葉の届く距離ではなかった。
だが冷泉院は既に彼方にいて、言葉の届く距離ではなかった。
トラックは合流地点へと向かう。
赤羽の望む情報が待つ、その地へと。
赤羽の望む情報が待つ、その地へと。
「ふふふふふふ……」
路地裏。長髪の男の含み笑いとともに、数人の男女が絶叫する。
倒れ伏すその表情には一様に絶望と羞恥の背徳が浮かび、
何やらただならぬ精神攻撃を伺わせた。
倒れ伏すその表情には一様に絶望と羞恥の背徳が浮かび、
何やらただならぬ精神攻撃を伺わせた。
「ぐふふふ……ふふふ、すっごいぜ、すっごい……!
街は無法地帯……つまり、僕のオカズも集め放題……!
さあさあ次は、どんな悪夢(ユメ)を見せに行こうか……
……ぐふふ、ふふ……」
街は無法地帯……つまり、僕のオカズも集め放題……!
さあさあ次は、どんな悪夢(ユメ)を見せに行こうか……
……ぐふふ、ふふ……」
スキップととともに路地裏から現れた男の名は、肥溜野森長。
その魔人能力『千年悪夢』による悪堕ちの幻影を何よりのオカズとするという、
弁解不能の非道悪虐魔人である。
その魔人能力『千年悪夢』による悪堕ちの幻影を何よりのオカズとするという、
弁解不能の非道悪虐魔人である。
彼はザ・キングオブトワイライトでの敗北を全く意に介さぬどころか、
それを引き金として発生した血で血を洗うこの無法状態すらも、
『これで合法的に悪堕ちし放題』としか認識せぬ、筋金入りの変態であった……
それを引き金として発生した血で血を洗うこの無法状態すらも、
『これで合法的に悪堕ちし放題』としか認識せぬ、筋金入りの変態であった……
「次のターゲットは……ぐふふ、ちょうどいいところに可愛い男のコ発見!
さあさあ僕の力で悪に堕グハァッ!!」
さあさあ僕の力で悪に堕グハァッ!!」
即座に顎を砕いたのは、ターゲットの手元から飛来した鎖分銅である。
少年――鎌瀬戌は、ヒュンヒュンと分銅を軽く回して、ローブの中へ収めた。
鎖鎌の鎌の側を使わなかったのは、せめてもの慈悲だ。
少年――鎌瀬戌は、ヒュンヒュンと分銅を軽く回して、ローブの中へ収めた。
鎖鎌の鎌の側を使わなかったのは、せめてもの慈悲だ。
「……クソッ、どうなってんだ!
この騒ぎで人間だけじゃあなく魔人までおかしくなってやがる……」
「こいつは元からおかしかったんじゃあないか」
「なおさら悪いだろ!」
この騒ぎで人間だけじゃあなく魔人までおかしくなってやがる……」
「こいつは元からおかしかったんじゃあないか」
「なおさら悪いだろ!」
隣に立つ筋肉質の青年――不動大尊を見上げ、鎌瀬は苛立たしげに言う。
「どっちにせよ、皆を守らなきゃあいけないのは同じだ。
俺の家族なんだぞ……! ここの孤児院の皆は!」
「ふん。とりあえず手の届く人間を守るか。いい動機だな。お前、魔人能力は?」
「どっちにせよ、皆を守らなきゃあいけないのは同じだ。
俺の家族なんだぞ……! ここの孤児院の皆は!」
「ふん。とりあえず手の届く人間を守るか。いい動機だな。お前、魔人能力は?」
「……。『ヒトヒニヒトカミ』……
俺のいる場所に雷を落とすやつで……あと一日一回しか使えないし……
さっき使ったからもう使えない! わ、悪いかよ!」
「俺は『ネッツ・エクスパンド』。カップに入れた紅茶の温度を1600℃にする。
温度は高くも低くもなく……1600℃だ。あとカップに入れないとダメだ」
俺のいる場所に雷を落とすやつで……あと一日一回しか使えないし……
さっき使ったからもう使えない! わ、悪いかよ!」
「俺は『ネッツ・エクスパンド』。カップに入れた紅茶の温度を1600℃にする。
温度は高くも低くもなく……1600℃だ。あとカップに入れないとダメだ」
「……」
「……」
「……」
顔を見合わせる2人を、不意に強烈な光が照らした。
一瞬目が眩みつつも、不動のボクサー級の視力は、それを認識した。
一瞬目が眩みつつも、不動のボクサー級の視力は、それを認識した。
「……運営本部のビルか?」
「こんな距離まで? 何か……魔人能力かな」
「どちらにせよ……」
「こんな距離まで? 何か……魔人能力かな」
「どちらにせよ……」
不動は歩き出した。路地の先で、魔人の少女が人間に追われている。
人間を警棒で必要以上に叩きのめす魔人警官の姿もある。
夕陽が異様なほど濃い影を作って、街の半分を黒く覆っている。
人間を警棒で必要以上に叩きのめす魔人警官の姿もある。
夕陽が異様なほど濃い影を作って、街の半分を黒く覆っている。
「やれる事をやるしかないさ。誰もがな」
「ったく、どいつもこいつも……!」
「ったく、どいつもこいつも……!」
「目的、は?」
待ち構えていたのは、10歳ほどの少年だった。
運営本部最上階。暴徒の突入でスタッフが逃げ出したドサクサを狙ったものの、
強行突入した以上は妨害者の存在を考慮してしかるべきだ。
彼も当然そのつもりだった。ただ、上手い返し文句を考えていなかっただけだ。
運営本部最上階。暴徒の突入でスタッフが逃げ出したドサクサを狙ったものの、
強行突入した以上は妨害者の存在を考慮してしかるべきだ。
彼も当然そのつもりだった。ただ、上手い返し文句を考えていなかっただけだ。
「……あのな坊や。怪我したくなかったらそこから逃げるんだぞ。
俺の得意技を教えてやろうか? 子供でも容赦なく殴れる事だ」
『それは君の人格が腐っているだけだ』
「とに、かく! パパとママのところへ帰れ!
こういうところにいるガキとかマジで……嫌な予感しかしないんだよ!
やっぱあの七葉樹ちゃんに騙されたんじゃないですか俺ら!?
どうすればいいですかね!?」
『脳の外科処理を勧める。その落ち着きの無さを即刻改善すべきだな』
俺の得意技を教えてやろうか? 子供でも容赦なく殴れる事だ」
『それは君の人格が腐っているだけだ』
「とに、かく! パパとママのところへ帰れ!
こういうところにいるガキとかマジで……嫌な予感しかしないんだよ!
やっぱあの七葉樹ちゃんに騙されたんじゃないですか俺ら!?
どうすればいいですかね!?」
『脳の外科処理を勧める。その落ち着きの無さを即刻改善すべきだな』
「どこかにもう一人いるのかな? ……と思ったら、それですか。
――その本。そうだ、結論が出ました。
大会参加選手の一人。相川ユキオ」
――その本。そうだ、結論が出ました。
大会参加選手の一人。相川ユキオ」
目高機関の尖兵。他者の言葉を借りて語る『少年』。
日本統括部部長、田村草介の最強の駒に、名前は存在しない。
日本統括部部長、田村草介の最強の駒に、名前は存在しない。
だが。
「……『もう一人』? ノートン先生。なんで……なんで、あいつ」
『落ち着け、と私は命じている』
『落ち着け、と私は命じている』
相川ユキオは、震える声で言った。
ふとした言葉だったが。それはあり得ない筈の現象だった。
「なんであいつ、ノートン先生の声が聞こえるんですかね……」
『落ち着くのだ。私の物語を汚すな』
ふとした言葉だったが。それはあり得ない筈の現象だった。
「なんであいつ、ノートン先生の声が聞こえるんですかね……」
『落ち着くのだ。私の物語を汚すな』
『――君は今、ついに最大の武勲を挙げる機会を得たのだ。
このサー・ノートン・バレイハートの英雄譚の最も輝かしい1ページ!
そこに居合わせる名誉を得る確率ときたら』
「じょっ! 冗談は! やめてくださいよ!」
このサー・ノートン・バレイハートの英雄譚の最も輝かしい1ページ!
そこに居合わせる名誉を得る確率ときたら』
「じょっ! 冗談は! やめてくださいよ!」
【それが君の編集者か?】
少年の口調が変化した。まるで別人が喋らせているかのように。
そしてそれと被さる何者かの声も、同類の編集者である相川ユキオの脳には――
はっきりと、聞こえているのだ。
そしてそれと被さる何者かの声も、同類の編集者である相川ユキオの脳には――
はっきりと、聞こえているのだ。
【喜劇の主役でも張れそうな無能の案山子。
折角ならば遊んでやろうと、わざわざ出向いたというのにこの様だ。
……眠りすぎて編集者の完全支配すらもできなくなったか】
折角ならば遊んでやろうと、わざわざ出向いたというのにこの様だ。
……眠りすぎて編集者の完全支配すらもできなくなったか】
誰もがその形態を想像し得ないだろう。小さな手帳だった。
パラパラとめくれてゆく、全てのページが黒だった。
そしてその黒の全ては、狂気的な程細密に書き込まれた……
呪詛と冒涜の文章の集積である。
パラパラとめくれてゆく、全てのページが黒だった。
そしてその黒の全ては、狂気的な程細密に書き込まれた……
呪詛と冒涜の文章の集積である。
人類の刻んできた長い歴史の中で。
『ミルキーレディ』や『ファントムルージュ』に匹敵する悲劇は、
現代に至るまでただ一度とて起こらなかったのだろうか?
それを意図的に引き起こそうと試みる悪意は存在しなかったのだろうか?
『ミルキーレディ』や『ファントムルージュ』に匹敵する悲劇は、
現代に至るまでただ一度とて起こらなかったのだろうか?
それを意図的に引き起こそうと試みる悪意は存在しなかったのだろうか?
――名も無きそれは、人類の疑問への回答であった。
“携帯する神殿”。魔導書に使役される、意志なき編集者《天使》。
“携帯する神殿”。魔導書に使役される、意志なき編集者《天使》。
……殺戮文書。『オレイン卿』。
――――
“少年”
魔人能力名:殺戮文書『オレイン卿』
――絶望で所有者を支配し、自己の意志で自己を編集する。携帯する神殿。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/35.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/79.html
魔人能力名:殺戮文書『オレイン卿』
――絶望で所有者を支配し、自己の意志で自己を編集する。携帯する神殿。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/35.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/79.html
――――
「防、御……!」
影の《壁》は一瞬でかき消された。
相川ユキオは自分の心臓を貫く光の《槍》を見た。
編集力の差は圧倒的に過ぎた。
相川ユキオは自分の心臓を貫く光の《槍》を見た。
編集力の差は圧倒的に過ぎた。
【鈍い。死ね】
光は影を打ち消す。
他の魔導書を冒涜するためだけに記された殺戮文書。
それが“携帯する神殿”。
他の魔導書を冒涜するためだけに記された殺戮文書。
それが“携帯する神殿”。
「……まさか、アナタが裏切るとはね……
……………。
……って、言っちゃっていいのかしら?」
……………。
……って、言っちゃっていいのかしら?」
―― 一方、運営本部最深部。もう一つの戦いが幕を開けていた。
巨大なアフロヘアーのオカマは、バロネス夜渡……こと千歯車炒二。
大仰にファイティングポーズを取る彼とは対照的に、
その横に佇む男――森田一郎は、静かな敵意で銘刈耀を睨んでいる。
大仰にファイティングポーズを取る彼とは対照的に、
その横に佇む男――森田一郎は、静かな敵意で銘刈耀を睨んでいる。
「『まさか』? 予想はしていらしたのでしょう。
七葉樹落葉が何を命じたのかは与り知らぬことですが。
……もはや、トーナメントに関する権限はあなた方にはありません」
七葉樹落葉が何を命じたのかは与り知らぬことですが。
……もはや、トーナメントに関する権限はあなた方にはありません」
――――
――――
「そうして主催者に責任を押し付け、瀕死の日本を戦争経済で吸いつくし。
自分は機関本部へと高飛びか」
森田一郎は一歩を踏み出す。
「大した計画だ。結末の成否を見せてくれる」
自分は機関本部へと高飛びか」
森田一郎は一歩を踏み出す。
「大した計画だ。結末の成否を見せてくれる」
その一挙一動が隣の千歯車すら竦むほどの殺意に満ちており、
当然、銘刈耀の力では刹那の一撃には耐えられぬ――と、見えた。
当然、銘刈耀の力では刹那の一撃には耐えられぬ――と、見えた。
だが、抉りこまれた正拳はパン、という破裂音と共に止まった。
目視不能な速度での割り込み。
拳を受けた腕をゆっくりと引き戻しながら、その存在が嗤う。
目視不能な速度での割り込み。
拳を受けた腕をゆっくりと引き戻しながら、その存在が嗤う。
「俺は裏切っていない。
そうだろう? ――森田一郎」
そうだろう? ――森田一郎」
「ああ、そうだ」
森田は無表情に答える。
銘刈耀の魔人能力。『偶像崇拝(アイドルマスター)』。
確かに奴には優れた才能がある。
魔人能力という『才能』を抜きにしたとしても、スカウトの条件を満たす。
森田は無表情に答える。
銘刈耀の魔人能力。『偶像崇拝(アイドルマスター)』。
確かに奴には優れた才能がある。
魔人能力という『才能』を抜きにしたとしても、スカウトの条件を満たす。
だが勧誘するまでもなく……奴はそちらにつくだろう。
「お前は、元より“味方”などではないからだ――儒楽第」
拳が唸った。千歯車は吠え、無数のナイフを投擲した。
儒楽第は、やはり嗤った。
儒楽第は、やはり嗤った。
「この体が覚えたぞ、森田一郎。
……てめぇの拳を」
……てめぇの拳を」
一度受けた攻撃を、二度目から防ぐ能力。
――『攻性変色<カメレオン・オーラ>』。
――『攻性変色<カメレオン・オーラ>』。
――そして、もう一人の『世界の敵』。
戦禍に沈む世界の中……
眠りについた筈の悪意が、呼応するかのように覚醒した。
眠りについた筈の悪意が、呼応するかのように覚醒した。
「というわけでこの私、パパテリアことカイエン・ゾルテリアも!
世界の敵(ワールドエネミー)として参戦することになりましたー!」
世界の敵(ワールドエネミー)として参戦することになりましたー!」
「なんでじゃああああああ!?
父さん、オナネタ手に入れて満足したって書いてあったでしょうよ!」
父さん、オナネタ手に入れて満足したって書いてあったでしょうよ!」
「いやー、そこんとこ正直に目高機関に正直に話したら、
そんなの目じゃないオナネタやるから日本滅ぼしてって言われたからのお。
一度引いたと見せかけて目的のブツを引き出す!
これがワールドエネミー級交渉術よぉ~~~っ!」
「やっぱめでたくなかったわ! 最低だこのクズ!」
そんなの目じゃないオナネタやるから日本滅ぼしてって言われたからのお。
一度引いたと見せかけて目的のブツを引き出す!
これがワールドエネミー級交渉術よぉ~~~っ!」
「やっぱめでたくなかったわ! 最低だこのクズ!」
なお、こちらも大会本部の程近く、
結局使用されなかった円形闘技場での出来事である。
結局使用されなかった円形闘技場での出来事である。
「さあ来い娘よ!
わたしは実は一回イカされただけで死ぬぞオオ!」
「くっ倒す方法がわかっていてもやりたくない恐ろしさ」
わたしは実は一回イカされただけで死ぬぞオオ!」
「くっ倒す方法がわかっていてもやりたくない恐ろしさ」
――――
カイエン・ゾルテリア
魔人能力名:『ZTM(絶対にチンコなんかに負けない)』
――性属性以外のあらゆる攻撃を無効化する。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/27.html
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/39801/1365175524/117-118
魔人能力名:『ZTM(絶対にチンコなんかに負けない)』
――性属性以外のあらゆる攻撃を無効化する。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/27.html
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/39801/1365175524/117-118
――――
「カイエン・ゾルテリア……許せない……!
祖国の、仇……!!」
ちなみにゾルテリア娘の横で涙を浮かべて剣を構えるのは姫将軍ハレルである。
一人だけシリアスだ。
「何をしてでも……あなたは……倒す……!」
「お姉さんちょっとまぁーーーった!!
ヒゲじいになるくらいまった! わかってんのハレっち!?」
割り込んだ甲高い声は、彼女の持つ日本刀、参謀喋刀 アメちゃんだ。
姫将軍ハレルは、その能力『刀語』によって彼女と会話することができる。
祖国の、仇……!!」
ちなみにゾルテリア娘の横で涙を浮かべて剣を構えるのは姫将軍ハレルである。
一人だけシリアスだ。
「何をしてでも……あなたは……倒す……!」
「お姉さんちょっとまぁーーーった!!
ヒゲじいになるくらいまった! わかってんのハレっち!?」
割り込んだ甲高い声は、彼女の持つ日本刀、参謀喋刀 アメちゃんだ。
姫将軍ハレルは、その能力『刀語』によって彼女と会話することができる。
「アイツを倒すってコトは……つ、つまり!
あの汚いオッサンのアレにゴニョゴニョしてムニャムニャして!
フニャンフニャンってコトなんだよ!? ダメ、ゼッタイ!
ハレっちがケガれる!! ほっといて次にいこうよ!」
「ええ、次はイカせる……!」
「ゼンゼンわかってなーーい!!」
あの汚いオッサンのアレにゴニョゴニョしてムニャムニャして!
フニャンフニャンってコトなんだよ!? ダメ、ゼッタイ!
ハレっちがケガれる!! ほっといて次にいこうよ!」
「ええ、次はイカせる……!」
「ゼンゼンわかってなーーい!!」
「くっわたしをどうする気だオカマッ……!」
「一人で何かやりだした! どうしよう!」
「オ、オゾましい……! アメちゃんこういうのセイリテキにムリ……!」
「絶対に許せないわ……! 私の怒り」
「一人で何かやりだした! どうしよう!」
「オ、オゾましい……! アメちゃんこういうのセイリテキにムリ……!」
「絶対に許せないわ……! 私の怒り」
アメちゃんを道連れに、カイエン・ゾルテリアに突撃を試みようと構えるハレル!
すわ大惨事か! ――その時!
すわ大惨事か! ――その時!
「……待ちたまえ」
呼び止める渋い声!
その男は立っていた!
比喩ではない……立っていたのだ!
全身をゾルテリアのラバースーツに包んだ謎の男性!
しかもその局部は、ラバースーツ越しでもありありと個性を主張していた!
その男は立っていた!
比喩ではない……立っていたのだ!
全身をゾルテリアのラバースーツに包んだ謎の男性!
しかもその局部は、ラバースーツ越しでもありありと個性を主張していた!
「俺は敗北から学んだ……ゴムをつけることは、モラルとして必要なことなのだ。
次からゴムをつけよう。そう決心したのだ……」
次からゴムをつけよう。そう決心したのだ……」
――長さ1m50cm。それは陰茎というにはあまりにも大きすぎた。
大きく、ぶ厚く、重く、そして大雑把すぎた!
大きく、ぶ厚く、重く、そして大雑把すぎた!
「……そして今が来た。今が、『次』だ」
「グ、グオオオオオ!? バカなァァァァァ――ッ!!」
カイエン・ゾルテリアは絶叫した!
男であれば誰しもが彼と同じ絶望を味わったであろう!
その力の差、歴然!
その威容、見るからに性属性!!
カイエンはラバースーツの謎の男の『男』に畏怖していた!!
男であれば誰しもが彼と同じ絶望を味わったであろう!
その力の差、歴然!
その威容、見るからに性属性!!
カイエンはラバースーツの謎の男の『男』に畏怖していた!!
「お、おのれェェェェ―――ッ!!」
苦し紛れのエネルギー弾を放つが、無傷!
鋼鉄をも凌駕する怒張が!
そしてあらゆる攻撃をどこかの層で防ぐ16層のゾルテリア特製ラバースーツが!
その男を無敵の鬼神へと変えていた……!!
鋼鉄をも凌駕する怒張が!
そしてあらゆる攻撃をどこかの層で防ぐ16層のゾルテリア特製ラバースーツが!
その男を無敵の鬼神へと変えていた……!!
「さあイクぞ『世界の敵』! これが我が『蛇神鞭』、究極の……!」
――夜魔口邸。
夕陽に包まれ始めた屋敷の一室で、
密やかに会話を交わす探偵が2人。
密やかに会話を交わす探偵が2人。
「穢璃様より、お話を頂きました。
拙の『検死結果』をここに」
拙の『検死結果』をここに」
「へぇ~。穢璃さん、偽原さんにあそこまでやられて、よく……
ってまあ、タイミング良かったよ。
何しろ『新黒死病の大元』については、すぐに知りたかったところだからね~」
ってまあ、タイミング良かったよ。
何しろ『新黒死病の大元』については、すぐに知りたかったところだからね~」
「……。佐倉光素様の、例の件ですか」
「そ。戦争を仕掛けた人たちを調べるのさ。
って、大体こ~いうデカい事ができんのは目高機関なわけだから、
実質目高機関の中の『誰が』仕掛けたかっていうのを調べる仕事なわけだよぉ~」
遠藤終赤は探偵である。こまねの物腰や言動から、
実際におおよその目星はついているだろう――と、察することができる。
「そ。戦争を仕掛けた人たちを調べるのさ。
って、大体こ~いうデカい事ができんのは目高機関なわけだから、
実質目高機関の中の『誰が』仕掛けたかっていうのを調べる仕事なわけだよぉ~」
遠藤終赤は探偵である。こまねの物腰や言動から、
実際におおよその目星はついているだろう――と、察することができる。
「嬢ちゃんらの方は、話終わりましたかねえ」
廊下から声。姿を見ずとも分かる。
夜魔口赤帽。夜魔口砂男。
夜魔口赤帽。夜魔口砂男。
「はい、今~」
「……もう行くぞ。ようやっと見つけた親父の仇じゃ。
パンデミックを仕掛けよった人でなしども。
ワシらが償わせる……絶対にな」
「こまね様、危険では」
「大丈夫大丈夫。伏線は、もう張ってあるでしょ~」
「……もう行くぞ。ようやっと見つけた親父の仇じゃ。
パンデミックを仕掛けよった人でなしども。
ワシらが償わせる……絶対にな」
「こまね様、危険では」
「大丈夫大丈夫。伏線は、もう張ってあるでしょ~」
一人残された遠藤終赤は、茶に口をつけた。
きっと、夜魔口組の2人だけではない。
こまねは、受け取ったこの情報を誰かに渡すのだろう。
だが誰が? ……誰が、この強大過ぎる敵を打ち倒すことができるのだろうか?
きっと、夜魔口組の2人だけではない。
こまねは、受け取ったこの情報を誰かに渡すのだろう。
だが誰が? ……誰が、この強大過ぎる敵を打ち倒すことができるのだろうか?
日本の転覆を目論んだ遠藤終赤に、この国の成り行きを救う意味はもはやない。
しかし、それができる存在がいるのだとしたら、それは……この大会が求めた。
滅び行く運命に負けぬ、世界最強の存在――なのだろうか。
しかし、それができる存在がいるのだとしたら、それは……この大会が求めた。
滅び行く運命に負けぬ、世界最強の存在――なのだろうか。
「『ニューヨークリロード』。……さあ、出番でございます」
硝煙を吹くライフルを投げ捨て、射手矢岩名はその場で優雅に回転する。
長い黒髪が流れた後には、既にその姿は変わっている。
水泳ゴーグルをかけた、水色の髪の少女。名を栗花落三傘という。
長い黒髪が流れた後には、既にその姿は変わっている。
水泳ゴーグルをかけた、水色の髪の少女。名を栗花落三傘という。
周囲を包囲する敵を極力視界に入れぬように、
彼女は頭上から降り注ぐ雨を意識した。
雲ひとつない夕陽の夜空に……雨が降る。彼女の周囲にだけ。
彼女は頭上から降り注ぐ雨を意識した。
雲ひとつない夕陽の夜空に……雨が降る。彼女の周囲にだけ。
銃火器を無限に取り出す『ニューヨークリロード』。
彼女の乱射は頭上――ビルの配水管を破壊し、人工の『雨』を作り出している。
そして、そこに雨があるのならば。
彼女の乱射は頭上――ビルの配水管を破壊し、人工の『雨』を作り出している。
そして、そこに雨があるのならば。
「行くよ。『レイニーブルー』」
それは一瞬にして鋼鉄の強度を誇る弾雨に変わる。
地を這う敵はアスファルトごと穿たれ、数百と潰える。
地を這う敵はアスファルトごと穿たれ、数百と潰える。
……そう。それは人間ではない!
どこからともなく這い出し路面を覆い尽くす、攻撃的ミナミコメツキガニ!
本来無害かつ小型であるミナミコメツキガニが、
関東核攻撃の放射能により殺人的に変化! 恐るべき群れ!
どこからともなく這い出し路面を覆い尽くす、攻撃的ミナミコメツキガニ!
本来無害かつ小型であるミナミコメツキガニが、
関東核攻撃の放射能により殺人的に変化! 恐るべき群れ!
「……危ない」
奇襲を察知した無量小路奏が、背後から迫っていた一匹を投げナイフで貫く。
見事な連携を見せた三人は、三人でありながら一人。
ザ・キングオブトワイライトにおける参戦登録名は……『トリニティ』という。
奇襲を察知した無量小路奏が、背後から迫っていた一匹を投げナイフで貫く。
見事な連携を見せた三人は、三人でありながら一人。
ザ・キングオブトワイライトにおける参戦登録名は……『トリニティ』という。
「……でも、一体どこから……」
(まるで地下から湧いてきたようだね)
(この下となれば……地下鉄でしょうか)
(まるで地下から湧いてきたようだね)
(この下となれば……地下鉄でしょうか)
――その時、アスファルトを突き破って、それは出現した!
それは異常成長した超巨大オカダンゴムシ(メス)であった!
それは異常成長した超巨大オカダンゴムシ(メス)であった!
トリニティ達は見た。その胸部、神経節付近でそれを駆る魔人の姿を。
オカダンゴムシは実験モデルに使われる程度に神経系の構造が単純であり、
精妙なトング術による物理的処置が進行方向を操作し得ると考えられなくはない。
オカダンゴムシは実験モデルに使われる程度に神経系の構造が単純であり、
精妙なトング術による物理的処置が進行方向を操作し得ると考えられなくはない。
……東京駅地下に異常繁殖した甲殻類。
そして聖槍院九鈴の出現の瞬間をトリニティ達が目撃したのは、
果たして全くの偶然なのだろうか? 真相は不明である。
そして聖槍院九鈴の出現の瞬間をトリニティ達が目撃したのは、
果たして全くの偶然なのだろうか? 真相は不明である。
「……はやくいかなきゃ。
今度は……今度は捨てない」
今度は……今度は捨てない」
オカダンゴムシの他に、その狂った呟きを聞く者はいない。
景色が無数の線と化して流れる。
運命は交差に向かって突き進む。
景色が無数の線と化して流れる。
運命は交差に向かって突き進む。
「わたしが……助ける……!」
《ケホッ、ケホッ……。私が、動くことになるか》
「そうだ……私としても実に不本意な事だが」
田村草介の『悪い予想』は当たった。
『ザ・キングオブトワイライト』そのものの事後処理に当たる銘刈耀はともかく、
『オレイン卿』までもが既に何者かとの交戦状態にあり、通信が途絶している。
当初、即座に動き出すと予想された日本政府の核攻撃も、
魔人側――高島平四葉からの過剰防衛も引き起こされていない。
「そうだ……私としても実に不本意な事だが」
田村草介の『悪い予想』は当たった。
『ザ・キングオブトワイライト』そのものの事後処理に当たる銘刈耀はともかく、
『オレイン卿』までもが既に何者かとの交戦状態にあり、通信が途絶している。
当初、即座に動き出すと予想された日本政府の核攻撃も、
魔人側――高島平四葉からの過剰防衛も引き起こされていない。
無論『オレイン卿』の能力を以ってすれば敵対者の排除に1分もかからぬだろう。
銘刈とて……才能を携え彼女の前に立ちはだかるものであれば、
敵対者だろうと即座に『スカウト』して味方に引き入れる事すら可能な能力だ。
銘刈とて……才能を携え彼女の前に立ちはだかるものであれば、
敵対者だろうと即座に『スカウト』して味方に引き入れる事すら可能な能力だ。
彼らの敗北など起こり得ない。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
(……が、それが起こっているかもしれない。
1分の遅れ! 予想との微妙な齟齬! それは私の破滅を意味する……
………………その『おそれ』があるんだ!)
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
(……が、それが起こっているかもしれない。
1分の遅れ! 予想との微妙な齟齬! それは私の破滅を意味する……
………………その『おそれ』があるんだ!)
この戦争経済は目高機関が独自で立ち上げた極秘プロジェクト。
日本政府も市民も、その勃発を予測する事すらできず、
故に全ての動きが『奇襲』となる。動き始めが最も脆い。
日本政府も市民も、その勃発を予測する事すらできず、
故に全ての動きが『奇襲』となる。動き始めが最も脆い。
それは目高機関自体も――例外ではない。
田村草介は後先を考えず恐怖への対処を『実行してしまった』立場であり、
リスクを十分に理解した上でプロジェクトを推進したわけではない。
いつもと同じ、奇跡的な綱渡りだ。今回も成功する保証は全くない。
田村草介は後先を考えず恐怖への対処を『実行してしまった』立場であり、
リスクを十分に理解した上でプロジェクトを推進したわけではない。
いつもと同じ、奇跡的な綱渡りだ。今回も成功する保証は全くない。
「……WL社を経由して得た『一段階強いウィルス』は、君の手にあるはずだ。
迷わず使ってほしい。パンデミックを仕掛けた君になら可能だろう。
私にその勇気はない。お願いだ――裸繰埜病咲風花」
《いいだろう。私も丁度……丁度、最後のテストをしたかったところだ》
「最後だって?」
迷わず使ってほしい。パンデミックを仕掛けた君になら可能だろう。
私にその勇気はない。お願いだ――裸繰埜病咲風花」
《いいだろう。私も丁度……丁度、最後のテストをしたかったところだ》
「最後だって?」
相手の言葉を訝る間すらなく、通話は即座に切れた。
田村は、足元から何かが這い登る、不穏な気配を感じている。
田村は、足元から何かが這い登る、不穏な気配を感じている。
それは破滅の気配だ。
常に彼に纏わりつき、離さない『恐怖』の具現化。
……今回のそれも、また錯覚だろうか? それを振り払えるのだろうか?
常に彼に纏わりつき、離さない『恐怖』の具現化。
……今回のそれも、また錯覚だろうか? それを振り払えるのだろうか?
それとも。
四車線を塞ぐほどのオカダンゴムシ(メス)は……
目的地への途上、その重戦車めいた巨体を停止させていた。
甲殻に刻まれた銃痕や刃物、火炎、その他諸々の傷は、
パニックに陥った群衆からの攻撃が殆どである。
目的地への途上、その重戦車めいた巨体を停止させていた。
甲殻に刻まれた銃痕や刃物、火炎、その他諸々の傷は、
パニックに陥った群衆からの攻撃が殆どである。
近代装備に身を固めた日本政府の部隊と遭遇しなかった点は、
聖槍院九鈴にとって唯一『運が良かった』点であろう。
聖槍院九鈴にとって唯一『運が良かった』点であろう。
彼方から走り寄る、小柄な影があった。
その人物……偽名探偵こまねを認識してもなお、九鈴はトングを構えた。
その人物……偽名探偵こまねを認識してもなお、九鈴はトングを構えた。
「待った」
息を切らせながらも、こまねは手で制した。
九鈴が構えを解くことはない。
九鈴が構えを解くことはない。
「あなたがこまね?
待ち合わせの場所は、ここじゃない」
「……こまね。ふふん、偽名だけどね~。
時間がなかったから、ここまで走ってきたってわけだよぉ~。
おかげで、赤羽ハルの方には渡せなくなっちゃったけど。
でもまあ、あたしなりの伏線は張っておいたからね」
待ち合わせの場所は、ここじゃない」
「……こまね。ふふん、偽名だけどね~。
時間がなかったから、ここまで走ってきたってわけだよぉ~。
おかげで、赤羽ハルの方には渡せなくなっちゃったけど。
でもまあ、あたしなりの伏線は張っておいたからね」
どこかから爆発音が響いてくる。近い。
こまねはふと真剣な顔になって、言った。
「本当に……時間がないんだよ。
電話や通信網は傍受されているから、直接渡すしかないの。
ほれ、ここに」
「!」
こまねはふと真剣な顔になって、言った。
「本当に……時間がないんだよ。
電話や通信網は傍受されているから、直接渡すしかないの。
ほれ、ここに」
「!」
……こまねはメモを無造作に、地に投げ捨てていた。
聖槍院九鈴は恐ろしい素早さで飛び出して、トングで掴みとる。
反射的な対応である。
「ゴミ。すてないで」
それは探偵の意図通りであった。
聖槍院九鈴は恐ろしい素早さで飛び出して、トングで掴みとる。
反射的な対応である。
「ゴミ。すてないで」
それは探偵の意図通りであった。
「……依頼どおりだよ。今果たし――」
偽名探偵こまねは炎に呑まれて、跡形もなく消えた。
その対戦車ロケットの一撃を皮切りに、無数の銃火が火を吹いた。
聖槍院九鈴は爆風にまかれてオカダンゴムシの甲殻の下へ転がって、
そこでようやくその事実を認識した。
その対戦車ロケットの一撃を皮切りに、無数の銃火が火を吹いた。
聖槍院九鈴は爆風にまかれてオカダンゴムシの甲殻の下へ転がって、
そこでようやくその事実を認識した。
「…………」
ロケットの弾道は、九鈴が先程立っていた地点を狙ったものであった。
ロケットの弾道は、九鈴が先程立っていた地点を狙ったものであった。
九鈴は無言で立った。
『新黒死病の大元』たる魔人能力者。
パンデミックを引き起こした存在が、このメモの地点に――いる。
パンデミックを引き起こした存在が、このメモの地点に――いる。
「ったく……ハハハ!
どうして俺、こんな事になってんだ……。
バカみてえだよな、バカだ……」
どうして俺、こんな事になってんだ……。
バカみてえだよな、バカだ……」
銃火をくぐり抜け、追っ手を撒いた赤羽ハルは、路地裏にもたれて自嘲した。
追ってくる『敵』が、政府の部隊か、目高機関の尖兵か――
それとも何も知らぬ市民なのか、その判別すらつかない。
追ってくる『敵』が、政府の部隊か、目高機関の尖兵か――
それとも何も知らぬ市民なのか、その判別すらつかない。
だが少なくとも、彼をはじめとした『ザ・キングオブトワイライト』の出場者は、
その他の人間、そして魔人にとってすらも、紛れもなく『世界の敵』であり……
出会う誰もがその姿を駆り立てようと熱狂しているのだった。
その他の人間、そして魔人にとってすらも、紛れもなく『世界の敵』であり……
出会う誰もがその姿を駆り立てようと熱狂しているのだった。
(佐倉光素に伝えられた場所には……まだ、向かえないか。
いや、どっちにせよこの状況じゃあ無謀過ぎる手段だ。
やっぱり駄目だな、俺らしくない……。返そうなんて、思わなきゃあ良かった)
いや、どっちにせよこの状況じゃあ無謀過ぎる手段だ。
やっぱり駄目だな、俺らしくない……。返そうなんて、思わなきゃあ良かった)
――そうだ。返せるはずなどない。
――殺し屋め。
――殺し屋め。
頭の中で声が響く。
絶望の淵に立たされた時、決まって聞こえてきた声。常に常に常に。
絶望の淵に立たされた時、決まって聞こえてきた声。常に常に常に。
――今更ルールを守って、何が変わるっていうんだ?
(分かってるんだよ……クソが)
それは自分自身の自責の声に他ならなかった。
『契約に基づく負債を、正しく返さなければならない』。
しかし赤羽ハルが真に心に負う負債は、誰に対する契約でもなかった。
『契約に基づく負債を、正しく返さなければならない』。
しかし赤羽ハルが真に心に負う負債は、誰に対する契約でもなかった。
――魂に値段はつけられない。殺した命を取り返せるのか?
ささやかな幸せを感じる時。その罪を忘れ去ろうとするたび。
それは命の負債を取り立てようと迫るシャイロックのように……
内なる悪魔が、いつも囁くのだ。
それは命の負債を取り立てようと迫るシャイロックのように……
内なる悪魔が、いつも囁くのだ。
お前は幸せにはなれない、と。
「ドーモ『お客サン』。ラーメン探偵です」
赤羽は路地を振り向いた。
先程から気配は感じていた。参加者の一人だ。
「あんたは……どっちだ?
敵か、味方か。どちらでもないのか?」
……だが、楽観はできない。
赤羽は路地を振り向いた。
先程から気配は感じていた。参加者の一人だ。
「あんたは……どっちだ?
敵か、味方か。どちらでもないのか?」
……だが、楽観はできない。
右手はだらりと垂れ下がったままだ。腱が切れているのだ。
全身に刻まれた傷は思いの外少なかったが、
時間経過による失血は確実にその生命を削っていた。
全身に刻まれた傷は思いの外少なかったが、
時間経過による失血は確実にその生命を削っていた。
「……」
しかしラーメン探偵・真野事実は、ずい、とオカモチを差し出した。
無言である。
「……Show You La Amen(「真実を見せる」という意味の英語)」
しかしラーメン探偵・真野事実は、ずい、とオカモチを差し出した。
無言である。
「……Show You La Amen(「真実を見せる」という意味の英語)」
赤羽ハルはため息を付いて、オカモチの中を見た。
笑い飛ばす気になどなれなかったし、その体力すらもなかった。
笑い飛ばす気になどなれなかったし、その体力すらもなかった。
オカモチの中にはラーメンはなく、ただシャボン玉だけがふわりと舞った。
それらは順に割れて、メッセージを伝えた。
それらは順に割れて、メッセージを伝えた。
《ごめんね~。こっちの都合で、君のところにはいけなくなっちゃった》
《でも、調査は終わったから……届けさせてもらったのさ~》
《でも、調査は終わったから……届けさせてもらったのさ~》
声は真実を伝えた。
暗殺対象の名。そして所在。
――探偵同士の連携。それが伏線。
暗殺対象の名。そして所在。
――探偵同士の連携。それが伏線。
「ハハッ」
赤羽は呆れたように肩をすくめて、ラーメン探偵を見た。
「あんたこのシャボン玉……
こんな中で、割らずにここまで持ってきたのかよ」
赤羽は呆れたように肩をすくめて、ラーメン探偵を見た。
「あんたこのシャボン玉……
こんな中で、割らずにここまで持ってきたのかよ」
「……」
言葉を発することなく、ラーメン探偵は踵を返した。
真実を配達する。それだけが彼の『哲学(ラーメン)』であった。
真実を配達する。それだけが彼の『哲学(ラーメン)』であった。
「……ケホッ、ケホッ」
パンデミック後の社会混乱の中、打ち捨てられた神社。
その境内に、彼女は座して待っていた。
その境内に、彼女は座して待っていた。
真新しい白衣。濃紺の髪と瞳。マスクで口元を覆った、女医である。
時折咳き込むその姿は、どこか禍々しい雰囲気を予感させた。
時折咳き込むその姿は、どこか禍々しい雰囲気を予感させた。
――――
裸繰埜病咲風花
魔人能力名:『ブレイクアウト』
――ウィルスを進化させる。
http://www18.atwiki.jp/drsx2/pages/103.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/22.html
魔人能力名:『ブレイクアウト』
――ウィルスを進化させる。
http://www18.atwiki.jp/drsx2/pages/103.html
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/22.html
――――
「……さあ」
WL社研究員にして、目高機関のエージェント。
パンデミックを仕掛けた張本人は、超然と呟いた。
WL社研究員にして、目高機関のエージェント。
パンデミックを仕掛けた張本人は、超然と呟いた。
「貴方なら、この災厄を乗り越えてくるはずだ。
そして私の問いに答えてくれ」
そして私の問いに答えてくれ」
ここからは街が――『ザ・キングオブトワイライト』の会場たる街が一望できる。
風向きに乗せてウィルスを散布すれば、市内の全員が……
即ち全ての大会参加選手が感染し得る、絶好の位置条件であった。
風向きに乗せてウィルスを散布すれば、市内の全員が……
即ち全ての大会参加選手が感染し得る、絶好の位置条件であった。
「ふふ、ふふふふふふ……」
そこには祈願を込めた絵馬が、今も飾られるがままに揺れている。
『早くお父さんが良くなりますように』。『パンデミックがおさまりますように』。
『おばあちゃんを助けて下さい』。『息子を』。『弟を』。『孫を』――。
誰かが誰かの無事を祈り、そしてほぼ全てが無駄に終わった、その願い。
裸繰埜病咲風花の含み笑いは、そのウィルスの『成果』を思っていた。
『早くお父さんが良くなりますように』。『パンデミックがおさまりますように』。
『おばあちゃんを助けて下さい』。『息子を』。『弟を』。『孫を』――。
誰かが誰かの無事を祈り、そしてほぼ全てが無駄に終わった、その願い。
裸繰埜病咲風花の含み笑いは、そのウィルスの『成果』を思っていた。
身に沁みて知っている。淘汰される弱者の願いなど無意味だ。
そんな中、その女性は更け始めた闇の中、石段を登っていた。
右手に提げた黒いトングの刃が、カリカリと地面を鳴らしている。
右手に提げた黒いトングの刃が、カリカリと地面を鳴らしている。
「やっと、あえたね……」
彼女の顔に憎悪や狂気はない。だが歓喜や慈愛もない。
ただ全ての物事を正確に、甲殻類の如く処理するための無表情が浮かんでいた。
ただ全ての物事を正確に、甲殻類の如く処理するための無表情が浮かんでいた。
「わたしのせいだ。ごめんなさい。
わたしがゴミを掃除できなかったから……
だからみんなが苦しんで、今も……。
あなただって苦しんでいる……」
わたしがゴミを掃除できなかったから……
だからみんなが苦しんで、今も……。
あなただって苦しんでいる……」
「聖槍院九鈴ちゃん、だっけ? 大会参加者の名はよく知っているよ。
貴方か、赤羽ハル。あるいは遠藤終赤、夜魔口の2人……
全部私の起こしたパンデミックの、間接的な犠牲者だね。
……その誰かが上がってくれれば良いと思っていた」
貴方か、赤羽ハル。あるいは遠藤終赤、夜魔口の2人……
全部私の起こしたパンデミックの、間接的な犠牲者だね。
……その誰かが上がってくれれば良いと思っていた」
裸繰埜病咲風花が立ち上がることはない。
その白衣をぺたりと地面に垂らしたまま、ただ近寄る死神を見上げるだけだ。
その白衣をぺたりと地面に垂らしたまま、ただ近寄る死神を見上げるだけだ。
「ウィルス進化、という学説を知っているね」
「おとうさんも」
「おとうさんも」
「それに限らず……生物種の進化の節目には必ず巨大な疫病の流行があった。
強靭な抵抗力を持つ者だけが『選別』され、次のステージへと進む。
まるで種族そのものが一つの生物のように、それは『抗体』を作り上げるのだ」
「……おかあさんも」
強靭な抵抗力を持つ者だけが『選別』され、次のステージへと進む。
まるで種族そのものが一つの生物のように、それは『抗体』を作り上げるのだ」
「……おかあさんも」
「――滅び行く運命に負けぬ、世界最強の存在!
まさに貴方たちがそれだよ。この最悪な世界を破壊し得る、『世界の敵』!
……それこそがこのパンデミックが生んだ抗体なのさ!
さあ教えてくれ……私に、私に最後に教えてくれ、ケホッ、ケホッ」
まさに貴方たちがそれだよ。この最悪な世界を破壊し得る、『世界の敵』!
……それこそがこのパンデミックが生んだ抗体なのさ!
さあ教えてくれ……私に、私に最後に教えてくれ、ケホッ、ケホッ」
風花は立ち上がらない。正確に言えば、もはや――立ち上がることすらできない。
彼女に求められる役割は、パンデミックの制御のみ。
ならば自身が病に侵されていようとも……
手足が腐り落ちたこの今であろうとも、支障などあるはずがない。
彼女に求められる役割は、パンデミックの制御のみ。
ならば自身が病に侵されていようとも……
手足が腐り落ちたこの今であろうとも、支障などあるはずがない。
「私は……私は乗り越えられなかったよ! ははははは!
だから次のステージに進んだ貴方に、見せて欲しいんだ!!」
「……くろう」
だから次のステージに進んだ貴方に、見せて欲しいんだ!!」
「……くろう」
裸繰埜病咲風花のその姿を見て、
例えば――彼女の弟の最後の姿に重なる様を見たとして、
九鈴の漂白された心に、僅かでも動揺が走っただろうか。
例えば――彼女の弟の最後の姿に重なる様を見たとして、
九鈴の漂白された心に、僅かでも動揺が走っただろうか。
そして弟の姿を彼女に重ねるという事は……
(――裏トーナメント決勝。あの時のように!
ウィルスを生んだ私を乗り越えてみせてくれ。
新しいステージに上がる資格を得たのは私ではなく……貴方なのだから)
ウィルスを生んだ私を乗り越えてみせてくれ。
新しいステージに上がる資格を得たのは私ではなく……貴方なのだから)
彼女の白衣に仕込まれた機構が、自動的に試験管の封を開いた。
新黒死病ウィルスよりも『一段階強い』、極悪のウィルスである。
耐えられる。家族の死という悲劇を乗り越えて……
そして世界の敵の犇めくこのトーナメントの中、
淘汰されずに生き残ってきた、この聖槍院九鈴であれば、この程度の試練。
新黒死病ウィルスよりも『一段階強い』、極悪のウィルスである。
耐えられる。家族の死という悲劇を乗り越えて……
そして世界の敵の犇めくこのトーナメントの中、
淘汰されずに生き残ってきた、この聖槍院九鈴であれば、この程度の試練。
九鈴は風花を殺すだろう。しかし風花に敵意はなかった。
むしろ信頼と、尊敬の念すら抱いていた。
むしろ信頼と、尊敬の念すら抱いていた。
(そうだ。貴方の勝ちなんだよ……!
貴方なら勝てる。私なんかとは違うんだ!)
貴方なら勝てる。私なんかとは違うんだ!)
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
だから、この程度で死んでもらっては困るのだ。
だから、この程度で死んでもらっては困るのだ。
――九鈴のそれとすらも異なる、異次元の狂気であった。
「ごめんね……くろう……。いま、たすけるね……」
涙を流しながら、彼女は黒い刃を、最後にして最初の敵の心臓へと向けた。
それを敵とすら認識せず……
涙を流しながら、彼女は黒い刃を、最後にして最初の敵の心臓へと向けた。
それを敵とすら認識せず……
「ごめん……」
もう一度呻いた九鈴の真横に、ウィルスの試験管が飛んだ。
彼女はそれをトングで掴みとった。
もう一度呻いた九鈴の真横に、ウィルスの試験管が飛んだ。
彼女はそれをトングで掴みとった。
それは反射的な動きだった。
家族への思いよりも上回る――否、むしろ家族との思い出そのものとすらいえる、
見事で正確な、『トング道』の動きであった。
家族への思いよりも上回る――否、むしろ家族との思い出そのものとすらいえる、
見事で正確な、『トング道』の動きであった。
「そんな」
風花は押し殺した悲鳴をあげた。
試験管から撒き散らされる筈の『一段階強い』新黒死病ウィルスは――
彼女のトングが掴んだその位置で、一つの結晶と化して停止していた。
風花は押し殺した悲鳴をあげた。
試験管から撒き散らされる筈の『一段階強い』新黒死病ウィルスは――
彼女のトングが掴んだその位置で、一つの結晶と化して停止していた。
掴んだものを離さない聖槍院九鈴の魔人能力、『タフグリップ』。
仮に、大気中の不純物すらをも選択的に掴み取れる能力なのだとしたら。
そしてあの一瞬、微かに残った九鈴の理性の残滓が……
『新黒死病事件の主犯』の放った試験管の中身を、看破していたのだとしたら。
仮に、大気中の不純物すらをも選択的に掴み取れる能力なのだとしたら。
そしてあの一瞬、微かに残った九鈴の理性の残滓が……
『新黒死病事件の主犯』の放った試験管の中身を、看破していたのだとしたら。
「……いいや……それでいい。それでこそ……だよ。
あいがとう九鈴ちゃん。貴方のお陰で、何も……思い残すことなく」
「ごめんね」
あいがとう九鈴ちゃん。貴方のお陰で、何も……思い残すことなく」
「ごめんね」
だが次の瞬間、裸繰埜病咲風花が感じたのは――心臓を啄むカラスの刃ではなく。
身を包み込むように抱きしめる、暖かな感触であった。
身を包み込むように抱きしめる、暖かな感触であった。
「ね……? くるしかったよね……?
ごめんね、ずっと側にいられなくて……」
「……」
ごめんね、ずっと側にいられなくて……」
「……」
――何故だ。
家族の仇であるこの私を、今、街の人間を巻き添えにしようとしたこの私を。
「な、何をしている……早く、淘汰するんだ。
私はもう、弱者の運命など、とうの昔に受け入れて……」
家族の仇であるこの私を、今、街の人間を巻き添えにしようとしたこの私を。
「な、何をしている……早く、淘汰するんだ。
私はもう、弱者の運命など、とうの昔に受け入れて……」
とめどなく流れる涙に頬を濡らしながら、九鈴は首を振った。
それは機関の仕掛けによって裏決勝を垣間見た風花も知る、
優しく悲しい姉の顔であるはずだった。
それは機関の仕掛けによって裏決勝を垣間見た風花も知る、
優しく悲しい姉の顔であるはずだった。
おかしい。何かがおかしい……こうなるはずでは、ない。
「ごめんね、くろう。ごめんね……
どんなに苦しくても、もうわたしは……はなれないから。
ずっと、そばにいるから」
どんなに苦しくても、もうわたしは……はなれないから。
ずっと、そばにいるから」
強く抱きしめる九鈴の腕の中で、風花はその理由を知った。
自身が敗北した――真の理由。
たった今、真横に飛んだウィルスを捕獲したその動きの中で……
彼女はそれを見たのだ。
自身が敗北した――真の理由。
たった今、真横に飛んだウィルスを捕獲したその動きの中で……
彼女はそれを見たのだ。
「……だったのか」
その方向に、家族の願いが書かれた絵馬が揺れていた。
――それは、聖槍院九鈴が書き記したものではなかったのかもしれない。
そのありふれた名が、たまたま一致しただけであったのかもしれない。
けれど、その願いを書いた誰かは、救いたいと願っていたに違いなかったのだ。
そのありふれた名が、たまたま一致しただけであったのかもしれない。
けれど、その願いを書いた誰かは、救いたいと願っていたに違いなかったのだ。
本当は、言うまでもなく……
最愛の弟を殺したいはずなどなかったのだ。
……だからこそその罪悪に、ここまで苦しんできたのだから。
最愛の弟を殺したいはずなどなかったのだ。
……だからこそその罪悪に、ここまで苦しんできたのだから。
「うふ、ふふふっ……『九郎が、ずっと元気でいられますように』……
この程度の、ことで」
この程度の、ことで」
その程度の絵馬が、その願いを思い起こさせたのだ。
淘汰される弱者の願いなど――
淘汰される弱者の願いなど――
「やっとつかめた、もう絶対に……絶対にはなさないから……!」
「ふふふふふ……馬鹿な。ふふふふふ……」
「ずっとわたしが……一緒に、いるからね。
あの時……あの時つかめなかったものを、やっと」
「ふふふふふ……馬鹿な。ふふふふふ……」
「ずっとわたしが……一緒に、いるからね。
あの時……あの時つかめなかったものを、やっと」
ウィルスを握りしめたままのカラスが、カラカラと音を立てて落ちた。
『タフグリップ』。一度掴んだものを決して離さない能力は、
彼女が望まぬ限り――このウィルスを解き放つことも、決して無いのだろう。
『タフグリップ』。一度掴んだものを決して離さない能力は、
彼女が望まぬ限り――このウィルスを解き放つことも、決して無いのだろう。
……家族。
風花の生まれである藍堂家は、既に滅びた医者の家系だ。
それを辛いと認識した事など、一度たりとてなかった。
風花の生まれである藍堂家は、既に滅びた医者の家系だ。
それを辛いと認識した事など、一度たりとてなかった。
「くろう……! くろう。辛いよね、苦しいよね……」
それが偽りの狂気による認識であったとしても……
本物の愛情と共に裸繰埜病咲風花を抱きしめて。
そして本気で涙を流す人間など――
本物の愛情と共に裸繰埜病咲風花を抱きしめて。
そして本気で涙を流す人間など――
「ふっ、ふふふふふふふふふ」
なんて愚かなんだろう……
「ふふふふふふふふふ……ふっ……」
「……っ、ふふふ……、ふふふ………………………
ふふふ……あああ………………うあああああああ………
うああああああああああああああああああっ…………」
ふふふ……あああ………………うあああああああ………
うああああああああああああああああああっ…………」
聖槍院九鈴は、本当に掴みたかったものを掴んだ。
彼女が『再び』世界を滅ぼすことは二度となく、
世界最悪の疫病を撒き散らした魔人との戦いは、終わった。
彼女が『再び』世界を滅ぼすことは二度となく、
世界最悪の疫病を撒き散らした魔人との戦いは、終わった。
【……】
少年は飛び退いた。手を通して伝わるのは、異様な感触……
存在せぬ筈のものがそこにある気配だった。
存在せぬ筈のものがそこにある気配だった。
【どういうことだ】
声からは感情の断片すらも見て取れぬが、その事態は明らかに異常だった。
咄嗟に引き戻した――相川ユキオを貫いたはずの光の槍の先端が、ない。
影の兵装に侵食されたのか? ……その気配もなかったはずだ。
咄嗟に引き戻した――相川ユキオを貫いたはずの光の槍の先端が、ない。
影の兵装に侵食されたのか? ……その気配もなかったはずだ。
「……こほっ、無茶苦茶だろ」
音もなく、その編集者は唯一の兵装を展開した。
心臓の位置から血を流しながら、黒い影の槍を杖のようにして立っている。
「いつも無茶苦茶をやらかすんだ。……うちの先生はな。
お前の方がまだ優しいかもしれないぜ……」
音もなく、その編集者は唯一の兵装を展開した。
心臓の位置から血を流しながら、黒い影の槍を杖のようにして立っている。
「いつも無茶苦茶をやらかすんだ。……うちの先生はな。
お前の方がまだ優しいかもしれないぜ……」
【ほう】
空気がビリビリと震えた。それは純粋に押し退けられた質量のなす風だった。
少年の足元から、目も眩む光が展開を完了している。
『オレイン卿』の力の一端……それは建物全体を覆い尽くす『神殿』であり、
内部に位置する存在すべてを喰らい尽くす捕食器官であった。
魔導書に支配される編集者《天使》であれば、指一本でその起動命令は足りる。
空気がビリビリと震えた。それは純粋に押し退けられた質量のなす風だった。
少年の足元から、目も眩む光が展開を完了している。
『オレイン卿』の力の一端……それは建物全体を覆い尽くす『神殿』であり、
内部に位置する存在すべてを喰らい尽くす捕食器官であった。
魔導書に支配される編集者《天使》であれば、指一本でその起動命令は足りる。
【――愚か者め】
「愚か者は!」
相川ユキオは、着古したシャツの胸を開く。
そこには形容困難な、紋章めいた刺青が刻まれており……
「どっちかな、“先生”!」
「愚か者は!」
相川ユキオは、着古したシャツの胸を開く。
そこには形容困難な、紋章めいた刺青が刻まれており……
「どっちかな、“先生”!」
高く差し上げた指は食いちぎられていた。
それはユキオの背から飛び出した、厚みのない蛇めいた異形である。
突き刺した瞬間にオレイン卿が覚えた違和感は正しかった。
槍の『厚み』は、あの刺青一枚を通して変化していたのだ。
完全にゼロの厚み……故に心臓を抉るはずが、致命傷を避けて――
それはユキオの背から飛び出した、厚みのない蛇めいた異形である。
突き刺した瞬間にオレイン卿が覚えた違和感は正しかった。
槍の『厚み』は、あの刺青一枚を通して変化していたのだ。
完全にゼロの厚み……故に心臓を抉るはずが、致命傷を避けて――
予測外のダメージにたじろいだ一瞬、光で形成された神殿が揺らいで形を崩す。
【……何】
「俺も、俺なりに……考えてんだよ。どんな奴が出てくるか分からないからさ。
ええ? 俺みたいな下っ端にやられて悔しいか、ざまあみやがれ!」
【……何】
「俺も、俺なりに……考えてんだよ。どんな奴が出てくるか分からないからさ。
ええ? 俺みたいな下っ端にやられて悔しいか、ざまあみやがれ!」
「――俺の力はこの程度のものでしかないが」
そして遠く、相川ユキオの背後。纏う気配と存在感の薄さは、
まるで彼自身が影そのものであるかのようだ。
この男が先の蛇をコントロールした存在に違いなかった。
そして遠く、相川ユキオの背後。纏う気配と存在感の薄さは、
まるで彼自身が影そのものであるかのようだ。
この男が先の蛇をコントロールした存在に違いなかった。
【魔人……薄気味の悪い大道芸人どもめ】
「そうだ。多少は、客を笑わせる事ができたか?」
倉敷椋鳥。 『正体不明のご招待(ストレンジ・インヴィテイション)』。
「そうだ。多少は、客を笑わせる事ができたか?」
倉敷椋鳥。 『正体不明のご招待(ストレンジ・インヴィテイション)』。
【その抵抗の無意味さを……教育してやろう……】
『さて。ならば、この偉大なるノートン卿が編集者を必要とするのか。
こちらはその理由を教授しようか、オレイン卿“君”』
こちらはその理由を教授しようか、オレイン卿“君”』
再展開を始める白い光を意にすら介さず、黒い書物は尊大に宣告した。
『一つ。完全に支配された編集者へのダメージは、君自身の魔術への揺らぎに繋がる。
二つ。私の物語は偉大かつ語り継がれるべきであり、公正な証人が必要だからだ。
三つ。この私、偉大なるサー・ノートン・バレイハートにとって――』
二つ。私の物語は偉大かつ語り継がれるべきであり、公正な証人が必要だからだ。
三つ。この私、偉大なるサー・ノートン・バレイハートにとって――』
同時、残された渾身の力で、相川ユキオは横手の窓を開け放った。
……窓の外の光景の半分は、夕陽の作り出す黒に包まれていた。
正確には、夕陽の影に包まれていた。
……窓の外の光景の半分は、夕陽の作り出す黒に包まれていた。
正確には、夕陽の影に包まれていた。
さらに正確に言えば、その影に隠れた『半分』は全て、
屋内や切り立った山岳地形では決して使用不可能な、殺戮文書の『本領』――
殺戮文書『ノートン卿』によって置換された、
経済機構と防衛機構を果たす城塞機構、巨大なひとつの《城下町》であった。
屋内や切り立った山岳地形では決して使用不可能な、殺戮文書の『本領』――
殺戮文書『ノートン卿』によって置換された、
経済機構と防衛機構を果たす城塞機構、巨大なひとつの《城下町》であった。
『――無能な編集者の存在程度は、枷にもならぬから、だ!』
無限に放たれる影の《矢》が、開け放たれた窓から滝のように雪崩れ込んだ。
倉敷椋鳥により《城塞》を運用し得る異次元の援軍を得た『ノートン卿』は――
ついに最大の災厄を叩きつけた。
倉敷椋鳥により《城塞》を運用し得る異次元の援軍を得た『ノートン卿』は――
ついに最大の災厄を叩きつけた。
蛇めいた異常な軌道で迫った豪速の拳は、
それ自体が森田のガードを回りこんで胴を打った。
それ自体が森田のガードを回りこんで胴を打った。
「――!」
同時、右足を下げ、半身で受ける。
人智を超えた反射能力――
だが、横合いから投げつけられる無数のナイフを避ける事はできない。
人智を超えた反射能力――
だが、横合いから投げつけられる無数のナイフを避ける事はできない。
(千歯車)
投げナイフ程度は森田の機能を裂くまでには至らないが、
皮膚を傷つけ、そこに血液を浸透させる事ができる。
銃声がそこに響いた。肉を抜けたその一撃は、銘刈耀のものだ。
皮膚を傷つけ、そこに血液を浸透させる事ができる。
銃声がそこに響いた。肉を抜けたその一撃は、銘刈耀のものだ。
「ぐぅっ……ウゥおああああああああ!!」
アフロヘアーの吸血鬼は、またも抵抗の雄叫びを上げた。
だが銘刈が一度その『才能』を見出してしまった以上は……。
だが銘刈が一度その『才能』を見出してしまった以上は……。
(――千歯車の魔人能力は。
血流が付着した対象を操作する魔人能力『ブラディ・シージ』。
皮膚一枚の感覚が妨げられるだけで、)
「よそ見を」
血流が付着した対象を操作する魔人能力『ブラディ・シージ』。
皮膚一枚の感覚が妨げられるだけで、)
「よそ見を」
ニィ、という嗤いの気配が同時に割り込んで、蹴りが空気を切断した。
皮膚感覚の心配をするまでもなく、森田の皮膚は袈裟懸けに抉られた。
皮膚感覚の心配をするまでもなく、森田の皮膚は袈裟懸けに抉られた。
「してくれるなよ。森田一郎」
「……」
「……」
問われるまでもなかった。
森田一郎がその持てるスペックの全てを防御に傾けているのは、
儒楽第の一撃だけは、まともに受けてはならないためだ。
森田一郎がその持てるスペックの全てを防御に傾けているのは、
儒楽第の一撃だけは、まともに受けてはならないためだ。
……銘刈とてそれを理解しているだろう。
故に千歯車を含めたこの二者の攻撃は、中距離からの――
故に千歯車を含めたこの二者の攻撃は、中距離からの――
「七葉樹落葉も、思い切ったことを考えましたね。
私の『偶像崇拝(アイドルマスター)』……を避ける手段として」
私の『偶像崇拝(アイドルマスター)』……を避ける手段として」
儒楽第の掌底と正拳がぶつかり合う。だがダメージは森田の側だけが受ける。
儒楽第の攻撃の全ては、カウンターへのガードを必要としない。
彼の魔人能力――纏うオーラそのものが、常にその体を防御しているためだ。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
「あなたのような、一切の才能を持たない男を側近として置くとは」
儒楽第の攻撃の全ては、カウンターへのガードを必要としない。
彼の魔人能力――纏うオーラそのものが、常にその体を防御しているためだ。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
「あなたのような、一切の才能を持たない男を側近として置くとは」
彼の根源は、ただ空手のみであった。
鍛錬に次ぐ鍛錬。魔人能力どころか、格闘の才も持たぬ凡庸な男。
それが――
鍛錬に次ぐ鍛錬。魔人能力どころか、格闘の才も持たぬ凡庸な男。
それが――
「……ッケンナコラー……」
「……」
「……」
銘刈は千歯車を見た。彼女は何が起こっているかを理解しなかった。
「テメッコラー……アタシをこの、程度で……
ワドルナッケングラー!」
ワドルナッケングラー!」
血流が付着した存在を操作する『ブラディ・シージ』。
『偶像崇拝(アイドルマスター)』はあくまでスカウトの時点で発揮される能力。
永久的に強制力があるわけではない。
それでも、まさか……強引に、自己の肉体を『操作する』事で、
『偶像崇拝(アイドルマスター)』はあくまでスカウトの時点で発揮される能力。
永久的に強制力があるわけではない。
それでも、まさか……強引に、自己の肉体を『操作する』事で、
「殺れやァァ――ッ! 森田ァァ――ッ!!」
千歯車は叫んだ。
だが森田はそれでも、最も注意を払うべき男への認識を逸らさなかった。
銘刈はそうしなかった。彼女は真の意味での戦闘者ではなかった。
……そして、千歯車はそれを理解していた。
だが森田はそれでも、最も注意を払うべき男への認識を逸らさなかった。
銘刈はそうしなかった。彼女は真の意味での戦闘者ではなかった。
……そして、千歯車はそれを理解していた。
その差が生死を分けた。
「……言っただろうが」
「あ……」
「あ……」
胸部の肉を割って生えた手刀を、銘刈は理解せずに見つめた。
だが、森田が眼前におり、千歯車の支配が完全に解けておらぬ以上は……
その正体は自明である。
だが、森田が眼前におり、千歯車の支配が完全に解けておらぬ以上は……
その正体は自明である。
「俺は裏切らない。俺は元から――」
『偶像崇拝(アイドルマスター)』を受けるまでもなく。
味方についたと……
味方についたと……
「味方じゃあ、ないからなァ。……銘刈耀」
、 、 、 、 、 、 、
思い込んでいた、だけ。
、 、 、 、 、 、 、
思い込んでいた、だけ。
「儒楽――」
その異様な行動に、森田は真に虚を突かれ、その時。
ほんの刹那……
ほんの刹那……
「死」
――そこまでが、儒楽第の策略であった。
銘刈耀。世界を牛耳る目高機関の存在すらも。
銘刈耀。世界を牛耳る目高機関の存在すらも。
この男にとっては、この半秒にも満たぬ。
ただ一瞬の復讐の好機を作り出すためだけの。
ただ一瞬の復讐の好機を作り出すためだけの。
( )
投げつけられた銘刈を、森田は空白の思考で認識した。
反射的な蹴り。爆発四散。だが、遅い……すでに遅い。
誰よりも森田がそれを分かっている。
反射的な蹴り。爆発四散。だが、遅い……すでに遅い。
誰よりも森田がそれを分かっている。
悪鬼の嗤いの気配が、後頭にあることを感じた。
奴ならば必殺だ。首を刎ねる。
奴ならば必殺だ。首を刎ねる。
「――ね」
金属音。
森田一郎は、致死の一瞬、首を守った金属の冷たさを感じている。
森田一郎は、致死の一瞬、首を守った金属の冷たさを感じている。
「……!」
「……!」
「……!」
好機は潰えた。それでも儒楽第は闘志を些かも減ずることなく、
森田と同時に飛び退いて構えた。
そして2人は見た。
森田と同時に飛び退いて構えた。
そして2人は見た。
「見事ね、儒楽第。目高機関を逆に手駒にせしめるとは」
「――お嬢様」
「――お嬢様」
そこには七葉樹落葉がいた。そしてその傍らに立つ男。魔人。
不敵な笑みを浮かべるそいつは……落葉の手駒であった。
不敵な笑みを浮かべるそいつは……落葉の手駒であった。
「森田。私達はついに目的を達したわ。
トーナメントの中で見出した最良の駒。それは……」
「悪いねえ。俺ってホラ、子供の味方なんだよね。
だから、まあ……ここは少し」
トーナメントの中で見出した最良の駒。それは……」
「悪いねえ。俺ってホラ、子供の味方なんだよね。
だから、まあ……ここは少し」
森田の頸部を守った槍の穂先は、光の帯に導かれて男の手元へと戻った。
「目立たせてもらう」
『……油断をしてくれるなよ武志。また折られてはかなわん』
『……油断をしてくれるなよ武志。また折られてはかなわん』
――この瞬間に乱入が間に合った偶然などあるはずもない。
七葉樹落葉は待っていたのだ。
銘刈耀の『偶像崇拝(アイドルマスター)』がなくなるその時。
森田一郎が死域を潜り抜け、銘刈を殺すその瞬間まで。
心を潰すプレッシャーに耐え、ただ待った。
七葉樹落葉は待っていたのだ。
銘刈耀の『偶像崇拝(アイドルマスター)』がなくなるその時。
森田一郎が死域を潜り抜け、銘刈を殺すその瞬間まで。
心を潰すプレッシャーに耐え、ただ待った。
「小僧」
千歯車が立ち上がる。形勢は3対1へと逆転していた。
だが儒楽第はむしろ嗤った。
心の底から、この窮地を楽しんでいるかのようであった。
だが儒楽第はむしろ嗤った。
心の底から、この窮地を楽しんでいるかのようであった。
「死ぬか?」
そして笑みを浮かべるのは、この男も……
黒田武志も同様であった。
黒田武志も同様であった。
「おお、こりゃすげー」
「全滅。全滅なのか……?」
田村草介は、携帯端末の情報を前に、ただ、震えていた。
WL社本社を襲撃した魔人集団――夜魔口組。
砂男と赤帽。鬼神の如き殺戮。そこまではいい。
どの道この事業の後は『捨てる』予定だった企業だ。
WL社本社を襲撃した魔人集団――夜魔口組。
砂男と赤帽。鬼神の如き殺戮。そこまではいい。
どの道この事業の後は『捨てる』予定だった企業だ。
だが、それによってこちらの逃走経路が限定された。
日本国内とはいえ、魔人達の跋扈する大会会場からは相当の距離がある。
この位置は安全だ――と、田村という男がそう思うことは、決して出来ない。
日本国内とはいえ、魔人達の跋扈する大会会場からは相当の距離がある。
この位置は安全だ――と、田村という男がそう思うことは、決して出来ない。
(……銘刈も。『オレイン卿』も……裸繰埜……病咲も)
彼はガリガリと親指の爪を噛んだ。
悪い予感が全て的中していた。誰も彼もが、もはや彼に連絡すら返さなかった。
悪い予感が全て的中していた。誰も彼もが、もはや彼に連絡すら返さなかった。
(おかしい。何かがおかしい。こんな事があるはずがない。
常識的に考えて、こんな都合の悪い展開ばかりがあるはずがない)
常識的に考えて、こんな都合の悪い展開ばかりがあるはずがない)
まるで、誰かが。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
そんな都合のいい、頭の悪いハッピーエンドを望む『誰か』が、
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
ささやかにこんな展開を、助けているかのようではないか。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
そんな都合のいい、頭の悪いハッピーエンドを望む『誰か』が、
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
ささやかにこんな展開を、助けているかのようではないか。
(世界が……変わってしまう。私の世界が)
田村草介はその理由を知らない。
黄樺地セニオがあの時どのような選択を成して、
その結果何が起こったか――知り得るのは、あの場にいた3人しかいないのだ。
黄樺地セニオがあの時どのような選択を成して、
その結果何が起こったか――知り得るのは、あの場にいた3人しかいないのだ。
(海外だ。この国にいれば、おしまいだ。
海外に逃げれば、魔人能力の射程は……!)
海外に逃げれば、魔人能力の射程は……!)
「WL社が壊滅……ハン、どの道そちらに損害はないのだろう」
「メディアの掌握は二菅の仕事のはずだが? 手回しは済んでいるのかね」
「それよりも面倒事は、戦後の利益分配の方法ですな。
ユニオンとしての表向きの機関を――」
「四橘の魔人が2名離反したという話は? 仮にそうであれば責任問題に」
「メディアの掌握は二菅の仕事のはずだが? 手回しは済んでいるのかね」
「それよりも面倒事は、戦後の利益分配の方法ですな。
ユニオンとしての表向きの機関を――」
「四橘の魔人が2名離反したという話は? 仮にそうであれば責任問題に」
……そして、その階下。知られざる一室で囁かれる会話。
彼らの役職は当然、日本統括部部長、田村草介よりも下回る。
しかしその声色に動揺はなく、それどころか恐怖すらもない。
それが彼らの立場からすれば当然の態度であった。
彼らの役職は当然、日本統括部部長、田村草介よりも下回る。
しかしその声色に動揺はなく、それどころか恐怖すらもない。
それが彼らの立場からすれば当然の態度であった。
日本を拠点とする7財閥すらも言葉一つで操ることができる、
それが彼らのポジションなのだから。
それが彼らのポジションなのだから。
「……よろしい。現在の取引総額を見て判断するとしよう」
「『商品』の輸入は万全です。第二次パンデミック発生の折には、
初期は市場への流通を絞り……2ヶ月後に増産という体で……」
「『商品』の輸入は万全です。第二次パンデミック発生の折には、
初期は市場への流通を絞り……2ヶ月後に増産という体で……」
本来ならば、彼らの態度が当然である。
戦場は遠く、彼らの暗躍を知る存在すら皆無に等しい。
戦場は遠く、彼らの暗躍を知る存在すら皆無に等しい。
彼らはこの魔人戦争に賛同した――ある種の悪党である。
田村がその話を誘導した当初は、反対した者も少なからずあっただろう。
だが……結果的には全員がそれを決断した。
田村がその話を誘導した当初は、反対した者も少なからずあっただろう。
だが……結果的には全員がそれを決断した。
それは利益のためかもしれないし、巨大な大義ゆえかもしれない。
家族や妻、自らのささやかな生活を守るための決断でもあったかもしれない。
家族や妻、自らのささやかな生活を守るための決断でもあったかもしれない。
「……この件に関する結論は前回と同様」
「フン。リソースの配分は公平に行う、というわけだ。言うまでもなかろう」
「はははは、違いない」
「フン。リソースの配分は公平に行う、というわけだ。言うまでもなかろう」
「はははは、違いない」
そして自らの意志で決断した以上は、その責任を負う。
自覚するとせざるとに関わらず、いつか。
自覚するとせざるとに関わらず、いつか。
「我らは運命共同体なのだからな」
「そう。一つの家族だ」
「そう。一つの家族だ」
「…… 家 族 ?」
老人たちは、新たな会議の参加者を見た。
まったく予想外の声だった。
まったく予想外の声だった。
右腕が千切れ、顔の半分が崩れ……
あまりにも不完全な再生の、半死半生の姿ではあったが。
“この人格”を持つ彼が『存在する』、という事実は――
そこで何かが起こっている事を暗示していた。
当然、この老人達が与り知らぬ事、ではあったが。
あまりにも不完全な再生の、半死半生の姿ではあったが。
“この人格”を持つ彼が『存在する』、という事実は――
そこで何かが起こっている事を暗示していた。
当然、この老人達が与り知らぬ事、ではあったが。
「いい言葉だなァ――」
「な、なんだ……お前、それはゴブッ」
「俺も、足りないんだ」
「俺も、足りないんだ」
一人の老人の鳩尾に拳を突き刺しながら、それは呻いた。
殺戮が目的ではない。求めるのは苦痛と恐怖。それだけだ。
殺戮が目的ではない。求めるのは苦痛と恐怖。それだけだ。
「家族が足りない……。
これじゃあ傷が、全然、足りない。
だから……さぁ、なぁ……皆」
これじゃあ傷が、全然、足りない。
だから……さぁ、なぁ……皆」
半死の体で、それでも無理に笑顔を作って少年は笑った。
家族を心配させることはできないからだ――。
家族を心配させることはできないからだ――。
「今から――俺の家族(リソース)になってくれよ」
消滅し、改変された筈の猪狩誠の復活。
それはこの黄樺地セニオの『世界の敵の敵』が……
善人は善人らしく。そして同様に、悪人も悪人らしい世界のままで。
『世界の敵の敵』そのものという『理不尽』すらも改変されつつある証明であった。
それはこの黄樺地セニオの『世界の敵の敵』が……
善人は善人らしく。そして同様に、悪人も悪人らしい世界のままで。
『世界の敵の敵』そのものという『理不尽』すらも改変されつつある証明であった。
ならば今まさに、この会議室の中で起こっている『理不尽』もまた……
いずれは改変される運命にあるのだろうか?
その答えはまた別の話である。
いずれは改変される運命にあるのだろうか?
その答えはまた別の話である。
「はっ、はははっ……
あははははははははははははははは!!
家族だ! もっと家族になってくれ!!」
あははははははははははははははは!!
家族だ! もっと家族になってくれ!!」
彼らは、自らの責任で災厄を撒き散らした悪党であった。
だが、おお……ここまでされる謂れは無い!
……この地に猪狩誠……少なくとも、猪狩誠の残骸が現れた。
それは即ち、田村草介の終わりを意味していた。
同じ終わりであれば、その恐怖を自覚していた田村は……
より『不幸』な結末であったと言わざるをえない。
それは即ち、田村草介の終わりを意味していた。
同じ終わりであれば、その恐怖を自覚していた田村は……
より『不幸』な結末であったと言わざるをえない。
(……終わりか)
迎えの機の一台も来ないヘリポートで夜空を見上げて、田村は終末を悟った。
彼の決断で、敵も味方も、どれだけの人間が死に絶えただろう。
しかし彼はそれでも、自らの罪を省みる気は微塵もなかった。
実体のない罪悪感は、安心という報酬を汚すからだ。
彼の決断で、敵も味方も、どれだけの人間が死に絶えただろう。
しかし彼はそれでも、自らの罪を省みる気は微塵もなかった。
実体のない罪悪感は、安心という報酬を汚すからだ。
他のどれだけを――良心すらをも踏みつけにしても『安心して』生きたかった。
それが彼の望む全てであったのだから。
それが彼の望む全てであったのだから。
「どうしてここに、と思っただろ?」
軽薄な男の声が、夜の屋上に響く。
こんなシチュエーションに自分は似合わない。
田村はそれも自覚していた。彼は涙を流した。
こんなシチュエーションに自分は似合わない。
田村はそれも自覚していた。彼は涙を流した。
「……佐倉光素の転移能力。
場所と対象さえわかれば、君一人を送る程度……造作も無いだろう」
「潔いな。そういうのは好きだぜ」
場所と対象さえわかれば、君一人を送る程度……造作も無いだろう」
「潔いな。そういうのは好きだぜ」
背後からのライトに長く伸びた影が、田村を追い越す。
すぐ後ろに、手を伸ばせば届く距離に暗殺者が立っている。
すぐ後ろに、手を伸ばせば届く距離に暗殺者が立っている。
「じゃあ、これから俺が何をするかも分かるな」
「ああ……分かる」
「ああ……分かる」
……最後か。
最後くらいは、大物として命を散らしたいものだ。
全ての責任を抱えたまま。身の丈に合わぬ悪行を成したことを誇りつつ。
全ての責任を抱えたまま。身の丈に合わぬ悪行を成したことを誇りつつ。
――本当はいつも、下の階の老人達を羨んでいた。
自分より遥かに下の役職にありながら、自信と自負を兼ね備え……
あらゆる障害を恐れず潰す、その『悪』に憧れていた。
自分より遥かに下の役職にありながら、自信と自負を兼ね備え……
あらゆる障害を恐れず潰す、その『悪』に憧れていた。
「私は」
……けれど、
「わ、私は」
言葉に詰まった。最後の最後で。
それが感情の決壊の皮切りになった。
それが感情の決壊の皮切りになった。
恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。
魔人は恐ろしい。
……自分は『違う』のだ。田村草介は常に常に、自覚していた。
魔人は恐ろしい。
……自分は『違う』のだ。田村草介は常に常に、自覚していた。
助かりたい。落ちぶれて地を這ったっていい。
他の何を差し出しても、命だけは。
本当は……
他の何を差し出しても、命だけは。
本当は……
「た、助けてくれ……お願い、お願いだ……」
その顔を泣き声で歪めて、田村草介は呻いた。
それが最後の、彼の本質だった。
それが最後の、彼の本質だった。
「……駄目だ」
暗殺者は一度答えた――だからその言葉が無駄だと自覚している。
それでも、絞りだすように叫んだ。
それでも、絞りだすように叫んだ。
「金はいくらでも出す。だから……だからお願いだ、助けてくれ……!!」
「その言葉を待ってたよ。田村草介」
姿は見えない。けれど背後の赤羽ハルが微笑んだように思えた。
あるいは彼がいつも浮かべる、自嘲めいた苦笑だったのかもしれない。
姿は見えない。けれど背後の赤羽ハルが微笑んだように思えた。
あるいは彼がいつも浮かべる、自嘲めいた苦笑だったのかもしれない。
「 駄目だ 」
――――――――――――――
―――――――――――
――――――――
―――――――――――
――――――――
『ザ・キングオブトワイライト』を発端とする一連の事件は、終わった。
日の沈んだ深夜の路地を、赤羽ハルは歩いている。
あれほど深かった負傷も気にならないほど、憔悴していた。
日の沈んだ深夜の路地を、赤羽ハルは歩いている。
あれほど深かった負傷も気にならないほど、憔悴していた。
「……馬鹿か。俺は」
夜空に浮かぶ月は、彼自身の心に深く開いた空洞のようであった。
日中の戦禍が嘘のように、街は平穏を取り戻している、ように見えた。
日中の戦禍が嘘のように、街は平穏を取り戻している、ように見えた。
(戦争の元凶を殺して。自分の副賞すら棒に振って。
……一体何が残るんだ。俺に何が)
……一体何が残るんだ。俺に何が)
世界は変わったのかもしれない。
しかし赤羽ハルには、それを思い出すことが――。
しかし赤羽ハルには、それを思い出すことが――。
「ダーツガチデ」
「サイヨー! ちぃーっす、ウェイウェーイ!」
「ちょアレマジアレじゃね?」
「アレテ! アレすぎっしょ!」
「サイヨー! ちぃーっす、ウェイウェーイ!」
「ちょアレマジアレじゃね?」
「アレテ! アレすぎっしょ!」
コンビニの前を通りかかった時、耳に障る陽気な会話が耳に入った。
――チャラ男か。そういえば見かけなかったっけな、最近。
――チャラ男か。そういえば見かけなかったっけな、最近。
「ウェイウェーイ! ドゥ~したのその顔!」
「顔てwww 普段通り系じゃネー俺~~?」
「サガってるサガってるフッフゥーッ♪」
「顔てwww 普段通り系じゃネー俺~~?」
「サガってるサガってるフッフゥーッ♪」
ウザったい会話を意識の端にすら入れず、
赤羽は通りすぎようとした。
赤羽は通りすぎようとした。
「――つか、アレっショ? カノジョっショ?
忘れてんじゃん? チッヒーいんじゃん! 元気だしなってガチで!」
「いぇーい! オツカレィ~~♪」
「おっクーちゃん来たジャーン! やっぱ噂ドーリ超マブじゃーん!」
「ッてか俺のカノジョチッヒーじゃねーし! 人ちがウィッシュ!」
「バッカ俺んな事言ってねーしwww」
「じゃあwww誰が言ったんだしwww」
忘れてんじゃん? チッヒーいんじゃん! 元気だしなってガチで!」
「いぇーい! オツカレィ~~♪」
「おっクーちゃん来たジャーン! やっぱ噂ドーリ超マブじゃーん!」
「ッてか俺のカノジョチッヒーじゃねーし! 人ちがウィッシュ!」
「バッカ俺んな事言ってねーしwww」
「じゃあwww誰が言ったんだしwww」
(……………………。
『チッヒー』)
『チッヒー』)
足が止まったのは何故だろうか。
そのせいで、コンビニ前から出発していたチャラ男の一団と肩がぶつかった。
静電気のような衝撃が走った。
そのせいで、コンビニ前から出発していたチャラ男の一団と肩がぶつかった。
静電気のような衝撃が走った。
「なんだよ……どうして、忘れてたんだ、俺は」
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
どうしてこの世界にチャラ男がいるんだ。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
深い負傷も気にならない。傷が、綺麗に消えている。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
戦禍が嘘のように平穏に戻って。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
どうしてこの世界にチャラ男がいるんだ。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
深い負傷も気にならない。傷が、綺麗に消えている。
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
戦禍が嘘のように平穏に戻って。
――――
黄樺地セニオ
魔人能力名:『イエロゥ・シャロゥ・パレット:世界への最後配当』
――自分の魂を、世界の復元力の通貨へと変える。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/242.html
魔人能力名:『イエロゥ・シャロゥ・パレット:世界への最後配当』
――自分の魂を、世界の復元力の通貨へと変える。
http://www49.atwiki.jp/dangerousss3/pages/242.html
――――
世界は変わったのだ!
黄樺地セニオが……変えたのだ!!
黄樺地セニオが……変えたのだ!!
覚えている。彼女の笑顔を。声を。名前を。
――忘れたいなんて、一瞬たりとも思わなかったはずなのに。
――忘れたいなんて、一瞬たりとも思わなかったはずなのに。
「智広さん……!」
赤羽ハルは走りだした。
その後姿を、チャラ男の一団の一人が振り返った。
その後姿を、チャラ男の一団の一人が振り返った。
「……ッと、こんなトコでいいだろ」
つッても、独り言でブツブツ説明すると、さすがのチャラ男にも引かれるからな。
……改変された前の世界の設定を思い出す手段のひとつだ。
今すれ違ったほんの一瞬だけ、『地の文を認識させた』。
……改変された前の世界の設定を思い出す手段のひとつだ。
今すれ違ったほんの一瞬だけ、『地の文を認識させた』。
……あァ? お前は出てこないんじゃないのか、だって?
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒ!! 馬鹿言うなよ!
お前らこそ、おれの設定をちゃんと読み込んでないんじゃあないのかァ~~?
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒ!! 馬鹿言うなよ!
お前らこそ、おれの設定をちゃんと読み込んでないんじゃあないのかァ~~?
『狂気的』で『敵だったり味方だったりして』、
しかも読者に『人気のない』キャラがよオ――
しかも読者に『人気のない』キャラがよオ――
真っ正直にアナウンスなんかするわけねえじゃねえか! ヒヒヒヒヒ!
……でもアレだな?
結局どんな『理不尽』も絶対的に打ち消す改変力が
『世界への最後配当』だったとしたらよオー
じゃあ何か? おれのこの動きまで織り込み済みってことか? ヒヒヒ!
結局どんな『理不尽』も絶対的に打ち消す改変力が
『世界への最後配当』だったとしたらよオー
じゃあ何か? おれのこの動きまで織り込み済みってことか? ヒヒヒ!
「ウェーイwww クーちゃん何やってんノ?
テンションアゲてアゲてー↑」
「ウェッ!? ヒヒヒ……じゃねえや、うはwwwおkwww」
テンションアゲてアゲてー↑」
「ウェッ!? ヒヒヒ……じゃねえや、うはwwwおkwww」
ま、最後くらいは後味の良い終わりがいいだろ。
ギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラギャラ……
+ + + + +
その神社は、小さな山の上に建っていた。
2人が暮らした家の裏手に立っている古い神社で、
赤羽ハルは初詣に行った事すらなかった。
2人が暮らした家の裏手に立っている古い神社で、
赤羽ハルは初詣に行った事すらなかった。
けれど、白詰智広は言っていたのだ。
いつかどこか。目が見えるようになったら――
高いどこかで、綺麗な場所で。一緒に景色を見たいと。
いつかどこか。目が見えるようになったら――
高いどこかで、綺麗な場所で。一緒に景色を見たいと。
真っ先に家に帰って、白詰智広の姿がなかったのならば……
赤羽ハルは、この神社の他に、どの場所を探せばいいのだろう?
彼女は待っているのだろうか?
目が見え、足が動き、すべて自由になったその体で……
この人殺しの俺を……それでも待っていてくれるのだろうか?
赤羽ハルは、この神社の他に、どの場所を探せばいいのだろう?
彼女は待っているのだろうか?
目が見え、足が動き、すべて自由になったその体で……
この人殺しの俺を……それでも待っていてくれるのだろうか?
(智広さん。俺、言っていないことがあったよ。
最悪だ……俺は、優しくなんかないんだ……)
最悪だ……俺は、優しくなんかないんだ……)
胸ポケットの中で今も鳴る4枚の100円玉が、彼を苛んだ。
シャイロックの悪魔。
シャイロックの悪魔。
(最強なんざ、笑わせるよ……俺は……強くもない。
……自分でも信じられねえよ。
クソッタレ……俺だって本当は、何も悩まず、チャラく生きてみてえよ……!)
……自分でも信じられねえよ。
クソッタレ……俺だって本当は、何も悩まず、チャラく生きてみてえよ……!)
白詰智広が赤羽ハルに頼っていたのではなく――
小さな山。けれどたかが『裏の神社』に向かう事が、
これほど苦しくて不安な事だとは知らなかった。
これほど苦しくて不安な事だとは知らなかった。
境内が見える。
そもそも神仏に頼る質ではなく、その点で赤羽ハルは凡庸な暗殺者であった。
けれどその時ばかりは、不確定な奇跡を祈った。
そもそも神仏に頼る質ではなく、その点で赤羽ハルは凡庸な暗殺者であった。
けれどその時ばかりは、不確定な奇跡を祈った。
「……嘘だろ」
涙が落ちた。
そこに待っていた人は
そこに待っていた人は
「おかえり、ハルくん」
振り返って、笑った。
――世界は変わった。
関西が滅びることも、関東に核が落ちることも、パンデミックが起こることもない。
魔人がいるという、少しだけ不思議で混沌とした暴力もある。
けれど気楽な世界に。
魔人がいるという、少しだけ不思議で混沌とした暴力もある。
けれど気楽な世界に。
善人は善人らしく。
悪人は悪人らしく。
悪人は悪人らしく。
……彼らはこの世界で、生きている。
以前の世界の記憶を持つ者もいる――それが『理不尽』でないのならば。
平穏に暮らすはずだった三姉弟は、三人のまま、平和な学園を謳歌するのだろう。
偽名探偵は今日も眠たげな目で依頼をこなすはずだ。
例えば世界の敵は、今も再び、何か恐ろしい計画を企んでいるのだろう。
そして悪魔の映画は、少しだけ良い映画になったのかもしれない。
けれど一つだけ確実な事がある。
以前の世界の記憶を持つ者もいる――それが『理不尽』でないのならば。
平穏に暮らすはずだった三姉弟は、三人のまま、平和な学園を謳歌するのだろう。
偽名探偵は今日も眠たげな目で依頼をこなすはずだ。
例えば世界の敵は、今も再び、何か恐ろしい計画を企んでいるのだろう。
そして悪魔の映画は、少しだけ良い映画になったのかもしれない。
けれど一つだけ確実な事がある。
彼らが『滅び』に縛られることは、もはやない。
核とウィルスで家族を失った潔癖症の殺人者は、
この世界では自分の罪に苦しむことはないのかもしれない。
仮に少しだけ頭が変であったり、言葉遣いが妙であっても、
それは悲しみの果ての狂気からくるものではないのだろう。
あるいは、幼少時の体験で少しだけ甲殻類が好きになったかもしれない。
この世界では自分の罪に苦しむことはないのかもしれない。
仮に少しだけ頭が変であったり、言葉遣いが妙であっても、
それは悲しみの果ての狂気からくるものではないのだろう。
あるいは、幼少時の体験で少しだけ甲殻類が好きになったかもしれない。
チャラ男は滅びず、この世界に生きている。
その中の誰かが、知らぬはずの物事を口に出すことがあるかもしれない。
それが世界に散った黄樺地セニオを、ふと『コピーした』残滓だったとしても。
彼らはチャラ男であるが故に――
それをありのまま受け入れて、気にも留めないだろう。
その中の誰かが、知らぬはずの物事を口に出すことがあるかもしれない。
それが世界に散った黄樺地セニオを、ふと『コピーした』残滓だったとしても。
彼らはチャラ男であるが故に――
それをありのまま受け入れて、気にも留めないだろう。
そして一人の暗殺者は……
金で得ることのできなかったものを手に入れて、幸せに暮らしたかもしれない。
金で得ることのできなかったものを手に入れて、幸せに暮らしたかもしれない。
ダンゲロスSS3 了